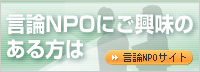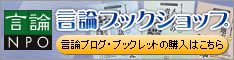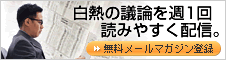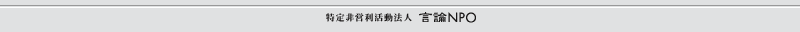« 2008年8月 | メイン | 2008年12月 »
2008年9月18日
第4回 東京‐北京フォーラムを終えて
今回のフォーラムは今までの3回に比べて分科会の議論は質の面でも数段良くなったと思います。それは日中間の現状の課題解決に皆が向き合う、という本気の議論にかなり近づいたからだと思います。第1回のフォーラム開催の時には、日中対話なんかやっても中国は建前的な議論しかしないから、本音の議論になんかなりっこない、と皆に言われました。確かに僕もそう思ったし、中国側も自分の政府の立場で説明することが議論だという感じが強かったのも事実です。今回も、実は新しく来た人の中には、そのような説明口調になる人もいました。ただ、それにもかかわらず、実際の舞台では議論がかなり噛み合った。これはどういうことなんだろうと思って考えてみると、やはりこの「東京‐北京フォーラム」は、日中の参加者が本音で議論する舞台なんだという意識がかなり定着してきたのではないか、と僕は思います。
本音で中国と本気で議論を行う、というのはそう簡単なものではないのですが、そういう舞台になったきっかけの1つは議論が世論調査の結果と連動して行われるからだと思います。特に、1回目のフォーラムの時、世論調査結果を見て、中国側のパネリストの顔がかなり変わったのを今でも覚えています。その時の調査からわかったのは「中国人の半数以上が日本が今でも軍国主義だと思っている」という驚くべき結果でした。日本人と中国人の認識の差がはっきりと出ていたのです。お互いの交流は極めて少なく、ほとんどの認識は、自国のメディアに依存してつくられている。そうした脆弱な相互理解の実態が明らかになりました。これはまずいと中国側も判断したようで、第1回目のフォーラムはあの厳しい日中関係の最中でも、お互いにかみ合った議論ができたのです。
2つ目のきっかけは、やはり第2回の東京でのフォーラムで、安倍晋三さんが日中首脳会談への大きな一歩となる発言をしたことだと思います。これは民間の対話でもお互いが尊重しあい、共通の課題に向かい合えば何かが実現できるという手ごたえを参加者に実感させたと思います。
今日フォーラムが終わった時に、今までの中で一番良かった、と多くの人に声を掛けていただきました。日本と中国が本気で議論ができる場へ更に成長している、そう思った人も多くいました。でも、議論の舞台がそういう形で整ってくると、今度はパネリストの議論力が問われるようになります。本当に真剣な議論を行うのなら、遠慮をしないで相手に議論を挑むべきで、建前だけではなく、課題解決への答えを出そうという努力が参加者に問われているのです。それができなかったとしたら、それが今の対話の水準なのです。
このフォーラムが素晴らしいのは、お互いが真剣に議論し、その内容が全部オープンになって両国民に見られていることです。今回は日中の課題になっている食品の安全性の対話には、中国側から政府の担当者が参加しました。この時期にそう言う人が来ただけでも画期的なことですが、その議論がすべて公開されているのです。
ただ実を言うと、最終日の挨拶でも言ったのですが、本音としては、ようやく間に合ったということが、僕の気持ちの中では非常に強いわけです。まだ本当の意味で、民間対話が成功しているかどうか、言い切れない部分はあります。今はアメリカの金融危機の問題が発生し、世界が混乱の最中ですが、そういう中でも、アジアの今後について自らが考え、解決への方向を議論していくことが大事になってきています。こうして課題に真剣に向かい合う対話の舞台がこの民間対話なのです。国際的な大きな変化が迫る中で、ハイレベルな議論はその変化に向かい合わなければなりません。そのための対話の舞台づくりが、今年何とか間に合ったと思うのです。このフォーラムを舞台として、アジアの未来を自分たちが切り開くため、僕は議論の力でそれ行おうと思っているわけです。あとは、その場で、日中双方がどう具体的な議論を作り上げるのかです。この舞台をもっと前進させようと多くの人が支えてくれているのは、その理念に共感してくれたからです。
僕はその意味でいえば、この日中の民間対話はこれからが本当の正念場だと思っています。僕たちが目指しているのは、日中のこの対話の舞台を、いずれアジアに広げ、この議論の内容を継続的に世界に発信させる仕組みを作り上げることです。本気の議論の舞台をアジアに作ろうというこのドラマは、これからまだまだ続きますし、僕はそれを必ずやり遂げたいと思っています。今回の議論については、公式サイトや今後出版する報告書を見てもらいたいですね。
投稿者 genron-npo : 20:52 | コメント (0) | トラックバック
2008年9月15日
今回の調査結果をどう見るか
9月8日の記者会見で日中共同世論調査の分析結果が発表されましたが、工藤さんは今回の調査結果をどう見ていますか?
これについては是非僕たちのWebサイトを見て頂きたいんですが、今回の世論調査はかなり重要な内容になったと思っています。3年前に僕たちがこの世論調査をした時は、反日暴動が中国であって、世論調査を実現するということ自体が難しかったんですね。でも、僕はやっぱり、デモをはじめ色んな形で抗議している中国の人たちがどういう意識なのかを知りたかったんです。この世論調査を行うことで、その民意をきちっと正確に僕たちが理解出来るし、その上で今の政策課題にきちっと取り組むことが出来るので、その内容を僕たちは非常に重要視していたんですね。
今回の調査結果では、非常に考えさせられる事がありました。それは日本と中国の世論に意識の差というか、世論が逆に動いていることです。去年から今年は日本と中国の政府関係が非常によくなってきました。胡錦濤さんも今年来ましたしね。つまり政府間関係はかなり良くなったので、中国の方は非常に日中関係に好意的な、かなり前向きで建設的というか、かなり良いイメージを持っている。にもかかわらず、日本の世論は逆に厳しくなっている。どうしてこんなに逆になっているのかということが、今回の世論を分析するときに一番僕たちが考えた点でした。
クロス分析など色んな分析をしてみたのですが、その中でわかったのは、中国の世論は政治を軸にして対日イメージを作っているということです。それは日中間の歴史の問題や、ある意味で政治の問題が課題となっていたという状況の中で、そうした意識を持つ傾向が強まっているのが分かります。しかし、面白いことに日本はそうではないと言うことなんですね。日本はむしろ生活者とか、消費者的な視点で中国を見ていることが、今回はっきりしたわけです。
それはどういう点を見てはっきりしたんですか?
僕たちは世論調査で、「日中間を阻害するもの、障害になっているものは何なのか?」という質問をしました。3月にはチベット問題、5月には聖火リレーの問題、そしてその後に胡錦濤氏の訪日があり、またその期間を通じてずっと、食の安全の問題があったと。だから、そういう点を質問に入れなきゃいけないと僕たちは思っていました。そこで、たとえば中国における愛国的な動きの問題とか、人権の問題とか、食の安全とか、そういう項目を結構いれておいたんですね。だけど一般の日本の国民は、少なくとも人権や愛国的な動きにはほとんど反応せず、一番反応したのは食品の安全性だったわけですね。日中関係というのは元々歴史問題というのが阻害要因になっています。しかし今回の調査を見てみると、この食の安全問題が半数近いんですね。「お互いの国に行きたいか」という設問でも、行きたくないという人が半数を超えています。その理由を見ると、やはり食の問題が出てくるわけですよ。世論調査の中に日中関係を阻害するものは何かという項目があるんですが、46.2%の人たちが中国産品の安全性の問題と答えている。これはもう歴史問題に匹敵するくらい大きくなってる訳ですね。
つまり、日本国民にとって食の問題、自分の生活観で理解できる問題というのは非常に大きいという事が今回分かった。とすると、今まで日中間の政府間関係があまりよくなくて、その中でお互いに対する印象が非常に悪かったのですが、政府間関係が良くなることによって改善した中国と、政府間関係は改善したけれど生活レベルで見て非常に違和感を感じてきた日本の世論、という点に今回の調査の非常に大きな特徴があったわけです。実をいうと、これはひとつの大きなテーマを僕たちに与えてると思うんですね。つまり、政府だけではなくて民間の視点、生活の視点というものがそのまま世論に大きく反映するという事が分かってきたわけです。そういう意味では、食の安全問題というのは日本と中国が本気で解決しないとまずい。私も当初はそこまで思ってなかったけど、非常にそれが今回の調査に出てきちゃったわけですね。
一方で前から指摘していたのですが、日本と中国には直接的な交流がほとんどないんですね。中国の国民は1%未満しか日本に行ったことがない。日本はそれよりは少し多いのですが、ほとんどの人がメディア報道でお互いに対する国のイメージを作っちゃってるんですね。しかし、メディア報道の責任も大きいのですが、一方でその間接情報に頼らないとお互いを理解できないという、閉鎖された、交流が少ないこの社会に大きな問題があると私たちは思っています。今回もその構図は変わってないんですね。
同時に中国の人は日本の事を半分くらいはいまだに軍国主義だと思ってるんですね。直接的に友達がいるとか、実際に日本に来た人などは自分の目で見てそれが違うということが分かるんですが、そういう経験がない人はテレビなどのメディアの報道を信じる。だから、メディア報道のあり方もあるけれど、やっぱりその根底にはお互いのその交流の薄さがゆがんだ相互認識を作ってしまうという事が今回の非常に大きな問題だったわけです。この二つが、今回の世論調査で浮き上がった問題だったわけですね。
では、世論調査の結果を受けて今回のフォーラムの中ではどういう事を議論されるのでしょう。
今回のフォーラムでは、特に「メディア対話」分科会で、世論調査で浮かび上がった日中問題そのものについて徹底的に議論しようと思っています。両国を代表する有識者、メディア関係者を集めて徹底的に議論しようと思ってます。是非皆様に直接会場に足を運んで参加して欲しいのですが、会場に来れない方も、議論の風景をインターネット会議方式で中継するので、それを見て議論に参加してほしいと思っています。(注:言論NPOサイトより事前の登録が必要です。お申込みはこちらなので、ご自宅でも仕事場でもね、仕事場でみると怒られちゃうかもしれないけど(笑)、見て頂いて、この両国の正反対に動いた世論とその中で浮かび上がった日中間の問題をどう考えていけばいいのかという事を議論しますから、それに色んな形で参加して欲しいと思います。
メディア対話分科会の他に、工藤さんのお勧めの分科会はありますか?
お勧めといえば全部お勧めなのですが(笑)、あえて言えば、今年は日中平和友好条約が提携されて30年です。この30年を踏まえて、これからの日中関係や、アジアの未来について政治家同士が議論する政治対話がお勧めです。中国側パネリストも、外務大臣経験者などがかなり来るんですね。政治対話は、前半は椿山荘の会場で、後半は東京大学の福武ホールで学生の前で議論します。登録さえしていただければ、無料で見れますので、ぜひ会場に足を運んでいただければと思います。
僕たちは、他にも食品の安全問題(食料対話)や、環境問題(環境対話)と安全保障問題(安全保障対話)、また今回は「地方対話」分科会を新設して、アジアと日本の地域対話も今回はスタートさせます。オリンピックも終わった直後、しかも日本はまさに総理大臣が辞任を表明し、総裁選が行われている真っ只中で、私たちはアジアについて、また日中のこれからについて本気の議論をしますので、是非参加していただきたいと思ってますね。
投稿者 genron-npo : 07:12 | コメント (0) | トラックバック
2008年9月 2日
福田首相の辞任表明について
Q. 福田首相が辞任表明しましたが、その点に関してどう思いますか?
驚きました。8月19日に僕は総理と会ったんですけど、そのときは、非常に前向きだったし、国会のことも語っていたからです。僕たちの東京-北京フォーラムに関しても非常に関心を持っていました。今年は特に日中平和友好条約30周年という、日本と中国が国交を回復した歴史的な区切れのときで、今の時期の意味もわかっていらっしゃった。そういう意味で非常に驚いたというのが今の心境ですね。
Q. 福田首相は1年足らずで辞任を表明しましたが、その点に関しては?
政治を投げ出すことはまずいと思います。ただ、福田総理はいろんな状況の逆境があって追い詰められて退陣したというよりも、今のまま臨時国会を開いても攻めに転じられる保証がなかったという見極めをしたのではないかと思います。でも、総裁選をしても攻めに転じる保証もない。それが福田総理の苦悩のように思います。
ただ僕がここで感じるのは、国民との合意に基づかない政治には非常に脆さがあるということです。安倍さんのときに参議院選挙はありましたけれど、2005年の小泉さんの郵政解散以来、有権者との政権公約をベースにした選挙が全然行われていない。ということは、国民との合意に基づかない政治が続いているということです。内外の課題が大きくなる中で、日本の政治は国民の約束に基づいた形を取り戻すチャンスをずっと狙っていたのですが、それがうまくいかない。日本の将来のデザインや設計と、増税を含めた負担の問題に、日本の政治がそれらにきちんと国民に説明できないという状況が今この事態を招いていると思います。
確かに、いろんな状況で困っている人はいっぱいいらっしゃるけれども、しかし将来こうなっていくんだ、そのためにこういうことが必要だという説明があれば納得できる。日本の政治はなかなかそれができない。
福田政権の1年間を見ても結局国会の中で行われたことは選挙のための戦いだった。だから僕も何回か「未来を語れない政治になっている」と警告したのですが、それができるかどうかの瀬戸際に日本の政治があると思います。福田政権では結局、その立て直しができなかったということです。
僕は日本の政治はかなり重症でこの間の失敗から立ち直ることは容易ではないと思っている。今の日本の課題をどう解決するかというビジョンや政策競争が日本の政治の舞台で始まらないと、日本の未来は見えないと思います。政党内で総裁が変わってもそれだけではもう無理な段階で、やはりこの状態は民意を問うしかないのが、今の日本の政治だと思います。これから自民党の総裁選挙があり、また民主党も、対立候補がいないという状況ですが代表選があります。その政党の党首選びから国民にオープンにしていって、そのプロセスを国民に見せた上で国民との約束をするというサイクルにこれから変えないと、日本の政治は本当に国民から離れてしまうのではないかと思っています。そういう意味で、僕たちは評価という視点でそうした政治へのプレッシャーをかけなければと思っています。9月15、16、17日に日中の対話(注:第4回東京-北京フォーラム)もあって大変なのですが、そろそろ私たちも日本の政治の評価の動きを本格化させようと思っています。
聞き手:インターン 安達佳史(早稲田大学)