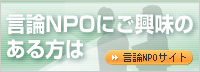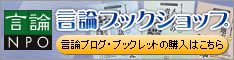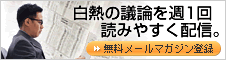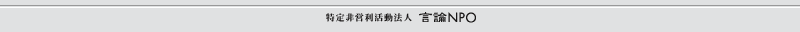« 2008年12月 | メイン | 2009年5月 »
2009年1月15日
麻生政権の100日評価結果で考えたこと
言論NPOは先日、「麻生政権100日評価」のアンケート結果を公表しましたが、この結果で何が明らかになったのでしょうか。
工藤 こうした調査では消極的な傾向が出やすいのですが、麻生政権に対する100日後の支持率がここまで低いとは、率直にいって想像外でした。11%ですから。しかも今後への期待もかなり低い。
麻生政権に本来期待されていたのは、なるべく早く「解散・総選挙」をして、「民意に基づいた政治」を回復させることですが、そのタイミングをズルズルと失い、経済対策に関してもそれに対する期待や信頼を集めていない、それがこうした結果になったと思います。
この100日評価は、どんな政権でも100日経ったら有権者の監視にさらされる、そうした緊張感ある政治を作ろうと3年前から取り組んでいます。
首相の評価は首相の資質と業績の評価の二つに分かれますが、その二つでも麻生政権は、前の安倍さん・福田さんに比べてもかなり評価が低い。首相の資質に関しては、たとえば「政策決定のリーダーシップ」とか、「国民に対する説明能力」とか、8項目を5段階で評価しましたが、麻生さんは5点満点で1.8点でした。こうしたアンケートによる評価は厳しめに出るものですが、福田さんは2.3点で、安倍さんは2.2点ですから、やはり1点台に落ちたというのは、非常に大きい事実だと思います。
それから21項目からなる麻生政権の取り組んだ政策課題についての評価では、評価が相対的に高く、「評価できない」という声と意見が分かれたのは、消費税の増税を全治3年の後に行うということを明言した点だけです。これに対しては一定の評価があったのですが、それ以外の20項目に関しては、ほとんどが現時点も、今後も評価できないという、かなり厳しい評価になりました。政権が取り組む課題のほとんどの項目で評価が低い、という状況は今までの安倍さん・福田さんではなかったことです。
今回のアンケート評価では日本の現在の政治状況に関しても聞いていますが。
工藤 今回の評価では麻生政権のことだけがメディアでも取り上げられたのですが、今回のアンケート結果の結論で一番私が注目したのは、回答者の多くが麻生政権にイエローカードを出しただけではなく、日本の政治そのものにもイエローカードを出したことです。
例えば民主党に政権交代を期待する声が5割以上ありました。これは今の政権が駄目だから民主党に期待していると思いがちですが、実はそうではない。民主党の政策を期待しているのはわずかに6.3%で、それよりも多いのは、政権交代をすることによって確かに政権は不安定になるかもしれないが、一回、政治の構造を変えない限り、チェンジしない限り日本はもたないだろうと思っている人たちであり、彼らが7割もいたのです。
今の日本の政治の現状をどう見ているのか。今回はもっと突っ込んでみました。すると、今の日本の政治の状況については、既成政党の政治の限界がはっきりして、「新しい政治に向かう過渡期」であるとか、いったん「政権交代によってこれまでの政治を一度壊すべき時期」であると捉えている人がそれぞれ半分以上もいるわけです。
いまの既成政党に期待していない回答者も半数を越えました。やはり日本でも政治の変化を求めている。それは既成政党の政権交代ではとどまらない、という見方です。これが、今回のアンケート結果が浮き彫りにした、非常に大きな傾向です。
そこで、私はこの結果に関して自民党と民主党の国会議員に参加してもらい、こうした回答結果をどう考えるか、座談会を開いて議論してみました。Webでも公開しているのでぜひ、見ていただきたいのですが、ここで私は、既成政党には今の政治を変えていく力はあるのか、と聞きました。
今の政治は、党首討論にも見られるように、国会でも今の危機に真剣に向かい合っているとは思えず、議論は、あなたは定額給付金をもらうか、もらわないのかとか、補正予算を出すか出さないかとか、そういう話だけで時間がつぶされている。こうした状況が政治への失望感につながっている、と思うのです。
それに対する政治家の答えには、正直に言って驚きました。座談会に参加していただいた政治家の人は私も尊敬する人ですが、正直に今の政治の状況を話してくれたからです。
多くの政治家には、政策を真面目に議論しても、それでは当選には結びつかないという無力感があると言うのです。だから目線が選挙だけを意識していて、日本の未来を考えるような論争が起きない。さらに、自民党の方から見れば、自民党の政治は限界だというのは何年も前からわかっていた、小泉政権で一度延命しただけで党を抜本的に変えないとならないことは分かっているが、その力はいまの政党にはない、とまでいうのです。
では、日本の政治は、なぜ自己革新の力を持たないのか。それに対する政治側の答えは、かなり強烈でした。有権者がそういうことを求めていない、から。それが答えです。今の危機は今の日本の社会経済の構造やこれからの日本の未来にとっても多くの問題を提起しているのですが。日本の将来がどうなるとかよりも、地方の経済の疲弊は厳しく今のサービスのことだけしか有権者は関心がない、だからバラ撒きでも公共事業を求める、というような内容でした。
座談会には皆さん、本音で参加していただき私も感謝していますが、こうした政治家の認識は今の多くの政治家に共通しているように、私には思えます。
私は、この100日評価の結果や議論を見ていて、日本の政治は今、歴史的な岐路にあるのではないかと痛感しました。
日本の政治は変わらなくてはいけない。それは言論NPOのアンケートの結果でも期待されていることです。でも、日本の政治を本当に変えさせる、チェンジさせるには、有権者がそれを求めないといけない。有権者が求めて、政治に迫っていくという力を持たないと、日本は変わらない、のです。
つまり問われているのは私たちなのではないか、それをこの「麻生政権の100日評価」が明らかにしたのだと思うのです。
聞き手:インターン 池田真歩( 東京大学)
投稿者 genron-npo : 16:49 | コメント (1) | トラックバック
2009年1月 1日
日本こそ「根本的な変化」が必要 認定NPO法人 言論NPO 工藤泰志

2009年 新年あけましておめでとうございます。
新しい年、世界では経済危機の影響が広がり、アメリカでは1月20日にオバマ大統領が誕生します。歴史的な危機への対応と新しい秩序に向けた変化。その世界的な大きな流れの中で、私がこの新しい年に思うことは、日本の政治にこそ「根本的な変化(チェンジ)」が必要だということです。
私が、日本の政治に「根本的な変化」が必要だと考える最も大きな理由は、今の日本の政治、あるいは政治家が、今ある危機に誠実に対応する意思すら欠いていることです。
つまり政治が機能していない。その象徴が、世界的な危機が日本経済に直撃する中で国民を代表して取り組むべき国会が、「言論の力」を失っていることです。
昨年末、言論NPOは「今回の危機対応と日本の政治」に関して多くの有識者と議論を行いました。そこで議論になったのは米国の議会と日本の国会の対応の違いです。
アメリカではこの危機で時間が迫る中でもあれだけの政策を総動員するプロセスの中で、なぜ金融危機が起きたのか、その間の経済政策にどんな間違いがあったのか、誰がどういう責任を負っていたのか、自動車のビッグ3については経営者を議会に呼び出し説明責任を問い、それを国民に示した上で政策の意思決定をしました。
この未曽有の経済危機に関しては、行き過ぎた金融主義やブッシュ政権の危機対応の失政の問題があるにしても、政治そして議会が課題解決に強い意志で向かい合う姿勢は、日本の政治とは比べものにならないほど誠実で民主統治の規律に基づくものです。
政治の緊張感ある行動が国民の政治への意識を変えていく
新しい年、そのアメリカではオバマ新大統領が強力な布陣でこの危機に臨む態勢を整え、圧倒的な国民が彼とともにこの困難の解決や、行き過ぎた資本主義によって失われた民主主義を市民のもとに復権させること、で合意もしています。
もちろん、その前途は厳しい。ただ、今の日本の政治と比べるとその取り組みの違いにがく然とするほどの差を感じます。かつては金融危機に取り組んだ日本もこの歴史的なグーロバル危機が日本に及んでも被害者であり、ある意味で他人事なのです。
では、日本の政治や国会はこの危機にどう向かい合ったのでしょう。
経済危機の日本での展開は年末の間際に派遣労働者の解雇という雇用調整となって本格化しました。その最中に先の国会で唯一行われた党首討論は「なぜ補正予算を出さないのか」という話だけで45分が終わってしまいました。
政府は「生活防衛のための緊急対策」を出し、解雇された労働者の住宅確保などの相談窓口の受付や事業者への助成金や地方への財政支援などを公表しましたが、その対策の内容がこの国会で専門家を呼び、集中して議論されたわけではありません。
この危機の構造を徹底的に議論し、定額給付金なども含め財政政策を出動させるのであれば、97、98年の小渕内閣の財政出動がどこまで効果がありどんな限界があったのかということを、当時の政策に当たった人たちを呼び出して徹底的に検証する。企業や金融支援の内容や企業の内定取り消しや派遣労働の解雇の実態を国会で国民に見える形で議論を行う。
さらに言えば、私は雇用調整が本格化する中で社会の不安を抑え込むには、個別の企業や労働組合任せにするのではなく、経団連や連合といったナショナルセンターが雇用のワークシェアリング(注)での合意を進める段階にきていると考えます。短期には賃金の一定の抑制と労働時間の抑制をする代わりに企業は雇用を保証する。そのためにこそ政府は動くべきなのです。
そうした政治の緊張感ある行動が国民の政治への意識を変えていくのです。が、残念ながらそうした議論や行動は、国会や政治の舞台において与野党ともにほとんど見られず、直近の選挙対策と自民党内の混乱に追われたままの状況下で、首相も暦通りの正月休みを取ってしまいました。
さらに、テレビの討論番組では、生活保護の申請が適切に受理されていないと指摘するNPO関係者に、「そういう実態があるなら報告すればいい」と開き直る政治家までみられます。
注:ワークシェアリング(work sharing)とは、「雇用機会、労働時間、賃金の組み合わせを変化させることで、一定の雇用量を、より多くの労働者の間で分かち合うこと」であり、雇用の維持・創出のための手段のひとつです。80年代から積極的に導入してきたオランダでは、政労使間の合意によりフルタイム労働者とパートタイム労働者の均等待遇を実現し、パートタイム労働者への労働のシフトを進め、失業率の低下を実現したとされています。
健全な政治姿勢への期待が、社会に届かない風潮
国民の間に広がる生活の不安に対して、日本の政治はどうして陣頭指揮に立って取り組まないのか、と私たちは疑問を抱かざるを得ません。
年末の言論NPOの議論に登壇していただいた齊藤誠教授(一橋大学大学院経済学研究科 (マクロ経済))が述べた言葉にとても重く感じるものがありました。
「企業の場合、倒産するかもしれないというときに経営者がやるのは、給料も何もかも返上して陣頭指揮に立って、従業員とともに経営の難局を乗り越えることです。ここ数年で日本経済が調整に迫られるマグニチュードはかなり厳しく、この一年の日本経済は調整が迫られる。国民にもこれから非常に強い負担を強いていく時に、そういう現実や現状を国民一人一人が受け入れられるように、政治家が言葉や態度で示すべきではないのか」
齊藤教授は、麻生首相は冬のボーナス300万円を返上し陣頭指揮に立つ段階では、とも述べていましたが、そうした健全な政治姿勢への期待が、社会に届かない風潮にこそ今の日本の問題があるのです。
危機は全てがマイナスとなるわけではありません。今回の緊急対応に真剣に向かい合えば、日本経済はいずれ、中国などアジアの先行する回復を元に高い水準で底を脱する可能性はあります。それだけではなく、健全な危機感があるからこそ、それをばねに危機後の日本の社会の在り方、ポスト危機における世界の中での日本の対応を議論ができるのです。ただし、それが可能なのは、日本の政府や政治への信頼の回復が前提なのです。
国民全体に向い合えない「分断された日本の政治」
私が今の日本に「根本的な変化」が必要と考えることには、もうひとつ大きな理由があります。すなわち、今の日本の政治は国民やこの国の未来に向かい合うよりも、自分の支持者や支援者の利益を守ろうとしているのであり、国民が直面する危機を他人事だと考えている、あるいは全てを政局の枠組みの中でしか構想できなくなっているという点です。
こうした現象は政治だけの問題でもありません。派遣労働者が組織的に解雇され、内定の一方的な取り消しが相次いでも経済界も労働界からもまだ目立った発言がなく、広告の減少を意識する多くのメディアもこうした現実に正面から向かい合うことができないでいます。これは、資本、労働、メディアという日本の社会を構成する主要な部門がそれぞれ分断され、国民、あるいは公(おおやけ)に対して持つ深い責任意識や社会的な機能よりも、この危機から自分のあるいは自分に関係する利害だけを守れば、あとは傍観者として装うという態度が顕著になっているからではないでしょうか。
目前に起きている社会問題を自らの問題として捉え考える社会性を失いかけ、この問題に関係者がひとつになって取り組むというよりも、むしろ個別の利害を追求するという構造から抜け出せないでいる。こうした構造が、国民全体に向い合えない「分断された日本の政治」を作りあげているのです。
有権者自身が変わらなければ、日本の政治も変わらない
2009年、世界はこうした日本とは異なる方向に向かっています。「分断された社会を一つにまとめ危機への対応と国の未来に向かう」という動きと、「公(おおやけ)の問題にも個人が自分の問題として向かい合う」という動きです。そうした市民側からの民主主義の復権の動きは、アメリカのオバマ現象だけにとどまらず、この日本でも問われているのだと私は考えます。
市民は政治的には有権者として、経済主体としては消費者として存在しています。有権者や消費者が、今の状況を自分の問題として向い合い、強い対抗力を作り出せれば、今の政治の状況を変える力となるからです。
作年末、私たちは「麻生政権の100日評価」という緊急アンケートを行いました。そこで浮かび上がった結論も「変化」でした。詳細な内容は1月6日に公開しますが、政権交代はあくまでもそのきっかけに過ぎず、多くの人は日本政治の「根本的な変化」を求めていたのです。
新しい年、日本の政治は政権交代に留まらず、それぞれの政党を作り直すくらいの変化が、問われなくてはなりません。この国の政治が変わらなくては、日本は未来を失う、それくらいの危機感が私にはあります。
その中で、私たちが考えなくてはならないのは、こうした日本の政治を許している有権者自身にも大きな責任があるということです。つまり有権者自身が変わらなければ、日本の政治も変わらない、と思うのです。
有権者自体が、自らの利益だけを優先し変化に向かい合わないとしたら、抵抗勢力は国民ということになってしまいます。そうではなく、社会や政治の問題を自分の問題として捉え考えることが私たちに求められています。有権者自身が新しい政治に向けて変化を求める、そうした強い市民社会が、この国には必要なのです。
「言論の力」にこれまでにも増して問われる決定的な責任
私はこの国の「根本的な変化」のためには、「言論の力」がこれまでにも増して大きな決定的な責任を持っていると思います。
そうした自覚をもとに、言論NPOは新しい年、この国に、市民社会を主体とした強い民主主義を作り出すため、そして「根本的」な変化を求めて、本気で議論を挑み続けます。