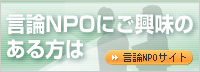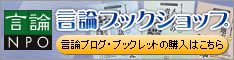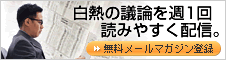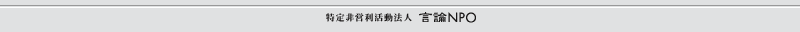2009年8月27日
今の日中関係は民冷官熱 ―日中世論調査記者会見を終えて
|
今の日中関係は民冷官熱 |
投稿者 genron-npo : 22:42 | コメント (0) | トラックバック
2009年8月24日
総選挙最終盤、工藤が語ります
|
2009 総選挙最終盤、工藤が語ります(1) 聞き手:田中弥生氏 (大学評価・学位授与機構准教授) |
|
2009 総選挙最終盤、工藤が語ります(2) 聞き手:田中弥生氏 (大学評価・学位授与機構准教授) |
衆議院選挙前半戦をどう見るか
田中: 18日に公示が行われて、選挙戦も後半戦になっています。8月12日に党首討論が行われて、この間、どんな議論が行われてきたかをメディアを通して見ていましたが、あのときの物足りない議論から変わっていない感じです。にもかかわらず、もう選挙の結果は出てしまっているような報道が行われています。投票までの期間が長いということもあるかもしれませんが、若干腑の抜けた感じがしてならないのですけれども、工藤さんはどのようにお考えになっていますか。
工藤: 確かに、私は12日の党首討論を見て、マニフェストを書き直してほしいと思いました。つまり、今の政党が出しているマニフェストは政策体系として説明不足だし、日本の未来を語っていないと。しかし結局、マニフェストは何も変わらなかったですね。一部民主党のマニフェストが2、3点追加されましたけれども。政策体系として国民に何を説明して未来をどう描くかということでは全く変わらなかった。党首の発言を見ていても、1カ月前と同じことをただ繰り返していますね。しかも、テレビを見ていると他の番組でも同じことしか言っていないので。ひょっとしたら、政策を有権者の疑問や関心に合わせて進化させて国民に答えるという感覚が、日本の政党にはないのかなと思いました。
各党間の議論は停滞したままで、政策としては同じことが繰り返し発言されています。やりとりを見ていても、言葉のレトリックだけで、本質的なことに関しては何も明らかにしていない。これでは、歴史的な政権選択、未来を問うような選挙としては迫力不足というか、無責任です。田中さんがおっしゃったように、メディア報道でも民主党大勝みたいな話になっていますから。「この選挙は何なんだろう」と、戸惑っている人も多いのではないかと思います。
田中: そうですね。本質的な問題については答えを出しきれず、マニフェストの内容と違うような発言もちらほら出ている。工藤さんが当初からおっしゃっている「未来を選択する」ための政策あるいはビジョンについては何か進化されたようなものは発見されましたか。
政治が説明すべき4つの課題とは
工藤: ないですね。私はひょっとしたら日本の既存の政党は未来を語らないのではなく、語れないのではないかと思いました。
それほどバラマキのような支出計画と、その財源に、話が集中している。新聞を見ていても「将来ビジョン」とか「目指すべき社会のあり方」が説明されていないとされていますが。では日本の政治が何を国民に説明すべきなのか、メディアは指摘しきれていません。
私は評価を行う立場から見ると、最低4つのことがマニフェストに書かれないといけないと思っています。
ひとつは、小泉改革の総括をきちんとしないといけない。改革路線を継承しなくてもいいわけですが、継承しないとすれば、日本の経済構造を変えるためにどういうプランを出していくのかを語る必要がある。継続するのであれば、格差拡大などの歪みが出てきているわけですから、それらにどう対応するのかということに加えて、政府として国民に保障すべき最低限のサービスをどれだけ行うのかということを語る義務があります。
2つ目は社会保障の問題です。少子高齢化の中で急増する社会保障の財源をどうするのか、制度設計をどうするのか。民主党も、最低保障年金を制度化すると言っていますが、新制度になるのは20年先の話なので。ではその間は今の制度をどうするのかを説明する必要があります。今の年金制度は結局、若い世代の未来に負担を先送りして、世代間格差を拡大し続けているわけです。財政が抱えている、国債の累増問題も同じです。今の課題解決を避けるがために、つまり負担の問題を国民に説明しないために、将来世代に負担をどんどん先送りしている。こういう問題をどう考えるかが、2つ目ですね。
3つ目はアジア、特に中国の台頭を含めて、アメリカの経済危機から世界が大きく変わっている中で、日本は国際社会でどういう役割を果たしていくのかということです。今年来年、日本はGDPで見ても世界第3位に落ちていくと思います。マラソンのレースでも同じですが、上位争いは常に映像で流れるけれども、落ちていくと日本がそこから外れてしまう、そういう時代になってきます。では日本は国際社会で何を目指していくのかと。これら3つはどうあっても説明するべきでした。
それから、4つ目に大事なのは、国民に対するメッセージのことです。アメリカの大統領選挙を見ていて感じたのは、オバマ大統領のメッセージ力の強さでした。それが日本の政党にあるのかというと、全くないですね。いろんなサービスを提供するという話はあっても、日本の将来に向けて何を国民にしてほしいのかという呼びかけがない。しかし、オバマ大統領は語ったわけです。アメリカは未曾有の経済危機の中で間違いなく将来が見えない。しかも過度な競争社会の中で格差が発生し、社会の土台になるつながりも分断されてしまった。その中でもオバマ大統領は、「みんなで一緒にこの危機を乗り切って新しい社会を建設しよう」そして「私たちならそれができる」と呼びかけたわけです。
これは間違いなく民主主義の復権のメッセージでした。国民と一緒に時代を変えるという呼びかけには、ショックを受けるくらい感動した人もいっぱいいたと思います。
今回の日本の選挙を見て、日本も同じように未来が全く描けないという状況の中で、政治は何を私たちに呼びかけているのかと。それが全くないですよね。私たちも、そういう呼びかけが選挙戦の中でどんどん出てくるかなと思って期待していましたが、議題として出ているのはそういう話ではなくて「財源は大丈夫か」とか、官僚の話とかムダの話とか、サービスの競争とか、そういうことばかりなので、こんなことで日本の将来は大丈夫なのかなと。率直に言って、私は心配な気持ちなのです。
田中: 4つの課題というお話がありました。「大きな政府」「小さな政府」というのはもう時代遅れだという批判もありますけれども、政府というのはどこまで公共ゾーンを担って―シビル・ミニマムと言っていますが―そしてそれ以外のところの公共ゾーンを誰がどういうふうに担っていくのかと。それは非常に保守的なものなのか、あるいは個人の責任と自由に任せる社会像なのか。それは今のマニフェストからはとらえきれないし、ましてや党首討論を聞いていても、そのあたりが全然出ていないですよね。
このまま選挙が終わってしまっていいのか
工藤: 私たちはこれまで5回、評価を行ってきましたが、民主党のマニフェストを見てみると、これまでの岡田代表や菅代表時代のマニフェストではまさにそういうことが書かれていました。目指すべき社会像、それから理念、ビジョンがあった。自民党も「美しい国」など、わかりにくさはありましたが、小泉マニフェスト以来、ビジョンから政策体系まで、描ききろうという意欲があった。しかし今回の選挙を見ると、政策立案のための時間が十分にあったにもかかわらず、マニフェストとしては非常にお粗末なものが出てきました。単なる支出計画のようなものを競っているような状況ですから。そうではなくて、政治が今の日本の何を解決したいのか。目指すべき社会に向けて、現在の課題を分析してその解決策として出すのがマニフェストのはずです。たとえば子育ての対策であれば、現物のサービス給付あるいはお金の直接支払いも含めて、どういう目標で、子育てを応援する社会をつくっていくのかとか、具体的なビジョンなり政策体系が示されていない。それが語られずにひとつひとつの支出計画で、「うちの党は子育て手当がこうだ」とかいう話になってしまっている。
本来マニフェストというのはそういうものではなくて、政策の目的や全体像、体系を示すことが重要です。オバマ大統領はアメリカをいつまでにどう変えていくのかを国民に具体的に示し、さらに一緒に危機を乗り越えていこうと呼びかけた。そういう問いかけが、日本では全くない。このまま本当に選挙が終わってしまっていいのだろうかという感じがありますね。
田中: 支出計画という言い方をされましたけれども、政府が何でもサービスを提供してくれる社会なのか、私たちが自分のことは自分でやっていかないといけない社会になるのか、そのあたりが、個別の政策を見ていても、どっちなんだろうと。見えてこないですよね。
工藤: 今の田中さんのおっしゃったことで言うなら、日本の政治はぜひそういう説明をしてほしいですね。全ての政党の公約を見ると、選挙という事情もあるのですが、政治が何でもしてあげるという話になりがちです。
でも社会保障の機能強化に向けて政府が責任をもつという社会もあるわけです。ただその場合は、負担の議論を政治は避けてはいけない。自分でやれというのであれば、では政府の役割は何か。政府は最低限何を行うのかと。どちらも説明不足です。これでは、国民は自分たちの将来について安心できないし、日本の政治がどういう進路を描こうとしているかわからないわけです。
私は政権交代に反対というわけではありません。国民は本格的な変化を求めています。しかし、政権交代はあくまでも手段であって、政権交代の結果、どういう社会に変えていくのかが大事です。そのための合意の形成こそ、選挙の中で行われるべきなのです。政治の約束が有権者との間で問われる。そういう緊張感のある政治に変えていかなければならない。今回の選挙がその第一歩だとするならば、日本の政治を本当に変えていくためには、有権者自身が、日本の未来を自分たちで考えるという覚悟を固めないと本当の政治の変化は始まらない、と思います。そのためにも、いい加減な約束を見抜けるような眼力が、有権者側にも求められている。
今回の選挙は「変化」への第一歩
田中: 変化とおっしゃいましたが、「チェンジ」という言葉は、日本でも特に政治家の間で流行っている言葉だと思いますけれども、目指すべき将来像があっての変化ですから、まだそこまでには至っていないということですよね。
工藤: そうです。言論NPOは今年初め、麻生政権の100日評価を行った際に、有識者を対象にアンケートを実施しました。その結果を最近思い出したのですが、「今の日本の政治状況をどう考えているか」という質問に対して、最も多かったのは「既存政党の限界がはっきりし、新しい政治に向かう過渡期にある」という回答で、半数以上ありました。
それから「政権交代によって日本の政治を一度壊さないといけない」という回答も半数近くありました。つまり、今の2つの政党の中で、「片方がだめだからもう片方」という二大政党が実現しているというような判断はほとんどありません。私は、この有識者の声が今の日本の政治状況を見事に説明していると思います。今回の選挙で政権が変わってもそれは始まりに過ぎないのであって、これから日本の政治がどう変わっていくかということが問われる局面になっていると思います。
そのときに一番重要なのは、私は今年の正月に「日本の根本的な変化が必要だ」と言いましたが、そうした変化、つまり「チェンジ」を行うのは有権者だということです。有権者なり市民が、自ら未来を選択して政治を判断するというふうに頭を切り替えないといけない。政治が提供するものをただ選ぶというだけでは、政治は変わらない。
日本の未来が問われているときに、政党がサービスだけを競っている。これでは、政治家は「有権者はサービスにしか関心がない」と考えているとしか思えない。
つまりサービスしか票にならない。しかしサービスには必ず負担があります。それを明らかにしないで、「今回の選挙では負担は言わなくていい、将来世代が考えればいい」というのでは、有権者がバカにされていると言っていいと思います。
有権者も、そうした扱いでいいのかどうかを考える必要があります。自分たちで自分たちの未来や国の未来を判断できるような力をつけないといけないし、そういう気迫が日本の政治を強くしていくのだと私は思っています。
田中: そうすると、「サービスはおねだりをするけれども負担はしたくない」というのではまさに55年体制から変わっていないということですから、それは政治家も発想が変わっていないし、有権者も下手をするとそこに引っ張られてしまうということですね。
問われているのは日本の民主主義
工藤: 私が気になっているのは、日本の政党は民主主義の弱いところを微妙に突いてきていることです。それを日本のメディア報道があおってしまうという構造もある。民主主義の弱さというのは基本的に、選挙が人気投票になってしまう可能性があるということです。でも政権選択の歴史的な局面で、人気投票の域から出られない政治でいいのか、ということを考えないとならない。
人気を得るためには、負担よりもサービスのほうがいい。だから負担の問題を隠してしまうのです。それから、誰か敵をつくり、それをあおることで人気を得ようとする。日本の官僚主義というのは、確かに目に余るものがありますが、官僚だけを批判すれば何かが変わるわけでもない。既得権益を改善するなら、政官財、全てのしくみが問われることになります。政党のあり方、業界と族議員との関係、政治とカネの問題、官僚の天下りの問題、全てが日本の政治の中では、まだ構造化している部分が残っているのです。
でもそういうことを抜本的に変えるために政党が競おうとしているわけではない。ただ、官僚の天下りを問題にしているだけです。
2005年の選挙のときも小泉劇場というものがあり、刺客を送ったりしていました。あのときと同じような選挙のパターンになっているところが今もある。
つまり民主主義の弱さが突かれているわけです。でも、そういうところで決まる民主主義は非常に薄っぺらです。もっと強い民主主義をつくらないといけない。政策をきちんと見て判断して、有権者が日本の政治を変えていく。それがマニフェスト政治の眼目だったわけです。
今回の選挙は、日本の未来にとっての第一歩にすべきです。そのためにも、この選挙を、日本の民主主義をもっと強いものにしていく契機にしなくてはならない。選挙まであと一週間。日本の政党には日本の将来の課題から逃げないで説明してほしい、のですが、本当に問われているのは私たち有権者自身の方だと、私は思っています。
私たちはこの国の未来から逃げられるわけではない。そうであるなら、有権者が日本の政治をもっと良いものにしていかないといけないわけです。日本の政治を本当に変えるには、そうした覚悟が必要だと思います。これからまたこの一週間で政治の議論は進化していくかもしれませんが、この間の選挙戦を見て痛感したのは、そういうことです。
田中: 有権者自身も力をつけないといけないということですね。
工藤: 有権者がこれからの未来を決めるのです。だから私たちはこの時代から逃げてはいけないと痛感しています。このような状況では、どこの政党に投票すべきか、内心悩んでいる人も多いと思います。しかし、この一票から始めるしか方法はないのだと、私は考えています。
田中: 今日はありがとうございました。
(文章は、動画の内容を一部編集したものです。)
投稿者 genron-npo : 01:37 | コメント (0) | トラックバック
2009年8月21日
「未来選択」サイトについて
|
マニフェスト評価専門サイト「未来選択」について 聞き手:田中弥生氏 (大学評価・学位授与機構准教授) |
マニフェスト評価専門サイト「未来選択」について
田中: 言論NPOでは来る選挙を前に「未来選択」というマニフェスト評価専門サイトをオープンさせました。私も拝見させていただきましたが、今回の評価だけではなくて、小泉政権のマニフェスト評価と実績評価、そして安倍・福田・麻生政権に至るまでの評価が政策別に閲覧できるというものでした。多くの有権者が、今回の選挙ではマニフェストを参考にして投票したいと言っていますが、このサイトをどのように活用すればいいでしょうか。
工藤: マニフェストを評価するには、2つの視点からマニフェストを読み込む必要があります。
ひとつはマニフェストが約束としての体裁を整えているのか、ということです。これを私たちはマニフェストの「形式要件」と呼んでいます。
ここでよく話題になるのは数値目標です。実現すべき目標がスローガンのようで具体的で明確でないと、約束としてそれが実現したか、判断できません。だから、明確な目標は約束にとっては必要な条件となります。
ただ、ここで気をつけるべきなのは、数値目標だけでは、国民との約束としては十分ではなく、むしろばら撒きリストに変わってしまう「落とし穴」があるということです。
私が今回の選挙で、これはまずいな、と思ったのは、その政策の目的が明らかにされないまま、様々なサービスのメニューやサービスの目標だけが競われた結果、マニフェストが国民との約束というよりも、単なる支出リストに変わってしまったことです。
支出には当然、その財源が必要ですから、選挙戦ではその財源がどうかということについて、激しいやりとりがありました。しかし本来は、何のための政策なのか、つまり目的を明らかにして、そのうえでその目標や政策手段がどうなるのかということを議論すべきなのです。
マニフェストがなぜばら撒きのリストに変わるのか。ここで明らかになったのは、マニフェストには数値目標だけではなく、政策としての体系性が必要だということです。では約束の体系性と何なのでしょうか。
言論NPOでは5年前に評価を開始してから、約束としての形式的な要件を満たすものとして、5つの評価項目に沿って、点数を分野別に公開しています。今回の「未来選択」サイトにも、それがしっかりと書かれていますので、そのチェックからしてみてはいかがでしょうか。
私たちが評価項目として採用しているのは、まず①なぜその政策が必要なのかという目的や理念が説明されているのか、ということ。そして、その目的を実現するための②目標とそれを実現するまでの③期限や工程、さらにそれを実現するための④政策手段や⑤財源が書かれているのか、の5項目です。それらの政策の体系がそろって初めて、マニフェストが約束として十分なものとして判断できるという構成なのです。
田中: 具体的に説明してもらえますか。
工藤: たとえば民主党は、高速道路の無料化や揮発油税の暫定税率の廃止を掲げました。
高速道路の料金が下げる、暫定税率をなくすという約束は具体的だし、その約束が実現できたかという結果は測定可能なものです。その点では目標は明確だと言えます。
しかし、この2つの政策の目的は何なのでしょうか。料金などの引き下げは車の利用者にとっては朗報ですが、車社会に優しい政策は環境にはマイナスになります。
また高速道路が料金収入で、過去の債務を負担している、ということを考えると、料金を下げた分は、租税でその穴を工面する、ということです。
でも環境上ではマイナスになること、さらに負担は納税者に肩代わりされるのに、それをマニフェストで触れないばかりか、それでも無料化などを行なう理由を説明できてはいません。ただ、無料化すること自体が目的なのです。また、暫定税率をなくすといっても、必要な道路はつくると言っています。
自民党のマニフェストも同じようなものです。料金を1000円にするということで無料ではありませんが、その根拠と財源の説明はありません。
マニフェストでは明確な目標が書かれてはいますが、政策の目的や財源が体系的に説明されないために、単なるサービスリストになってしまう。これを、約束に基づいたマニフェストと呼んでいいのか、という問題があるのです。
ここまではマニフェストの約束としての体裁に関する形式的な評価を説明しましたが、私たちは実は、こうした形式的な要件だけでマニフェストの評価を行っているのではありません。
より重要なのは中身を吟味する、つまり、政策としての妥当性を判断することです。つまり、マニフェストを体裁ではなく、実質的に評価するということになります。
ここにもいくつかの評価基準があります。「未来選択」では各政策分野の評価が、評価項目に沿って、説明されています。
その中のひとつに関して簡単に説明しますと、マニフェストに書かれる政策は、日本が抱えるそれぞれの分野の課題に対する解決策を提起していないと、約束にはならないということです。そのためにはまず、現状や課題をどう認識するのかを明らかにする必要があります。それが間違ってしまうと、課題解決の処方箋以下が、全て間違ってしまうということがあり得るからです。
マニフェストを評価する以上、評価する側が、その課題をどう認識しているのかを明らかにしたうえで、その政策の妥当性を判断する必要があります。
この妥当性も基準を明らかにした上で評価をしています。例えば、政策目標と手段の整合性や、目標自体がその課題解決としてふさわしいのか、などかなり専門的な視点がそこでは必要になります 。
その点で言えば、「未来選択」はまず政策を評価するにあたっての「視点」を明らかにし、そのうえで評価の結果を公開しています。
つまり、言論NPOの評価は、政策の背景がよくわかるようになっているのです。背景を理解したうえで、皆さんも一緒に評価を考えてみよう、という構成になっているわけです。
田中: ただ、政策の背景を分析するためには、その分野に関する専門的な知識がかなり必要になると思いますが。
工藤: 言論NPOは約30分野の政策評価をやっていますが、各分野に日本を代表する専門家、学者などが評価委員として参加しています。委員のコメントもこのサイトでは同時に公開しています。同時に、私たちは政策を政党とか、霞が関の実際に政策をつくっている人たちとも議論をしています。討論会や座談会の様子も公開しています。つまり評価結果だけではなくて、そのプロセスもわかるようになっていますから、より深く政策の中身を理解できると思います。
田中: 専門性や信頼性が高い、のみならず、ある意味でいろんな方々の参加によるサイトになっていると言うことができますね。そういう意味では、サイトをご覧になった方々の中にも、何らかのかたちで参加したいと考える方も出てくるのではないかと思いますが。
工藤: 私たちは今後のオープンなフォーラムを何度かやっていきたいと考えております。マニフェスト評価というのは選挙の前にやるだけではなくて、選挙が終わった後も、その政策が実行できているかということをきちんと監視していくことが必要なんです。だから私たちは毎年、年間を通じて、このマニフェストに関するフォーラムや勉強会など様々な企画をつくっていきますので、ぜひご参加いただきたいと。それだけではなくて、私たちはこの評価結果を、メールマガジンなどを通して配信していきます。その中で皆さんの意見をいただいたり、疑問に対しては可能な限りこの評価サイトの中で答えていきたいと思っています。双方向でできるしくみを整えていきたいと思っていますので、活用していただければと思います。
田中: まさに、有権者のエージェントたりうるところだと思います。頑張ってください。ありがとうございました。
(文章は、動画の内容を一部編集したものです。)
投稿者 genron-npo : 10:47 | コメント (0) | トラックバック
2009年8月13日
党首討論を傍聴して ―党首は本気で未来を説明してほしい
|
党首討論を傍聴して 聞き手:田中弥生氏 (大学評価・学位授与機構准教授) |
投稿者 genron-npo : 10:41 | コメント (0) | トラックバック
2009年8月11日
両党ともマニフェストを作り直すべき
|
マニフェスト検証大会で工藤は何を言いたかったのか-1- (全5分7秒) 聞き手:田中弥生氏 (大学評価・学位授与機構准教授) |
|
マニフェスト検証大会で工藤は何を言いたかったのか-2- (全8分9秒) 聞き手:田中弥生氏 (大学評価・学位授与機構准教授) |
投稿者 genron-npo : 07:38 | コメント (0) | トラックバック
日本の政治は未来を競っていない
私たちのマニフェスト評価の作業は、有権者に選挙の際に一つの判断材料を提案したい、ということで6年前から始めています。
そこにはある目的があります。政治に何でもお任せするような政治ではなく、有権者が政治を自ら選んで判断していくような、強い民主政治を作りたい、という強い思いです。
この気持ちが、言論NPOが真っ先に取り組んだマニフェスト評価の原点にあります。
そのために私たちの評価は、あくまでも「国民との約束」にこだわっています。政治が国民に提案する公約が約束としてふさわしいのかを、形式や実質の二つの側面から八つの評価基準を用いこの7年の間に5回にわたって評価してきました。特に、今回はその評価作業をオープンにするため、10分野で自民党と民主党の政策別討論会を事前に開催する中で、評価作業を行いました。
今回、まとめた報告書は、これまで言論NPOが公開したものと若干異なります。八つの評価項目に対する点数もすべて公開しております。
全ての作業結果を公開しようと考えたのは、日本のマニフェストが一つの転機を迎えていると判断したからです。
マニフェストは確かに有権者との約束にふさわしいものです。しかし、その体系性なり課題解決の本質的な議論が抜けてしまうと、それがばら撒きのリストに変わってしまう。その危険性を私たちは感じました。
そのために今回は、言論NPOがどのような基準で、またどのような課題認識で評価を行なっているのかをすべて皆さんに公開し、評価項目ごとの具体的な評価の点数も公開して、皆さんの判断を仰ぐことにしたのです。
約束としてはどちらも「不合格」
今回の自民党と民主党の評価は、自民党が100点満点では「総合点」で36点、民主党が31点になりました。
これはかなり低い数字ですが、ただ2年前の07年の参議院選に時にも私たちは自民党に26点、民主党に27点をつけましたから、今回が特別低い評価ということではありません。
この総合点は、「外交・安全保障」から「政治とカネ」まで17分野の個別の評価点数の平均点がその基礎にあります。
ただし、17分野の点数を積み上げた合計の単純な「平均点」は自民党が36点で民主党は27点に過ぎません。
この「総合点」と「平均点」の違いは、総合点には「マニフェスの策定手続き」というマニフェストの立案過程に関する評価を加え、そこに20点の配点をして100点としたため、「総合点」では点数が少し動いたということです。
この30点前後という評価をどう判断するか、ですが、これは約束として体をなしていない。どちらも不合格だと私たちは判断しています。
しかも今回は、政権交代という歴史的局面の中での選挙です。それでも政権を判断するための約束に信頼をもてない、これはきわめて深刻な事態だと私は考えています。
日本の政治が国民との約束を大事に考えるというのならば、私は2年前と同じことを今回も言うしかない。「マニフェストを作り直してほしい」ということです。
評価はなぜ厳しいのか
では、なぜここまで評価が低くなったかということです。
これには三つの要因があります。まず、この二つの党のマニフェストは、約束としての形式的な物差しで見ると、今回も非常に大きな問題があったということです。例えば、目標の数値基準なり期限は約束としてとても大きな要素ですが、それが明らかな政策項目は今回の自民、民主のマニフェストはそれぞれ15%、13%しかないわけです。
つまり約束の形になっていない。しかも、マニフェストそのものが、その政策の目標、手段といった体系性を持っていない。そのために約束としての形式を判断する形式要件で点数がとても低くなった。
次に、マニフェストそのものが日本の直面している課題の解決に対して、具体的な約束になっていないという問題があります。依然、内容はスローガン的で、特に外交問題のあたりは交渉の「心構え」みたいな言葉で語られている。これは、全く約束と言えません。
最後に、マニフェストの策定にも大きな問題がありました。このプロセスは非常にわかりにくいものですが、私は、マニフェストの作成は、党内の党首選挙からそのドラマが始まっていると考えております。
つまり、党内がマニフェストの作成または決定に関しては一丸となって支持し、その実行に関しては首相なり党首が全責任を負うという形になっていなければ、策定過程に問題があるといわざるを得ません。
しかし、自民党に関しては、マニフェストの作成が遅れ、党内では途中まで自分のマニフェストで戦う、という人たちがいました。麻生首相の姿はマニフェストの中で非常に限定的です。つまり選挙を経て、政権を得たときに誰がこのマニフェストの約束を実現するのか。そのメッセージが国民に伝わらない構造になっています。
民主党は鳩山代表が党首選で掲げた「友愛主義」はマニフェストの骨格になっていません。しかも、マニフェスト自体の政策がアメリカとのFTAの問題のように、重大政策でありながら反発が高まると後から変更になる。これでは、党内におけるマニフェストを軸とした政策決定のメカニズムが確立しているか、かなり疑わしい。
党内でマニフェストを決定し、それが政権公約になり、国民の信を得てそれを実行するというのがマニフェストのサイクルです。
党内の政策の決定メカニズム、つまり党内のガバナンスに問題があるとすれば、どんなに政治主導の制度を整えても、約束の実行に問題を生じる可能性が高い。それを私たちは考慮しました。
評価基準に従ってマニフェストを評価する
今度は言論NPOの評価基準に基づいてマニフェストを見てみます。私たちのマニフェストの評価体系は、「形式基準」と「実質基準」の二つで評価を行なっています。
形式基準とは、内容が約束として認められるような要件を備えているか、を問います。これは数値目標などの測定可能性だけではなく、内容の体系性が問われます。
その課題になぜ取り組むのか。目的や理念など、明確な目標をどのように実現するのか。それが体系的に語られないと、これはまずいわけです。
しかも、マニフェストは現在の日本に問われた課題解決の設計図になっていなければなりません。
この場合は現状や課題の認識が決定的に重要になります。この認識を誤ると、課題設定ができないために、政策自体が意味を持たない、状況を更に悪化させてしまうということがあります。
つまり、言論NPOの評価は、課題認識に裏付けられた政策目的と成果、つまり政策を実行したことで社会にどのような影響をもたらしうるかを求めるもので、その判断の上に立って、私たちは課題解決の政策手段の妥当性を判断し、その実効性を判断しているのです。
こうした評価を皆さんに理解していただくために、私たちは今回の評価書の中に、言論NPOが考えているその分野の課題認識を参考資料として全部つけました。私たちが設定する課題認識のソリューションのスペースの中で、政党がどのような解決策を国民に提示できるか、そこまで踏み込んでいかないと、実質的なマニフェストの評価はできないと私は判断しております。
その上で言わせて貰いますと、まず形式的な問題としては、先ほどから言っているように、二つのマニフェストには共通して体系性がない。数値目標についても不十分です。
ここで私が、特に強調したいことは、体系性を持っていないマニフェストは、ばら撒きリストに変わってしまう可能性があるということです。これは自民党と民主党のマニフェストに共通する傾向ですが、特に今回の民主党のマニフェストに顕著です。
約束というのは問題の課題認識や解決策があってはじめて、その手段として予算や支出があるわけです。それを飛び越えて支出だけを並べて、その財源を明らかにしようとしても、それはあくまで支出の計画表に過ぎなくなる。
これはマニフェストとは全然違うものだと判断せざるを得ないわけです。
言論NPOとしては、例えば民主党のマニフェストが提案している既得権益に縛られたムダを削減し、それを本当に必要な人たちに振り向けることは非常に大事だし、政治に大きな変化をもたらすものだと考えています。
しかし新しく支出するものの内容が政策目的と一致せず、公正なものでないとすれば、それ自体が壮大なムダを創る、壮大なばら撒きになってしまう可能性もあるのです。例えば、民主党がマニフェストで掲げた「子ども手当」や公立高校の実質無料化だけで、年間約6兆円が必要になります。
これは昨年の税収の約46兆円の13%にもなります。
こうした異常な予算の再配分をマニフェストで提案しても、負担の問題は提起していない。それをおかしいと思わない感覚自体、サービス競争がもたらす怖さだと考えます。
そのために私たちは、支出の内容についてもすべて評価基準で判断しなければならないと思ったのです。
個別の政策はどう評価したか
個別の問題に関しても言いたいことはありますが、一言程度にとどめます。まず自民党は、政府で行われている政策を並べているだけですから、体系性があるけれども新しさがない。それからこれまでの実績に伴う総括がない。その教訓をベースにして新しい課題設定ができていない。
つまり、約束のPDCAサイクルが全く働かないまま、マニフェストの作成だけを間に合わせたという内容になっています。
マニフェストは党のカタログではなく約束ですから、国民に約束を提案して、その信を問おうという気迫がないと、今後も政権を継続し、約束に基づいた政治を行なう意志を本当にもっているのか、それを疑われることになります。
個別に言えば、消費税増税とか、財政再建の実行をマニフェストで約束していることは評価できます。しかしこれは、景気回復という仮説の前提条件付きの約束であり、景気が回復しなければこの問題が全部発動しない。
さらに、この景気のために、2年間は経済対策をするという形でマニフェストは主張しており、そうした危機後の出口戦略と財政再建の道筋が整合性をもって語られていないという問題があります。
また、環境、医療、農業などに関しては、利害団体との関係に配慮しているために、抜本的な対策を打ちだせないという問題があります。
これに対して民主党は、個別の政策面では、約束としてかなり新しさを感じさせるものがあります。例えば今回の私たちの評価で最高点を取ったのが、医療の62点でした。ここでは医師不足や地域の医療崩壊という現状認識の下に、その解決のための成果目標を設定して期限と財源を明らかにしています。これはマニフェストとしてはかなり完成度が高いものです。
同じような課題認識でほとんどの政策を民主党が作っていれば、点数はかなり上がりました。しかしそうなっていないところに大きな問題があるわけです。現に、個別の政策では先進性がありながら、マニフェスト全体や他の政策との整合性から政策自体の先進性を失わせている項目はあります。
例えば環境などの問題に関しては、これまでの京都議定書の目的が達成しない理由として、省エネや企業の自主行動計画頼みでは無理だとの判断から、排出権取引市場の創設などを提案しましたが、今回のマニフェストではその導入時期がはずされました。そして、この環境の問題の上位に、暫定税率の削減という、つまり環境政策の目的と相反する車社会のサービスを提供する政策がおかれてしまった。
つまり個別政策にはっきりとした後退があるのに、それに対する説明もない。個別の政策の先進性を、全体設計の中でそれを壊してしまう。
これでは党内における政策の調整、決定メカニズムがばらばらでマニフェスト型になっていないといわざるを得ません。
問われているのは「政党政治」そのもの
今回全体としてマニフェストを見て言えることは、「日本の政党は未来を競っていない」ということです。
日本の課題で最も大きなものは、急速に進行している少子高齢化・人口減少にどう対応しているか。この一点に尽きます。自民党は「安心社会実現会議」の報告書を軸にその骨格をまとめています。課題の設定でその方向は妥当だと判断しますが、公助・共助・自助のバランスを含めた目指すべき社会のあり方を国民に提起できてはいない。
また、年金・医療でも現状の問題の把握が遅れ、結果としては若い世代に負担を押し付け、世代間のギャップを広げることを黙認しています。
これに対して民主党は、少子高齢化の時代にどう臨むのかについて、課題設定自体に問題があります。少子高齢化の社会は、明らかに経済のパイが縮まります。そのパイを広げる経済対策を全く語らないまま、所得の再分配政策自体を自己目的化している。これでは、この対策はつじつまが合わない。
しかも、急増する社会保障費にサービスについては、誰がどのようなバランスで負担するか、その考えを提示していない。これは国家の運営にとっては致命的な問題であると私たちは考えます。
急増する社会保障を租税だけで対応するのはかなり難しい、と私は考えます。自民党が行ってきた構造改革は、問題はありますが、少なくとも自助の割合を増やす為に競争型社会を目指したということができます。しかしその反面、公助の設計が不足しているところに自民党の問題がありました。
自民党は、今回のマニフェストで曖昧な形ではあるが、消費税の増税を一応は提案した。これは、自民党の公助に対するひとつの答えとも言えます。
では民主党はどういう社会像を描いているのか。問題はそれが全くマニフェストに書かれていないことです。
規制緩和など民の成長に関する政策は全く描かれていない以上、民主党は大きな政府を設計せざるを得ない。ではその負担はどう提起したかというと、マニフェストではそれを先送りしている。
むしろ、自らのばら撒き色の強い支出計画を進めるためには、行政には効率化を迫るという矛盾した政策を並べている。
これでは、政策の全体的な設計の甘さがあるといわざるを得ません。年金制度では保険料と税を分ける問題提起は妥当ですが、ではどう設計するのか、答えは出していない。
つまり、自民党、民主党ともに、人口減や高齢化に伴う課題解決に答えを出せないまま、選挙対策でサービスの競争を行なっている。そうだとしたら、これはマニフェストの書かれ方にとどまらず、日本の未来に対してこの二つの政党は「無責任」としかいいようがない。
政治が、この選挙で未来を語れず、そのツケは若者の未来に先送りする、というのであれば、この選挙で問われているのは政権交代ではない。日本の政党政治の信頼そのものではないか、と私は思う。
まだ選挙が公示されるまで時間はあります。自民党・民主党には日本の未来に向けた責任あるマニフェストを再構築することを、言論NPOはこの場で提案したいと思います。
(この文章は、21世紀臨調が8月9日に開催した「政権公約検証大会」での工藤の発言を一部修正したものです)