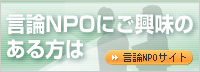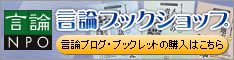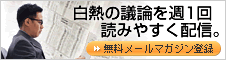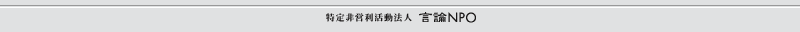2010年8月28日
「第6回 東京‐北京フォーラム」いよいよ開幕
「東京‐北京フォーラム」を目前に、工藤がその意気込みを語ります。
聞き手:田中弥生氏 (言論NPO 理事)
田中: 工藤さん、こんばんは。いよいよ8月29,30,31日と東京-北京フォーラムが、ザ・プリンスパークタワー東京(芝公園)で行われますが、すでに延べ2000人を超える方達が参加されると伺いました。まず、東京-北京フォーラムとはどういうフォーラムなのでしょうか。
工藤: 2005年に中国で反日デモが起こったということをご存知の方もいらっしゃると思います。ちょうど日中の政府関係が厳しい時期に、民間レベルで本当の議論をして、新しい環境を作るために「議論」で何かの力になろう、というためのプラットフォームを作り上げました。
この受け皿が、日本側は言論NPOで、中国側は中国日報社(チャイナ・デイリー)というメディアでした。このフォーラムが普通のフォーラムと少し違うのは、「本当の議論」だということです。僕たちは友好のためというよりも、本当の議論をすることによって、その結果、相互信頼を得ることができるような形の対話のチャネルを作りたかった。それが今回6回目となるこのフォーラムです。
田中: 確かに私も何度か拝聴させていただいているのですが、やはり日中関係は緊張関係が長かったこともあって、お互いに遠慮し、言葉を選びながら、という会議が多い中で、このフォーラムは結構やり合いになるくらいの議論をしていますよね。
工藤: 僕たちは、趣意書に「喧嘩しよう」って書いたんです。つまり、喧嘩ができるほどの関係が重要だということです。実際中国と話してもなかなか儀礼的で本音を話せないのではないかということをいわれたのですが、実際やってみると、中国も結構言うんですよ。だから、日本側の有識者も本当の議論になる。この対話の中から本当に未来を考えなくてはいけないと考えています。
田中: もう少し、具体的なことをお伺いしたいんですが、3日間の会議の内容・あらましを教えてもらえますか?
工藤: 今回は6回目になります。今までの5回は、両国民の相互理解とか関係を強化するという視点が強かったんですが、今回は日本と中国が未来にむかって議論します。中国が、GDPで日本を逆転するといわれていて、中国はかなり大きな国になろうとしているわけです。それに対して中国の国民はかなり自信を強めていて、それに対してかなり日本の国民はそれを不安に思っている人が多いんです。こういう局面において未来を語って、今の課題について解決するためにきちっと議論をしようと考えたんです。
そのために、5つの構成を考えていまして、1つは「政治対話」で、日本の大学生たちの前で、両国の政治家が議論しようという試みです。中国では、李肇星さんや趙啓正さんのような大臣経験者・全人代の外事部の主任クラスの方が参加し、これに対して日本は、加藤紘一さんとか枝野幹事長が参加して、本当の議論をするんですね。
それから、注目している「経済対話」です。日本の経済問題は今かなり深刻な状況ですが、中国の経済力を背景に日本の経済が伸びているというのは事実で、中国は本当にこのまま経済発展するのだろうか。そして、ここには色々な問題があり、それをしっかりと話しあおうと。日本は、山口日銀副総裁が参加し、対して中国も人民銀行の前の副総裁が参加する。あと、起業家も参加しますので、これもかなり本気の議論になると思います。特に今、中国の企業が日本の企業を買収するという状況もあるので、そういうことについて議論しようと。
相互理解という点で非常に関心をもっているのが「メディア対話」で、世論調査でも明らかになったように、お互いまだまだ相互理解が遅れている。日本は報道の自由が無いと思っている人は中国の中にはすごく多い。日本を軍国主義だと思っている人も多い。こういう問題を含めて、メディア報道のあり方を含めた形で日本と中国のメディア関係者が激突します。これはニコニコ動画で完全生中継するのですが、実を言うと会場には中国の若い記者が40人近くいるんですよ。日本も今記者の人達が集まっていまして、会場一体型でかなり本気で議論しようと思っているんですね。
「外交・安全保障対話」では、中国の軍事力を日本が不安がって脅威感を感じたり、中国も日本についてはいろんな意味での軍事的な脅威を感じているということが世論調査では明らかにされています。両国の安全保障とか外交の責任者、有力者が円卓方式で4時間半徹底的に議論しようというものです。日本側は、自民党の石破政調会長とか、民主党は長島さんっていう防衛省の政務官とか国連の明石さんとか、そういう人達が出て、中国側も前の国連大使とかそういう人達が参加します。ここもかなり本気の議論をやるわけですね。
「地方対話」では、地方の首長、日本では京都知事や、溝口島根県知事が参加し、地方の首長が中国と同じように、議論して地域的な交流をきちっとやるための議論をしようと思っています。
今回の議論の特徴は、会場から意見を聞いて、会場参加型の議論をしようとしている点です。さっき田中さんが言ったように、だいたい会場が満杯になります。今までにないくらい参加者の規模が多くて、完全登録制の一般の受付は締めきっています。やっぱり中国が大きく発展していく中で、日本も未来にむけてきちっと議論していかなくてはいけないと。そういう舞台が必要だと思っている人はいっぱいいるということです。
今の日本の政治は未来ではなくて、永田町のゲームだけになってしまっているんですけど、国民レベルから見れば、世界が大きく動く中で、未来に向けて本当の議論をする。その舞台が、その民主党の代表選のまさに直前に東京で、しかも2,000人くらいの規模で行われると。それで、日本と中国の有力者がガチンコで議論すると。これは僕たちから見ても、非常に大事な対話だと思います。この内容はインターネットで中継しますので、ぜひ皆さんにも見てほしいなと思っています。
田中: ついつい今政治で日本国内、内向きな感じになっていますが、世界にむかて目を見開くいい機会なると思います。
工藤: このフォーラムを機に日本も未来にむけて、社会が動いたり、政治が動くようなるといいのですが、かなり中国は戦略的に動いているので、普通の議論ではだめですね。本当の議論をしていかないとだめでね。そういう風な真剣な舞台をどれだけ僕たちができるか。しかもそれがどれだけ両国民に伝わって、相互理解についても新しい流れを作れるか。これが僕たちにとっても達成目標なわけです。みなさんもぜひ注目して見てほしいなと思っています。
(文章は、動画の内容を一部編集したものです。)
|
「第6回 東京-北京フォーラム」
|
投稿者 genron-npo : 22:52 | コメント (0) | トラックバック
2010年8月14日
先進的な日本の課題を乗り越えるために、日本自身が問われている
記者会見をし公表した、2010年日中共同世論調査から何が明らかになったのか。記者会見から一夜明け、改めて代表工藤が語ります。聞き手:田中弥生氏 (言論NPO 理事)
田中: 工藤さん、こんばんは。言論NPOでは2005年から「東京-北京フォーラム」を毎年開催していらっしゃいますが、その一環として毎年日中共同で世論調査を行っていますね。昨日、その世論調査の結果を記者発表されたそうですが、ポイントを教えていただけますか。
工藤: この世論調査は日本と中国の国民に対して、僕たち言論NPOと中国の中国日報社と北京大学の共同で行なっている世論調査です。中国で世論調査を行うということは、もの凄く大変なことで、なかなかできないのですね。僕も、これを実現するために、非常に大変でした。ただ、2005年から6回を継続して行ってきて、やはり両国民の相手国に対するイメージや感情、相手国に対する基礎的な理解が明らかになってきました。調査を開始した2005年は反日デモがあり、日中関係が最悪の時でした。その時は中国の国民は日本に対して非常に悪いイメージを持っているし、日中関係は非常に良くないと思っていました。日本の人もそう思っていました。その時と比べますと、お互いのイメージとか両国関係の現状に対する認識はかなり改善されました。ただその中身で色んな形で違いが見えてきたというのが、昨日の記者会見で説明した世論調査のポイントです。
田中: 違いというのは具体的にどういうことですか?
工藤: 中国国民の日本に対するイメージの改善がすごく大きいのです。お互いの国に対してのイメージですが、日本人の多くはまだ中国に対して良い印象を持っていないし、中国国民の6割が日本に対して良い印象を持っていないのです。ただ中国国民の日本に対する印象は非常に改善しています。しかし一方で日本国民の中国のイメージはなかなか改善していません。実は日本の中国の印象も05年から見れば、改善してきたのですが、2008年調査から悪化してしまいました。その原因はギョーザ事件の中国の対応の悪さで、日本国民は中国に対して非常に嫌なイメージが出来てしまったのです。今回の2010年の調査では昨年と比べると良くはなりましたが、十分な改善ではありません。それが日本人と中国人の相手国の印象において大きな違いです。
両国関係に関しても中国人は「日中関係は非常に良い」と思っており、7割くらい(74.5%)が「良い」と答えている。日本の方も改善して現状はいいと思っているし、「悪い」と言う人はかなり減ってきています。でも依然として日本の国民は日中関係に関して48%が「どちらともいえない」と答えています。ただ、日中関係は実際には2005年から大きく改善しています。首脳会談も再開しましたし、「東京-北京フォーラム」のような民間交流も増えています。それでも日本の国民の半分が、両国関係が改善していることに確信を持てていない。これはなぜなのか。
僕はこれを分析して昨日も記者会見で説明しました。1つは、中国の人は政府間関係が改善するとことは非常に大事だと思っています。ですので、政府間関係が改善することによって非常に日中関係が良いという印象になっています。一方、日本は政府間関係が改善するのは非常にいいことだし、それに対して日中関係は今親密になっているのを感じていますが、それ以上に日本の人は生活感覚で中国のことを見ると言う傾向が出ています。例えば今日中関係の両国関係で障害になっているものは何かと聞かれれば、ギョーザ問題みたいな中国食品の安全性を掲げる人は減ってきたとしてもまだ7割もいます。つまり、日本人は生活感覚の中で中国に対する印象を形成している。そこの最も大きな影響を与えているのはテレビメディアで、軍事に対する不安感もその中で強まっています。
もう一つは、僕たちは日中の共同世論調査と同時にそれと並行して中国では北京大学などの6大学で中国の大学生のアンケート調査を行なっています。この学生調査と世論調査に間に意識の差が広がっています。中国の国民は戦争経験、つまり過去の視点でまだ日本を見ている傾向が非常に強いのです。たとえば中国国民の38%、これは毎年減ってきていますが、いまだに現在の日本を「軍国主義」だと思う人がいるのです。 ショックだったのが、「日本には報道や言論の自由はない」と思っている人も多いのです。つまり、中国人は過去から今の日本を見ている。
一方、日本ですが、先には生活感覚と言いましたが、今の中国を見て印象を形成しているのです。中国の経済は巨大になってきて、日本はこうした中国経済的の発展に依存しながら自国の経済を支えている。しかも今年は日本のGDPは中国に抜かれます。中国の経済力が大きくなるにつれて中国の大国的なイメージを日本の国民は気にし始めているという問題があります。つまり政府間関係、それから過去、を意識している中国国民。日本人は中国を生活感覚で今の変化を見ているという状況。もっと詳しく調査結果を見る必要がありので、言論NPOのHPの中で公表している今回の日中共同世論調査の詳細のデータを見ながら一緒に考えてほしいのですが、僕はこの2つの要因が大きいと思っています。
田中: 時間軸とどのくらい多層的に相手国を見ているかの差がこの結果に出ているのですね。
工藤: そうなのです。だから逆を言えば、中国の大学生はその点で非常に客観的にものを見始めています。記者会見時に、東京大学の高原明生教授が指摘していましたが、例えば「日中関係に障害になっているもの」という設問の対する答えとして、中国の大学生は「日本にあるナショナリズム」よりも「中国の中にあるナショナリズム」と答えている人が多いのです。
田中: もう1つ伺いたいのですが、「2050年のお互いの国の姿」をどう見ているかという問いで、両国民の間でだいぶ差があったと思います。どうしてこんなに差が出たのか説明していただけますか。
工藤: 中国はかなり自分の国に自信を感じています。経済的な成長がかなり続いていて、たとえば自分たちは2050年にどうなっているか、では、中国国民は8割がアメリカと経済力が並んでいるか、もうアメリカを追い越していると見ています。中国の学生はそこまでいっていませんが、やはり中国の国民はかなり強い自信を持っています。これからの国際的な政治・経済のリーダーは誰なのかという問いでは、「アメリカ」と答える中国国民が一番多かったのですが、やはりそれに中国が迫っています。中国国民は自国が国際社会において政治的なリーダーシップを取っていくと見ている人が、アメリカと並びかけているのです。しかし、日本の国民には逆の傾向が出ています。日本人は2050年に関しては非常に自信を失っていまして、というよりも未来においてこの国がどうなるかを今の段階で判断できない状況なのです。その結果一番多いのが、日本の2050年を「中規模の国で何の影響力もない国」という予想だったのです。これは、日本の世論調査と同時に行った日本の有識者にも同じ傾向があります。
田中:しかし、「2050年の日本」について中国人はもう少し前向きにみていて、日本人はペシミスティックに見ています。
工藤: そうです。僕はこれを色々な政治家の方に話をしましが、「これは大変なことだ」と言っている政治家の方と、「日本のメディアの報道が悪い」って言っている方、「日本人はもともと悲観的なタイプだ」と言っている人がいました。
僕はこれからの日本を考えた時にそこまで順調に中国が大きな力を持つか疑問に思っていますが、巨大な国への発展に自信を深める中国、自信を失う日本、この構造は多分これからの国際政治やアジアの中で非常な重要な問題だと思います。ただ気をつけなければいけないのは、日本が抱えている課題と中国が抱えている課題は違うということです。日本も高度成長の時にはかなり自身を持っていました。それがある意味で成熟社会となり、成長が鈍化し、つまり豊かになった。一方で少子高齢化という大きな先進的な課題を持っていて、その中でシステムチェンジができず方向が見えない。中国はどんどん発展しようと言う状況ですが、その中国もいずれは国民の意識も変わり始め、生活の質の豊かさを求めたり、少子高齢化という問題にぶつかるはずなのです、つまり、日本の課題は先進的であり、かつ今の局面を打開するというのにはもっと複雑になっています。
しかし日本がそれを乗り越えない限り、アジアや世界の中で存在感のある国にはなれないと思います。日本が問われていると非常に感じました。
田中: 確かに悲観的に成らざるを得ないような材料はありますが、戦う前に気負い負けをしている気がしますので、情けないような感じがしました。ですので、憂うよりももっとポジティブに考えないと駄目ですね
工藤: 今度8月30日(月)から開催される「東京-北京フォーラム」で、この世論調査を使って日中の有識者が激しく議論をします。中国からは116人もの方が来ます。現役の閣僚、閣僚経験者など各分野のトップクラスが訪日します。日本もそれに向かい打つために経済人、メディアや政治家など色んな人が参加して議論を行ないますが、両国の政治家同士が議論するときに、日本の学生の参加がいつも少ないのに非常に気になっています。
昨年中国で同じことをしたときは、たくさん学生が会場に集まり、質疑応答の時にはみんなが手を挙げるのです。一昨年東京大学で開催した時は、参加する学生は少ないだけではなく質問も少なかったです。その時に中国の方より、「日本の学生と対話をして何の意味があるのか」と言われました。私は日本の若い世代に、是非30日午後の政治対話に参加して傍聴してほしい、そして両国の政治家に意見をぶつけてほしい、と思っています。
田中:多くの人が参加して下さることを願います。それではありがとうございました。
![]() 「第6回 東京-北京フォーラム」開催概要・お申込みはこちら
「第6回 東京-北京フォーラム」開催概要・お申込みはこちら
|
先進的な日本の課題を乗り越えるために、日本自身が問われている 聞き手:田中弥生氏 (言論NPO 理事) |
2010年現在、日中両国民がお互いの国をどのようにみているのか。世論調査の分析結果を受け、現代中国政治が専門の、東京大学大学院法学政治学研究科教授の高原明生氏が解説します。
![]() 2010年日中共同世論調査結果詳細はこちら
2010年日中共同世論調査結果詳細はこちら
|
2010年日中共同世論調査のワンポイント解説 高原明生氏 |