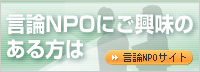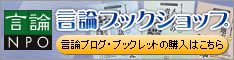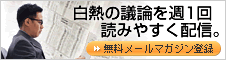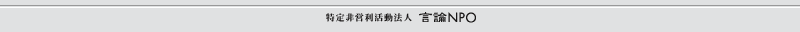« 2010年10月 | メイン | 2010年12月 »
2010年11月24日
「日本の社会保障、本当に持続可能なのですか」
-ON THE WAY ジャーナル 2010.11.24 放送分
放送第8回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、日本総研調査部主任研究員の西沢和彦さんをお迎えし、日本の社会保障について考えました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「日本の社会保障、本当に持続可能なのですか」
工藤: おはようございます。ON THE WAY ジャーナル水曜日、言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝、様々なジャンルで活躍するパーソナリティが自分たちの視点で世の中を語るON THE WAY ジャーナル。毎週水曜日は私、言論NPO代表の工藤泰志が担当します。
はやいものでもう、11月も終わりです。東京は銀杏が非常にまぶしい季節になっていますけれど、皆さんのところでは紅葉はまだ見られるのでしょうか。さて、今日はスタジオにゲストをお招きしました。日本総研調査部主任研究員の西沢和彦さんです。西沢さんは僕たち言論NPOのマニフェストの評価で、社会保障の分野を担当してもらっているんですね。西沢さん、今日はよろしくお願いします。
西沢: よろしくお願いします。
工藤: というわけで、今日は西沢さんをお迎えして議論をしたいと思います。今日のテーマは、「日本の社会保障、本当に持続可能なのですか」です。実を言うとこれは、2週間前にですね、私は、必ず社会保障の話題を議論しますと皆さんに約束しました。
それで今日は最強のサポーターを呼んで、議論することになったのですが、今、僕たちが日本の未来を考えるときに一番考えなければならないことは2つあるとそのときも言いました。1つはこのままでは日本の財政破綻の可能性が出てきているということ、もう1つは日本の超高齢化、それから人口減少という問題を真剣に考えなければならないのではないかと。にもかかわらず、政府なり政治が、この問題に対する対応を非常に中途半端にしている、怠慢だなと思うところがあるのですね。ということで、今日はこの問題を中心に考えたいと思っています。社会保障といっても医療の問題、年金の問題、それに介護など、そういう問題が全部あって、これはほとんどが、今の現役世代の人たちがとくに高齢者のサービスを負担するお金を出しているという支え合いの構造でやっているのですね。そうなってくると、人口が減少してお年寄りが増えてくると、このモデルは非常に難しくなってくると、そのほころびがかなり出てきているんですね。この前、政権交代が行われたときに、この年金・社会保障問題というのはとても大きなテーマでした。民主党はまさにこれを抜本的に変えなくてはいけないということをおっしゃっていました。にもかかわらず、政権交代をしたこの1年あまりを見ますと、年金改革とか社会保障の話が急になくなってしまったような気がするのですが、西沢さん、このあたりはどのようにごらんになっていますか。
西沢: そうですね。この社会保障の話というのは、限られたパイの中で誰からお金を取って誰に与えるかという話ですね。パイが増えない以上、誰から取るかということを、きちんと取られる人に説得しなければならないわけです。これは非常に骨の折れる話であって、政治的にそれは避けたいのでしょうね。政権与党になっている以上は。ですから議論が非常に停滞しているのだと思います。
工藤: ただ、政治というのは、やはりいまの政策のアジェンダ、課題から逃げられないわけですから、政治がそれを怠っているということは、実際の状況は非常に悪化していくと思うんですね。今、年金とか医療とか、この社会保障の現状は、簡単に言うとどのように悪化しているのでしょうか。
西沢: 超少子高齢化と雇用の流動化・多様化、非正規の増大などが社会保障を直撃しているわけです。というのも、現役の所得の一部を高齢者の医療や年金に移転しているわけであって、その現役が少子高齢化で減っている。そして、現役の雇用自体が、大卒の内定率が非常に低いというのもありましたけれども、悪化しているわけで、現役から所得の一部を高齢者に移転するというシステムは、非常に機能しにくくなっているというところです。
工藤: すると、その中でさまざまな制度や仕組みが壊れ始めているのが見えてくると。実は2004年のときも、僕も西沢さんとずっといっしょにマニフェスト評価をやっていたのですが、年金の改革があったんですよね。このままだったら年金制度というものが破綻していくのではないかと。当時、国民年金の未納も増えていましたし、そういう形で制度に対する信頼も失われていたと。それで何とか100年もたせようということで、給付は抑制し、保険料は上げていくということを決めましたよね。なんだか値上げのほうだけは動いたのですが、そのあと経済も悪くなったからかわからないのですが、給付の抑制がほとんど利いていないという状況で、あの2004年の改革はちゃんと機能していないような感じがするのですが、どんな状況なのでしょうか。
西沢: 機能していないです。柱は3つあって、工藤さんの言われた給付の抑制と保険料の引き上げ、そしてもう一つが基礎年金という全国共通の年金の国庫負担の引き上げ、これは毎年2兆5千億かかるのですが、この財源の目処が立っていない。ですから、3本柱のうち2つができていないわけです。
工藤: まさに基礎年金の2分の1というのは、本当は自公政権が続いていたら、来年から消費税が上がって、2兆5千億が入るという話になっていたわけです。
西沢: そうです。
工藤: それがないということになれば、そのお金はどこから・・・、2分の1はやるわけですよね。
西沢: 2分の1は、いますでに、2009年、2010年とやっているわけですけれど、いわゆる埋蔵金から捻出しました。来年以降は目処がたっていないわけでして、来年、基礎年金を配るお金の一部はもう目処が立っていないような状況なのです。もう11月が終わろうとしている中で。
工藤: ということは、いま言っていた自公政権時代に年金は100年安心だと言っていたのですね。それが今はその3つのうちの2つが機能していないと。それはどういうことかというと、100年間の財政のバランスなのですね。入りと支出。で、それがつまりうまくいっていないということで。
西沢: うまくいっていない。
工藤: しかし今のお年寄りに対する年金の給付はしっかり守られているわけですから、その資金源は将来の若い世代とか、これからの人たちにどんどんしわ寄せがいっていると、そういう状況ということですね。
西沢: はい、そうです。給付水準はむしろ上がってしまっていて、本来、将来の世代が使える今の積立金を先食いしてしまっているわけです。しかし政治はそれをきちんと問題として認識していない。与党も、それを作った野党も、問題提起すらされていないと。そういった問題が放置されてしまっている。これは非常に専門的ではあるのですが、こういった状況が続いているというのは国民も皮膚感覚でわかっていると思うのですよ。問題があるのに、政治が認識、問題提起すらできていない。それが、社会保障、将来に対する不安の根底にあるのではないですかね。
工藤: そうですね。年金の若者層も含めて、さっき雇用の流動化の話もあったのですが、未納がやっぱり多いですよね。4割くらいありませんか。
西沢: そうですね。まあ、国民年金は2200万人ですかね。第一号被保険者というのですが、この納付率が6割を切りました。
工藤: ということは、半分近くの人から信頼されていないと、そういう状況があるわけですね。
西沢: ありますし、また、制度的に、所得にかかわらず一定額の保険料負担なので払いにくいということがありますね。これは直さなければならない、とずっと前から言われているのですが、ここも全く手つかずです。
工藤: 一番問題なのは民主党政権になって、自公政権のときにそれはおかしいと言っていたことが、どんどん悪化しているまま放任されているということはよくないですよね。
西沢: 全くよくないですね。
工藤: 年金財政という、その再試算というのはやっているのですが、次は2014年ですよね。13年でしたっけ。
西沢: 2014年です。
工藤: すると、菅政権の終わった翌年じゃないですか。終わったというか、任期の後ですよね。ということは、この政権中に、今、行われている年金制度の問題点を国民にきちんと説明してね、それに対してどうするかというチャンスがないわけですよね。もし2014年にやるとすれば。それはおかしいと思いませんか。
西沢: そうですね。民主党が政権につく前は、「ミスター年金」という長妻昭さんとか山井和則さんが、2009年の2月に出された自公政権のときの年金の将来像の姿、数字がおかしいと、楽観的すぎると、強く批判していたわけですね。彼らが政権について大臣、政務官になって、もっと保守的な姿で将来像を示す、チャンスがめぐってきたわけです。
工藤: もっと積極的にやるんじゃないかと思いましたよね。
西沢: それなのに何にもしないと。
工藤: どうしてしないのですかね。怖くなっちゃったんですかね。
西沢: そう。おそらく、保守的な経済前提や人口の前提で年金の将来像を示すと、今よりも悲惨な姿が現れるわけです。とくに高齢者にとって。そうすると彼らは手を打たなければいけない。手を打つということは、高齢者に年金の一部を我慢してもらう、増税をするということにつながりますから、それをするまでの勇気、責任感、義務感というものがなかったのでしょうね。
工藤: 菅政権は強い社会保障をしようということで、こういう問題を解決しようという意識を言ったのですが、ほとんど手はつけられない。それで口をつぐんでしまった。一方で自公の人たちも、自分たちで作っていた100年プランが、今うまくいっていないと言うことを認めないとだめですよね。ただ民主党を批判するだけでなくて。だから政治が、今やっていることがおかしいのだと、これを認めないとすべてのドラマが始まらないのですが、そういう議論は国会ではありますか。
西沢: まったくないですね。自公政権でつくった年金プランというのは、政治家がつくったわけではありません。厚生労働官僚が、給付抑制で負担増であることを国民にも政治家にもわからないように仕組んだわけであって、それを100年安心というオブラートに包んできわけですよね。ですから政治家自身がつくった案ではなく、たぶん多くの方は理解していないと思います。
工藤: ただこのままいったら若い世代にどんどんつけを飛ばして、自分たちだけが良ければという雰囲気になってしまいますよね。
西沢: ですから、官僚も、与党や野党の政治家にこういった問題点があるということをきちんと言わないといけないですね。
工藤: いまの安心プランというのは破綻していると、だから抜本的に変えないとだめだということですよね。さっき言った、今の社会保障の全ての制度が、現役世代が高齢者を支えるという構造になっていて、どんどん高齢者が増えていくわけですから、理論的に難しいですよね。人口の推計を見ていると、何十年後には1対1で支えると、今は3人で1人を支えている。昔は10人とか7人くらいで1人を支えていたのが、いまは3人で1人だと。1対1で支えるという構図は、誰でも無理だと思うじゃないですか。それがわかっているのに、今の状況を認めないだけではなくて、抜本的な手を打たないということになると、この国の未来はかなり厳しい事態になると思うのですが、これはどういうふうに考えていけばいいのでしょうか。
西沢: そうですね。いま年金の話をしましたけれど・・・
工藤: 医療もみんなそうですよね。
西沢: 医療もそうです。例えば後期高齢者医療制度、国もやりたくない、都道府県もやりたくない、市町村もやりたくない、みんな財政的な負担になることを恐れて、やりたくないということを各所で繰り広げているわけです。
工藤: 抜本的な解決が無理なので税金を投入し、一方でとれる現役世代からお金をつないで、なんとか応急措置でやってきたわけです。介護も、医療もすべて。それがいずれだめになりますけれど、だましだましでやっている状況じゃないですか。それで今度、税金投入で日本の財政破綻のほうにつながっていって社会保障のゾーンの1.3兆円の自然増は、いまそれを止めようというよりも、放任しているから、どんどん国債が増えていく。悪のスパイラルというかね、大変な事態だと思うのですが。これは抜本的に変えなければならないという局面にきているでしょ。
西沢: そうです。健康保険も年金も1980年代の初めくらいからですからね、だましだまし対処してきたわけです。既存の制度を変えずに、ちょっとずつお金を融通してきたりしながら。それがいよいよ限界に来ていると思いますね。ですから1つの主義主張、プリンシプルのもとに、新たに制度を作り直すと、国民の誰がみてもわかりやすい制度をつくって、そのうえできちんと負担増を求めるということにしていきませんと、だましだましをいつまで続けていくのかということになります。
工藤: 非常に良くないのは、こういう時代状況のときは政治ができないことを約束するのですね。給付は守ります、保険料は上げませんと、それは僕たち有権者にとっては非常に居心地が良くて、聞きやすいのですが、それはつじつまがあいませんよね。やっぱりサービスが増えると負担は誰かがしなければならない。その当たり前の現実が、かなり巨大な額になってしまおうとしているという状況なので、これは有権者も、事の重要性を考えなければならないという局面にきたといえないでしょうか。
西沢: だいぶ前に来ていると思います。
工藤: だいぶ前・・・。もう手遅れですか・
西沢: うーん、次、選挙があるときがラストチャンスととらえた方がいいですね。そのときに政権与党は具体的な時間軸、負担増の幅をきちんと提示して、国民に受け入れてもらいながら選挙をしないと、結局その選挙のときに、みんなハッピーです、みんな幸せです、負担もないですよと甘いことを言って選挙に突入したら、もう終わりかもしれないですよね。
工藤: 終わりということはどうなっていくのですかね。つまり、まずは財政の破綻が始まるということですね。社会保障関係のお金がない。
西沢: 急激には年金は破綻しません。積立金が数年分ありますので。ただしそれは後の世代が使うべきお金であって、それを先に使ってしまうと。後の世代の負担が急激に増えるか、あとの世代の年金支給者の年金が急激に減るか、ある時点で急激な下落なり負担増が起こるということです。
工藤: そういうふうなお金がないとなれば、その使い方を考えなければだめですよね。本当に困っている人に出すとか。医療でも何でも本当に必要な人とか。そういうことを調整して決めるということが、まさに政治の役割ですよね。
西沢: 誰が困っているかということは、科学というよりも、主観的な問題ですから、それをまさに政治が考えて言葉でしゃべるべきことですが、全然語らない。誰が困っているかを政府がとらえるというのは、例えば納税者番号制度ですとか、行政インフラがしっかりしていないと誰が困っているかわからない。でもその行政インフラを整える議論もなかなか進んでいないわけですね。
工藤: これはかなり、政治の役割が今問われてきていますね。決定的に問題なのは若い世代ですよね。これからの日本を背負う人たちの老後がまったく見えない、つまり未来が見えない状況になっちゃいますよね。そうしたら今度はそういう人たちが反発しますよね。
西沢: します。反発するか、反発する気力もなく、心の中に不安だけを抱え続けていくのか。
工藤: でも今でもフリーターなど、若い人たちがきちんと収入を得ることが難しいと。非常に社会が不安定になるという状況ですよね。そういう状況は何としても回避しなくてはいけないので、やはり政治的にそれを直す時期にきたのだなと思います。今日、西沢さんのお話を聞いて、次の選挙が最後だと、僕は鳥肌が立ちました。今まで僕たちも何回も言ってきたんですよ。だけど、僕たちの言う側の方がね、何回も言っているからといって慣れてくるんでですね。だけど、もういま決めないとだめな局面まできていると。ただこれは決められるのですよ。僕たちが、有権者がこういうことをちゃんと考えなければいけないのだと考えれば、流れを変えられると僕は思います。だから次の選挙は、いつあるかわかりませんけど政治は間違いなく、年金や医療など社会保障に関するプランを出してくれないといけないし、今の制度がここまで崩れている、これは大きな問題があるんだということをまずは認めてくれないと。それから国民に選択肢を出してもらいたい。有権者側はそれに関してはきちんと見て、どの政治家が、政党が本当のことを言っているかどうか、を考える、そういうふうな段階にきたのだと思います。
ということで、時間になりました。今日は、僕がずっと喉に魚の骨が刺さったように気になっていた社会保障の問題を、ぜひみなさんに考えてもらいたいと思って、僕の最強のパートナーである西沢さんをお呼びしました。西沢さん今日はありがとうございました。
西沢: ありがとうございました。
工藤: 今日は日本の社会保障制度について考えてみました。意見があったらどんどん寄せて頂きたいと思います。今日はどうもありがとうございます。
(文章・動画は放送内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【後編】
投稿者 genron-npo : 14:06 | コメント (0) | トラックバック
2010年11月17日
「日本が財政破綻するって本当なの?」
-ON THE WAY ジャーナル 2010.11.17 放送分
放送第7回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、IMF前副専務理事の加藤隆俊さんのインタビューを交えながら、日本の財政危機について考えました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「日本が財政破綻するって本当なの?」
工藤: おはようございます。ON THE WAY ジャーナル水曜日、言論NPO代表の工藤泰志です。早速ですが、今日のテーマは、先週に引き続いて財政問題を中心に皆さんと考えたいと思います。私が考えたテーマは「日本が財政破綻するって本当なの?」ということです。この前の放送終了後、IMFという国際通貨基金というものがあるのですが、その前副専務理事の加藤隆俊さんという人が、今、日本にいらっしゃいます。私が会ってきましたので、ぜひ加藤さんとのインタビューを、皆さんに聞いていただこうと思っています。
その前に、IMFと加藤さんについて簡単に一言で説明します。加藤さんは昔、財務省の財務官という国際金融のプロだったのですが、それからIMFの副専務理事になって6年間ワシントンにいらっしゃいました。その間に、ギリシャの財政破綻とか色々なことがありました。そういうことについて、IMFとして色々取り組んでいましたので、国が財政破綻するということについて、非常に考えています。一方で、日本の状況にも詳しいということで、この人の話は非常に重要だと思いました。
【インタビュー】
加藤: IMFが最近発表した論文がありまして、それによると、財政的な余裕がほとんどない国として、PIGSではなくて、PIGJを挙げております。ポルトガル、イタリア、ギリシャ、日本です。だから、日本はそういうグループに入っているというのが分析結果ですし、論文ではギリシャに見られたように、国債のリスクプレミアム、金利が上がり始めると、ある時点を過ぎると、ギリシャの経験を踏まえても急角度で金利が上がります。だから、日本についても潜在的なそういうリスクがあるという分析内容です。それは、広く読まれていますから、国際的に見た日本の立場はそういう評価だと思いますし、6月のトロントサミットで、G20の他の先進国は、2013年までに財政赤字を半減させ、2016年までには債務残高のGDPに対する比率を減らし始めることになっています。ただ、日本だけは例外になっている状況です。
工藤: 日本の財政というのは非常にわかりにくいのは、こんなに深刻なのに金利が上がらない。それは、国内で国債を消化しているからだ、といつも解説されているのですが、どこかで金利が上がり始めたら...。
加藤: 急角度に上がります。日本について、いつかということは言っておりませんけど、去年のIMFの年次審査で発表されたペーパーによると、2020年にかけて国債の消化というのは難しくなっていくだろう、ということになっています。
工藤: 市場はどうしたら、日本が財政改革に取り組んでいると判断するのでしょうか。
加藤: 6月に政府は財政運営戦略というのを閣議決定しておりまして、その中身は良くできていると思いますし、それから、今度財政運営戦略というのは、G20のトロントサミットでも国際的な公約になっていますから、この中身を実現するのは結構厳しいのですが、日本としては着実に実行していく。そうでないと、約束違反という目で、G20の他国からとられかねないと思います。
工藤: ただ、日本は2015年までにプライマリー赤字を半減するという話ですよね。これを私のほうでも見てみたら、プライマリー赤字を半分に削減しただけですから、債務残高はどんどん悪化して、その頃は二百十数%になっているという状況なんですね。でも、それでも、国際公約だから日本がそれをやればだいたい大丈夫だと見ているのでしょうか。
加藤:今年のIMFの年次審査では、ともかく国債残高、公的な債務残高のGDPに対する比率を240%で頭打ちで、240%まで上がるのは仕方がない。それがピークで、段々なだらかに下げていくためには、GDP比で1%の債務削減を10年間やらなければいけない。毎年5兆円の削減を10年間続けてやらなければいけない。1%でずっとやるのではなくて、1%ずつ毎年積み上げるということを10年間やっていかないといけない。
工藤: 10年間で最終的には50兆円の債務が減少していないといけないわけですか。10年後に。
加藤: もっと具体的に色々な組みあわせがあるのですが、1つの組み合わせでは、消費税を5%から10%上げて、15%にするということもメニューの1つに入っています。
工藤: これは、IMFの今年の審査ですか。
加藤: 今年の審査です。
工藤: 今、加藤さんの話を伺って、少なくとも世界は、国際機関も含めて日本の財政問題を非常に深刻に考えているということがわかると思います。日本の借金があまりにも多くて、金利が上がってしまうということは避けなければいけないのですが、加藤さんに、その金利上昇というのはどれぐらいまでに起こるのか、と聞いてみたところ、2020年ぐらいまでに金利の上昇があるかもしれないと。そうすると、あと10年、日本の政治がこの財政問題、この前も言いましたが、社会保障の問題も含めて、そういう問題にきちんと向かい合って、しかも、国民にきちんと説明しないと、本当に財政破綻の可能性が高まってきているのではないかと思っています。メディアを見ても、そういう風な感じは伝わってきませんが、今回のインタビューを通じて、そんなことを非常に痛感したわけです。そこで、財政破綻したらどうなるのだろうか。万が一、日本がそういう状況になった場合はどうなるのだろうか。IMFなり世界は、各国の財政破綻という問題について、どういう風に取り組むのか。そういうところについて、ずばり聞いてみました。
【インタビュー】
工藤: ずばり聞きたいのですが、財政が破綻するということになった場合、今まで韓国やギリシャもありましたが、その場合、国際的な枠組みなり、色々な枠組みの中で、世界はどう対応して、どういうことが迫られていくのでしょうか。
加藤: 幸いにも日本の国債の場合、外国人の保有比率というのは5%ぐらいですから、ギリシャと違ってあまり外国に迷惑をかけることは、現状ではあんまりありません。ただ、僕の担当していたケースで、ジャマイカの破綻がありました。ジャマイカの場合も国債の大半は国内で消化されていました。しかし、財政赤字が拡大して、このままでは立ちゆかなくなるという問題がおきて、長い時間をかけて国内でコンセンサスをつくって、発行した高金利の国債を低金利のものに借り換えていく。それを強制的にやるのではなくて、ボランタリーなプロセスでやっていく。つまり、みんなこのままでは破綻するのはわかっていますから、借り換えていくのは国が破綻しないためにはやむを得ない、というコンセンサスをつくるために随分時間がかかりました。コンセンサスをつくる一つの軸になったのは、IMFのプログラムで、それができて、今までの所は比較的順調にいっています。国が破綻するということはあり得ないので、そういった場合には、何らかの形で国債の保有者に負担を求める、あるいは一緒に増税もやると、その組み合わせは国によって違うと思います。
工藤: つまり、このままでは財政が厳しいので、高い金利でないと買わないと。それを低金利に代えるということは、保有している人が損をするわけですよね。どうして納得してくれるんですか。
加藤: 損になるけれども、もし、みんなが応じなかった場合には、全く国債の償還というのがないかもしれない。国によっては、もっと極端なカットオフがありました。アルゼンチンの場合なんかはそうですが、それよりも...
工藤: 一応、全額返すということを。
加藤: 返すことを前提に、金利が低くなる、あるいは償還期間が長くなる、という形で、コストは今の国債保有者も負担する。その方が、全体として成長も続いて行くだろうから、うまく回っていく、ということをみんなが納得するまでに、時間がかかりました。
工藤: その代わり、ジャマイカ政府は何を見返りに、どういう改革を行ったんでしょうか。
加藤: それは、歳入面での増税もありますし、国債のかなりの部分は金融機関がもっているので、金融機関の改革。破綻している金融機関には、政府が資本注入をすると。金融セクターの改革と、歳入増などの色々な総合的なパッケージとして打ち出すと。
工藤: 日本のマグニチュードはかなり大きいですよね。規模が800、1000兆円ぐらいまでこのまま行けばなるわけですから。
加藤: 日本の場合は、それにいく前に、必要なことをやっていく。それで、マーケットが納得するかどうかということです。
工藤: 企業が再建するのと同じような位置付けみたいな状況ですよね。まさに、ちゃんと管理をして、国債を減らしていくとか、かなり具体的なメニューをだして、それに国民が納得してと。でも、日本はそういう時期にきているということなのでしょうか。
加藤: そう思います。外国人の保有比率は5%ですが、これから年が経っていくと、日本の消化能力に制約が出てくるので、その分海外での消化に期待せざるを得ない状況になってきます。そうなってくると、マーケットの反応ということが、もっと強い形で出てくる。
工藤: どうしたらいいのでしょうか。ここまで厳しい状況になりますと。
加藤: 両方ですね。個々の国民が、こういう問題についてもっと真剣に、自分の問題として考えるということはありますし、歳入にしても、歳出にしても、やはり政府、議会で決定するものですから...せっかく、戦略を決めたわけですから、それに沿って現実の歳出削減策なり、歳入増を図る施策として落としていく。その具体的な受け皿に落としていく、というプロセスが、今度の予算編成を始めてずっと続いて行く。政府、議会での覚悟でしょうね。
工藤: 覚悟ですね。国民の覚悟と...国民はもっと知らないといけないのですが、政治側の覚悟も必要になってきているということですね。最後に、IMFについて、一般の人は知らないというか、かなり自分たちよりも別の世界...
加藤: 向こうの世界、アメリカの
工藤: と思ってしまう人が多いのですが、IMFの役割というのは、僕たちも韓国の時や、ギリシャの時も、必ずIMFが出てきますし、どういう役割を果たしている組織なのでしょうか。
加藤: 一つはよく医者の例を使うのですが、外科医であると。もの凄い出血をしているときに、手術をして出血を止める。国際収支困難に陥っていた国に、経済の再建策をまとめて、融資もする。韓国の例もそうですし、ギリシャの例もそうです。それと共に、IMFは予防医の役割ということももっと高めて行かなければいけない。日本についていえば、今のGDP1%を10年続ける、消費税でいえば税率を5%から15%に段階的に上げていく。
工藤: 15%に段階的に上げていく。
加藤: 色々な組み合わせの中の一つですが、具体的に踏み込んで、一つの処方箋を出していく。国毎にだしていく、ということが予防医としての役割ですし、もう少し国際収支危機が起きないようにするために、一種の保険を提供する。そういうことも今からやろうとしています。
工藤: IMFが出てくるということは、どのタイミングからなのでしょうか。例えば、破綻して...韓国でも、ギリシャでも何かの時に出てくるのか、どういう形でマッチングというか、コーディネートするのかとか、それとも、イエローカードとか厳しい時に、何かをして介入してくるのか、どういう風な形で参加してくるのですか。
加藤: それのレンジを非常に広げようとしていまして、ギリシャの例なんかは、最終局面で出てきて、それで資金も出すということですし、去年から始めているのは、メキシコやポーランド、コロンビアの例ですが、これまで経済政策をきちんと行ってきた国に対しては、いざというときには、かなり大量の資金を用立てます、ということもあらかじめ約束しておく。それから、後は、G20なりで、お互いの経済政策を監視する際の事務局的な役割をIMFが果たす、というようなことがIMFの主な役割です。
工藤: 日本みたいな場合、IMFが関わることになった場合、こういう巨大な債務が多いところに対して、どう対応するのでしょうか。
加藤: 日本はGDPでも世界3位での国ですから、IMFが対応するというには、ちょっと大きすぎるので、それはやはりG20の枠組みの中で、例えば、日本の問題が世界経済システム全体に影響を及ぼす、という風に心配される場合には、G20の国全体が、日本に対して注文を出す。その時に、IMFもベースとなるような経済分析なり、処方箋の色々なオプションを提供する、そういう役割かと思います。
工藤: トロントでやった今年のG20の時に、日本だけ例外となって、財政赤字を半減するとなりましたよね。日本に対するG20の認識は、かなり厳しいのではないかという認識を持ち始めているということでしょうか。
加藤: 自分たちよりも更に、財政、公的債務のストックが並外れて大きい、そういう認識だと思います。だから、半減するというのはもっと時間がかかるということでしょうし。
工藤: となると、状況としては本当に今、覚悟を固めないといけない局面だ、という風に僕たちは理解した方がよろしいのでしょうか。
加藤: 行動を...具体的な行動を起こすことが、マーケットから期待されている段階だと思いますね。
工藤: かなり厳しい意見でした。最後に加藤さんが言った言葉が、胸に突き刺さったのですが、要するに、もう具体的な行動を起こす段階だということです。やはり、世界がこういう風に見ている。そして、日本はまさに当事者なわけですから、本当はこの問題に、課題解決に取り組まなければいけないと思うわけです。それから、もう一つ言っていたのは、国民も覚悟を固めなければいけない、ということでした。前々回の放送で佐々木毅さんが、そろそろ、何が本物かを見極める段階になっている、と仰っていましたが、これもまた一つの問題であって、我々は、日本の未来のためにこういう財政問題が今どういう局面なのか、ということについて考えていかなければならない。今回の放送を通じて、皆さんにも何か感じてもらえたのではないかと思います。
ということで、今日はお時間となりました。今回は、財政破綻という問題、絶対にこれは起こしてはいけないということで、財政破綻の議論を紹介しました。こういう問題についても、私は考えていきたいと思っています。ありがとうございました。
(文章・動画は放送内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【 後編 】
投稿者 genron-npo : 12:00 | コメント (0) | トラックバック
2010年11月10日
「日本の未来、みんなで考えよう」
-ON THE WAY ジャーナル 2010.11.10 放送分
放送第6回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、「日本の未来、みんなで考えよう」と題し、日本の財政危機と社会保障について考えました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
工藤: おはようございます。「ON THE WAY ジャーナル」水曜日、言論NPOの代表の工藤泰志です。毎朝様々な分野で活躍するパーソナリティーが自分たちの視点で世の中の出来事をばっさり切っていく番組ですが、毎週水曜日は私、言論のNPO代表の工藤泰志が担当します。
もう11月10日ということでさすがに寒くなって来ました。風邪なんかひいていませんか。実はうちの事務所は暖房をかけていますが、男性陣が寒いと言うのですね、しかし女性陣は暑いと言うのです。僕もそこの調整が大変になっています。さて、私は先週佐々木毅さんが発言したことが非常に心に残っているのですが、つまり国民は今、何が本物なのか嘘なのか、そろそろ本物を見極めるぎりぎりの段階にきているのではないかということです。。今日はその問題をやりたいのです。つまり日本が今直面している問題は何なのかということに関して皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
番組へのご意見やご感想、取り上げてほしいテーマなどを是非お寄せください。番組HPの水曜日「工藤泰志のページ」に行っていただいて、そこでメールやtwitterでお寄せ下さい。
「ON THE WAY ジャーナル」水曜日、言論NPOでは政治・経済・事件などなど様々な問題に関して、私工藤泰志が市民レベルの視点から皆さんに投げかけます。それでは今日のテーマはこちら。
谷内: 「日本の未来、みんなで考えよう」です。
おはようございます。番組スタッフの谷内です。暖房全開で、男性は・・・、結構ね・・・。最近寒かったり暑かったりで大変だと思いますが、さて、今日のテーマは、「日本の未来、みんなで考えよう」ということです。工藤さんは日本の未来はかなり明るいと思っていますか。
工藤: そうですね、僕は明るくなってほしいと思っているのですか、何か不安なのです。ただ考えてみると、僕たちはただ未来に期待するだけではなく自分たちが未来を切り拓いていかないといけないのです。僕たち次第で未来は明るくなりもするし、暗くなりもするのです。ただ未来を考えるときに今の日本はどうなのかと。それではじめて未来を考えることが出来るのです。私は今日未来を知るために今を知る、ということをテーマに議論を行ないたいと思います。
谷内: なるほど。
工藤: 今日実は面白い本を持ってきました。それは「高橋是清暗殺後の日本」という本なのです。著者は松元崇さんですね。この人は現役の内閣府の官房長、非常に偉い官僚の人です。皆さんも「高橋是清」ってご存知だと思います。以前、NHKのドラマ、司馬遼太郎の「坂の上の雲」をやっていましたが、あのドラマで西田敏行が演じていた英語の先生が、高橋是清です。あの人はその後総理大臣になって、戦前の昭和金融恐慌のときの大蔵大臣になり、そして軍事の拡張を抑制しようとしたために二・二六事件で暗殺されてしまいます。その後、日本の政府とか国会が戦争にまっしぐらに進んでいくわけです。それがどういう風に進んでいったのかとか、その結果、日本経済なり財政がどんな事態に追い込まれたのかがすごく詳しく書かれています。僕も本をよく読みますが、こういった本を初めて見ました。あの戦争で、結局310万人くらいが亡くなりました。東京大空襲とか原爆とか、民間人もたくさん死ぬのですが、ただ人が亡くなるだけではなく、日本の経済や財政そのものが壊滅的になっていくのです。つまり国が滅びていく。最後は1億総玉砕、本土決戦みたいな状況に追い込まれていくのです。それで驚いたのが、敗戦の前の年1944年ですが、この本によると、国民総生産と軍事費の比率が98.6%とほぼ同じ額なのです。つまり今に例えれば、日本のGDPは600兆円でしょう。だからそれと同額の600兆円くらいが軍事費なのです。政府の軍事費をベースにした予算が、その年の国民が頑張って作り上げた経済活動の結果であるGDPと同じ額くらいが軍事費に投入されるのです。「欲しがりません、勝つまでは」とか、国民が総動員されて戦争のためにすべてが投入され、それだけでは軍事費が賄いきれないので、借金、つまり国債をたくさん発行するのです。その結果どうなったかといえば、GDP対比で政府が作った国債が199.1%、つまりGDPの2倍近い額がまさに借金になったわけなのです。そういう状況に追い込まれたのです。
それで戦争に負けて、しかし負けても借金は残りますよね。それを政府は国としてどうしたのかというと、その後、3年位すごいハイパーインフレになり、物価が100倍くらいになるのです。すると、国民の資産も金融資産も100分の1、しかし物価だけは100倍なのですが、みんな働くところもないわけです。すさまじく高い物価、財政の破綻の状況の中で、みんなが強制的なインフレで借金を埋めるという状況になるのです。つまり財政破綻の現実はこういった問題なのです。
僕がすごく怖いのは、今の日本の借金はどれくらいの規模なのかということです。今年の政府の見通しで、日本の債務とGDPの関係がどれくらいかというと、200%越しているのです。204%くらいと言われています。すると、あの戦争時の壊滅的な日本の財政状況よりも今の財政、つまり借金の量が大きいのです。この問題は非常に深刻だと思います。ただ、なんかそういう緊張感がないではないですか。
谷内: 数字がすごく大きすぎて分からないですね。
工藤: そうですね。しかし財政破綻はそれぐらい大変なのです。それでよく見ると、その借金が膨らむペースが拡大したのは1990年、つまりこの20年ぐらいなのです。その当時を考えてみると、やはり景気が悪いので財政拡大しろ、ということで財政拡大をして色々やっているのですね。景気対策で何かをしてほしいと思いますが、何をやっても経済が回復しない。つまり経済がほとんど回復しないままお金をどんどん出して、借金だけが膨らんできている。
それからもう1つ。後で説明しますが、その間に日本ではもっと大きな変化が始まりました。それは、異常な高齢化です。お年寄りの数が増えていますから、医療費とか年金の給付によって、支出が非常に増えてきて、その中でまた財政が拡大していく。もうかなり厳しい状況になっています。
それでこの前菅政権が、6月に「中期財政フレーム」を出して、このままいったらまずいので、借金を、今年の予算で44.3兆円ですが、その額と同じ額の上限を維持しましょう、と決めるのです。それを国際公約にして、そして2015年までに、後で説明しますが、プライマリーバランスの赤字(GDP比)を半分にしましょうと言ったのです。それが実は参院選のマニフェストになっていました。
しかし実はこの約束は何なのかということです。メディアでも一応報道はされていますが、ほとんどの人はなかなか分からないのです。今年の6月に、トロントでG20、つまり20カ国の先進国の首相がみんな集まりました。財政破綻というのはギリシアが厳しくなって財政破綻して、IMFを含めていろんなところが融資しました。かなり世界経済がきびしいので、先進国は、財政赤字を2013年までに半分にしましょう、ということを首相間で合意しました。しかし、実はたった日本1国だけはその合意に入れなかったのです。その2013年まで財政赤字を半減するというのは大きい目標なのです。どれくらい大きい話かというと、日本の財政赤字は44.3兆円で、借金の額と同じです。これを、3年後の2013年に半分の20兆円くらいにしないといけないのです。20兆円を3年で減らすとなれば、消費税も7%くらい上げないといけない話なのです。これは無理なので、日本はできないと言っています。しかし、もし日本が財政破綻となれば世界的に大変なことなので、「それでは日本だけは特別にしましょう」ということで、日本だけ実は別の目標があります。それが2013年ではなく2015年という目標になったのです。ただ実をいえば、私はつい最近財政学者で有名な慶応大学の土居先生と議論をしましたが、土居先生が言うには、2015年まで財政再建なり目標を達成するということできちんと政府は政策体系を作って取り組んでいるのかといえば、実はまだそうはなっていないのです。今の日本はそれ以前なのです。前回も話しましたが16.8兆円というバラマキのマニフェストがあって、それを止めるのか止めないのか、まだその問題があるのです。16.8兆円の支出増は2013年までなのです。16.8兆円も財政の支出が増えて、同時に20兆円を減らすというのは非常に大変です。いろんなことを整理しないとこの目標が実現できない状況なのです。そこで日本は2015年までに「プライマリー赤字を半減する」と言ったのです。
このプライマリーバランスとは一体何なのか、これからもこの言葉はメディアでたくさん出てきますので、簡単にこれを理解する方法を教えます。実はこれは「借金はいっぱいあるのですが、借金のことは今は忘れましょう」ということなのです。家計でいえば、借金を忘れて毎月の収入と生活費のバランスをきちんと見ましょうということです。例えば収入より生活費が増えるのであれば、支出が多いので赤字ですよね。これを「プライマリー赤字」というのです。例えば、私が30万円の収入があって生活費に40万円かかってくれば10万円足りないですよね。これがプライマリー赤字なのです。これを半分にするなら10万円のうち5万円を削減しましょうという目標なのです。それをまた5万円減らすのは大変ですが、ここで忘れていることが1つ。実はその後ろに僕は今まで900万円の借金があり、その支払いは毎月20万円あります。しかしその支払いの20万円は今、忘れましょうと。忘れても5万円を減らしましょうというのがプライマリー赤字です。しかし待てよ、と。「あなたは借金の支払いがあるだろう」、本当は30万円減らさなければいけないのですよと。それを2013年までにするのは無理だから、2015年までにプライマリー赤字分だけ半分に減らしましょうということにして、それを国際公約にしたのです。
谷内: 国際公約で実現できるのですか。
工藤: 僕が政府なのか、個人なのかよく分からなくなりましたが、政府は目標をプライマリーバランスの赤字削減にしてくれたのは、赤字削減のペースが遅くなりましたので大変助かったと思います。ただ気になっているのは、目標年次を「2015年度」にしたことです。しかし、2013年には、今の菅政権が途中で解散選挙をやらなければ任期が終わります。だから任期中であれば「ここまで実現する」と菅政権が国民との約束として言えますが、2015年になれば、任期が終わった2年後ですから、責任があいまいになります。そういう場合は、今の政府は自分の任期である2013年までに何をするのかということを国民に明らかにしなくてはいけない。でもそれを政府は何も話していないんですね。すると先ほどのプライマリー赤字の話はフィクションですが。
谷内: ノンフィクション。
工藤: ノンフィクションかもしれませんが、先の家計の話を政府で考えるとどうなるのか。今の政府のプライマリー赤字は今年30兆円あるのです。30兆円をあと5年で半分にするというのは、実は15兆円の赤字を削減しないといけないのです。となると毎年3兆円。でも例えばさっきのマニフェストで必要とされる16.8兆円。16.8兆円は新しい歳出ですから、その歳出の財源の目処はないのでそのまま赤字になります。それを全額やるというのなら、それとあわせると30兆円の削減がこの5年で必要になる。
しかしそれだけではないのです。日本は今極端な高齢化なのです。毎年1.3兆円ずつ年金・医療など社会保障のお金が増えています。するとこれが5年で6.5兆円増えることになります。すると合計で36兆円もあるのですよ。今税収が37兆円しかないんですよ。すると同じ額を削減するのはどういうことなのかと。するとまず、先ほどのマニフェストの16.8兆円の歳出は無理だと言えば、15兆円とさっきの6.5兆円で21.5兆円です。しかしこれでも大変な話ですよね。それくらい深刻な状況を、今政府は少なくとも国民に語っていないのです。しかもそれが国際公約になっていて、世界は固唾を呑んで日本を見ているのです。
なぜかというと、先のギリシア問題ですが、ギリシアの財政の債務とGDPの対比で見ると129%なのです。でも日本は200%ですよね。戦争時より多いのですから。日本は国債は国内の人が買ってくれるのでギリシアとは状況が違うなど、何かと理由を付けていますが、だけどこの国がそろそろ危ないとなれば、将来金利が上がり、国債の価格がどんどん下がるので、これではまずいのではないかと思って国債を売り出す人が出てきますよね。なので、そんなに安定はしていないのです。でもそれだけではなく、日本は世界レベルでもはるかに高い、「人口減少、超高齢化社会」に突入しています。人口はどんどん減少しはじめていますし、生産人口は今8100万人ですが、これからどんどん減り、2050年には5000万人を切ってしまいます。日本の社会保障は、現役世代が年寄りを支えて成り立っている賦課方式なのですね。だけども、現役がお年寄りを背負いきれないという状況にもうなっています。単純な数字で言えば、今は3人に1人のお年寄りを支えています。過去は7人に1人で支えていました。このままでいけば1人が1人を支えるという段階に来ます。これは避けられません。そうなれば、今つくっている社会保障なり年金・医療・介護制度などが維持できなくなるのです。「こうなれば1人になっても高齢者を支える」と現役世代が覚悟を決めれば理論上は多分成り立ちますが、現役世代も自分たちの生活がありますので難しい。
そうなればこの問題を抜本的に見直さないといけない。これを見直さないと日本の未来は見えない。若い世代の皆さんは自分たちの老後がどうなるかなんて全く見えない状況だと思います。これをなんとなく辻褄を合わせるために、政府は税金を投入したり、保険の中でいろんな人からお金を集めてぎりぎり埋めていますが、もう持たないことがはっきりしています。これが実を言えば、今の日本が直面している最大の課題なのです。
日本の政治は社会保障に対して抜本改革をしないといけない。それが財政問題と連動して一緒に解決しないといけない。だから社会保障の問題はかなり複雑なのです。でも、日本の政治は今の政権も含めてこうした未来への課題で競っていないのです。これに関しては必ずまた皆さんと考えたいと思います。未来を知るためには、今を知らないといけないのです。そういう意味で、今現実がどうなっているかを僕たちが考えて、様々な発言の中から何が本物か見抜いてほしいと思います。
今日もそういうことで時間になりました。また熱く語ってしまいましたが、皆さんと未来を一緒に考えていきたいと思います。どうもありがとうございました。
(文章・動画は放送内容を一部編集したものです。)
投稿者 genron-npo : 12:00 | コメント (0) | トラックバック
2010年11月 3日
「日本の政治、このままでいいの?」
-ON THE WAY ジャーナル 2010.11.3 放送分
放送第5回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、元東京大学総長・政治学者の佐々木毅さんへのインタビューを中心に、日本の政治はいまどうなっているのか?について考えました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「日本の政治、このままでいいの?」
谷内: おはようございます。番組スタッフの谷内です。きょうは、工藤さんがインタビューをしてきたということで、そちらを聞きながら進めてまいりましょう。どなたにお話をお伺いしてきたのですか?
工藤: 元東京大学総長で、今は学習院大学法学部教授の佐々木毅さんにインタビューに行ってきました。日本の政治学では本当の大御所です。1時間ぐらい話をしてきたのですが、かなり熱い議論になりました。今日は、佐々木さんの話を交えながら、日本の今の政治について考えたいと思っています。
今、国会中継をやっていますが、それを見てがっかりしている人がいると思うんですね。誰が言った、言ってないとか、責任問題とか、本当に喧嘩ですよね。ただ、こういう喧嘩ってここ何年もあったのですが、日本の政治は日本の未来に向けて、機能していないのではないか、という不安を本当に持っているんですね。それを佐々木さんに聞いてみました。そうしたら、佐々木さんから驚くべき発言がありました。つまり、今の日本は「ナショナルクライシス」、つまり「国家の危機」だと言うんですよ。僕も日本の政治はかなり厳しいと思っていたのですが、危機という言葉まで使う以上、これは僕も無視できないなと。その政治の状況を、佐々木さんにどうしても説明してほしいと思ったんですね。では、佐々木さんの話をまず聞いてもらいたいと思います。
【インタビュー】
佐々木: 私は、だんだん世論は変化をしてきつつあって、一種の「ナショナルクライシス」という感じで、大丈夫だろうか、と思う人が増えてきているという状態だと思うし、工藤さんであれば前からそうだったと言うに決まっているんだろうけど。で、統治の方向はこうだねということが結局固まらないというか、自信がないというか。そうすると、結局後ろ向きのメッセージが復活してきて、何十年経っても政治とカネの問題ばかりやっているというような塩梅になっていくと。
工藤: 結局「ナショナルクライシス」という危機は、まさに財政や社会保障とかそれだけじゃなくて、統治が崩れてしまって、日本の政党政治に課題解決をする、未来に向かって動く力が非常に低下してしまったという事ですよね。
佐々木: だから、その根本を辿っていくと、政党が自分を統治しようということを考えない政党なんだから、日本の政党は。今でもそうなんです。だから、自分のマネジメントをしないのに、国民のマネジメントをしようというのだから、話がおかしくなるのは非常にみんなにも見えているわけです。その意味でいうと、やはり政党自身の経営能力というものが、根っこにある問題です。
谷内: 今、佐々木さんが言われた「ナショナルクライシス」、つまり国家の危機ですが、どういうことなんでしょうか。
工藤: 佐々木さんがここで言っているのは「統治」、つまり「ガバナンス」という言葉を使っているんですが、政党が経営面でも、政策面でも党内で決定し、実行していく、誰かがリーダーシップを発揮してそれを実現していく。政党政治から見れば当たり前の事なのですが、それが本当にできていない。それどころか、バラバラになってしまっている状況があります。これを佐々木さんは「統治の危機」だと言っているんですね。
今回、佐々木さんの話を聞いて非常に気になってきたことは、この前の尖閣列島の問題、それから為替もかなり通貨安の競争がおこり、世界は非常に不安定化しています。今僕が気になっていることは、皆さんの地域でもお年寄りが本当に増えてきていると思いますが、超高齢化社会が進行していると同時に、財政状況も非常に厳しくて、まったく未来が見えないということです。このままいくと、日本がどうなっていくかわからない、というギリギリの土俵まできています。だけど、そういう時でも政党がきちんと機能していれば、日本の政治がちゃんとしていれば、課題に対しての解決方法を国民に提案することができますよね。しかし、佐々木さんは、その政党自身が、政治そのものが機能不全になってしまっていて、自分をマネジメントできない、政治をマネジメントできない。だから、国会で説明しろとか、今まで何十年もやっている政治とカネの事ばかりやっている。政治とカネの問題は、大きい問題だし、大事なことなんですが、そんなのは本来、政党が自分たちでルールを決めて、ルールを破った場合は辞めてもらうとか、自ら解決すべきなんですよ。党内の問題を何年も同じ事を繰り返し、政治が何もできないために、最終的には官僚を叩けば何となくみんな納得するのではないかと。
インタビュー終了後、佐々木さんが言っていたのですが、企業経営者が自分たちの職員のことをバカだ、バカだと言っている。でも、従業員のことをバカだと言っている経営者の方がバカだっていうことあるじゃないですか。だから、日本の政治も、自分の従業員である官僚をバカだ、ダメだと言っているけど、あんたは何なんだ、という話になる。前回も言いましたが、そのような状況の中で、マニフェストが非常に機能しなくなってきている。佐々木さんは、マニフェストについても、一言言っているのでお聞き下さい。
【インタビュー】
佐々木: だから、マニフェストは自己統治のツールだったわけですね。それ以上でもなければ、それ以下でもないという面があったと。しかし、選挙に勝てばマニフェストは国民を統治するツールになるわけです。だから、よく考えてつくれよと。
工藤: その前者のところが曖昧になっちゃいましたよね。
佐々木:前者のところが曖昧なものだから、全部が曖昧になっていく。僕は、政治資金の問題も、基本的には政党の自己統治能力の問題だと思う。つまり、カネを組織の中にあるお金をどういう風に集中して管理するかというメカニズムが、政党の中にないんだから。
工藤: 二大政党を期待したときは、党がガバナンスもきちんと、組織と政策におけるガバナンスを発揮して、未来に対する競争をすると、一応仮定したわけですよね。期待した。
佐々木: そういうことだろうと。
工藤: 期待したけど、それができなかったと。
佐々木: それができなかったし、未だにそれをどうしようかという事について...。だから、僕は、例えば、政治資金制度を抜本的に変えるべきだと。これは党のガバナンスの問題として、避けて通れない問題で、特定の人物がどうとかいう話とはやはり区別して考えないといけない問題だということを前から言ってるんだけど、その意識はまったくないんだよ。
工藤: 僕はこの話を聞いて、言論NPOのこれからの議論の作り方も、少し考えないといけないなと思いました。つまり、僕たちは、選挙時に政党がマニフェストを出し、その党が政権をとったら約束なのだからちゃんと実行してほしいということで、6年ぐらいずっとマニフェストの評価をし、公表してきました。ただ、ここには政党が機能しているという非常に重要な仮定がありました。イギリスのブレア政権の時もそうなのですが、党員の中でマニフェストをつくるところからドラマが始まるわけですね。その中で、2年もかけてみんなで議論をして、各界の人たちの意見を聞いて、ようやく党のマニフェストをつくるわけです。そして、党で決まったことを選挙で出して国民の支持を得たら、ガバナンスや統治のメカニズムをきかせて実行に責任を持つわけです。
だから、日本でも2大政党になって侃侃諤諤の未来競争が起こると思っていたのですが、今の佐々木さんの話を聞くと、現状の党が機能していない。これはよく言われていることですが、鳩山さんの時のマニフェストは、4人が数ヶ月でつくった。普天間の問題についてはマニフェストに入っていなくて、アドリブで鳩山さんが言っていくわけです。つまり、政権公約をつくるという党の機能が非常にうまくいっていない、というところに問題があるから、政権をとった後に、公約を実現するというプロセスが機能しないのは当然なのだな、と思ってきたわけです。
そうなってくると、党の評価は必要ですが、それよりも、政治家の評価をきちんとしていかないといけないのではないか、とすごく感じました。
ただ佐々木さんの話は政党の問題にとどまりませんでした。佐々木さんが言っている「ナショナルクライシス」は、党の統治が崩れているというだけではなく、社会の中にある様々な統治の仕組みが壊れているのではないか、と言っているわけです。僕も思い当たる節があって、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の先生の本に、アメリカでも色々な政府機能への信用が失われていると書いてありました。これは、日本に限ったことではなくて、世界の先進国の中でも同じような現象があります。ただ、日本の場合はそれがドラスティックに動いているような気がします。
例えば、皆さんは、この国の仕組みで何を信用できますか。今の佐々木さんの話では、政治は信用できない。お医者さんは信用できますか、大学の先生は信用できますか、メディアは信用できますか。僕たちは、日本と中国の世論調査を行って議論したときに、日本の国民は日本のメディアの報道が公平で客観的だと思っている人は、2割を切っているような状況があるわけです。メディア報道は信用できない、ひょっとしたら胡散臭いかもしれない。政治も信用できない、大学の先生はどうなんだと。僕は佐々木さんに、大学は信用できますか、と聞いたら、僕が助教授の時に信用を失っていたよ、と言っていました。信用を失った社会の仕組みの象徴が、今度の検察の問題だと思います。色々な問題の信用が崩れているときに、地検は巨悪に対して挑んでいたのではないか、という信用があったと思いますが、今回崩れた。すると、日本の社会の「信用」、つまり統治というものは、それぞれの部門で、それぞれの人たちが責任を持って仕事をしている。その「信用」という社会の仕組みが非常に壊れてきたという状況だと思います。この辺りについても、佐々木さんのインタビューをお聞き下さい。
【インタビュー】
工藤: この転換の主役は誰なんですかね、
佐々木: 日本のリーダー層というものが問われているんだよね。
工藤: 経営も、経済も全ての分野で。
佐々木: 経営、経済、政治、役所も含めて、このグループがディスオリエンテドと言うか、方向喪失状態。
工藤: 信用を失い始めているわけですよね。
佐々木: 全体としてがさっと落ちかねない。で、政治の悪口を言っていい気分になっていると、全部落ちちゃう、という意味で統治能力の危機というのはあるわけよ。日本の場合に。で、僕は20年、30年見ていて、これほど日本の統治能力という問題がクローズアップされたのは初めてだね。
工藤: 初めてですか。
佐々木: 初めてというか、かなり深刻...
工藤: つまり、統治構造の信用力が色んな分野で形骸化して、弱体化している。
佐々木: ついに、検察までいっちゃった。
工藤: すると信用するところがなくなっているわけですね。
佐々木: こういう時はある意味で、ポピュリズムと要するに過剰な約束。できもしない約束をする政治勢力ができていたりするという環境が非常に整っているから、危ないんだよね。で、本当に国民もこれは偽物か、本物かという見極めをしなきゃだめだというギリギリの段階がだんだんと近づいてきているのではないかと。
工藤: かなり厳しい見方だと思います。でも、佐々木さんの言っていること1つ1つが、今回胸に突き刺さりました。インタビューの後に、佐々木さんに、どういう風にしたら解決できるのでしょうか、と聞いてみました。すると、佐々木さんは外部環境に追い込まれるしかないのではないかと言っていました。今、龍馬伝を見ていて、明治維新に関心があるのですが、あの時も黒船が来て、世界が大きく変わっていたことにびっくりしちゃうわけです。世界の大きな変化から日本を守ろうと、その中で日本国をつくろうと龍馬達が立ち上がっていくわけです。同じように、黒船のような大きな変化、外圧がないと統治側にいる人たちが本気にならないのではないかと。ただ、実を言うと、それはそんなに先ではないような気がしていますし、佐々木さんも同じでした。いずれ、そういう話をやる機会はあると思いますが、日本の経済、環境、社会保障など色々な問題に綻びが出始め、壊れ始めている。どこかで、バンとはじけてもおかしくない状況です。ただ、それでも、日本の政治はその課題に対して挑まなければなりませんよね。ですから、どこかで目を覚まさなければいけない状況になると思います。
ただ、僕が一番言いたいのは、目を覚ますのは政治というよりも、僕たち有権者だということです。この番組でも何回も言っていますが、自分たちが本気にならないといけないと思っているわけです。インタビューの最後で、佐々木さんがすごくいいことを言っていて、国民は何が本当なのか、嘘なのか、本物を見極めるギリギリの段階にきている。選挙の時には、こういう手当をあげますとか、こういうことで楽になりますよという甘い言葉しかないじゃないですか。そういうことを実現するのは、お金がないと不可能です。だから、選挙の時には、必ず私は皆さんのためにやります、と言っているけれど、選挙が終わった後には全然違うことをやってしまう。全てに嘘があるとは思いませんが、おいしい話にはそういうことがあると言うことを考えないといけない。そうであるなら、どうやって見抜けばいいのか、ということが、次の段階で問われてくると思います。
まさに、この「ON THE WAY ジャーナル」でやりたいのはそこなんですね。つまり、僕たちは有権者が主役にならないといけないと思っている。みんなが色々なことを自分の目で見て、判断して、自分たちが政治や日本の未来を選ばなければいけない。僕は、そういう社会が一番すてきな社会だと思っています。しかし、あまり余裕が無くなってきました。そういう風な時代にあるという状況を皆さんに、お伝えして、今の日本の政治はどうなの、ということを問わせていただきました。また、意見が、あったら寄せて下さい。ありがとうございました。
(文章・動画は放送内容を一部編集したものです。)