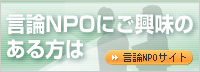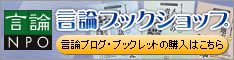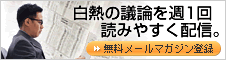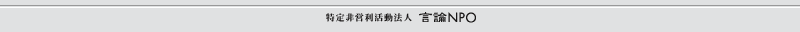« 2010年11月 | メイン | 2011年1月 »
2010年12月29日
「菅政権の100日評価 日本の有識者はどう評価したの?」
-ON THE WAY ジャーナル 2010.12.29 放送分
放送第13回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、「菅政権の100日評価」結果をもとに議論しました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「菅政権の100日評価 日本の有識者はどう評価したの?」
工藤: おはようございます。言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝様々なジャンルで活躍するパーソナリティが、自分たちの視点で世の中を語る、ON THE WAY ジャーナル、毎週水曜日は、「言論のNPO」と題して、私、工藤泰志が担当します。早いもので、今年ももう最後の放送となりました。もう皆さんはお仕事を終わって年末の、年越しの準備を始められていると思います。私はまだ全然仕事で、年賀状は31日になると思いますので、皆さん届かなかったら許してください。27日に菅政権の100日評価というものを、私たちは公表したんですね。その際に、私たちは日本の有識者500人の緊急アンケートを行っていますので、その調査結果を元に今日は菅政権の100日を先週に引き続いて、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。さて、番組では、ご意見やご感想、取り上げて欲しいテーマなどをお待ちしております。皆さんもご意見・ご感想をお寄せください。番組ホームページの水曜日、工藤泰志のページに言っていただいて、そこでメールやツイッターでどうぞ。ON THE WAY ジャーナル、「言論のNPO」今日のテーマはこちらにしました。
谷内: 「菅政権の100日評価その2 日本の有識者はどう評価したの」
おはようございます。
工藤: おはようございます。
谷内: ON THE WAY ジャーナル、「言論のNPO」スタッフの谷内です。言論NPOでは、菅政権の100日評価を公表しましたけれども、かなり低い結果っていうことに...。
工藤: そうですね。予想通りかもしれません。
谷内: ですね。これは有識者のアンケートによる評価と、言論NPOの独自の評価の2つで構成しているということなんですか。
工藤: そうです。やはり僕たちの評価はちゃんとした評価委員が、分野ごとの評価をして、配点基準が全部あるんですね。
谷内: 配点基準。
回答者は508人
工藤: 評価基準が全部ありまして、それに基づいてやっています。言論NPOの評価はいつも厳しいとよく言われているのですよ。それはただ、政策をきちっと評価するための評価のフォーマットがちゃんと決まっているのですね。ただ、この100日だけに限ってはね、有識者にだいたい2000人くらい僕たちは郵送します。かなり企業の経営者とか官僚ですとかね、ジャーナリストとか、各界で話題になっているような人たちにずっと送ります。その人たちの回答をベースにして、僕たちの評価をやっています。よく新聞の世論調査とかがあるじゃないですか。だいたいあの結果の数ヶ月前の状況、つまり僕たちの有識者アンケートは数ヶ月先取りしているんですね。僕たちの有識者アンケートで、支持率が何%と出ると、大体2、3ヵ月後にはその数字になっちゃうんですよ。なので、先行指標と言っているんですね。今日はその有識者アンケートの先行指標、アンケートを元に、ちょっと考えてみたいと思っています。
谷内: 先週も、ちらっと言いましたけど、菅さん100日って難しいです...
工藤: そうですね。菅さんはもう半年経っています。ただ、実をいうと、菅さん、鳩山政権が退陣して、それを引き継いでっていう形になったけど、あの時は菅さんが何をやるのかよくわからなかったですよね。この前の参議院選で、菅さんは自身のマニフェストを出しました。そのマニフェストを実現するということで、ちゃんとした組閣をして第二次っていうか改造内閣ができましたよね。それから100日が12月25日、この前のクリスマスだったわけですね。だから、この100日で菅さんが国民に約束をしたものが、本当にちゃんと実現の方向に向かっているのか。それから国民に、自分たちが取り組んだ問題をちゃんと説明しているか、そういうことを含めてちゃんと聞かなければいけないタイミングに入っているんですね。
谷内: 菅さん、仮免許って言って怒られちゃいましたよね。
工藤: 仮免許って...それは怒られますよね、半年前からやっているのにね。僕たちはこのアンケートはだいたい全部で20項目ぐらいあります。ただその半分以上は菅さんの業績評価になっています。この100日評価は、菅政権だけやっているのではなくて、安倍政権以降、毎回やっています。だから、歴代政権の総理の100日の通信簿と、比較ができます。(安倍政権、福田政権、麻生政権、鳩山政権)それを比較してみると、菅さんは今までの歴代総理の中で、麻生さんと同じレベル、最も低いんですよ。中身によっては、かなり最悪の状況になっています。
谷内: 回答者は、どんな方が多かったんですか。
工藤: 回答者ですか。サラリーマンの人が、サラリーマンって言っても、普通のサラリーマンではなくて、多分企業の中では部長とか、そういう人たちなんですね。それから、企業経営者、社長、会長とか、あとマスコミ関係者も一般の記者さんもいらっしゃるのですが、論説委員や編集長、編集局長とかそういう人とか、学者。後、公務員は政府、国の公務員ですね。そういう人たちがいます。
100日目の支持率は15.9%
谷内: 結構バランスが取れていますね。
工藤: それで、年齢としてはね、40代と50代が多い...でもバランス取れていますね。大体10%ずつですね、それで、菅政権を100日の段階で支持している人が、15.9%なんですよ。
谷内: あ、16%以下。
工藤: 今メディアでこういう世論調査をやっていると、だいたい20%ですよね。多分、遅かれ早かれ、この数字になると思いますね。大体そうなっていくんですよ。この私たちの有識者アンケートでは、鳩山政権の時が33%でした。だから菅さんはその半分くらいなんですね。
谷内: その状況でも30%あった。
工藤: あったのですが、今回はその状況の半分です。それから今回、菅さんにそもそも期待してないっていう人も多いんですが。そもそも期待してないっていう人が、33.4%いました。一方で、はじめ期待していた人たちが、やっぱりこの人には期待できないって思う人が、58.5%います。だから、期待した人がもう期待できないといっている58.5%と、そもそも期待してないという33.4%を合わせるとね、91.9%の人が菅さんにもう期待してないのですよ。じゃあ、あなたは何を期待していたのだということなんですが、やっぱり一番多いのが、3つなんです。1番多いのが、「財政再建の道筋を明確にすること」なんですね。これが34.5%。2番目に多いのが、29.7%で「中長期的な成長戦略を立てて、強い経済を実現すること」なんですね。それから3番目が、25.4%で、「持続可能な社会保障制度を確立すること」です。菅さんがマニフェストを掲げ、参議院選挙のときに言ったのは、強いものを3つつくるということでした。強い財政、強い経済、強い社会保障、つまりこの3つが、基本的に多くの人たちが期待した役割だったわけですよ。それに対しても期待ができないということになっているわけです。
今後の菅政権に期待できないが71.7%
そこで、これからの菅政権に期待できるかということになると、期待できないという人が71.7%なんですよ。だからかなり低い。それで100日間で評価する項目は内政、外政とかいっぱいあるのですが、内政と外政でいずれも評価できないというのが68.8%。逆にどちらも評価できるというのが、2.2%。なので、やっぱり実績ベースではかなり菅さんに対して評価が低い、かなり厳しいんですよ。今まで、僕たちがやってきた100日評価の有識者アンケートでも、全然違うんですよ。僕は今回驚いたのは、コメントがあって回答を拒否する人が結構いたんですよ。この政権は評価するに値しないなんていう。
谷内: そういう人は今まであまりいなかったんですか。
首相の通信簿は1.8点(5点満点)
工藤: そんな声は1つもなかったですね。だから、今、有識者レベルでの見方は、かなり厳しくなっているのは事実ですね。それで、首相の資質っていうものをね、歴代政権についても8項目で私たちは必ず聞いています。これは、「首相の人柄」、「首相の指導力や政治手腕」、「それから首相の見識、能力、資質」、これで3つですね。4つ目は「基本的な理念や目標」、5つ目は「政策の方向性」、6つ目は「実績」、7つ目は「チームや体制づくり」。8つ目は「説明能力」なんですね。これはさっき言ったように、安倍さんの時から毎回聞いているのです。5点満点で、有識者に点数ちゃんとつけてもらうのですが、全体平均は、5点満点で菅政権の100日は1.8点なんですよ。5点中1.8点。
谷内: 半分以下と。
工藤: ただ、よく見たらさっきも言ったのですが、今までで同じ点数の政権があったんですよ。それが麻生さんでした。麻生さんが1.8点。ちなみに安倍さんが2.2点、福田さんが2.3点。鳩山さんが2.4点で、高かったんですね、100日の首相の資質としては。100日時点ですよ。
谷内: 支持率もさっき高かったですもんね。
工藤: それが菅さんは1.8点なのですが、この中でよく見てみると、この5つの政権の中で、最も低いという項目が3つあったんですね。それは「指導力」、それから「実績」、「説明責任」この3つです。これが歴代政権で最も低いんですね。他にも、政策課題、つまり100日間で取り組んだ政策課題はいっぱいあると思うのですが、それを30項目について全部評価するんですよ。「期待できますか」、それから「上手く対応していますか」とか。「今は期待できないけど今後は期待できますか」とか。でも期待できるっていう人が過半数を超えているものが1つもないですね。まぁ、相対的にということでいえば、30%ちょっと、例えばTPP参加の検討とか、法人税率の引き下げなど税制の問題とか、そういう問題がちょっと出ましたけど、ほとんどがうまく対応ができておらず、今後も期待できないという結果でした。段々さびしくなって...、年末なのに、このままどうしたらいいのか...
谷内: 言葉が出なくなりますね。
何が、約束かよくわからない
工藤: 100日はかなり厳しい状況なんですね。それから、菅さんが今のこの時点で国民に説明をするべきじゃないかということで、何を国民に説明が足りないのかとの設問で、一番多いのは何なのかというと、「日本の今後の経済成長に向けた中長期的な戦略を説明すべき」じゃないかというのが42.3%なんですね。そこに迫るように37.2%で並んでいるのが、菅政権が任期中に何を実現したいのか、それを政策面で何を約束しているのかよくわからないというんですよ。それはやっぱり説明してくれないかと。これは僕もちょっと言えるなあと思うんですね。菅さんのマニフェストそのものが曖昧だという問題もあったのですが、やっぱりこの政権中に何を実現するのか、いまいちわかりにくいですよね。この前も財政再建の話をしましたけど、G20で財政再建は2015年までに、プライマリー赤字を半減するということが国際公約として約束されているわけです。でも菅さんは2013年で任期は終わるわけです。任期末までに彼は何をするかということを語ってないですよね。だから、やっぱり自分がその政権を担うということは、政権を担うことが目的ではなくて、何かを実現するために政権を担うわけだから、それがなかなかわかりにくいという状況なんですね。確かに菅さんの政策評価という点ではかなり低いのですが、よく考えてみるとね、政権に対する評価という以前に、どうもこの回答者、有識者の意識の中にはね、日本の政治に対する幻滅がね、かなり広がっているような感じなんですよ。
谷内: この番組でもずっとやっていますよね。
日本は国家危機の段階が、43.7%
工藤: ええ。実をいうと今回、僕が非常に驚いたことは、日本の政治の現状を皆さんはどう見てるのか、ということなんですね。この結果が、非常に面白くて、今まで何回も同じ設問があるのですが、国民の認識が段々変化しているんですよ。一番多いのが、43.7%です。これが、昔この番組で前の東大総長の佐々木毅さんが、今ナショナル・クライシスじゃないかと言ったことがあるんですが、全くそれと同じ答えなんですね。「政府の統治、ガバナンスが崩れ、政治が財政破綻や社会保障などで、課題解決できないまま混迷を深める国家危機の段階」という回答が43.7%なんですよ。でね、国家危機なんていうのが半数近くいるということを、日本の政治家は考えなければいけない局面だと思うんですね。ちなみに、去年の衆議院選挙で政権交代したじゃないですか。衆議院選のときもアンケートをして、この日本の政治の現状をどうみますかと聞きました。それから鳩山さんが100日経った時点でもそれを聞きました。それから、政権交代する前の麻生さんの100日のときにも、日本の政治の現状をどうみるかと聞いたのですが、認識が変わっていっているんですよ。麻生さんのときに、有識者はどういう風に見たかっていうとね、1番多いのはちょっと違うのですが、半数ぐらいに迫ったのは、「政権交代でこれまでの政治を一度壊すべき時期」というのが、46.8%だったんですよ。なので、麻生さんの100日のときは、もう自民党じゃダメなので、政権交代して壊さなきゃいけないのではないかという声が半数あって、もう1つ半数あったのが54.5%なんですが、やっぱり既成政党の限界はもう明らかだったと。だから政界再編すべきじゃないかの過渡期だという回答でした。これが2つ並んでいたんですね。その後、昨年の総選挙で政権交代しました。それで、その総選挙直後にアンケートをしたときに、多くの人はどうみたのかというと、「政権交代をすることによってこれまでの政治を一新すべきとき」というのが、23.4%に減ってですね、「民主党や自民党などの既成政党の限界が明らかになって、政界再編に向かう時期」が半数を超えるわけですよ。つまり政権交代を期待して総選挙になって政権交代が実際に起こった。その後、鳩山さんの政権が始まった中で、もう有識者の認識は、政権交代の期待はまだ残っているのですが、やはり既成政党では限界があるのではないか、という声が出てしまっていたんですよ。それで今回ですね、今回の評価はどうなったかというと、正に国家危機の段階というのが43.7%、それに並んでいるのが、「未来の選択肢が政党から提起されないまま、サービス合戦や官僚たたきに明け暮れ、ポピュリズムが一層強まる時期」。それから「出口が見えない日本の政治的な混迷や空白の始まり」。つまり、麻生さんから始まった今の政治に対する皆さんの意識はね、はじめは政権交代に期待したけど、それがなんか違うのではないか、それだけでは。つまり期待したものが裏切られているんじゃないか。
有権者が問われる段階
ただそれをどうやって変えればいいのかっていうことを、多くの人が見えなくなっているわけですね。それが多分、今の混迷にきてしまったのだと思うんですよ。だけど展望が無いままで終われないので、その中で僕たちは、日本の政治を変えるために、誰をあなたたちは信用しますか、と聞いてみたんですよ。そうしたら、半数近くの人が信用したいという人がいました。それは有権者。55.3%。それは有権者に期待しているのではなくて、有権者がしっかりしないとこの状況は打開できないのではないか、ということを多くの人は言っているのですよ。それに並んでいるのが、50%でNPO・NGO。それで、政治家に期待している人が49%いました。メディアに期待している人は25%しかいないんですよ...既成メディアだと思うんですが。それから、学者に対しても期待が少ないですね。あと、地方などの首長には50%期待があるので、NPO・NGOと地方知事は同じくらいなんですね。だけど一番多いのは、有権者。今回の僕たちの評価は、菅政権を約束に基づく形で政治をみるためにちゃんと評価して、チェックしてこうということを目的にやっているのですが、この有識者の調査で、評価にとどまらず、日本の政治を本当に変えていかないといけない、しかも、有権者がきちっとしっかりしないともうダメなのだという事が、アンケートの中からも浮かび上がったんですね。これは、今年私がON THE WAY ジャーナルで言っていたことですし、色んな人たちが言っていましたよね、色んな人たちが言っていたのは、有権者も自分たちの判断が、誤った判断をするということを自覚し、もう許されない段階にきてるんだと。やっぱり嘘を自分で見破ることが必要だと。しっかりしろということを言っていたということがね、このアンケート結果から浮かび上がったわけですね。
さて、そうなると新年、私たちは責任重大だなと思うんですね。そういう覚悟を固めて年を越したい。さびしいよりも、木枯らしの中で覚悟を固めて来年に向かって除夜の鐘を聞いて、新年、くそっ、がんばるぞと思っていきたいと思います。
新年は奮起しよう
谷内: 奮起しろと。
工藤: 奮起したい。私も頑張ります。ということで、時間になりました。なんか決意表明と決意を迫る形で終わらせてもらいましたが、来年、多分日本は変わる時期になると思いますので、是非皆さんと一緒に色んな日本の将来、未来を考えたいと思います。今年はどうもありがとうございました。また来年、一緒に皆で議論していきたいと思います。どうもありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【 後編 】
投稿者 genron-npo : 20:04 | コメント (0) | トラックバック
2010年12月22日
今の政権は何を実現したいの?「菅政権の100日を考える」その1
― 増田寛也氏の見方 -ON THE WAY ジャーナル 2010.12.22 放送分
放送第12回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、元総務大臣で野村総研顧問の増田寛也さんへのインタビューを中心に、言論NPOが毎回実施している政権100日評価について話し合いました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「今の政権は何を実現したいの?菅政権の100日を考える」その1
― 増田寛也氏の見方
工藤: もうまもなくクリスマスということで、楽しい予定がいっぱいあると思います。でも、私はクリスマスの日は、菅改造内閣の100日評価をまとめるために作業を進めています。菅政権というのは半年前にできたのですが、参議院選挙が終わって代表選挙が行われ、第二次の改造内閣ができて100日目というのが、まさに12月25日なのです。で、僕たちは政府の100日目の実績はどうなのだろうということを発表することにしていますので、今その作業で大わらわです。それから、この評価作業に活かすために有識者2000人にアンケートを出したり、年末なのに、かなり忙しい状態です。
今日はこの100日に関して、地方分野の評価を担当していただいている、増田寛也さんにインタビューを行ってきましたので、増田さんと一緒に菅政権の100日を考えてみたい、と思います。増田さんは今は、野村総研の顧問ですが、昔は岩手県知事や総務大臣をやったりして、まさにマニフェストを提案し、主導していた人です。
ON THE WAY ジャーナル、「言論のNPO」、今日のテーマはこちらにしました。
谷内: 「今の政権は何を実現したいの?菅政権の100日を考える その1」
おはようございます。ON THE WAY ジャーナル「言論のNPO」のスタッフ谷内でございます。言論NPOでは、毎年のように年末に100日評価というものをやっているのですよね。この100日評価作業の一端をここでは紹介したいということで、今回がその1ということですね。
100日後から監視を始める
工藤: そうですね。
谷内: 師走で慌ただしいのですが、まず、100日にこだわっているのはなぜですか。
工藤: 最近、日本の政権は、毎年9月頃に誕生しているので、いつもクリスマスの時期に100日の評価をすることになっているのですね。なぜ、100日評価をやっているかというと、やはり有権者と政治との関係をもっと緊張感のある関係にしたいからです。やはり、政治家は選挙の時に、有権者にこういうことを実現しますよということを約束して、その実現に責任を持ってもらいたいじゃないですか。そのためにも、有権者が、約束の実現をきちんと監視する始まりは100日からだと、思っています。結婚しても、ハネムーン期間というのは100日ぐらい必要じゃないですか。その時は温かく見守って、でも100日経てば有権者は厳しく見るぞ、ということを日本の社会に定着させたいと思ったのですね。
谷内: ただ、菅さんの場合は100日ってわかりにくいですよね。
工藤: ただ、菅さんが自分の約束を国民に出したのが、この前の参議院選挙だったのですね。その後に、代表選に出て、自分の約束、つまり何を実現したいかということを一応、出した上で、政権を誕生させたのは第二次菅内閣だと思っています。だとすれば、そこから100日ということを厳しく見ないといけないと思っています。ただ、実は評価をしてみると、本当に大変です。つまり、菅さんは何を実現したいのかということが、段々見えなくなってきているのです。今、各省庁の官僚や、専門家にヒアリングしているのですが、基本的に今の政権は、ある目標をベースにして、それを実現していくというプロセスになっていないために、非常に苦労しています。だけど、こうした評価をやることがマニフェストのサイクルを回すことにもあるのです。では菅政権の100日は期待通りだったのでしょうか。今回は増田さんにインタビューをしてきましたので、その話を元に議論を進めたいと思います。
がっかりの繰り返しの100日
増田: まず政治の意思決定ははっきりと行う。そのために意思決定の仕組みを変えて、その上で政策をきちんと決めて実行していく。私は、そのあたりに期待をしていました。国家戦略局構想だとか色々ありますが、それがどういうものにしろ、内閣がきちんとリーダーシップを発揮して、社会保障とその財源としての消費税の問題だとか、今までの従来の決定の仕組みでは大きな決断ができなかったところ、その意思決定の仕組みを変えてそれできちんと実行して欲しいと思っていたのですが、仕組みを変えることもできない。そこは従来型の自民党タイプだし、結果として決まることは何もない。
目がうつろになっただけで結局何も決まらない。そういうがっかりの繰り返しの100日だったと思います。
自分はこういう世界をつくりたい。例えば中曽根さんが前川レポートによって、内需主導型の経済をつくっていきたいとか、田園都市構想をまとめた大平内閣、最近では小泉改革。色々議論があるにしても規制緩和を行って、経済の成長を目指すとか何かそれなりのものがありました。今回は政権が変わったわけだから、例えば政治に信頼を取り戻すクリーンさ。その一点でも良いですよ。
工藤: でもその一点もやらないでしょ。
増田: 総理のポストについて、総理大臣でいるということが目的で、だから石にしがみついても離さないと。駄目と言わない限りはずっとこのまま続きますね。
工藤: 佐々木毅さんが、今、日本の政府の統治が壊れてきていて、ナショナルクライシスじゃないかという話をされていました。やっぱり今の目的が間違っていると、存在、権力を維持することが目的になっていると、それを活用して...
政党の作り直しこそ必要
増田: 手段が完全に目的化してしまっている。佐々木さんがいみじくも言ったように、政権の構造を作り変えなければいけないのですが、それは結局政党のつくりかえをやるしかないと思います。政党というのは我々がまさに選んでいる政治組織なわけですが、これまでは政治リーダーを政党の中で曲りなりにも育ててきたわけです。つまり、政党が政治的なリーダーシップのある人間を見つけて、その中で代表者としてね、党の総裁なり何なりで送り出して、それで政権を作り上げてきましたが、現在は、その政党が実は政治的な人間を形成させるという能力を失っています。これは、民主党の中を見ても自民党の中を見ても、今のこういう中で次に担うリーダーがいるかというと心もとないですね。ですから私は政府に問題がありすぎると思うのですが、つきつめてみれば政党のつくり直しみたいな、政党のほうに行き着くんじゃないかと思います。
工藤: つまり、政党そのものが壊れているというか、政策を軸にして何か動いていくという形ではないので政権もそうなってしまいますよね。
増田: 民意をきちんと受け止めて、それを政策という形で辛い決断もして、それでまとめ上げる。それを政権についてから、権力を武器に実現していくというのが、今までの政治だと思っていました。しかし、今の政府では、役人が社会保障などを政府の中で案としてまとめれば、政党が言ってくることは、そのうちの負担は全部重過ぎるからそこはやめにしようと。だから、場合によっては国民に厳しい負担もお願いせざるをえない。それを自分たち政党は、選挙で負ける覚悟で捨て身の覚悟で国民に訴えるということを何もしてないですからね。
工藤: のっけから、かなり厳しい話になりました。この前出ていただいた佐々木さん、石破さんも、今回の増田さんも、皆さん共通しているのですが、政府の統治ということがうまく機能していないということを、非常に気にしているのですね。実は、この間、国家戦略室とか、官僚の人たちにヒアリングをしてきたのですね。そこでまだ成立していませんが、政治主導法案が国会に出されており、継続審議になりました。国家戦略室を局に格上げして、その中で色々な国家の戦略プランを立案して動かそうということが、去年の民主党のマニフェストにもあったし、それを動かそうとしていたのですが、それが全く機能していません。それだけではなくて、色々な人に話を聞いて、ちょっと何か変だなと。つまり、縄張り争いをしているような感じで、国家戦略室という動きと、官房副長官補室というのがあって、指揮ラインが2つあって、その下に省庁がぶら下がっている状況です。その統合が行われていないのですね。だから、役割の奪い合いというか、それだけで何ヶ月も使ってしまって、その間は何も議論が動いていない。やはり、政権とか政治が、政策実行を動き出す仕組み作りに、今の100日時点で見ると、かなり失敗しているのだと感じています。この状況が改善されないということになると、例えば年金、財政破綻など今の日本には色々な問題がある中で、政府として機能しないのではないかということが、今100日評価する時点で気になっています。これに関して、増田さんがどう思っているか聞いてみたいと思います。
工藤: となると、このまま民主党政権でいっても期待ができないということになりますよね。これはどこがだめだったのでしょうか。
国家戦略局(室)は機能していないし、行政刷新会議も本来は制度設計をするところだったのにそれもできずに、事業仕分けだけになってしまった。つまり、官邸機能として、官邸中心の政策立案・実行という仕組みがないわけですよね。
増田: しかも事業仕分けも3回やったけど、「この法的根拠はいったい何なんだ」と。仕分け人の権限はいったいどういうものに基づくんだ、ということを相変わらず言わないままだから、各省だって、事業仕分けの会場で黒板に廃止と書いたって何の意味もないことはわかっているので、名前だけ変えて正々堂々と予算要求復活させる。
工藤: だから、まずそういう形で政策立案・決定のプロセスが壊れちゃいましたよね。一方で党側に政務調査会をつくったのだけれど、今度、党の人たちは意見がありすぎてそれをまとめきれない。
増田: 党は今壊れていますからね。きちんとした責任を果たすという機能は失われていて壊れています。そうすると、党もラクな国民受けのすることばっかり言うようになってくる。結局、党が政府に言ってくるのは、負担が重過ぎるから国民負担を求めるのやめよう、やめようということになる。
工藤: そうですよね。そうなると、今の政治、日本の政府は日本の課題に答えを出せない非常に危険な状況にきているということ。日本の今の政治の現状っていうのは、どういう時期なのでしょうか。
日本は政治的空白であり、国家危機の時期
増田: 全く期待を持てないし、正直に今の事態をとらえると空白の時期であり、さらには、もっと国が危うくなる危機の時期と思いますね。その打開をどこかでしなければいけない。でもあえて、突き放して言えば、おそらく年が明けてから一層ポピュリズムは横行するでしょう。
工藤: 実は今、2000人の有識者にアンケートをやっています。その際に、今の日本の政治についてどう思いますか、という設問を毎年聞いています。そうすると、最近の傾向は、二大政党がきちんと機能すると思っている人はほとんどいません。それよりも、既存の政党に対して、非常に疑問が出てきている。去年の段階で、政界再編を含めて、色々な新しい政治を模索する時期ではないかという声が、日本の有識者の中にはかなり多いのですね。にもかかわらず、最近気になってきたのが、政党や政治の再編よりも、ひょっとしたら日本の政治が混乱して、全く出口がみえない、そういう時期になっているのではないか、国家危機の段階にきているのではないか、という設問を今回入れてみました。それを、増田さんに聞いたところ、増田さんがそこに食らいついてきました。まさに、政治の空白と国家の危機だと仰っていました。多分、日本の多くの有識者もそういう風な見方をしている可能性があります。しかし、日本の統治が崩れてきても、財政や社会保障など、日本の課題というのはあるわけですね。そうなってくると、非常に困難な状況を国民は覚悟しなくてはいけないという状況になってしまうわけですね。そこに、さっき増田さんが、無責任な発言になるかもしれないと言いながらも、そういう状況になるのではないかと仰っていたわけですね。その辺りを、もう少し聞いてみました。
甘んじて危機を受け入れる
増田: しかし、この状況は小手先のことで変わるようなことではありません。2年3年続くかもしれませんし、国がどうなるのか、という話があるかもしれませんけれど、むしろ今は色々なことが、国政に限らず、地方行政も含めて、様々に起こったほうがいい、何でもありで起こったほうがいいと思います。そういう混沌の中から、やがてはポピュリズムからもう少し冷静に考える方向に...
工藤: 民主的にきちっと議論を重ねて。
増田: プロセスを大事にすると。その上で成果を求めるという風に変化していくのではないでしょうか。今は二大政党にもなかなかなっていないような状況ですが、今の混迷を脱するためには、菅さんは早く辞めたほうがいいと思います、本当は。選挙しないでしょ、なかなか、怖くて。
工藤: 選挙をすればいいんですよね。国民が全く参加できない政治の混乱ですから。
増田: 混迷が2年くらい続くと、出口も見えない。その間にTPPも参加できないとかいう話になりますよ。参加できなくなってどうなるかというと、経済がさらに悪くなるだけというくらいのつもりでね。また、さらに国民生活は苦しくなるかもしれない。結局開き直っていえば、我々が全部選んだ国会議員の中で行われていることです。地方政治と違って国政についてはリコールできませんから、それを甘んじて受け入れながら次の2013年の衆参同時選挙に備えるしかないのではないでしょうか。そういう現実を一度本当に甘んじて受けるということを我々もやらないといけないのではないでしょうか。そこから始めて、政党をしっかりと自分たちで動かす。地域政党のほうに行く人たちもいると思いますが、私としては、それは限定的だと思います。むしろ、全国規模の政党がもっとしっかりする必要があると思うのですが、全国規模の政党が各地方選挙で足腰も強くした上で、本当に国としての世論を統一するような責任を果たすべきだと思います。そういう全国政党のつくり直しのようなことに繋がっていって、はじめて政府が機能してくるのではないでしょうか。高機能の政府というのはそういうことだと思います。
ただ319議席で3分の2の議決に足りないからといって、社民党とくっついたりするのは無理で、数合わせをしたところで、中の政党の考え方が違うわけです。政党は基本的には主義主張、思想、信条を同じにするものの集まりだという原点に立ち返って、政党のマネジメントをもう一回やり直すという、政党の作りかえをやらないといけないと思います。
既成政党の数合わせでは答えにならない
工藤: 今回、増田さんの話を聞いて、かなり深刻なのですね。つまり、政権交代をして、一つの政治をチェンジするということ自体はよかったし、大事だったのですが、政府があるものを実現するという「統治」というものがあります。政策を実現したり。そこが、非常に準備不足のまま、混乱してしまったと。ただ、そこの原点には政党そのものの機能が非常に脆弱になっているのではないかと。そうなってしまうと、単なる既成政党の枠組みを数合わせでやったとしても、ほとんど答えにならないと思っている訳です。だから、彼は、これは甘んじて受け入れるしかないと仰っているわけです。つまり、日本の政治を選んだことのツケが来るだろうけど、それを経ることによって、本当の意味で、政治が強くなるのではないか、そういう問題提起をしたわけです。ただ、その時は、まさに、住民とか有権者が、そのプロセスの中で、きちんとした政党の在り方とか、自分たちと政治との関係を見つめ直すとか、そういうことができないといけない。そういう話だったわけです。最後に、そうは言っても、マニフェストは大事なのかと聞いたところ、増田さんは凄い大事だと言っていました。つまり、こういうプロセスが大きく変わる時も、有権者と政治との緊張感が絶えずないといけないわけです。
2011年、日本は新しい時代への基礎固め
今日は、クリスマスの前夜としてはあんまり楽しくない話でしたが、これまで議論してきたことと同じで、僕たちが今の政治に対して、ある程度覚悟を固めないといけないのだなと思いました。そうやって、2011年は新しい時代に向かい合おうと、そういう覚悟を新たにして、時間になってしまいました。
次週は、僕たちが今評価作業をしていますので、それについてきちんと皆さんに説明をしたいと思っています。また、皆さんの意見などありましたら、どんどんお寄せください。今日はどうもありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【後編】
投稿者 genron-npo : 15:00 | コメント (0) | トラックバック
2010年12月15日
「強い市民社会」はどうやってつくるのか
-ON THE WAY ジャーナル 2010.12.15 放送分
放送第11回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、ゲストに大学評価・学位授与機構准教授の田中弥生さんをお迎えして、市民社会と非営利組織について議論しました。田中さんは、あの経営の神様、ピーター・ドラッカーと「友人」。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「強い市民社会」はどうやってつくるのか
工藤: 今日は先週に引き続いて「日本の政治の危機と市民社会の可能性」について考えてみたいと思っています。先週は元フランス大使であり 国際交流基金理事長の小倉さんのインタビューを中心に議論をしてみました。彼は、日本の政治が危機だからこそ市民社会を成熟させるチャンスであり、多くの人は本音では社会とか地域とみんな繋がりたいと思っているのではないかと話をしていました。
この繋がりということを聞いて「はっ」と思ったのですね。やはりこの市民社会の中で、一般の市民と社会とを繋げる役割というのは、非営利組織なのですね。ここでやはり非営利組織、NPOという問題をここで1回しっかりと考えてみようと思いました。ということで、今日は私の仲間で、日本のNPOの研究では第一人者だと思うのですが、大学評価・学位授与機構准教授の田中弥生さんをスタジオに呼んでいます。彼女と一緒に、今日のテーマである、「強い市民社会はどうやってつくるの」を話し合ってみたいと思います。田中さん、今日はよろしくお願いします。
田中: よろしくお願いします。
工藤: さて田中さんといえば、あの経営の神様で、今、日本でも大ブームになっているのですが、ピーター・ドラッカーの翻訳もしているのですね。で、よく聞いてみるとあのピーター・ドラッカーとは友達だというのですよ。で、えっと思ったのですが、僕も写真を見て、ピーター・ドラッカーのおじさんと並んでいる2ショットを見てびっくりしたことがあるのですが、ドラッカーさんと田中さんはどのような関係だったのですか。
田中: はい。そもそも93年になるのですけども、ドラッカーさんを4年越しで、企業の話ではなくて、企業と非営利組織の話をしてほしいということで、日本にお招きしました。それが93年でした。1000人近い方がそこに集まったのですが、翌年に私はなぜかクレアモントに勉強しに行ってしまいまして。
工藤: クレアモント大学でドラッカーが教えているわけですね。
田中: そうなんです。クレアモント大学の教授でいらっしゃって、市民社会とか、非営利組織のことを勉強したいと言ったら、じゃあアメリカに来れば、ということで、近くに家を探して下さいまして、時々車で学校に送って下さったりして、夏で、短期だったのですが通いました。
工藤: なんだか友達みたいでしょう。友達なのですか。
田中: あの、Dear old friendということでFAXをいつも下さっていました。
工藤: そうですか。なんか危ないという感じもしましたけど。そうでもないのですか。
田中: いえいえ。
ドラッカーの非営利セクターへの関心
工藤: 僕もドラッカーさんの本をよく読んでいるんですね。非常に感心したことは、経営の神様というか、経営をやっている人は、晩年はみんな市民社会とか非営利セクターの研究に走っちゃうじゃないですか。あれはなぜですかね。
田中: たぶん経営の先生というのは、営利、非営利というよりは、組織に関心があるのだと思うんです。
工藤: 経営をするということですからね
田中: で、非営利組織の場合には、目的を達成するための道具というところが非常にはっきりしていますので、営利以外の目的を達成するための組織というものに関心があるのだと思いますね。
「流動化する知識ワーカー」とは
工藤: 僕も彼の長い、分厚い本を読んでいて途中で大変だったのですが、アッと思ったことがあったのは、たぶん「断絶の時代」...ちょっと違う書名だったかもしれないのですが、知識社会という中で、大きく社会の仕組みというかが変わってきたのだと。それはどういうことかというと、これまでは若い人たちは会社で働くと会社人間になってしまうと。つまり会社に忠誠を尽くすという生き方がほとんどだったのが、ある局面から会社への忠誠ではなく、自分の持っている知性、知能とか技術とか、つまり自分の能力に忠誠を尽くすと。つまり、例えば会社ではなく、自分の力が発揮できるところに結構動いていって、流動化していると。だから、「流動化する知識ワーカー」という言葉があったのですがね。ただその人たちはふらふらしているわけで、その人達は最終的には自分の能力を社会のために使いたいんだと。その「流動化する知識ワーカー」を社会につなぐ役割が、非営利組織、NPOなのだと、と書いているのです。これは本当にそうだと思ったのですね。というのは、僕たち言論NPOも 大学生のインターンがいっぱい来るのですよ。その人たちは何か自分で社会のためにやりたい、自分の勉強していることを何か活かしたいのだけど、大学の中で先生がそれに向かってくれないというのでよく事務所に来てね、彼らはどっかに就職して一生を生きるというよりも、何かを実現したいということをよく言うのですよ。だからこの底流は日本でもあるのだな、と思ったんですが。そのあたりはどうですか、ドラッカーさんと一緒に話をしていて。
「会社のため」に働くのではなく、「会社と」働く
田中: はい。おっしゃるとおりなのですね。若干重複しますが、「流動化する知識ワーカー」という言葉は、ドラッカーさんが90年代中頃から使い出すのですけれども、要は、今までは会社人間だから自分の忠誠の対象は会社だったのですね。でも、知識をベースにする知識ワーカーというというのは自分の能力や関心にロイヤリティがあるので、「会社の」ために働くのではなく、「会社と」働く。会社はたまたまそれを活かす場だと言い切っています。
で、その時に、でも人間というのは何かに属していたい、あるいは社会で生かされているということを実感する場がほしいので、おそらくそれはもう企業ではなくなる。じゃあ何かといえば非営利組織でのボランティア、コミュニティでの活動だろうとはっきりおっしゃっていたんです。
工藤: そう言っていたんですね。
田中: はい、おっしゃっていました。それで、1995年、日本に非常に関心を持っていましたね。なぜかというと、95年...
ドラッカーは日本の何に関心を持ったか
工藤: オウム事件だよね。
田中: オウム事件と、それからもう一つは阪神淡路大震災。この2つの事件をドラッカーさんは結びつけたのです。なぜかというと、オウム事件はたいていの場合はリスク管理の問題として議論されることがあるのですが、全然違った側面を見ていまして、つまりオウム真理教の上層部、幹部の人たちが非常に高学歴の優秀な若者だったということが一番に気になると言っていました。
工藤: なるほどね、そういう人たちを、きちっと社会につなぐ受け皿が全くないために、そういう誤った動きに発展してしまうという危険性ですね。
田中: こういう人たちのエネルギー、帰属欲求みたいなものをプラスの方向に、正しい方向に受ける、受け皿がないという社会は非常に危険だとおっしゃっていました。
工藤: 一方で、阪神淡路大震災のときは、全国からボランティアがリュックサックを背負ってみんな行って、やっていましたよね。あれもドラッカーはびっくりしたんじゃないのですか。
田中: そうなのです。だから、オウムの事件を最初に言って警鐘をならしますけど、でも明るい兆しもあるよと。それは阪神淡路大震災のときに活動したNGO、NPOの活動であるし、そこに集まってきた人々のエネルギーだと。それをプラスに変える力があるじゃないかと結びでおっしゃっていました。
工藤: 最近僕もニュースを見てびっくりしたのは、アメリカの中でもやっぱり政府とか...アメリカは元々政府を信用しないという傾向があるのですが、統治に対する不信があると。その中でハーバードを出た最優秀の学生達が企業や官僚、政治家になるのではなくて、NPOで働くという風になっていると。これはどういうふうな現象なのですか。
アメリカのエリートは非営利セクターに関心
田中: 今おっしゃっているのは特にTeach For AmericaというNPOなのですが、実はビジネスウィーク誌によりますと、今年の文系の人気ナンバーワンの就職先は、ウォルト・ディズニーを抜いて、
工藤: え、そうなのですか。
田中: そうです。企業を抜いて、このNPOが1位になったのです、就職先として。それで、今おっしゃったようにハーバード、イェール、コロンビアなどのいわゆるエリート層と言われている学生が、毎年2年間のインターン、教師のインターンをやるということで、毎年4000人近い人たちが応募してくるのです。
工藤: つまり、リーマンショックなどいろいろな経済危機があって、政治も、国際政治も多様化して非常に混迷化しているんだけど、確かな何かの変化が始まっているということですね。
田中: そうですね。
工藤: 僕も実をいうと、言論NPOの仲間で、ある石油会社の大会社の会長だった人がいたのですよ。僕の友人で、日本のオフィスに行くと、本当に日本の大会社の社長なので、ちょっと偉い感じなのですが。その人が何を血迷ったというか、何を考えたか、イギリスのクリントン財団、NGOに転職しちゃったのですね。それで、その人が一年後に、僕の事務所に入ってきたのです。顔が全然違うのですよ。「工藤さん、元気?」という感じでした。どうしたの、と聞いたらNGOに行ったと。じゃあ何をしているのと聞いたら、世界の若者が大体2000人くらいボランティアとかスタッフでいるらしいのですよ。そこに、世界のハーバードやオックスフォードなどのトップクラスの人たちがいる。その人たちは給料が安いのにそこに来て、働くというんですよ。何をやるかというと、例えば、アフリカの医療の問題の仕組みをデザインして課題を解決するために何かプロジェクトをしたり。どうしてやっているのかということを、彼もびっくりして聞いたらしいのですが、つまり世界の若者は何かの課題の解決をしたいんですよ、自分たちで。政治家とか、誰かに任せるのではなくて、世界がこれだけ困っていて、色々な問題があるときに自分たちにも何かできるのではないかと思ったわけね。
田中: そうですね。まさにドラッカーが言うように、自分が社会の課題の解決に向かい合って、しかもそこに貢献しているという実感があるから、ご本人いきいきしたんじゃないのですか。
課題を解決する、世界の若者に見られる価値の転換
工藤: いきいきしていましたね、魅力的で。そうやって考えてみると、日本の政治家で課題解決している人って誰なのかよくわからなくて。政治家こそがそういうことで競わなければいけないわけなので、ひょっとしたらね、この今の政治的構造を大きくシステムチェンジする局面に来ているんじゃないかという風に感じているのですね。
ただ、一方で、やっぱり田中さんに聞かなければいけない問題があるのですね。そういうふうに大きな変化が始まっている、世界的に。日本も間違いなく変化は始まっているのですよ。だけども、その受け皿としての市民社会を考えた場合、何かこう非常に低迷しているというか、何か運動家みたいな、自分たちは近寄りがたいという、何か、なんとなくピンとこない感じがあるのですよ。それはなぜですかね。
日本のNPOの何が問題なのか
田中: ドラッカーさんの話に戻れば、NPO法ができたのは98年なのですが、95年の時点で、たぶん欧米並みに非営利セクターが成長すると予言していたのですね。その数は、今はNPO法人の数は4万ですから、予言は当たってはいるのです。だけど、問題は中身で、おっしゃるとおりで、市民との繋がりとは具体的に言えば、「ボランティア」と「寄付」なのですが、4万のうち過半数が寄付を全く集めていなくて、ボランティアも全くいないという団体がけっこう増えてきているのです。では何をしているかというと、行政からの委託を受けて仕事をしているということで、行政の下請け化とよく言われるのですが、そちらに走ってしまっている。それで、市民との距離が開いているんです。
政府系NPOって何?
工藤: この前事務所に『チェンジメーカー』を書いた渡邊奈々さんが来たじゃないですか。で、田中さんも一緒にインタビューしたのだけど、やっぱり日本のその雰囲気は考えられないと言っていましたね。何かこう、政府NPOと、民間NPOは違うのではないかと
田中: 政府系NPOって
工藤: 政府系NPOと言っていましたね。つまり、そうではなくて、もっと自発的で、市民が自発的に何かを感じると。それに対して、何か取り組みたいという流れが世界の流れなわけですよね。何かが日本流にアレンジされているためにね、何となく政府系、官僚系みたいになってしまうというイメージなのですかね。
田中: そうですね、まあ基本にあるのはお上意識。
工藤: お上意識。誰かにお任せしたいというか...
田中: お任せしたいし、お上はやはり権威なのだと。そこに入り込んでしまうことで、いつのまにか、自分たちは既得権益を壊す存在だったはずが、自分たちも既得権益に入ってしまっている状態だと思いますね。
工藤: もう一つ感じているのは、例えば言論NPOのボランティアというのは、さっきの学生だけではなくて、大学の先生とか、田中さんもそうなのですが、そういう人たちがひょいと来て手伝ってくれるじゃないですか。ハイレベルの専門的な人たちが、アフター5や休日を利用して、社会に色んな形でお手伝いするという大きな流れがあるじゃないですか。これが多分、大きな変化なのだけど、何となく非営利型も運動家というか、古い感じ、近寄りがたいような雰囲気もあるじゃないですか。
田中: 一部の草の根の人たちの専有物のように見えているというところは確かにあるかもしれないですね。
工藤: でも、それだけでは、大きなこの人たちの受け皿になっていきませんよね。
田中: それはそうですね。
工藤: ということは非営利のセクターの世界も今変化を求められているということなのでしょうか。
立ち位置は行政側か、市民側か
田中: そうですね。自分たちの立ち位置を行政側に置くのか、市民側に置くのかということを今一度見直す必要があると思います。
工藤: でも、それを考えると別にNPOだけではなくて、大学もそうだし、みんなだよね。みんな機能してない感じがしませんか。例えば日本の経済的な問題や財政、色々なことに危機があるのに、それに対して誰が取り組んでいるのだろうと。メディアはどうなのだろうと、既存のメディアも含めて。日本が本当の危機なのかもしれないのに、それに対しての色々な動きが、何で色々なところに出てこないのだろうか。田中さんは、その辺りはどう見ていますか。
田中: 既存の...先程の言葉では、エスタブリッシュメントとか、制度の中に取り込まれてしまっているので、今のやり方が違うのだということを、体制に言うことによって、自分に返り血を浴びるわけですから、その勇気がもてないのだと思います。
工藤: 諦めてしまっている感じですか。それとも、何となく悶々と悩んでいる感じですかね。
田中: 長いものには巻かれろ、ですね。
工藤: そこまできてますか。
田中: と思います、私は。
工藤: 昔は、居酒屋で愚痴をこぼすということがあったのですよ、サラリーマンはね。でも、それは、愚痴をこぼすだけまだいいのだけど、諦めてしまったら話にならないではないですか。
田中: 後は、目をつぶっているとかね。
工藤: でも、もうそれがすまされないような状況なのだけど、これを変えていく何かというのは、どういうことなのですかね。
今の日本は、長いものに巻かれろでは済まされない段階
田中: それこそ、先週ですか、小倉さんが仰っていたように、それこそ小さな一歩なのだと思うのですよ。やはり、身の回りにある課題を提起し、そこで自分も当事者としても議論に加わることによって、この問題がどうして起っているのだろうか。その原因は何なのだろう、ということに、必ず問題意識を持つと思うのです。そうすれば、自分たちの納めた税金がどんな風に使われているの、それから、どういう政策になっているの、というところまで、自分たちの視野というものは広がっていくし、それが強い有権者、納税者をつくっていくことだと思いますね。
工藤: ただ、あれですよね...その前に、誰かに任せても答えはない、ということに気付かないとダメだよね。これはちょっと他人に任せておけばいいとか、長いものに巻かれる、という状況では済まされないところにきているような気がするのですね。
社会を変えるための「議論の砦」をつくりたい。
本当は、田中さんはNPOの専門家で、実証的に色々なことを語れるので、ぜひ田中さんの本を読んでいただきたいのですが、ただ、田中さんが言っていることは、僕の思いと共有してまして、市民が今変わらないと、本当にこの社会は変わらない。ただ、市民が変わらないといけないような前提なり、チャンスは広がっているのですよ。いわば、もう後は、アクションというか、変えるしか...自分たちが、何かそのチャンスを使いこなして、動かすしかないのだという感じだと思うのですね。言論NPOはまさにそのために実現したので、私たちは、まさにその砦を、この社会を変える議論の砦をどうしてもつくってみたいと思っています。ということで、話していたらまた時間になってしまいました。今日は先週の小倉さんに続いて、市民社会という問題を、つまり僕たちの可能性を、田中弥生さんと一緒に考えてみました。つまり、強い市民社会をどうやったら、僕たちはつくる事ができるのか、皆さんも何かお考えになったことがあると思うのですね。ぜひ意見をお待ちしております。今日はどうもありがとうございました。
田中: ありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【後編】
投稿者 genron-npo : 16:39 | コメント (0) | トラックバック
2010年12月 8日
「日本の危機を救えるのは誰?」
-ON THE WAY ジャーナル 2010.12.8 放送分
放送第10回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、元フランス大使の小倉和夫さんのインタビューを交え、強い市民社会とはなにか?市民社会の役割について考えました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
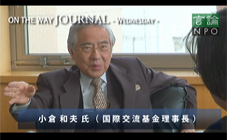 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「日本の危機を救えるのは誰?」
工藤: 「ON THE WAYジャーナル」水曜日「言論のNPO」、今日のテーマはこちらです。
谷内: 「日本の危機を救えるのは誰?」
おはようございます。噛んでしまいましたが、番組スタッフの谷内です。「ON THE WAYジャーナル」水曜日、「言論のNPO」ではこれまで日本の政治をどう考えればいいのかを考えてきました。今まで9回の放送があり、多くの人に議論づくりに協力していただきましたが、その方々が口を揃えていたのは「日本は多くの課題に直面しているのに、政治はそれを解決できない状況に陥っている」と。政府や政党で、様々な機能が信頼を失っていて統治の危機に陥っていると。よく「ガバナンス」という言葉がでてきましたが、ではこの状況を誰が変えられるのかということを今日考えていきます。
工藤: そうですね。以前、元東大総長の佐々木毅さんが「ナショナルクライシス」と言っていましたが、僕もこの言葉にはすごく驚きました。課題を乗り越える力が日本の政治になければ、この国は滅びてしまいます。ただこれを誰が解決するのかと、それについて考えていかなければいけない、そういう段階に来ました。それでこの前、昔からすごいなあと思っている論客がいまして、その方は元フランス大使で今は国際交流基金の理事長の小倉和夫さんっていう方です。今回、その方と僕はこの問題を議論してみましたが、そうしたら非常に本質的な議論になりました。これをちょっと僕は皆さんに紹介しながら、「日本の危機を救うのは誰なのか」ということを考えてみたいと思います。
先週、石破茂自民党政調会長とお会いしたときの発言から振り返ってみますが、先のメールでもありましたが「いい加減な気持ちで政治家を選べば自分たちの身に色んなことが降りかかってくる、それを覚悟しなければいけない」と言っていましたね。「まだ間に合うので、今そのための覚悟を固めろ」、という話もあります。また別の人は、何が嘘か本当か見抜く目をつけるべきと、そのギリギリのタイミングに(有権者は)来ていると言っています。考えてみれば、結局ボールは僕たち有権者にあります。つまり僕たちがしっかりして変われば、この今の日本の状況を、時代の流れを変えられると。僕もそれに賭けたいと思います。
石破さんも「まだ間に合う」と仰っていました。そういうことを考えていったときに、私がよく言っているのが「健全な社会には健全な議論が必要」ということと、「強い市民社会が必要」ということです。強い市民というのは、何でも政治にお任せして、もう自分たちの運命をもお任せするのではなく、自分の運命は自分で考える、みんなで考えるということです。自分たちでこの政治や未来に関してきちんと考えて、議論して意見を持っていく。社会の問題に関して「なんか自分でも貢献できないか」とかそういう気持ちを持っている人たち、こういう人たちが強い市民です。
こういう「強い市民」が動いて行かないと流れを変えられないと思います。それでこの問題を小倉さんにお会いした時にずばり聞いてみました。日本の政治の混迷と市民社会の役割をどう考えればいいかと。
それではまず小倉さんの話を聞いてみましょう。
政府不信は、市民の自己不信であり、だからこそ、市民社会の役割が一番大事
工藤: 基本的な話なのですが、今市民社会の状況ということに関する小倉さんの認識ですか、どういう風に今とらえているんでしょうか。それから今まさに市民社会を強くしなければならない問題提起は今の状況においてどれぐらい大事なのでしょうか。
小倉: 世界で今一番大事な...政治の上で社会問題の上で大事なことの一つだと思います。なぜかといいますと、政党、機関、国際機関もそうですが、既存の制度や団体に対する不信感、これが先進国を中心に世界中を覆ってるわけです。しかし、そういった状況をつくったのは誰かといえば、あなたは選挙でその政党なり政府に投票したではないかと。あなたはその国際機関としての代表を送り込んでいる政府になぜ文句が言えないのか、ということになるわけです。制度不信、組織不信というのは翻って考えれば自己不信なのです。よく考えれば。つまり、自己責任。あたかも自分がつくったもののように、自分とは関係ないように思っているところに重大な問題がある。そうじゃない。政治が悪ければそれは政党も悪いかもしれんが一人ひとりの市民の意識がまだ十分成長してないからではないのか、ということにもつながるわけです。そのギャップを埋めるのは何かというと、それは一つしかない。それは市民自身が直接市民運動をしたり、市民社会をつくっていく。その声を制度的にエスタブリッシュされたルートとは別に違ったやり方で、もちろん同じやりかたもあってもいいですが、社会に投じていくことしかないだろうと思うんですよ。そういう意味で市民社会の役割というのは、制度に対する不信感、それから組織に対する不信感が先進国を始め、世界中にみなぎっている今こそ実は一番大事なことではないかと思います。
工藤: 例えば若者たちの中で一番優秀なのが非営利セクターに働きにいくっていうのはその現象なんでしょうか。
小倉: それも関連しているとは思います。それだけではないですけどね。例えば今のアメリカのティーパーティーとかですね、あれを全部見て結局は既存の組織政党に対する民衆の不信感というものが非常にあることを感じるわけです。あれを単なる保守の回帰とかオバマへの反発とかみるのは間違いだと思います。
工藤: 今の発言が、佐々木さんの問いかけの答えなのですよ。つまり、不信が強まって、ポピュリズムになっていって、最後、地検も崩れてほとんど信用失って統治が崩れていくという、ナショナルクライシスという国家の危機の段階ではないかと佐々木さんはおっしゃっていました。ただ、それに対する答えはどうなればいいかっていうと、佐々木さんは権力のリーダー側の転換をやはり考えるのですよ。だけどそのとき、僕はやっぱり市民側じゃないかと思ったわけですよ。
小倉: 僕はそう思いますね。権力というか、そっちのほうが変わればいいということであれば、自民党から民主党に変わったからよいではないかということになるのではないですか。
工藤: この発言でね、少しショックを受けたのは、つまり日本の政治の不信は自己不信ではないかということです。自分たちの自己不信ではないかと言っています。つまりこういう権力とか政府とか政党に対する不信は世界中で高まっていると仰っており、しかもそれはあたかも自分とは関係ない話ではなく、自分たちがそれを選んだのではないかということです。僕たちは傍観者で、映画やテレビで見ている話ではないのです。この政治は自分たちが選んでいる話で、それが信用できないのは自分に不信がある、自分が信用できないのと同じだと。ということになれば、やはり僕たち一人ひとりが市民として成長していかないといけないのです。自分たちの成長が問われる段階に来ているのではないかと思います。これはやはり日本を変えるっていう時にかなり本質的な発言だと思います。ではどうすればいいのか、これをまた小倉さんに聞いてみました。
工藤: でも今市民が変わらなくてはいけない図式っていうのは明確になってきているけども、しかし考えてみれば、それが一番困難なところですよね。でもその一番困難なところに僕たちは動かなくてはならない。
小倉: 日本社会で市民度とか市民社会が成長していく上での一つ大きな問題は、集まるフォーラムの問題でしょう。教会があれば教会にみんな集まるわけですし、モスクがあればモスクに集まるわけですが、日本の場合はどうでしょうか。信じるかどうかは別にして、社会的な集合の場所があればそこから色々な市民的なものが発生していく、ということは十分あり得ます。日本の場合は、市民が集まるお祭りはあっても、信条を基にして集まるという場所は他の国に比べると非常に少なくなっている。
工藤: そこをどう再設計するかなのですが、例えば、大学や色々なところだって本来はそういう役割を果たさなきゃいけなかったところが、自分たちがやらなきゃいけないところが結構崩れていますよね。
課題に対する対話を様々な分野で始める必要がある
小倉: 僕は、一つ一つのイシューだと思います。小さなものでいいと思うのですよ。小さなイシューでいいから、不登校なら不登校、小学生の制服がいいのか悪いのか、非常にささやかな問題ですよね、ささやかな問題での市民との対話というものを、もっとたくさんつくっていく、ということからスタートするより仕方ない。
つまり、市民に問題を提起して、市民にこの問題について議論しましょうという場を与える、機会を与える。大学もそれができればいいのですけが、大学はいささか偉すぎる人が多いから。でも、大学みたいなところでもやる必要があるだろうし、新聞社がやる、政党もやる、地方自治体もやる、イシュー、結局は市民社会が成熟して、みんながそういう風になっていくためにはイシュー・オリエンテッド、つまり課題からのアプローチが大切でしょう。
工藤: まさに課題に対してみんなが考えるという、まさにそれは言論NPOがやろうと思っているのですが、そういう積み重ねが、色々な人たちにかなり見えていく。
小倉: それしかないと思うのですよ。それがやっぱり本筋じゃないかと。
その積み重ねの中で、当事者としてこの時代に参加する意味を感じ始める
工藤: その積み重ねの中で、自分たちが当事者として、今の時代や地域とか社会に参加していることの意味を感じていくわけですよね。
小倉: 実は、みんなそれを本質的には望んでいると思いますよ、どこかでは。ただ、チャンスがなかったり、そうは言われてもめんどうくさかったりするからだろうけど、心の奥底ではみんな望んでいると思いますよ。
今は市民社会が成熟するためのチャンス
工藤: みんな社会につながっていないのですよ。みんなバラバラで、他人事みたいに考えていて。本当はそれをつなげるのが非営利セクターだったのですよね。
小倉: これはある意味ではチャンスだと思うのです。というのは、既存の組織、あるいは団体に対する不信感が増しているということは、市民社会の成熟のためのチャンスでもあると思います。というのは、彼らは普通ならそこに属して安泰して、会社人間になったらいいわけですから。そうではなくなってきているわけです。逆にいうと市民社会を作っていくためのチャンスが出てきているのでは。
工藤: 今の話は一つの答えを出していると思います。やはり課題ごとにどんな小さな問題でもいいのでみんなで一緒に考えていく、その積み重ねが大事なのだということを仰っています。僕もまさにこの番組でそれをやりたいなぁと思っています。つまりこれからの時代、僕たちは自分たちが決められるのです。国も自分たちの運命も。ある意味でこの国が危機で統治が動かないからこそ、僕たちが考えなければいけないことになったということで、これはチャンスだと思います。それに気づくための状況に直面している。
今僕が気になっているのは、大学にしてもメディアにしても会社にしても、様々な組織がその社会性に関して機能していない感じがします。でもそれぞれの人たちが、やはり自分たちの与えられた課題に関しきちんと仕事をすると同時に、その中で参加する人たちと一緒に社会的な問題に関しても考えたり向かい合っていくという流れが出てくると、本当にこの国は強くなります。
問題は、このチャンスを多くの人が感じること。そこから流れが始まる
その中でポイントは、メディアの役割もあると思います。言論NPOはそのために非営利で参加型のきちんとした議論をして、それが時代とか社会の課題解決に向かって動いているNPOです。僕も10年前までは営利企業のメディアの記者でしたが、言論NPOを始めて何が変わったかというとそれは当事者意識なのです。つまり会社の中で与えられた仕事をするのではなく、自分も社会の当事者なのだと。自分の行動とか仕事に関しても責任があるのだなというのを自覚してから、何か僕の視界がひらけた感じがします。だから皆さんも同じ状況だと思います。ですから無関心だと思わないで、その社会の当事者として地域とか社会に何らかの形で参加していくべきです。
小倉さんが言っていましたが、こういうときだからこそ市民社会の成熟のチャンスだということです。僕たちが当事者として社会に関わっていく。そういう感じが大事なのだと思います。多分この動きが始まれば、この国は間違いなく変わると思っています。問題はこのチャンスを自分の問題として考えられるかです。チャンスといっても他人の話ではなく自分のチャンスなのです。なので自分も何かを今日から、明日からでもいいですが、社会に関して自分で考えてみようとか、友達同士で考えてみようとか、学生であれば先生に質問してみようとか、親と家族とかに話してみようとか、何かしてみるべきです。新聞を見てみるとか。新聞はあまり信用しすぎないで、「これは本当かな」と疑問を持ちながら読んでみる。自分を主体にして自分で社会に立ち向かっていく。それが多分これから大事なのです。ボールは僕たちにあり、必ずこの国と未来は変えられるのです。そういうことを本気で考えてみてはどうでしょうかと思っています。
小倉さんがここで最後に言っているのがもう一つあって、僕が非営利セクターの話をしましたが、市民が色んな形で自発的に参加するときのその受け皿は何だろうと考えれば、それは僕たちNPOや大学、地域社会です。しかしそれがきちんと機能していないのではないかという問題が一つあります。僕はこの問題は次の週に議論したいと思います。つまり僕たちが意識を変えないといけない、しかし意識を変えた人たちが参加できる仕組みをつくっている人たちも、もっと意識を変えないといけないのです。そうやって市民社会を強くして、一気にこんなどうしようもない政治ではなく、本当に競争して未来に向かって生き生きと自分たちの人生を考えるような流れに変えたいのです。
「まだ間に合う」と石破さんは先週、言ってました。それを信用してやっていきたいと思います。
ということで今日はここで時間です。政治の危機と市民社会という問題、「市民社会」ということで非常に分かりにくい部分もありますが、小倉さんの話を聞いて少し掴めたのではないかと思います。また皆さんからいろんな意見をお待ちしています。今日はありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【後編】
投稿者 genron-npo : 12:37 | コメント (0) | トラックバック
2010年12月 2日
なぜ、今「エクセレントNPO」なのか
ブックレット16『「エクセレントNPO」の評価基準 「エクセレントNPO」を目指すための自己診断リスト―初級編―』発売にあたって、なぜ、「エクセレントNPO」の評価基準を公表するに至ったのか、代表の工藤が語ります。聞き手:田中弥生 (言論NPO 理事)
 |
なぜ、今「エクセレントNPO」なのか
|
田中: 工藤さんお久しぶりです。
工藤: お久しぶりです。
田中: 本当に久しぶりなのですが、今日は、昨日発売になった『「エクセレントNPO」の評価基準「エクセレントNPO」を目指すための自己診断リスト―初級編―』 、できたてほやほやの本についてお聞きします。マニフェスト評価の言論NPOという印象があるのですが、NPOの評価基準というのを、なぜおつくりになったのですか。
工藤: この本つくるために、徹夜もしたし、体調崩すぐらい非常に大変でした。マニフェスト評価をやっていて感じるのは、有権者や市民が、自分たちが政治を判断して、自分たちがこの国の未来を自分で考える、というふうな動きがでてこないといけないわけです。だから、今の日本を変える、日本の社会が将来に向かって動き出すためには、市民が強くならなければいけないのですね。言論NPOは、そこに絶えず問題意識がありました。この間、私もメディアから非営利の世界に飛び込んで感じたことは、市民の受け皿である非営利セクターというのが、どうなのだろうということでした。非営利セクターが市民の受け皿として、きちんと機能して、しかも、組織として社会の課題解決に自発的に取り組んでいるのか、ということに非常に大きな問題意識を持っていました。やはり、強い市民社会をつくるためには、非営利セクターや市民社会のことについて議論しなければいけないということで、私も、田中先生が中心にやっている研究会にエディターとして、また議論形成者としてずっと参加していました。
最終的な結論は、やはりこの市民社会に大きな変化を起こすためには、非営利セクターが変わらなければいけない。非営利セクターが、まさに市民に向かい合って課題解決を競争し合うような、質の向上を目指すような大きな変化が始まらないと、多分、強い市民社会はできないと思ったのです。そうなってくると、その望ましいNPO像を明らかにした上でそれを目指そう、という動きをつくる必要があると思ったのです。それが、3年がかりでつくった...「エクセレントNPO」という言葉に抵抗がある人がいるのですが...「エクセレントNPO」を提起して、それを目指そうという動きをつくるために、この評価基準をまとめたということなのです。ただ、私たちは評価の専門家ではなくて、田中さんが専門家なので、田中さんが中心となってやってきたのですが、色々なNPOやNGO団体の人も集まりましたよね。
田中: そうですね。国際協力NGOから子どものことをやっているNPOまで。そして、研究者の方にも参加していただきました。
工藤: そうですよね。大学の先生も参加していただき、夜も飲みながら議論したり、いっぱいやっていましたよね。それに、田中さん中心に課題の調査もしたじゃないですか。その結果、この評価基準を生み出したので、僕も最後はこれをきちんとしたものにまとめないといけないと思ってやっていたので、かなりのレベルにできたと思っています。田中さん、専門家としてこの本はどうでしょうか。
田中: 自分でつくったので、自画自賛になってしまうので恥ずかしいのですが、非常に出来がいいです。いくつか特徴があるのですが、1つは、普通、組織の評価というと、ガバナンスや会計の所に集中しがちなのです。でも、この評価基準の場合には、「市民性」「社会変革性」「組織の安定性」という、3つの基本条件についてきちんと議論を進めた上で、評価基準をかなり論理的に設計して、なおかつその基準を満たしているかどうかということを、自己診断できるようにチェック項目をつくっています。普通はここで終わるのですが、さらに、チェック項目それぞれに、1ページずつ説明文を書いていますよね。
工藤: そうですね。だから、僕たちのインターンも含めて、これをつくっている時に、ドラッカーの非営利組織の評価とか色々なものを見ながら、顧客やお客さん、つまり非営利セクターの人も、市民の人も、望ましい非営利セクターとはどういうものなのか、ということが分かる目線でこの本を作ったので、非常にくどいくらい丁寧ですよね。
田中: そうですね。
工藤: 実を言うと、昔メディアにいたし、出版社の編集をやっていたのだけど、こういうものは確かに見たことがない。
田中: 普通は基準だけとかのものが多いのですよ。
工藤: だから、この評価基準によって、市民社会の中でどういう組織が望ましい非営利組織なのか。多分、それは非営利セクターだけではないと思います。市民との関係ということで考えれば、色々な各種団体、企業だってあり得るわけですよね。そういう人たちが、市民との関係を色々考えながら、その中で大きな社会に対して向かい合って、課題解決について動き出すという組織を「見る」という点でも、この評価基準というのは参考になるという気がしているし、そういう思いでつくりました。
田中: 今、工藤さんから「市民性」というキーワードが出ました。「社会変革性」が2つ目のキーワードですが、社会変革性という言葉自体、何となくNPOより社会起業家の十八番のように言われています。
工藤: だけど、企業そのものが社会変革をすることだからね。
田中: そうです。今まで、賞品やサービスを提供することによって、人々の生活を大きく変えてきたわけです。そういう視点でもこの「社会変革性」というところを、企業の方も見ていただければ、きっと納得されると思います。
工藤: そうですね。僕はリーマンショック以降、日本の経営論という形で、「企業は誰のものか」という本質的な議論が問われているような気が、今はします。やはり、その時に地域社会や市民、消費者との関係を考えながら企業を考えることが必要だろうと思います。一方で、市民という以上、甘えないで社会的な課題について、自発的に自分の力で何かに挑んでいくような動きが、市民側から出てくる必要があると思います。だから、今は丁度いい時期だと思うのですよ。この本をつくるときに、田中さんと一緒に色々な人たちに会いましたけど、世界はまさにそういう価値の転換が始まっているじゃないですか。優秀な学生の中で、非営利セクターで働きたいという人たちが増えてくるような変化が出てきているけど、日本の中ではまだまだです。大きな変化は始まっているけど、方向が何か違うような気がするのですね。やはり、行政や政府が主導している市民社会ではなくて、市民側が自ら自発的に参加していくような社会の方が、僕はいいと思っています。だから、これを僕たちの手でつくって、評価基準を表に出すということは、非常にいいことだと思っていますが、田中さんはどう思いますか。
田中: そうですね。基準は絶対ではないのですが、実は他の団体とも議論をしてみると、「市民性」「社会変革性」「組織安定性」というのは、ほとんど皆さんが合意するところなのですね。でも、それをどう実現していくかというところで、皆さん悩んでいる状態です。そのような中で、完璧ではないけど、ここまで具体的に説明をしているものというのは、私は1つの大きなインパクトを与えると思いますね。
工藤: そうですね。このブックレットは、徹夜もして突貫作業でつくりました。そして、今ようやく色々な人たちにご紹介する段階にきました。全国の主要書店でも置くし、言論NPOのホームページでも買えます。だから、ぜひ読んでほしいと思っているし、僕はこれをきっかけに、市民社会の議論がもっと色々なかたちで進まないかと思っています。それができれば、この本をつくった事に意味があると思います。せっかく政府側も「新しい公共」ということで動いているのであれば、それをまず僕たち側から主導して動こうという気持ちでがんばるので、田中さんにも協力してもらいたいと思っています。
田中: そうですね。そういう意味では、タイトルは『「エクセレントNPO」の評価基準』ですけが、ぜひともそれ以外の方に読んでいただきたいですね。
工藤: そうですね。それから、非営利セクターの人は、この本には自己診断リストというのが付いています。これをチェックしていくと、自分の団体の採点ができます。それから、実を言うと、昔の警察庁長官で、今は救急ヘリ病院ネットワーク理事長の国松さん、国際交流基金理事長の小倉さん、横浜市芸術文化振興財団代表理事、専務理事の島田さんの3人を共同代表とする市民会議を立ち上げ、そのホームページもできました。これは言論NPOではないのですが、この市民会議のホームページを見てみると、なかなかよくできているな、と思うのですが、ホームページ上でお試しのチェックができるようになっています。チェックし終わると、自分の非営利組織が何点かというのができるようになっています。
田中: 後、コメントも出ます。
工藤: 何か色々考えているなと思っています。話を元に戻して、このブックレットは非常にいいものなので、ぜひ読んでほしいと思っています。
田中: そうですね。ゴールは、まさに市民が強くなることですよね。
工藤: そうです。そのために、私たちは何かの貢献がしたいと思って、こういう動きをやっていました。ただ、3年がかりで、ここまでやってきてよかったですよね。
田中: そうですね。できるだけ多くの方に読んでいただきたいと思います。
工藤: 僕たち言論NPOは、これからも市民社会を強くするために色々な議論をしていくので、ぜひ皆さんも参加してほしいと思っています。
投稿者 genron-npo : 21:32 | コメント (0) | トラックバック
2010年12月 1日
「日本の政党、こんな状況で本当にいいの?」
-ON THE WAY ジャーナル 2010.12.1 放送分
放送第9回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、自民党政調会長・石破茂さんのインタビューを交え、財政破綻・社会保障の問題など山積する日本の状況について、政治的側面から考えました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「日本の政党、こんな状況で本当にいいの?」
工藤: おはようございます。ON THE WAY ジャーナル水曜日、言論NPO代表の工藤泰志です。さて、今回も私がインタビューをしてきましたので、そちらを聞きながら話を進めていきたいと思っています。
今日のテーマは「日本の政党、こんな状況で本当にいいの?」です。今回、私が会ってきたのは、自民党政調会長の石破茂さんです。
この間、私が特に気になっていたのが、財政破綻とか、社会保障とか、日本が取り組まなければいけない課題がたくさんあるのに、日本の政治はなぜそれに向かっていかないのか、なぜ課題解決ができないのかということなのですね。そこの中には政党のガバナンスが崩れているという大きな問題があると思うのですね。つまり政党は形では1つにまとまっているけれども中身はばらばらで、しかも政党として日本の未来を競い合えないという状況があると思うのですね。そこで、今日はこの政党の問題を考えたいと思います。
石破さんは自民党の政調会長なのですが、別に自民党だから彼に会ってきたのではありません。実は石破さんが昔、今の日本の状況は政界再編に向かう過渡期にあると言っていたことが、すごく頭に残っていたんですね。そこで石破さんになら、日本の政党がなぜだめなのか、ということを話していただけると思ったのですね。では石破さんの話をさっそく聞いてみたいと思います。
政党のガバナンスは機能していない
工藤: 僕たちはNPOなのですが、僕たちですらミッションを支援者にきちんと語って、それに基づいて活動の成果が評価されて、それから中立性とか何かを証明するために事後評価をして、すごいガバナンスで苦労してやっているのですけど、政党はある意味でNPOなのですが、そういう経営のガバナンスと政策のガバナンスなのですが、機能していないのではないかという気がするのですが。
石破: していません。
工藤: ですよね。
石破: 全然していないです。
工藤: これを機能させなければいけないという動きが出ていないのですかね。
石破: 何かを実現したくて、その手段として大臣になったり、はたまた内閣総理大臣になったりするわけで、今は、目的と手段がひっくり返ってしまっていると思います。だから、政治家になること自体が目的だ、政権を取ること自体が目的だということになってしまって、何のためになるの、何のために政権を取るのということが、分からなくなってしまっているのだと思います。だから、ガバナンスは利かないですよ。
工藤: でも、それはすごい深刻です。つまり、日本に今、財政や社会保障、経済にかなり大きな課題があるときに、その政治の統治がきちんと機能しないと、誰がこの課題解決をできるのか。これは、日本の危機だと思うのですが、それをどういう風に考えればいいのですかね。
石破: それは、政党が国民に向けて語りかけるという本来の姿を取り戻すことだと思います。私は、この程度の国民にこの程度の政治家、という言葉がすごい嫌いで、それは政治家の側が語りかけない限り国民は変わらないと信じているのですね。リーダーはそういうものであると思います。
今はダメ比べになっているわけです。去年の総選挙は、別に民主党がすばらしいから勝ったというよりも、自民党があまりにダメなので、何か替わるものはないかと思って、民主党を選んでみた。だけど、どうも自民党よりひどいらしいということになって、また自民党に戻る。というのは、あっちがダメだからこっち、こっちがダメだからあっちというネガティブ競争になってしまっているわけです。
工藤: 永田町のゲームみたいに、国民と関係なく動いているという感じがしますよね。これを直すエネルギーは永田町にあるのでしょうか。
石破: 私は、それは自民党がやるべきだと思っています。
工藤: 政調会長としては当然そういう話なのですが、冒頭に、政界再編の過渡期だとおっしゃっていましたよね。つまり、自民党という枠組みそのものも、色々な考えの違いがあって、最終的に課題型で政党が機能していない、集まっていない。そういう限界を指摘されているということなのでしょうか。そこを、課題別に政治が集まり直さなければいけない。
国民の手による政界再編
石破: そうだと思います。だから、一度だけ特別措置法で中選挙区に戻してみたらどうかと、私は言っています。その代わり1回だけです。党を離れて、みんな無所属で出ればいいと思います。基本的に、消費税を上げ、法人税を下げるべきだということについて、賛成か反対か。集団的自衛権を行使可能とすることについて、賛成か反対か。これだけでもいいと思います。何人の候補者が出るかは分かりませんが、この設問に対して、○か×かを掲げて、選んでもらって、それで意見があった者が政党を作ればいいのだと思います。それが、国民の手による政界再編だと私は言っているのだけれど、なかなかそれは難しいのです。
工藤: 政治家一人ひとりが、どういう立場かが問われる仕組みは、政治の中でできる事なのですか。それとも、国民側から要求していかないとだめなのですか。
石破: 私は、国民側から要求していただいた方がいいと思います。
工藤: すごく率直な意見でね、ここまで日本の政党が機能していないということの現状や原因をきちんと話してもらって、非常によかったと思いますね。政治家になるという、また権力を握るということは、何かを実現するためだと思うのですね。つまり今であれば日本の置かれている課題に対して、困難に対して、実現するために政治があって政党がある。それが、政治家になることや権力を握ることが自己目的化しているのではないか、という指摘です。僕はすごく興味深かったのは、そういう風な政治が、もう一度立ち直るきっかけはどこにあるのかといったら、それは国民側から政策を軸に政界の再編を要求するしかない。そういうかなり刺激的な発言がありました。ここが非常に重要だと思いますね。続いてお聞き下さい。
工藤: 僕たちはマニフェストの評価をやっているのですが、それには前提があって、政党が機能していないとマニフェストを評価するということは難しいのですね。党の中で、政策立案についてかなり激しい議論があってもいいのですが、そのプロセスが公開されて、その中で意見がこういう形でまとまった、まとまらなかったら分かれてもらうとか、そのプロセスが見えることがまず必要で、それだったらわかりやすいですよね。そういうプロセスを政治側で動かすということは、難しいですか。
石破: 私は、もっと国会議員が政党から自由であるべきだと思っています。今、工藤さんがおっしゃるように、嫌なら出ていく、ということがなぜできないかというと、それは第一番に、無所属になってしまうと政党助成金が配分されなくなるわけですね。あるいは、民主党であれば、民主党を離れてしまうと、労働組合の支援がうけられなくなるということもある。あるいは自民党を離れてしまうと、なんとか団体の支援がうけられなくなる。選挙に落ちるのは嫌だよなと。お金もらえなくなるのも嫌だよなと、みんな思うわけです。だから、民主党のマニフェストだって、本当に全部の議員が賛同したかといえば、そうではないわけですよ。
工藤: 政治問題で気になっていることが、政権は自分の任期中にコミットメントしているものは何なのかを、国民に明らかにしてほしいと思っています。この前、G20で財政再建の目標が2013年だったのですが、日本だけ2015年になりました。ということは、(任期が2013年に終わる)菅政権はそこまでは責任を持っていないわけですよね。
石破: 持っていないです。
工藤: ということは、今の政治は何を約束して、かならずやるということで動いているのかよく分からないのですよ。ただ、国会ではお互いに自民党と民主党がやり合っているだけになっていますから、結局国民からすれば、今の政治が何の課題を実現するために、いつまでに、何に危機感を持って取り組んでいるのかということが、非常にわかりにくい状況が続いて、それが政治不信に繋がっている感じがします。
国会議員でいることは目的でない
石破: 本当のことを言って、選挙に落ちようがそれでいいではないか、と言えないとダメなんでしょう。国会議員でいることが目的ではなくて、日本を変えることが目的なのだから、本当のことを言って、選挙に落ちるのは、それはそれで構わないのだといえる議員がどれだけいるのかということでしょう。
工藤: 自民党の中に何割ぐらいいるのですか。
石破: 3割ぐらいはいると思います。
工藤: 民主党にはどれぐらいいると思いますか。
石破: やっぱり3割ぐらい。でも、1期生が多いから2割かもしれない。
工藤: つまり、2割しかいないわけですね。本当に政策立案能力があって、きちんと課題解決に対する構想力があり、実務的にそれをこなせる人たちというのは。
石破: でも、どの社会でもそうじゃないですか。できるの3割、どうでもいいのが4割、できないのが3割。大体そんなものでしょ。ちゃんとした3割がちゃんとした発信力を持てば、4割は付いてくると思います。
工藤: そこがすごく重要です。ちゃんとした3割がリーダーシップを発揮できていないから、政治が混乱している状況に見えるわけですね。その人たちが今動かないといけない。
石破: 例えば、私と民主党の政調会長で国務大臣の玄葉光一郎さんというのは、二人で話していると95%は一致するわけです。
工藤: 2つの政党に分かれているのはどうしてなのですか。
石破: それは、選挙区事情でしょう。ここは、前原さんとも前に論争したことがあるのだけど、同じ考え方を持った人間が、2大政党の両方にいるべきだというのが前原説です。私は、そうなのだけれど、今はそういうことを言っている場合ではないだろうと。財政も外交も安全保障もみんな危機なのに、こういう同じ考え方の持ち主が両方にいて、政権交代なんていうのんびりしたことを言っている場合ではなくて、同じ考え方の者同士が集まって、大政翼賛会にしないような配慮は必要ですが、国民に向けて語りかけるということをやらないとまずくないか、ということを、言った覚えがあります。
工藤: だから、まとまってそこから脱出しないわけですね。
石破: そうなんですね。
工藤: 日本の政党が課題解決に向かえないというのは、僕は非常に危機だと思っているのですが、しかしそれは政党のあり方という問題がね、ここで非常に問われているということがわかってきたんですね。ただこの政党が、政策課題、本当にそれをきちっと実現するような、本当の意味で未来に向けて競争するという状況になるためにどうしたらいいのかということが非常に疑問なんですね。僕は石破さんにずばり聞いてみたんですよ。そういうふうな政治をつくるために、有権者つまり国民は、何をするべきなのかと。
石破: やはり、政治のトップ、例えば、民主党代表・内閣総理大臣、あるいは自由民主党総裁、そういうトップが揺るがぬ信念を持って、ぶれないことだと思います。同時に、その人は法律をある程度知っている。官僚機構を統制できるぐらいの法律的な知識はあるということ。それから、外交・安全保障などの知識もあること。そして、本当に心ある官僚達が、よし一緒にやろうという思いを持つ。上がきちんとした考え方を持って、俺はこの党をこう導く、この国をこう導くということがあれば、相当に変わると思っています。で、国民はどうすればいいのかという話ですが、誰の言っていることが本当なのだろうかということ...
国民には政治家のうそを見抜いてほしい
工藤: 嘘を見抜けなければダメですね。
石破: 見抜いてくださいという事なのですね。政治家は選挙の時に、結構でたらめを言いますからね。で、誰の言っていることが本当なんだろう、この通りやったら何が起こるのだろうということを、1回立ち止まって考えてほしいなと思います。
私は、民主党政権の壮大な実験の失敗、私は失敗と断じていいと思うのですが、国民は、あれはまずかったのではないだろうか、そして、外交・安全保障を考えてこなかった人をトップにしたということは、やはりまずかったのではないだろうか、という思いは、持っていただいていると思うのです。「だから自民党を選んでくれ」と言っているのではありません。民主党が変わればそれもよし。自民党がきちんとしたものを出せばそれもよし。本当に、今度こそいい加減に政治家を選ぶと、自分たちの身に降りかかってきますよということを、ぜひご認識いただきたいと思います。
工藤: 最後は、政界再編のイメージ。自民党と民主党は残っている状況なのでしょうか。
石破: そこは、それぞれの党で突き詰めた議論をすると、自ずから差が明らかになってくると思います。自民党でも、私が防衛庁長官を辞めてから、防衛大臣になるまでの3年間の間に、安全保障基本法というのを書いて、日米安全保障条約の改正案を書いて、日米地域協定の改正案というものを書いたのですね。大臣ではないときというのは、そういうことをやるのが仕事です。で、私の小委員会ではまとめたのだけれど、党の決定にはならなかった。そんなのを党の決定にかけると、党が割れてしまうかもしれないからでしょうね。
だからダメなのです。それぞれの党の中で徹底的に議論すると、自ずから「合わない」人というのが出てきます。自民党でも、民主党でも。だったら、「もういいではないか、合う者同士でやろう。選挙に落ちてもいいではないか、選挙に通ることが政治家の目的ではないのだろ?、何のために政治家になったのだ」ということを、誰かが言わないとダメなのでしょう。
やはり、自民党であれ、民主党であれ、何党でもいいのだけど、お前達何のために議員になるのか、ということを問いかけるべきだと思います。そうすると、変わる人は必ず出てくるだろう、と。
工藤: 自分たちが下手な決断をしてしまうと、大変なことになるということを、今痛感していると思います。だからこそ、有権者側がしっかりしていくことによって、政治も強くなりますよね。
石破: はい、そうだと思います。
今ならまだ間に合う、むしろ今しかない
工藤: その流れをどうしても、これから作っていかないと、と思っています。
石破: まだ間に合う。
工藤: まだ間に合いますか。
石破: まだ間に合う。今ならまだ間に合う。
工藤: そうですか。徳俵から足が出ていないですか。
石破: 出かかっているのですが、やはりまだ国債が暴落しないというのは、日本に一縷の望みがあるからなのだと思います。日米安全保障条約がまだあるということは、やはりアメリカにとって日本はまだ利用価値があるのですよ。だから、本当に(徳俵から)足が出かかっているのだけど、まだ出ていない。まだ間に合う。でも、今しかないということだと思います。だから、政治家達が、今しかないのだという思いを本当に共有するならば、それはまだ間に合う。
工藤: そういう風な一歩を踏み出したいと思っていますね。
石破: はい。
工藤: どうも今日はありがとうございました。
石破: はい、ありがとうございました。
工藤: 石破さんの最後の言葉で、若干、救われたな、ほっとしたなという感じを持ちましたね。つまり、まだ間に合う、今ならまだ間に合うと。今しかないと、政治家がそういう思いを本当に共有したら、ここからがスタートになれるという話だったわけです。
僕はこの間、日本の政治の統治の崩れが日本の課題解決に向かいあえないという日本の危機を生み出している、とこの場で指摘してきたのですが、こういう政治家が日本にいるのだということを喜んだし、非常にうれしいことだなと思いましたね。ただ、石破さんだけではなくて、今から始めれば大丈夫だというようなことを、日本の政治家がどれぐらい思ってくれるかということなのですね。
僕たち自身が強くならないと、日本の政治は変わらない
その中で石破さんは、いい加減に政治家を選ぶと、自分たちの身に色々なことが降りかかってくるということをぜひ理解してほしい、とおっしゃってました。冒頭に、「政治家は選挙のときはでたらめをいうものだ」と言って、そこまで言うのと思ったのですけどね。しかし、やっぱりこの言葉も非常に重いなと思いましたね。つまり僕たちが嘘とか本物をきちんと見分けて、何が大事かと言うことを見分ける目をつけない限りは、何も始まらないのです。僕たち自身が強くならないと、日本の政治は変わらないんだなと、そういう段階に日本の政治はきているんだなという感じがしました。これから日本が未来に向けて、僕たちは何を考えればいいかという段階にきていると思います。僕はこのON THE WAY ジャーナルで、みんなで考えたいということを主張しているのは、まさに未来をつくるのは僕たちだからということで、今日の石破さんは僕の思いと非常につながってくれたなと思っております。
さて、時間になりました。今日は「日本の政党、こんな状況で本当にいいの」という問いかけをしました。かすかですが、光が見えた感じがしたのですが、またいろいろと議論していきますので、みなさん、ご意見を寄せて下さい。今日はありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【後編】