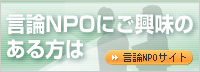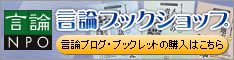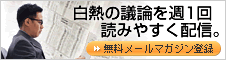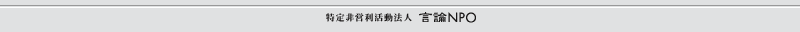« 2010年12月 | メイン | 2011年2月 »
2011年1月26日
「中国人は、今の日中関係をどう考えているのか」
-ON THE WAY ジャーナル 2011.1.26 放送分
放送第17回目の「工藤泰志 言論のNPO」は工藤が中国・北京を訪問!その際に、現地の人たちに直接インタビューを敢行。この間まで大学生だった女性や外交学会秘書長にお話を聞きました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「中国人は、今の日中関係をどう考えているのか」
工藤: おはようございます、言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝、様々なジャンルで活躍するパーソナリティが、自分たちの視点で世の中を語る「ON THE WAYジャーナル」。毎週水曜日は「言論のNPO」と題して、私、工藤泰志が担当します。
僕は、1月の9日から3日間、北京に行ってきました。北京に行ってきた理由ですが、僕らは毎年日本と中国の間で、民間の対話をやっています。かなり大きな対話なのですが、その準備のための打ち合わせで行ってきました。ただ、今年はかなり深刻で、尖閣諸島事件以降、日中関係は非常に良くないのですね。なので、この民間の対話の役割が非常に大事だと思いながら、今回行ってきました。僕は、今回は中国の人たちと本音の話をしたかったのですね。その本音の話をこの「ON THE WAYジャーナル」のリスナーの皆さんにも聞いてもらおうと思って色々チャレンジをしていました。そうしたら、偶然本音で話をしていただける人を見つけましたので、今日はその時の話を皆さんに聞いてもらいながら、今の日中関係はどうなっているのか。「中国人は、今の日中関係をどう考えているのか」ということについて、今日は皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。
その内容を聞いてもらう前に、どんな状況だったかということを少しだけ説明しますと、たまたま中国のある学会の秘書長、日本で言うと総務部長のような役職の人ですが、その人はもともと日本の大使館にもいた人で、結構偉い人とお茶をしていました。そうしたら、たまたまその人の部下で、昨年まで北京の外国語大学にいて、卒業したばかりの若い女性が書類を持ってきたのですね。なので、彼女に話を聞かせてほしいと。それから、映像もとらせてほしいと伝えると、非常にびっくりしていましたが、その上司の了承も得てこの話が実現したのです。中国の人たちというのはカメラやテレビを向けると、あまり本音を喋らないのですが、今回はかなり本音で、今の日中関係、そして尖閣諸島問題以降、中国人は日本をどうみているかということを率直に話してくれました。それを早速聞いてほしいと思います。
中国の若者は日本に親近感を失っている
女性: 日本のことは、やはり中国の若者の中では日本に親近感を持っている人はかなり少ない。
工藤: 少ない?少なくなったの?元々少ないのですか?
女性: 元々少ないですが、最近はもっと大変になりました。
工藤: どうして大変になりました?
女性: やはり一連の事件で...特に釣魚島の事件で。
工藤: 釣魚島の事件で、何が一番印象を悪くしたのですか?
女性: みんなインターネットで見ているのですが、日本が日本の法律で
工藤: 粛々対応しますと
女性: やはり釣魚島は中国の領土で、日本の国内法にはならないと、みんなそう思っています。インターネットではかなり日本を批判しています。
工藤: 批判する声がすごく多いわけですね?
女性: はい。
工藤: つまりそれは領土問題として、中国の領土なのに日本にそういうことを言われたから「おかしい」ということを言っているわけですか?
女性: まぁそういう感じ...そういう感じはかなりあります。そう考えている人もかなりいます。
領土問題だけでなく、日本のやり方に反発
工藤: 日本は自分たちの領土だと思っているので、お互いその違いがあるじゃないですか。だったら、ただ領土意識だけで反発になっちゃうじゃないですか。
女性: 領土意識だけじゃなくて、日本のやり方も。やり方を批判する人もかなり多いです。
工藤: やり方ね。そのやり方はどういうところに?
女性: 昔はそのような事件が時々中国の漁船が臨海地域に入ることもありましたが、やはり今度の日本のやり方は、急に変わりました。
工藤: 変わったって言うのは...もしくは日本政府の対応が変わったのだとすれば、それは中国とちゃんと話していなければいけなかったけれども、そういう事がなかったということですかね、急に、ルールが変わったのではないか、そういうことがあるのですね。
女性: 日本の考え方も変えた...という
工藤: つまり、あそこには魚を捕る為に中国の漁船が結構いつもいるのですよね。
女性: すぐ近くで、盛々大々、魚を採ります。でも急に、そういうやり方で...。やはり、私は、学生の考え方でやはりインターネットでみんなの色々な思い...
日本人は中国のデモに違和感をもっているが...
工藤: やはりデモとか...日本側から見てね、中国の人がいろいろ騒いだじゃないですか。あそこまで騒ぐというのが日本側は違和感を覚えたんだけど、それはもう当たり前みたいな感じですか?
女性: デモ?...それほどの規模にはならない。
工藤: あれは散発的にちょこちょこあった感じが、メディアによって大きく報道されたっていう印象?
秘書長: それは日本の報道によって大規模になるのではないかという印象ですが、中国政府、が結構抑えた結果、そんな規模ではありませんでした。
工藤: そんなに大きな規模ではなかったけど、しかしそれが結構大きな...メディアに報道されているから...
メディア報道が印象を作り上げた?
秘書長: もし日本の右翼が中国の大使館を囲んで抗議とか、その場面をね、もしCCTVで、何回も何十回も繰り返して放送すれば、中国の国民も、日本はダメとか、右翼はこんなに中国に反対している、うちの大使館に迷惑をかけていてダメだとか、いう印象になってしまう。それと同じで日本のメディアが、学生のデモを繰り返し、繰り返し、その中のごく少数の人間がね、石を投げたりとか、そういう場面を何十回も、何百回も報道すれば、すぐ、中国人がみんなそういう風になっているという印象になってしまう。
工藤: 今回もやっぱりそういう印象でした?
秘書長: そうです、繰り返した。
工藤: 日本のテレビの報道って、中国でも見られるのですか?何か見ました?
女性: 日本語のテレビは見えない...でも日本の勉強をした人はかなりいます。
工藤: 領土問題の問題があったから...というよりもやり方の問題なんですかね。今解決できないんだったら将来っていう、外交の中ではそういう話にしたわけですよね?
秘書長: 今の日本の指導者がね、これが日本の固有領土だと。元々全然領土問題がないという言い方ね、説がちょっとおかしいですよ。中日国交正常化の時、実はそのとき毛沢東さんとか周恩来さんとかですね、みんな日本の友人と話し合うとき、日本の友人自らですね、中国の領土はどうすればいいかを聞いてくれたのですよ、その時は。周恩来総理は棚上げしたほうがいいんじゃないかと。
工藤: 将来の世代で考えようと。
秘書長: そうそう。鄧小平さんのときになれば、我々がこの問題を解決する知恵がまだないと。これからの人間は我々よりか知恵があるのではないかと。これはその人びとに任せた方がいいのではないかという事を言って、反対の意見も全然なかった。もちろんお互いのですね、実はこのことについてある意味での黙認とか。
でも、急にこれは自分の領土とか、固有の領土とか、誰も入っちゃいけないとか、今まではここで魚を採っていても今はダメだとか、それが今まで追い出すという形が急に逮捕するとか、急に変わっちゃった。一方的に変わったら「反応」があるんですよ。それで簡単なことが複雑化された。
政府間のコミュニケーションも不足しているのでは?
工藤: こんなに今日の日中関係が大事だと動いている割には、政治間の、政府間のコミュニケーションがかなり不足しているっていう風にみえますよね。だとすると、
秘書長: そうそう。そのチャンネルがもしなければ、その意欲がなければ、この問題が悪循環になってしまうわけですよ。
工藤: 今、日本語勉強しているわけでしょ。今、率直な感想としてどうですか?
女性: 私は一般の学生で、一般の若者にとってはやっぱり難しい、日中関係って。
工藤: 日中関係は難しい?
女性: はい。国民感情をどのようにすれば上手くいくことができるか。
工藤: どうしたらいいか分からないっていう状況ですか。
女性: 分かりません。
工藤: でも、良くしたいっていう気持ちはあります?
女性: みんなそういう気持ちがあると思いますが、一部の人がやはり悲観的になっている。
工藤: そうか、そんなにがっかりしましたか、今回は。
女性: びっくりしました。
工藤: びっくりしたのね。
日本の政治家の発言を中国人はどう思ったか
女性: 今回の日本のやりかた、また前原大臣の発言。中国のインターネットでも、その人は...
工藤: 前原さんの発言が。どんな発言ですか?中国が気にしているのは。
女性: 今回の漁船事件で、前原さんは色々と強硬な...強い発言をしました。
秘書長: 普通の庶民だったらまぁ何を言っても構いませんが、政治家の話は慎重に話したほうがいいのですよ。中国側は中国と日本で戦争したくはないですよ。だから冷静な考えを一旦持って、一旦何かあればアメリカは日本を保護するというのが、それは結構おかしいです。あれは戦争を前提として考えたんです。でしょ?つまり戦争を狙っているじゃないかという、お互いにあるのではないですか?
工藤: そこまで日本の国民は誰も考えてないよ、全然。考えてないのだけど...ただ中国の中にね、やっぱり経済的な大きな自信過剰の意識があってね、それで大国的にものを見るって言う意識が最近出てきているような感じはしませんか?
中国の大国意識に日本は戸惑っている
秘書長: 中国政府の政策が変わっていない。しかし、国民の一部分の人の中には、自分が元々ずっと苛められた弱い国だと、今度は自分が強くなったと豊かになったと。だから、まぁ自信を持っていると。だからもともとは苛められた状況を変えたほうがいいんじゃないかとそういう考えを持っている人が確かに居るんですよ。特に、若者の中にも確かにいるんですよ。ただし、それが、政府の政策にはなっていない。中国の判断としては、まず領土問題をもし弱めすぎると、すぐ反発を招く...。
世論の悪化が、政府の発言を強硬にする
工藤: 領土問題に関して、弱めると国民の反発が来るということですか?
秘書長: そういう感じがあるんじゃないかと思う。
工藤: それでやっぱり、強い発言をせざるを得なくなるっていう。
秘書長: そうです。それは仕方ないです。ただ領土問題...
工藤: 確かにそうですね、世論が騒いでしまうと、政府レベルの対応も引きずられますよね、それは中国も日本も同じだけど。
秘書長: 中国の言葉で、自分が欲しくないことは他人に与えない。
工藤: なるほど、自分が嫌なことは他人にするなってことでしょ?
秘書長: そうです。自分の嫌なことは他人にするな。しかし、日本がね、自分が嫌なことを、他の国がしてくださいと、いうようなことをしたんですよ。
工藤: だからやっぱり中国が大きくなっていくっていう事の中に、大国っていう意識ということが、やっぱり日本だけじゃなくて世界もね、感じている動きがあるんでしょう。
秘書長: あります。
工藤: ありますよね。そう考えてみる中国も、今回の問題って本当に困りましたよね、
秘書長:みんなマイナスです。
工藤: 今の状況はマイナスになっているでしょ?
秘書長: だからね、このマイナス状態について政治家もマスメディアもちゃんと反省しなくてはいけないんです。どうしてこうなったのか、自分の責任があるかどうか、ここまで中日関係を悪くしたのが、政治家として何をしたのか、メディアとして何をしたのか。
工藤: みんな困っているんだと。困っているんだから助け合うしかないじゃないですか。
この事態に日中ともに困っているのでは。
秘書長: そうそう、みんな困っているという感じがあれば、みんな方法を探す。
工藤: 探すよね。どっちかが正しいとかいう話になっちゃうとだめです。
秘書長: 全然。どっちが正しいとか、どっちが勝つとかですね、じゃなくて、このような状況、ここまで中日関係を悪くしたのは、全くどっちの責任とか言っても意味が無いんですよ。それが問題解決には何の役も立たない。だから、このようなことになったら、どうすればいいか、それこそ意義がある。
尖閣問題の背景にはお互いの相互理解の不足や
中国の大国化に対する不安がある
工藤: かなり本音の発言になっています。僕も、単なるお茶飲み会が、こんなに本気の話になるとは思っていなかったのですが、ただ、この女性とその上司の2人の発言が、今の日中関係の中国側の状況を垣間見えるような感じがしたのですね。私は、実を言うと、今回の訪中で、この2人以外にも、中国のジャーナリストや政府の人たちともいっぱい話をしましたが、大体共通していました。ただ、この尖閣諸島問題で日中関係が非常に傷ついているということもあって、それを何とかしなければいけないという段階まできています。ただ、この何とかするということが、かなり大変です。なぜかというと、この尖閣諸島問題の背景には、領土問題以前に、政府間のコミュニケーション不足とか、国民の相互理解や交流が決定的に足りない、という問題があります。それから、日本側からみると、中国がかなり大国化してきている中で、中国がやっていることに関して非常に不安がある。一方で中国も、自分たちがどうなっていくかという将来のことを語っていない。つまり、色々な問題の中でのコミュニケーション不足がこういう風な状況を招いてしまうわけです。でも、その時に単にどっちが正しいかではなくて、ある程度相手が何を言っているかというところを聞くことから始めるしかないと思うのですね。それが相互理解を深めるということなのです。今回は中国の人はこういう風に考えているのか、ということを皆さんも「へぇ」と思ったのではないかと思います。ただ、日本側にも色々と意見があると思うので、ここの辺りから、大国化する巨大な中国とどう向き合って、僕たちは付き合っていけばいいのか、という議論を始めないといけないし、考えなければいけないという段階にきたのではないかと思っています。
率直な対話を始める時期
今日はもう時間になってしまったので、これで終わりますが、私たちがやっているON THE WAYジャーナルの議論は、私たち言論NPOのWEBサイトでも映像で見ることができますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。
ということで、時間になりました。また、来週、この続編をやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【 後編 】
投稿者 genron-npo : 14:44 | コメント (0) | トラックバック
2011年1月19日
「2011年の世界の潮流の中で、日本は何を考えればいいのか」
-ON THE WAY ジャーナル 2011.1.19 放送分
放送第16回目の「工藤泰志 言論のNPO」は早稲田大学教授の深川由起子さんにインタビュー。2011年とは日本にとってどんな年か?世界の中の日本の位置づけなどを議論しました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「2011年の世界の潮流の中で、日本は何を考えればいいのか」
工藤: おはようございます。ON THE WAY ジャーナル水曜日。言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝様々なジャンルで活躍するパーソナリティが、自分たちの視点で世の中を語る、ON THE WAY ジャーナル、毎週水曜日は、私、言論NPO代表の工藤泰志が担当します。
さて、新年もまだ1月で始まったばかりですが、今日は少し大きなテーマで話をしてみたいと思っています。僕たちは、「日本の未来」についてずっと言ってきていたのですが、未来をつくるための戦略というものを、どのように考えればいいのでしょうか。実を言うと、僕たちのNPOでは、4年前にそういうことに挑戦したみたことがあります。その時は、1つの方法論がありました。まず、日本の生き様とか生きる道を考えるときは、世界がどういう風に変わっているのか、ということを考えなければいけないといった、世界の潮流の変化を考える。それから、日本の強さ、弱さをきちんと考えなければいけないわけです。そして、強いところを伸ばしていかないとダメなのですね。それから、最後は、日本としてどういう国になりたいのか、何をしたいのかということ。この3つがあって初めて戦略というものはつくられるのですね。僕たちは4年前に日本のパワーアセスメントということで、日本の評価ということをやりまして、それがかなり大きな話題になったことがありました。今回、僕は日本の未来ということを考えていますので、折角の機会ですから、世界の潮流を知りたいと思いました。つまり、世界では大きく何が変わろうとしているのか、その中で日本は何を考えなければいけないのか、ということを考えたいというのが今日のテーマです。
そう考えていたら、僕の友達にぴったりの人がいたのですね。まさに、アジア経済の専門家で、早稲田大学の教授で深川由起子さんという女性です。非常にズバズバと言うので、初めて会う人はびっくりしてしまうのですが、かなり本質的な話をされる方なのですね。なので、色々と頼んでいたら、時間が取れて話を聞くことができました。彼女に話を伺って、それをベースに、「2011年、世界の中で日本は何を考えればいいか」ということを、今日は皆さんと考えてみたいと思います。
では、早速、深川さんの話を聞いてみたいと思います。
2011年の世界は構造変化がはっきりしてくる
深川: 私は、2011年は世界が向かって行く構造変化がはっきりしてくる年だと思います。いわゆるG7はみんな経済苦境にあり、財政面での出口が見えない。日米欧が揃ってここまで悪い時期は稀でしょう。そこに新興の大国が台頭している。いわゆるBRICsはみんな大国意識が強く、しかもG7が仕切ってきた世界や国際秩序に歴史的な反発を持っているわけです。その他小規模な新興国も心情的には同様なところがあり、南北の対立が顕在化しがちです。南北対立は少しも動かないWTO交渉やCOPなどの環境関連に止まらず、通貨や領土や歴史問題にも及び、G7が仕切ってきた世界を変えたいという動きが表面化し、これまではグローバル化の中に埋没していた「国家」というものに焦点が当たる気がします。
殊に財政危機の欧州各国が中国への支援を頼まないといけなくなる局面は多いでしょうし、アメリカが中国の資金フローに依存する構図も変わっていません。新興国とG7の力の交代が鮮明になってくると思います。そうすると、もともと経済力しかない日本という国の経済苦境はパワーの凋落に拍車をかけるでしょう。
国際社会の中で大国として生きるか小国として生きるかではゲームが違いますが、日本は今までは(経済)大国だったわけです。国連の分担金はまだ2位です。しかし、経済停滞が続くうちに高齢化が進行し、この過程には「大」からダウンサイズしていく自主的な戦略がありませんでした。よって国際的には未だ「大」の責務だけが残り、それ故に国内には未だ「大」国だった過去のイメージを払拭できない二十世紀型自画像を持つ国民が残されました。「中」規模国家という自画像模索と、「大」国の残像の混在を整理し、自分がどれくらいのサイズの国として認識して勝ち組になれるところを見つけられるかが20011年の課題だと思います。それについて国民のコンセンサスをつくっていくということです。
日本は「中」レベルの国に見合った戦略を考える時期
工藤: 日本はもう「中」規模国家なわけですね。いつ頃から「中」になったのですか。
深川: 象徴的には中国に抜かれた2010年ですが、あるいは東アジア危機について期待されたリーダーシップをとれなかった2000年ぐらいなのかもしれません。この頃に購買力平価では既に中国に抜かれつつあったわけですから。
工藤: 国民とそういうことをベースにして議論し、どういう風に日本が生きていくかということを提示しないといけない段階にきているわけですね。そうすると、2011年ですが、EUは厳しくなるのですか。
深川: EUは厳しくなると思います。財政危機からの出口がみつからず、新しい成長戦略やイノベーションも目立たないままです。景気のバッファーだった移民との摩擦も起きています。人権につながる福祉社会は欧州の価値観そのものだから看板は下ろせないし、厳しい調整が続くでしょう。
工藤: つまり、G7が崩れ始めてくるわけですか。
日米欧はババ抜きゲームの段階
深川: EUは財政危機。アメリカは、ずっと体力はあるが失業率の高止まりが社会を揺るがす点で変わらず、財政危機が先に来るか、基軸通貨の危機が先に来るか、両方一緒に来るか分からない。日本は言わずもがな。日米欧で誰が一番危ないのかというババ抜きゲームが続いている気がします。
工藤: EUが崩れればどうなっていきますか。
深川: 失敗すれば統合EUは分解するのでしょう。アイスランド、アイルランド、ギリシアぐらいならまだしも、スペインやポルトガルが危機になれば統合の維持は難しいと思います。小国はEUから離脱すれば通貨は切り下げられますし。ここで問題となるのは分解するか、連帯責任を続けるかの政治的決断ですね。今はまだドイツが頑張っているので、政治的意思が堅いわけです。しかし、ドイツ国民が「やめた」となれば分解圧力は増すでしょう。
工藤: 分解すればどうなりますか。
深川: 分解すると、一部はまた小さい国々に戻るのでしょう。ギリシアとかアイルランドとかは、多分通貨が暴落して、その中で輸出振興や観光振興などを考えてもらうしかないでしょう。しかしEUにとっては域内の不良債権を切り離せることの意味は大です。財政統合はしていないが、金融だけは統合されているという矛盾は大きいと思います。
工藤: すると、日本がそんな国際政治上の中でダウンサイズするには、どうすればいいんですか。
日本の課題は、一人あたりの所得をどう上げるのか、だ。
深川: トータルのGDP規模が中国より小さくなるのはどうでもいい話で、問題は1人当たりの所得を世界の中でこれ以上貧しくしないようにすべきです。バブル崩壊前は2位でしたが、そこからヨーロッパが上がりましたので、今はOECDの中でやっと中位でしかない。また、格差ばかりが話題になりますが、維持不能な財政支出で短期の格差を埋めるより、機会の平等の維持を図ることが重要と思います。
工藤: それを最低限維持するということですか。
深川: これ以上は落とせません。むしろ上げないといけない。当たり前ですが、1人あたりの所得は生産性を上げ、成長し、雇用が増えれば上がるわけで、その大前提はデフレ解消ということでしょう
工藤: そのためにはどうすればいいのですか。
深川: やはり思い切った構造改革と経済連携の組み合わせしかないと思います。。
工藤: 後は、日本の構造改革ですね。
軸は経済連携
深川: ヨーロッパの一人当たり所得が上がった過程をみると、ドイツやフランスが1カ国でやっていても、あんなに上がるわけはありません。みんながEUという枠組みで5億の市場を作り、為替リスクのないビジネスを拡大したから上がった面が大きいと思います。この経験をみれば日本と国内体制が比較的近く、価値観が似た国、例えば韓国、台湾、香港と、ASEANの上位国、この辺とはもっと深い統合を追求すべきです。関税を引き下げるだけではなく、日本も農業を開放しなければいけないし、結びつきの強いサービスとか人の移動をもっと自由にする。しかし、深い統合には競争条件とか人の移動による社会不安の問題もあるので、相手がある程度共通の体制も持っていて、犯罪の取り締まり協定とか、国内の制度面が整っている国から結束を高めていくべきだと思います。そうすれば、大体5億人位の市場ができ、やっとEUと同じくらいになります。後は「事実上の」統合が進んでいる中国とインドが加われば、日本は欧米に比べてさえ、ずっと地政学的に恵まれたポジションにあると思います。となり、中国の13億、インドの10億も統合が深まることになります。
工藤: 日韓のFTAやASEAN先発国の高い水準で完成させながら進むわけですね。その場合は自分も農業を開放すると。それに合わせて日本の構造改革をやれるかどうかですね。
深川: アジアに対しての農業市場開放は向うも大した生産性ではないので、今、TPPで議論されている米国への開放に比べれば大したインパクトはないはずです。しかし、アジアの皆さんに一番先に開放しますということは、政治的にはパフォーマンス効果があるわけです。そういうことを、政治家がやらないといけないわけです。
工藤: それができると、その次はどうなるのですか。
深川: 日本自身も、他のアジアも既に中国との経済的紐帯は濃密なので、結局は中国を視野に入れることになります。日中は、経済統合の制度化はどうあれ、もう今更別れられない関係です。特に経済界は。しかし他方で、中国の自己主張願望に基づく一国主義を修正するには、もはや今の日本の力では足りず、必ずアメリカとの関係も必要なわけです。昔みたいに世界第2の経済大国ではなくて、中規模に過ぎないんですから。一方で、欧米に向かっては、日本をゲートウェイにするというアイデアは未だある程度は有効だと思います。上海や北京など空気悪いところに行きたくなければ、東京か九州に駐在して、物流も自由なのでいいですよという政策を打っていく。
工藤: 国を開くということはそういう考えですね。
深川: と、私は思っています。
工藤: それに対して、政治の動きはそうなっていないわけですね。
深川: 経済連携のゲームは3通りしかないと思っています。大・中・小と。「大」は大のゲームがあり、市場の大きさを求めてFTAは向こうから言ってくるので、自分が働きかける必要はあまりない。日本もついこの間までそうだったので、ロードマップはありませんでした。他方、韓国は「小」もしくはせいぜい「中」だったので自分から言わないと誰もやってくれないわけですから、ロードマップ作って一生懸命やっているわけです。さらに、「小」のシンガポールはむしろ失うものはないので、フリーハンドを最大限活用し、好きなようにやればいい、ということです。日本の場合は「大」のゲームをしているつもりだったら、いつの間にか「中」になっていたので、国民が日本はもう「大」ではないという事実を直視できていない。政治家のFTA議論を見ているとそれを痛感します。自分のゲームリーグが決まれば、FTAもやり易くなると思いますよ。
工藤: 今の深川さんの話はかなり本質的で、つまり経済規模を競い合うような時代ではなくて、日本は既にそこから見れば落ちていると。しかし、日本の1人あたりの所得をきちんと守ろうよ。また、それを拡大するために、日本の経済体制を変えなければいけないのだと。ただ、それを日本の政治ができるかどうか、ということがポイントだと言っているわけですね。その部分について聞いてきましたので、お聞きください。
日本の政治は構造改革ができるのか
工藤: 政治家1人ひとりは構造改革を意識している人はいますが、今の政治全体では構造改革という流れではないですよね。選挙対策政治。
深川: 構造改革などという全体像はほとんど感じられません。あるのは、このところいつも選挙に勝てるか勝てないか、小出しで連携性のないアイデアだけ。もはや有権者の方が政治家の平均よりは、多分、上なのだから、有権者が投票して自分の意思を示すしかない。だから、言論NPOが大事なのですが、相変わらず政治的無気力とポピュリズムだけで浮動層は動かない。これについては、メディアも悪くて、昨年の最大の話題は、名目GDPで中国に抜かれることより、購買力平価で見た1人当たりのGDPが台湾に抜かれ、さらに5年から6年で韓国にも抜かれつつある、ということだと思うのですが、そんなことも報道されていないことです。
工藤: この流れを変えないといけないわけですね。
日本は衰退し、大国でなく、多額の借金がある
深川: だから「私たちは衰退している、大国でもない、借金を多額に持っている」ということを徹底して認識してもらうしかない。政治家や問題先送りインセンティブの大きな高齢者など、都合良く、みんな忘れていますよ、この3つ。単に悲観することと現実を直視することは明確に違うはずなんですが。
工藤: さっきの1人あたりの所得を上げながら衰退していくというシナリオは、今のままでは無理ですね。
深川: 問題先送りのその場しのぎでは衰退は衰退でしかない。でも成長しなかったら、誰が、どうやってあの900兆円の借金を返すのですか。返せませんよ、やっぱり。
工藤: まだ間に合うのですか。
深川: 全体像を描いた上でパズルを組み直し、出来ることをやるしかない。しかし戦争に負けたわけでもなし、日本は市場の持っている能力は非常に高いので、ポテンシャルはあります。農業だって、物流だって、恐らく公的セクションの改革だって、知恵があるところではいろんなアイデアが生かされている。生産性が上がる余地はまだまだいろんなところにあると思います。
工藤: 市場が持っている能力というのは具体的には何ですか。
深川: 技術力、複合的な付加価値力、それにある種の社会資本などです。最近の流行でいえば、それに文化力が加わるということでしょうか。
工藤: ということは、それらで勝てるようにするための障害はなんですか。
深川: まず、最低、企業には国際的にみて公平な競争環境を与えるべきです。日本企業は六重苦以上を背負っています。例えば、法人税も高く、無策を反映した為替レートの変動に翻弄され、環境負担、厳しいコンプライアンスに耐え、FTAもなく、ゆとり教育の失敗が本格化しつつある人材不足など。短期的にはもうデフレを何年もやっているので円高は財界が言うほどでもなく、そう円安になることは期待できない。これだけ世界全体が混乱した中で、勝ち残れる国は自分が比較優位なことを徹底して、しかも着実にやる国だと思います。やはりヨーロッパの中でドイツが一番強いのは、金融だけに踊らず、EU市場や世界市場への輸出、特に中小企業輸出を強化して製造業を捨てなかったからです。日本は製造業をほとんどアジア圏に撒いてしまいました。だから、もはやアジア圏をみんな外国だと思わず、みんな日本の経済の一部と思わないとだめです。企業もみんなアジアに出ていってしまいましたから。また、若い人は大会社や公的セクターなら食べさせてもらえるだろう、といった甘えを根本から捨て、個人として組織に依存せず、自立してグローバル化社会を生きる、という発想で人生設計をしないと、非常にみじめになると思います。
工藤: そうすると統合っていうのが追いついていないということですね。
深川: 制度化が追いついていない。あとはアジアの重要性を認識して、日本が折れる姿勢を持たないと先は開けないでしょう。
工藤: 折れるというのは、さっきの大から中ということですか。
深川: 「中」に過ぎないのだから、農業の交渉でアジアに対しては思い切って折れる。自分が折れることなく相手に一方的に要求できるのは「大」国のゲームであり、「中」ではそうはいかないからです。それでもアジアの競争力や成長力を欧米以上に取り込めるのであれば、プラスマイナスで言えば、圧倒的にプラスの方が上回ります。
工藤: でも今のことは有権者が投票しないといけないとかありますが、そこまでの決断は...
メディアは日本の状況を何も語っていない
深川: それはメディアが何も言わないことも大きく影響していると思います。みんな、都合のいいことばかりを書いてきたわけです。GDPが世界第3位になる時は言いましたが、台湾や韓国に負けていくことはつい最近まで、報道してきませんでした。報道はこれが現実だと、もっとリアルに言わないといけないと思います。結局、「大」だった額縁が壊れて自分の自画像を入れる額縁の大きさが分からなくなっているから、どうしたら政策をその中にパズルで入れるのか、優先順位がつけられなくなっているのです。それが今、政治がやっていることのように思えます。
工藤: 政治をそういうふうに向けさせるためには、どうすればいいですか。
日本の現実を知るところから始めるしかない
深川: だから額縁の大きさの現実を思い知るしかない。日本はこの額縁の大きさの中でしかゲームができないということを、国民にもきちんと言って、国民がその額縁の中で一番合った政策を示す人を選ぶという、当たり前のことをやるしかないのでは。少なくとももう大国ではないことを知ってもらうことから始めるしかないと思います。実際、かなりの国民は気づいているが認めたくない、という人が一番多いのではないかと思います。
工藤: その前に財政破綻しませんか。
深川: いまは単に延命されているだけですからね。本来ならもっと先に市場からの死刑宣告がきていたかもしれませんが、アメリカと欧州が同時に崩れているから、安全な資本の投入先が円しかなかっただけです。都合良く使われているだけですよね。
工藤: つまり、彼らがもっと困っているから、日本が...。
深川: 相対的な問題ですから。中国は人民元を切り上げたくないし、他に受け皿がないのですね。
工藤: ということは、実体的には日本は破綻しているのだけれど。
深川: だから、「JGBバブル(国債バブル)」と呼ばれているのではありませんか。バブルは所詮、泡でしかない。
工藤: 延命されているわけですね。今のやり方は全体的にばら撒いてその中でいいものを引っ張り出すという、温室的な発想ですよね。
これ以上ばら撒いても、ただ衰退していくだけ
深川: これ以上ばら撒いても、ただ衰退していくだけ。でも、最後にはバラ撒く麻酔が効かなくなりますので、突然苦しくなり、非常に痛ましい光景が繰り返されていくことになる気がします。集中配分し、現状を突破し、成果を分配するサイクルを見いだせない限りは。
工藤: しかし国民にも矛盾があるわけですね。分かっているならそれが投票行動に結びつくはずなのに。つまり政治を自分たちが思っているものを選んでいない。
深川: しかも、責任を回避しているということですよね。有権者には政治を監視する義務と権利があるのです。しかしどこかで誰かが何とかしてくれるのではないかと甘えている。この点ももたれ合い社会の悪さが露呈しています。
工藤: それで2011年と2012年を考えた場合、2011年の意味というのは何でしょうか。
2011年はもう最後だ、という意識が大事
深川: だから2011年は色んな意味で最後のチャンスだと思います。日本が自分たちで考えて自分たちの将来を選択するという許された時間は多分、比較的平和な2011年ぐらいしかない。2012年には次第に出口のなさが表面化する先進国の財政危機の問題とか、非常に異形な大国になってきている中国とかエマージングパワー(新興勢力)の人たちの現状、秩序、変革、意欲というのが政治現象となって噴出する気がします。何しろ、2012年は米国だけでなく、ロシア、韓国、台湾と揃って選挙ラッシュの年です。中国も政権交代となります。各国とも政治の年を迎え、極端な事件が起きやすくなるでしょう。だから自分だけで動ける余地は少なく、2011年が自分たちだけで答えを出せる最後の年になるような気がするのです。
工藤: 2011年、日本の政治が次に何を迎えるかの基礎ができないとだめですね。2011年、最後のチャンスですね。
深川: そうですが、これまでも最後だという意識がないのでいつまで経っても駄目なのです。ずうっと問題の先送り。小さな問題を先送りし続けて、最後に統制不能な巨大リスクを背負い込む、その危険性を直視して国民が行動するしか、この閉塞を突破する道はないと思います。国民に示す必要があると思います。
困難が大きくても乗り越えるしかない
工藤: 深川さんの話を聞いて、新年なのですがかなり緊張感が増してきたと思います。今年が最後のチャンスだと。ただ、今自分たちが考えなければいけないということが、彼女が言っていることからも、かなり伝わってきたと思います。国際政治も、国内の課題も本当はかなり難しい段階にきているのですが、それでもこの状況を僕たちの力で乗り越えなければダメなのですよ。なので、私たちは議論の力でこれをどうしても乗り越えて、日本の未来をつくり出したいと思っています。まず、僕たちが一歩前に踏み込む、というところから、今年の1年をがんばっていこうかなと、今日思った次第です。今日も熱い、というか、かなり本気の議論になりましたが、この形でまた続けていきますので、皆さんもご意見があればお寄せください。今日は、どうもありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【 後編 】
投稿者 genron-npo : 13:25 | コメント (0) | トラックバック
2011年1月12日
「2011年度予算は未来に向かう予算なのか」
-ON THE WAY ジャーナル 2011.1.12 放送分
放送第15回目の「工藤泰志 言論のNPO」はゲストに慶応大学経済学部教授の土居丈朗さんをお迎えして、年末に言論NPOが行ったアンケート結果でも評価が低かった政府の予算案について議論しました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「2011年度予算は未来に向かう予算なのか」
工藤: おはようございます。言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝様々なジャンルで活躍するパーソナリティが、自分たちの視点で世の中を語る、ON THE WAY ジャーナル、毎週水曜日は、「言論のNPO」と題して、私、工藤泰志が担当します。
さて、既に新しい年が始まっています。今年は、この国の未来を決めるための基礎固めの年にしたいと先週、私は言ったのですが、相変わらず政治では、依然として内閣改造とか、小沢さんをどうするかとかごたごた続きです。だけど、この1月に僕たちが本当に考えないといけないことは、この国の予算の問題なのですね。今月開催される通常国会で、予算を決められるかが焦点になっています。私たちはこの予算について、この間議論してきましたけれど、日本が財政破綻しないために、また財政再建に対する道筋をきちんと描いているのか、さらには私たちの約束についての実現がどの程度、政府が真剣にこだわっているのか、ということを、きちんと考えなければと思っています。
今日は、この予算を考えるときに、この国では無くてはならない先生がいまして、今メディアでも引っ張りだこなのですが、慶應大学の土居丈朗教授に、スタジオに来ていただいています。土居さん、今日はよろしくお願いします。
土居: よろしくお願いいたします。
工藤: さて、番組では、ご意見やご感想、取り上げて欲しいテーマなどをお待ちしております。色々とメールがかなりきているのですが、その内容が全部本格的なものでして、これを説明するためには、1番組とらなければいけないので、今日は勘弁してもらって、必ず改めてやりたいと思っていますので、よろしくお願いします。皆さんもご意見・ご感想をどんどんお寄せください。番組ホームページの水曜日、工藤泰志のページにいっていただいて、そこでメールやツイッターでよろしくお願いします。
ON THE WAY ジャーナル、「言論のNPO」今日のテーマは「政府の予算案、何で言論NPOの評価はこんなに低かったの」という形で、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。
言論NPOの評価は21点
昨年の暮れに、僕たちは100日評価を発表しました。菅改造内閣発足後100日というのは、12月25日のクリスマスの日だったのですが、その後の27日に評価を発表しました。財政分野での評価は100点満点中21点でした。21点は低いかどうかと言ったら低いに決まっているのですが、他の分野も低いので、相対的に低いかと言われれば、真ん中ぐらいの点数でした。だけど、やはり菅政権は、まさに強い財政をつくり、財政再建をきちんとやるということを、少なくとも参議院選挙の時には言っていましたので、私たちは、かなり厳しく評価したという感じなのですね。今日は、土居先生もいらっしゃいますので、僕たちの評価は厳しかったのですが、この100日について、まず土居先生の感想はどうだったのかということを、一言お願いできますか。
中身は非常に説明不足
土居: 確かに、昨年の6月に菅政権は財政運営戦略というものを出しました。ここでは、いくつかのことを決めているのですが、まず1つは、平成23年度予算案の歳出の大枠、つまり国債費を除いた歳出全体を71兆円に押さえること、それから、国債発行額について44兆円を下回るようにすること。それから、2015年までにプライマリーバランの対GDP比を半減させて、2020年までには黒字化するということをいっていました。前2者については、最初の関門になっているのですが、これは何とかかろうじてクリアしました。そういう意味では、一応点数をあげてもいい点だと思います。ただ、その他の中身ということになると、71兆円の枠に収めることで精一杯という感じがあって、社会保障費の高齢化によって増える自然増の部分については結局野放しにされ、その辻褄合わせに四苦八苦したという状態です。本当はもっときちんと説明をすれば、私ならばそれなりに説明できる部分はあるのですが、全然菅内閣としては説明をしていない。例えば、法人税を減税して、所得税の内、高所得者の給与所得控除を縮小した。この1つをとってみても、その2つは学者からすれば整合性がある、と政権交代の前から言っていたことだったりするのですが、その説明たるや、企業には優遇して高所得者のような取れるところから取る、みたいな雰囲気すら漂わせている程度にしか、残念ながら菅内閣は説明できていません。それから、確かに、公共事業を削減し、教育費は全体としてはちょっと減っていますが、メリハリをつけている面はあるのですが、それについての説明はほとんどないような状況です。いい予算をつくっているようにも見えるのですが、中身は非常に説明不足、さらにはマニフェストとの整合性もきちんと説明できていません。
工藤: 今、土居先生に基本的なおさらいというか、評価をしていただいたのですが、これから僕も聞きたいこともありますので、議論を進めていきたいと思います。今日は、こういう形で、土居先生と予算案について話していきたいと思います。
何のための財政運営戦略なのか
早速なのですがこの予算案を見て、まず、菅さんは財政再建をやらないといけないだろうということを言って、それに踏み込むために財政運営戦略をつくったわけですね。だから、予算案を見ると、財政運営戦略は実現した、ということですよね。でも、財政運営戦略が何のためにあるのかというと、日本の財政を再建することです。つまり、財政の中で非常に過大な借金が累増して、規律が働いていない。この問題を何とか変えて、最終的な国際公約である2015年のプライマリー赤字のGDP対比の半減、2020年のプライマリーバランスの黒字化、という目標があると思うのですが、今回の予算案はそれとの整合性ということで、道筋が非常に見えない。それだけではなくて、去年もそうなのですが、今回も税収を上回る借金、これは僕たちが家計レベルで考えても、自分の家計の収入よりも毎年借金が多い、ということはマズイのではないかと思うじゃないですか。今回もそうなってしまっている。だから、結果としてどんどん借金が拡大していく構造が今回も止められなかった。これについては、どう見ればよろしいのでしょうか。
土居: 結局の所、政治主導と言っている割には、党内の目に見えない反発を恐れて、及び腰になっているというところだと思います。例えば、2015年、2020年というのは、確実に衆議院議員も参議院議員も、1回は選挙をしなければいけないというぐらいのことは分かっているので、自分の任期中ではないかもしれないとか、もう1回選挙する時に新しく何かを言えば、2015年とか2020年までの目標を達成するような方策を、その時になれば考えられるかもしれないという淡い...
工藤: 誰かがね。自分ではなくて。
土居: そうそう。淡い期待があって、そこはアグリーするわけです。ところが、目先の来年度予算とかいう話になると、確実に自分は衆議院議員や参議院議員であって、それをきちんと自分の手で、賛成するなら賛成する、反対するなら反対するというふうにしないと、有権者から突き上げを食らうということは分かっている。ということになると、歳出については増加圧力、税収については増税反対圧力がくるということになるわけですね。そうすると、結局歳出の大枠を71兆円と言っているのですが、確かに平成23年度予算というレベルで言うと、それなりの妥当性があるかと思うのですが、次の24年度、25年度についてもこの3年間連続して71兆円以下にすると言っているだけでは、全然プライマリーバランスは改善しないのですね。余程、景気が良くなって、税収が増税せずとも大きく増えるということでない限りは、プライマリーバランスは改善しないという動きになっているわけです。結局のところ、それが分かっていて、党内をきちんと説得する必要があるのにやっていない。こういうことじゃないと、プライマリーバランスは改善しないのだから、申し訳ないけれど来年、再来年と協力してほしい、歳出削減に協力してほしいとか、もっともっときちんと浸透させていかなければいけない。そのためには、ある意味で恨みを買うとか、嫌われ役にならざるを得ないという人が、閣内にいないといけないわけです。ところが、そういう汚れ役、嫌われ役がいなくて、結局自分もいい顔をしようと思っているところがあるから、結局は緩い歯止めしかかかっていない。それが、財政健全化のための道筋とは、必ずしも整合的にはなっていない、ということになっているのだと思います。
工藤: 僕から見ていると、官僚は悪い悪いと言うのだけど、政治が政治主導で今までの昔の政治と違うのは、自分たちの意思で財政再建をちゃんと動かせようと。さっき、汚れ役と仰っていましたが、そういう人たちがいないと成り立たないわけですよね。でも、見ていると、官僚の方が、財政当局の方が何となく色々と縛りをかけて、このままいったら日本は破綻してしまうかもしれないけど、それを押さえていて、かろうじてそのレベルは何とか守られている。しかし、政治の意思で、本当に財政再建をして、何かをするというビジョンなり、そのための道筋が全く見えないために、このままいったら、ダメになってしまう感じがしてしまうのですよ。
財政再建に向けた政治の強い意志が感じられない
土居: 私もそう思います。つまり、よくある予算絡みの俗説で、財務省陰謀説とか、財務省主導説というのはあるのですが、その裏返しは何かというと、政治家が汚れ役になっていないことだと思います。つまり、省庁横断的に、こういうビジョンのためには、メリハリ付けをすると。優先順位の低い予算は申し訳ないけどカットする、というような嫌われ役を買って出ないといけないわけですね。それが嫌だから、結局その嫌われ役を財務省に押しつけて、財務省も頼まれているから、もしくはある種の自分たちの力を誇示するということも含めて、出ていって抑制をするとうことをやっている。極端に言えば、財務省の官僚がやっている程度にしか抑制できない。
工藤: そうですね。だから、政治は無責任ですよね、完全に。
土居: そうそう。本当は、政治主導というのは、省庁横断的にやってこそ政治主導だと思うのですね。ところが、今の政治主導というのは、各省の三役が省内で自分の意見を通すために、省庁縦割り丸出しで政治主導をやっているということです。
工藤: これ、色々な人たちにちゃんと説明しなければいけないのは、この菅政権が任期上続く2013年まで、支出にキャップをかけるような枠組みはきちんとやろうと言っているわけですね。しかし、それをやったからといって、2015年、つまり任期満了2年後のプライマリー赤字という目標とは、全然連動していないということですよね。
土居: そうです。
消費税の増税頼みなのに、その説明もない
工藤: この前、内閣府の試算を見ていたら、8兆円ぐらい足りないという試算でした。ということは、消費税を値上げして初めて成り立つということです。しかし、政治家は消費税の増税を今恐くて言えないから、その間はちゃんとやりますよ、ということに過ぎないわけですよね。
土居: そうですね。一番鍵になってくるのは社会保障だと思います。つまり、もう消費税を10%ぐらいまでに上げないといけないだろうなという腰だめの見通しは、自民党も民主党もできてはいるのです。ところが、それを言っただけではだめだというのが、この前の参議院選挙の結果だったわけです。つまり、まず税率がありきで、その中身がなしというのは、国民は受け入れないと。そうすると、後はコンテンツをきちんと提示しないといけない。そういう時期にきているわけです。
工藤: そうですね。今回予算の一律削減の時に、シーリングに戻しました。やはり、社会保障の自然増が毎年1.3兆円増えることは容認する。そして、他のところを切り詰めて、切り詰めたところから、特別枠1兆円とやったわけですが、この仕組みもうまく成功しなかった。しかし、この論理の組み立て方が変ですよね。社会保障は大事にするということはわかるけど、それをどうやって効率的にやるかというビジョンを示さないといけない。社会保障は毎年1.3兆円ずつ増えていくわけですから、10年で13兆円になってしまう。そうなったら、他の予算がなくなってしまうじゃないですか。こういうことも非常に綱渡り的な感じがするのですが、どうでしょうか。
土居: 明らかに言えることは、自民党の厚労族と言われていた方々は、その分野については非常にエキスパートではあったのですが、業界と癒着しているのではないかと疑惑があったので、風評をかったところがありました。一方で、民主党の中の社会保障の専門家を見ていると...
工藤: あんまりいないでしょ。
土居: もちろん、いないというのはあるのですが、もう1つは、ここが足りない、ここをもっと充実させてほしいという不満の声を聞いている専門家が多い。
工藤: それだったら、自民党と似ているじゃないですか。
土居: ところが、自民党はここを削らないでくれ、ここの診療報酬も守ってくれという部分も請け負っていた部分もあるわけです。
工藤: なるほどね。
土居: だから、本当はここの部分はちょっと余分ではないか、こっちは足りないのではないかというところを、きちんと余分なところを削って、足りない部分を埋めるということをしないと、社会保障というのはうまく回らないわけです。それが残念ながら、民主党内の専門家でもそこまで把握している人がいないので、削ってもいいところは削ればいいのに、足りないところばかりつけている。
5兆円の補正をなぜ組んだのか
工藤: だから、どんどん増えていくという感じになってしまうわけですね。
時間が無くなってきたのですが、1つ土居先生に聞きたいのは、昨年の11月に5兆円の補正予算が組まれているわけですね。そこで、僕たちが気になっているのは、あの時は日本の経済がデフレスパイラルでどんどん落ち込むというわけではなくて、経済はかなり良かったわけですね。じゃあ、その5兆円は何のために使ったのか、その中身を見てみると、例えば、本来は成長戦略など本予算で使えるようなことが、前出しで使われているわけですね。もしくは、その5兆円があるのであれば、本予算をもっと削れたのではないか、ということが言えると思うのですが、その辺りはどうでしょうか。あの補正予算は、国会対策のためにやったという議論があるわけですよ。
土居: 明らかに政治的な意図を多分に含んでいるとしか思えないですね。
工藤: でしょ。でも、あれは財政運営戦略プランをつくった後ですよね。
土居: そうです、後です。だから、結局、自民党時代から相変わらずということなのですが、補正回し、補正で逃れると。シーリングをはめているのは、あくまでも当初予算までで、補正予算は枠外ということになって、この予算は、当初予算でシーリングがはめられて認められなかった各省の不満を、ガス抜きするために補正でやっている。
工藤: でも、それだったら財政再建を本当に厳しく、覚悟を決めて国民に説明していると言えないよね。
土居: そうですね。だから、私も菅内閣になる前ですが、国家戦略室の中にあった予算編成の在り方に関する検討会のメンバーに加わったのですが、その時にも直接大臣以下に申し上げたのは、補正予算を含めたシーリングをはめずに、当初予算だけだと補正予算で逃れられてしまうと。ところが、残念ながら菅内閣ではできなかった。
マニフェストは実現できないのに修正もしない
工藤: できなかったということですね。最後に、マニフェストなのですが、菅さんは国会でマニフェスト実現については誠実に取り組むと。できなければ、国民にちゃんと説明しますというふうに代表質問で説明しているのですね。今回見ていても、3.6兆円をマニフェストで使ったのですが、一昨年の衆議院選挙の公約と比べると4分の1ぐらいです。できないのだったら、できないで説明したほうがいいと思うのに、依然それを説明しない。あたかも、それがまだ続いているかのごとく幻想を維持している。それだけではなくて、今回ペイアズユーゴーという形で、財源がないものはやらないというルールに変えたのに、そのルール変更についても国民にちゃんと説明していません。僕は、マニフェストをそのまま実現しろと思っているわけではないのですよ。ちゃんと優先順位をつけて、できないことはできないと言って、国民に伝えないといけないのにそれもしない。これはどうですか。やっぱり、点数は低くなってしまいますよね。
土居: つまり、正直に言って得るモノと失うモノがあると。できないモノを意固地になって守っていることによって、得することと損することがあるとすれば、比較衡量してどうするかということを判断すればいいのですが、まず比較衡量している形跡がない。更には、今の私の見方では、正直に言った方が得るモノが多いと思うのですが、そういう判断もしていないから、なかなかマニフェストをやるのだか、やらないのだか。生かさず、殺さずという形になっているという気がしますね。
工藤: 僕はね、財政再建をするということは、当然国民に対して、ある程度の負担を今後必ずお願いすることになるし、公共サービスの低下につながることもあるかもしれないと思っています。だとすれば、政治側として、こういうことについて規律を持ってやるのだというかなり強い、そこまでやるのか、とこちらの側が驚くぐらいのことがないと、国民は信用できないでしょ。
土居: そうですね。だから、欧米の政権交代というのは、むしろそうなのですよね。自分たちの党を支持してくれなかった人に対する予算は、申し訳ないけど削りますよとか、そういうメリハリがあって初めて、政権交代だと思います。悔しかったら、今度の選挙で勝ってみろ、というようなくらいの覚悟がないと、予算のメリハリづけはできない。八方美人になってはダメだということだと思いますね。
バラまきで満足する時代は終わっている
工藤: ただ、土居先生が初めに言っていましたけど、財政再建は国際公約ですから、欧米も非常に厳しいのですが、政権は自分の任期とか、目先の選挙とか、今年統一地方選挙があるとか、それだけで政治を繰り返していたら、この国は本当に終わってしまうと思うのですよ。これでは話にならないので、菅政権、少なくとも今の日本の政治は、政治にまず責任を持ってほしい。その上で、国民にちゃんと説明して、国民との信頼関係を回復しないと、ダメだなと。で、この問題が、まさにこの1月に国会で話し合われるわけですよね。徹底的に話し合わないといけないときに、内閣がどうとか、政治的な議論だけで終わってしまったら話になりませんよね。最後に一言お願いします。
土居: やはり、国民はばら撒きだけでは満足するという時代は終わっているので、政治が財源と、政策の中身をきちんと国民に示す。それで評価を受けるという覚悟を、政治家は持ってもらいたいですね。
結局、未来が見えない予算としか言いようがない
工藤: ということで、今日もまた時間になりました。また熱い話になったので、時間が足りなくなってしまったのですが、今日は土居先生と、政府の予算案について議論しました。この予算案は未来を切り拓く予算だったのか、について色々議論しました。多分、皆さんの中でも色々な考えがあると思うので、意見を寄せていただければと思います。私たちは、今年も、こういう形で議論をしていきますので、またよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
土居: ありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【 後編 】
投稿者 genron-npo : 13:25 | コメント (0) | トラックバック
2011年1月 5日
「2011年、日本は未来に向かって動き出すことができるの?」
-ON THE WAY ジャーナル 2011.1.5 放送分
放送第14回目の「工藤泰志 言論のNPO」は新年最初の放送ということで、様々な有識者に「新しい年に期待すること」をインタビューしてきました。小林陽太郎氏(富士ゼロックスの前最高顧問)、佐々木毅氏(元東京大学総長)、明石康氏(国際文化会館理事長)、武藤敏郎氏(大和総研理事長)、高橋進氏(日本総研副理事長)、宮本雄二氏(前中国大使)、島田京子氏(横浜市芸術文化振興財団代表理事・専務理事)
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
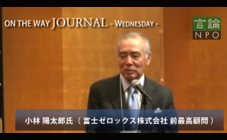 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「2011年、日本は未来に向かって動き出すことができるの?」
工藤: おはようございます。そして、新年あけましておめでとうございます。言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝、様々なジャンルで活躍するパーソナリティが、自分たちの視点で世の中を語る、ON THE WAY ジャーナル。毎週水曜日は、「言論のNPO」と題して、私、工藤泰志が担当します。2011年、初めての放送になります。今年もよろしくお願いします。今日は、2011年、この日本をどう考えればいいのかということをまず皆さんと考えたいと思っています。
実は、昨年の暮れ、言論NPOは9周年を迎えました。本当は10周年とかになると区切りがいいのですが、9周年のパーティーをやったのですね。その時に、日本を代表するかなりの論者が、250人ぐらい集まりました。その時に、私は、2011年は日本の未来にとって勝負の年だと思いましたし、それについて、色々な人たちと語り合いました。なので、その時のスピーチと、私も会場で色々な人たちと話をしましたので、その人たちの話もここで紹介します。日本が直面している課題が何で、それをどう乗り越えればいいのか、新年どういう年にしていきたいのか、ということについて皆さんと考えたいと思っています。
さて、番組ではご意見やご感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしています。皆さんもご意見やご感想をお寄せください。番組ホームページの水曜日、工藤泰志のページに行っていただいて、そこでメールやツイッターでどうぞ。ON THE WAY ジャーナル「言論のNPO」、今日のテーマはこちらにしました。
谷内: 「2011年、日本は未来に向かって動き出すことができるの?」
おはようございます。そして、あけましておめでとうございます。
工藤: おはようございます。
谷内:去年暗い感じで終わったので、今年は明るくいきたいと思います。ON THE WAY ジャーナル「言論のNPO」スタッフの谷内です。今話が出ました、昨年末のパーティー、9周年のパーティーということで、岡田民主党幹事長とか、福田元総理とか、仙谷官房長官や石破茂さんとか、沢山の方がいらっしゃったということなのですが、そのインタビューを中心に、今日は進めていきたいのですが、どういう感じのパーティーだったのですか。
工藤: 僕はね、びっくりしました。今回20人ぐらいにスピーチをしてもらったのですが、普通、こういうパーティーってスピーチする人はみんな嫌がるのですよ。飲んでいるし、そんな時に話したくないというのですが、今回は、会場がシーンとして、皆さんずっと聞いているのですね。
谷内: あんまり酔ってらっしゃらない。
工藤: 酔ってない、酔ってない。飲んでいるんだけど、発言者のスピーチをちゃんと聞いていました。で、発言者のスピーチも、かなりレベルが高かった。今年、つまり2011年が日本の未来にとって非常に大事な年になるということを感じていますね。それについてみんなで考えなきゃいけないし、議論、言論ということの大事さを皆さんが痛感していたんですよ。
谷内: 早速聞いてみたいですね。
工藤: じゃぁ、まず聞いてもらってから、どんどんコメントします。
谷内: まず、どなたから。
工藤: 言論NPOにはアドバイザリーボードというか、言論NPOに対するご意見番が10人います。小林陽太郎さんという、昔経済同友会のトップで、富士ゼロックスの最高顧問だった人なのですが、その人と、元国連事務局次長の明石康さん。後は、誰だっけ。
谷内: 誰だっけって。佐々木毅さん。
工藤: 佐々木毅さん。元東大総長の。この人もアドバイザリーボードです。アドバイザリーボードはまだいるのですが、まずこの人たちの聞いて...
谷内: わかりました。まず、富士ゼロックスの小林さん、佐々木毅さん、それで明石康さん。この順番で聞いてみましょう。
2011年に必要なもの
質の高い言論-小林陽太郎
小林陽太郎: いま日本に必要なのは、質のいい言論です。また、発信はもちろん、その基になるきっちりとした考え方を、志を持つ人達が切磋琢磨してつくっていくことが必要です。いま政界だけでなく経済界などいろいろなところで、「小さくなった」とか「言葉が軽くなった」といった批判があります。言葉の基にある考え方そのものについて、我々として大いに自省し、言論NPOがいろいろな形で場を提供して、日本における言論の質を高めていくことで、どんどん変わりつつあるグローバルな世界の中で、日本の存在価値というものを、質の高い言論を通じて認めてもらうことに通じるのではないかと思っています。
現実を見極めること―佐々木毅
佐々木毅: 若干語弊がありますが、冷戦が終わって20年くらいは、世の中が単純化してきたように思っていました。その前は「日本異質論」などたくさんあったのですが、それからは、見方によっては議論が大変単調になってきた。しかし、ポールソン財務長官のおかげなのか、リーマンショックがあり、これ以降、再び世界が複雑になってきています。政策にしろ言論にしろ、やはり現実に対する耐えざる執念、これを解き明かそうという執念があって初めて議論は生き、根を持つものだと私は確信しています。この国は、やたら政策が多い国でして、どこにその根があるのかといささか心配なところであります。ちょうど今は現実を見極めるために、大いに言論を活発にし、お互いの現実認識を磨き上げ、そしてじっくり取り組むべき時期かと推察しているところであります。
タフな市民社会が必要-明石康
明石康: 民主主義にはタフな市民社会がそれを支えている必要があります。我々がやっていることが徒労に見えることもありますが、ますます厳しくなる東アジアの情勢の中では、お互いの間に何本でも横のパイプをつなげることが大事になってきています。特に縦割りの日本社会においては、こういうパイプを横につなぐことで、いろんな風穴を空けることができるはずです。そのような意味で、我が国の民主主義を本物にするために言論NPOが果たしている役割には大きいものがあると思います。
とにかく、回を増すごとに意義が増している言論NPOですので、「どうして9回なのか」というような野暮な質問は、私はしないことに致します(笑)。このような団体が政治や外交問題に対しても質の高い、多様性のある議論を政治・外交にぶつけることが、我が国の独立と繁栄につながるだけでなく、変なナショナリズムに流れることを防げるのではないかと思っております。
工藤: 今、3人の方の発言を紹介したのですが、ここの中で皆さん言っているのは、「質の高い議論」、「質の高い言論」が必要だろう、と言っているわけですね。つまり、佐々木さんは、今の現実を見極めなければいけないと。つまり、日本の政治がここまで問題を抱えている、日本の未来に対して、課題解決ができる力を持っていない。一方で、世界もかなり大きく変わっているわけですね。その中で、やはりそれを乗り越えるような力強い議論が、色々なところで出てこないとダメなわけですね。その役割を、僕たちにも期待されて、皆さん発言したのですが、やはり、言論という側、つまり議論によって何かを変えるということが、まずどうしても必要だと。その人たちがまず元気になっていかないと、始まらないのではないかと思っているわけですね。もう1つ言っているのは、そうした議論によって、僕たちが守らなければいけないのは、本当に民主主義であって、自由な社会なのです。そのためには、それを支える市民が強くならなければいけない。明石さんも話の中で、市民社会がその中で支えられなければダメだと仰っていました。これも私が、ON THE WAY ジャーナルの中で言ってきた点ですね。皆さん、日本の知識層が考えることは同じなのですよ。ただ、パーティーの挨拶だけでは足りないので、僕、主催者だったのですが、ON THE WAY ジャーナル用に、インタビューして歩いていました。その人たちの発言を続いて聞いてもらいたいのですね。
谷内: どなたに...
工藤: これもですね、言論NPOのアドバイザリーボードの方が2人なんですね。それは、武藤さんという元日銀副総裁。
谷内: 武藤敏郎さん。
工藤: それから、宮本雄二さん。これは前の中国大使ですね。それから、言論NPOの理事で、日本総研の副理事長で、よくテレビに出ている高橋進さん。この方々にも聞いています。それから、会場を歩いていたら、昔日産で社会貢献の担当室長をやっていた、島田京子さんという非常に綺麗な方がいまして。
谷内: なるほど、回っていたら、お美しい方がいたから、最後に聞きたいなと。
工藤: みんな言っていることは、僕の気持ちと同じなのですよ。だから、それを聞いてもらいたいと思います
谷内: わかりました。じゃあ、まずは武藤敏郎、前日銀副総裁ですね。
健全なオピニオンリーダーが必要―武藤敏郎
武藤敏郎: 日本には、今、オピニオンリーダーが不在なのです。政治は司令塔不在、民間はオピニオンリーダー不在。だから、オピニオンリーダーの役割を言論NPOに期待します。
工藤: そうですね。そういう人がいないと、日本を変えられないですね。
武藤: このオピニオンリーダーという意味ですが、やはり、国民を超えた政治というのは出現しないのですよね。国民のレベルより、よりよい政治を望んだところで、所詮は無理なのだと僕は思います。民主主義の一つの欠陥なのだけど、国民と同じような政治しか実現できない。そういう意味で、国民の質を高めるしかないのですよね。政治から高めるというのは、ちょっと手順が逆だと僕は思う。そういう意味で、時間はかかるけど、工藤さんのやろうとされている、言論から立ち上げていこうというのは、私は処方箋としては全く正しい処方箋だと思います。問題は、効果的にそれをどうやってやるかということになると、難しいですよね。でも、一緒に考えてやりましょうよ。
独立した民間のシンクタンクが必要―高橋進
高橋進: もうやらなくちゃいけない政策のリストができているわけですよ。ところが、リストが相互に矛盾する。その時に、どうやって優先順位をつけてやっていくかというのが、政治のガバナンスですよね。だけど、今の政府も野党もそれができていない。だから、そういうことについては民間からどうやって優先順位をつけていくのか、あるいは折り合えるところはどうやって折り合っていくのか。その辺の接着剤というか、触媒的な役割を僕らがやらないといけないのではないかなと思っています。そういう意味では、民間に研究所は沢山あるけど、僕は持論として、日本にシンクタンクはないと思っているのですよね。だから、言論NPOみたいなところが、本当の意味での日本のシンクタンクになれる可能性があるのではないかなと思います。
未来の日本に向かって基礎を固める時期―宮本雄二
宮本雄二: 一番日本にとって問われていることは、日本がどういう国になり、どういう生き様の国になるかということを決めることだと思います。国際的な関係、それについてはあまり心配なさらないで、とにかく自分の国をいかにして立派な、それから、10年、20年、50年経っても安心できる日本の国にするという基礎をつくる第一年。そのためには、何をしなければいけないのか。単に経済政策だけではなくて、日本の民主主義というものを、いかに根付かせるか。民主主義の根本は、議論をすることなのですよ。だから、「言論」が重要です。そして、非常に重厚な質の高い市民社会ができあがって初めて、日本の民主主義というのは完成に近づいていくのですね。そのための第一年に言論NPOの工藤代表とともに、私も一生懸命やりたいと思っています。
ですから、2011年、何が大事か。日本がどういう国になって、何をするかという覚悟を決める年だと思います。
市民を支える強いNPOが必要―島田京子
島田京子: 一人一人市民が、社会に参加していくための言論の...ですよね。
工藤: そうですね。やっぱり、市民が自分の意思とか社会がどうかということを考えないといけないし。
島田: 責任を持たないといけないですよね。
工藤: そうですね。国際交流基金の小倉さんと話をしていたら、政府を批判するのは簡単だけど、それは自分が選んだ政府...
島田: 自分がどうしたいのかと...
工藤: そういうことを考えないといけないじゃないですか。だから、そういう議論のプラットホームを、何としても言論NPOは来年つくり上げたいと思っていますが、どうでしょうか。
島田: 本当にそう思います。だから、それを支えるNPOも強くならないといけないし、一人ひとりでがんばるのもあるけれど、それをきちんと下支えするNPOが強くなる必要があるかなと思っています。
工藤: やっぱり、市民社会が強くなるためには、市民が強くなるから、それを社会とつなげる非営利組織が強くならないといけないですよね。
工藤: このパーティーに色々な友人や、多くの人が来てくれて、非常に嬉しかったのですが、話題になったのは、なぜ9周年パーティーなのかということでした。
谷内: 確かに、そこ不思議ですよね。
2011年 この国の未来に向けて本気で議論を始めたい
工藤: 10周年でやるのではないかと。でも、皆さん、そこには工藤なりの深い意味があるのではないかと言っていたので、僕はその答えを言ったのですよ。僕は、言論NPOを立ち上げたときに、当面10年はやると言っていたのですね。10年の間に、日本の社会に健全な議論を起こす、そういうふうな健全な社会にしたいということが、僕の9年前の決意でした。で、残りラスト1年じゃないですか。このラスト1年の時に、このパーティーをやりたかったのですよ。この1年、つまりこの2011年に、日本の議論づくり、日本の未来に向けてきちんとした、しっかりとした議論をつくっていくことに関して、本気で覚悟を固めて取り組みたいと思っているのですね。ただ、その時に、会場でも言ったのですが、今、政治が厳しいのですね、よくない。ただ、単にその政治じゃダメだと言っているだけではダメなのですね。その政治をつくっているのは僕たちですから。だから、僕は今年、僕たちが主役にならなければいけないと思っています。つまり、僕たち市民が主役になって、自分たちがこの国の将来に対して、どんな形でもいいから、考えたり議論したり、ひょっとしたら自分なりの社会貢献をしてもいいのですが、そういう形で参加していく、そういう年にしないといけないと思っています。未来は、僕たちが変わって、強くなっていかないと変わらない。自分たちの未来を実現できないということを、今年、僕たちは決意を新たにして、始めなきゃいけないと思うのですね。で、このON THE WAY ジャーナルでも、今まで僕が一貫として言ってきたことは、僕たちが主役だ、ということですね。僕たちは、本当にみんなで一緒に考えて、日本が直面していることにかんして、答えを出す。その答えを出しながら、議論の力で社会を変えていく。そういう形を、今後考えていきたいと思っています。
ということで、新年早々、色々な人に登場していただいて、熱い議論になってしまいましたが、今年もこの調子でやっていきますので、皆さん、よろしくお願いします。意見がありましたら、ぜひ、お寄せください。今日も、どうもありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【 後編 】
投稿者 genron-npo : 13:37 | コメント (0) | トラックバック
2011年1月 1日
2011年、市民が動けば日本は変わる大きなチャンスの年に
2011年、言論NPOの活動がどのように動いていき、どのようなことを実現したいのか、代表工藤が語ります 聞き手:田中弥生 (言論NPO 理事)
 |
2011年、市民が動けば日本は変わる
|
田中: 工藤さん、あけましておめでとうございます。
工藤: おめでとうございます。
田中: 今年、最初のインタビューなのですが、誰もが今注目しているのは、政治の行方だと思うのですけれど、どんな展開になるか、工藤さんのご意見を聞かせていただけますか。
工藤: 展開は、今回の国会では、予算の関連法案が今のままでは通らないので、常識的に考えると、政治は非常に混乱していって、場合によっては何があってもおかしくないという状況だと思います。ただ、一番僕が気になっているのは、今の政治で行われている全ての問題は、何かの答えを出す方向に動いていないということです。つまり、僕たちから見れば、この国が未来に向かって今直面している課題を解決して、どう未来に動き出すかということに一番関心があるのですが、今、永田町で行われていることは、それとは違うのですよ。自分たちの権力基盤や、政権を維持することの中での争いですから、今回の政治の混迷は、今の国会で行われているゲームの中では、僕たちが望んでいる変化を起こすことはできない、ということを考えないといけない段階だと思っています。
田中: 確かに、そのことを私たちも感じているのですが、昨年の12月27日にマニフェスト評価、菅政権100日評価の記者発表をしましたけど、皆さん政策の統一性みたいなものが、個別の政策を見ていてもわからないという点が共通していたのですが、今仰っていることと共通しますか。
工藤: それ以前の問題で、去年僕がラジオである議論をつくっていたのですが、今日本にとって一番まずいことは、政府の統治が崩れていることです。政府の統治とは、例えば、ある政策や日本の将来に対する戦略を立案して、その実行に対して、総理がリーダーシップをもってやるという、その回転が始まっていないわけです。問題なのは、その背景にある政党はなんだろうと。政党は日本の将来に向けてどういうビジョンを持って、国民にそれを提起しているのか、ということは無いわけです。よく見ていると政党の中もバラバラで、色々な人たちが意見を持っているという状況です。つまり、政治の現象そのものが、一つの政策軸をベースにした競争になっていない、だから答えがでないわけです。この前の、27日の発表の時に100日評価と同時に、508人に回答してもらったアンケート結果も公表しました。そのアンケート結果で驚いたことは、今の日本はまさに政府の統治が崩れて、財政破綻や社会保障などの課題に答えを出せないまま、日本の政治が混迷をどんどん強めていく、国家危機の段階と思っている人が43%いるという結果でした。「国家危機」という言葉は、そんなに簡単に言える段階の話では無いわけです。つまり、多くの有識者が、政治はこのままいっても課題に向かい合えないということを感じているのですね。それが、今の日本に問われていることだと。
一方で、僕が気になっているのは、来年1年間、今年2011年の1年間はどういうことかというと、多分、日本が将来に向けて行動を起こしたり、国民に呼びかけて、その中で議論が起こったりということができるかどうかの試金石の年だと思います。2012年、つまり来年になるとアメリカの大統領選、中国では権力交代があるし、韓国でも大統領選があるなど、世界の指導者層が大きく変わり始めます。一方で、今世界を見ていると、G7、つまり先進国の力が低下して、ほとんどの国が財政破綻とか、財政危機に直面しているわけです。逆に、中国を含めた新興国が大国意識を持っている国がかなり大きくなってきています。その中で、日本は理念や思想とか、ビジョンによって世界の中で存在感を持っているわけではなくて、ある意味、経済力で持っていたような日本がどんどん衰退に向かって、しかも将来に向けて課題解決もできないまま、漂流しているという状況になってみると、本当に今年は日本の未来について議論をし、そのための基礎固めを始めないと、本当に取り返しのつかない段階になるのではないかと思っているわけです。だからこそチャンスで、僕たちは色々なことを積極的に考えないといけない段階にきているのですが、それから見ると、今田中さんが言っている政治の局面が、余りにもお粗末過ぎるわけですよ。
田中: 今、チャンスという風におっしゃいましたが、具体的にどういうチャンスでしょうか。
工藤: それは、今までの僕たち有権者から見ると、政治や政権交代とか、政治の中でのゲームの展開を期待したところがあったわけです。それによって、日本の未来が変わるというふうに思ったのですが、よく見たら、全然変わらないではないか、体質がほとんど同じだったと。つまり、これは、政治に期待したり、お任せするような状況では、もう答えは出せないということに気付いた段階だと思います。だから、ある意味で今年、僕たちは目を覚まして、自分たちが考えないといけないという段階にきているということです。これは、日本の民主主義を考えた場合に、非常にチャンスだと思うわけです。そもそも政治というのは、僕たちの代表としていっているわけですから、僕たちが日本の将来とか、課題をきちんと考えるような姿勢を取り戻すことによって、日本の政治を変える大きな転機にきている。だから、今年は僕たちが動けば日本は変わる、それぐらいの大きなチャンスにある。そのチャンスを活かすかどうかは、僕たちにかかっていると思います。だから、僕たち言論NPOは、そのためにかなり大きな議論形成をしなければいけないと思っています。
田中: 非常に皮肉な結果ではあるのですが、こうした状況は、政治が有権者に近づいてきたというか、有権者の近くに政治がきたという感じですね。
工藤: もっと皮肉に言えば、有権者のレベル以上の政治ははっきり言って出ないということです。つまり、今の日本の政治は、やはり選挙を意識して、自分たちが志を持って日本の将来に対して、国民を説得するという政治家はいないのですよ。だから、結局、選挙に当選するためにはどっちが有利かという議論だけじゃないですか。だったら、僕たちが日本の将来に向けて、俺たち有権者はこういうことを真剣に考えるのだ、というメッセージを政治に送らないといけないのですね。だから僕は、「議論の力」が今年、非常に大事になっていると思います。
田中: では、具体的に2011年、言論NPOではどのような活動を予定されていますか。
工藤: 僕は2つあって、少なくとも日本は政府を始めとして、様々な仕組みが信用を失い始めているのですが、やはりきちんとした論壇があるべきだと思うのですよ。健全な人たちがきちんと議論をして、その議論をしていることを目に見える形で表に出さなければいけないと思っています。だから言論NPOは、対案力を持った議論を、オープンな形でみんなの前でやっていくことが必要だと思っています。今、課題になっている財政や社会保障、教育など色々な問題があるじゃないですか。自分たちの身の回りには、様々なイシューがある。それについて僕たちは議論をして、答えを出すような議論をしたいということが1つです。
もう1つは、そうは言っても、有権者が政治に対してきちんとした意思を持って、有権者と政治の間に緊張感のある関係を取り戻さないと、日本の政治は変わらないのですね。だから、僕たちはこれまでやってきた評価というものをもっと一段レベルを上げないといけないと思っているわけです。そこで政党の評価だけではなくて、政治家の評価に入らなければいけない。つまり、政策軸をベースにした形で、日本の政治家が何を考えているのかということを、僕たちがきちんと調査をしたり、評価することの材料を有権者に提供していく。また、政治家や政党別の考え方にどのような違いがあるのかということを、議論を通じて目に見える形で、表に出していくということをしたいと思っています。やはり、政治のレベルの中で、私たちが議論でできることは沢山あると思いますので、それを今年から次々にやっていこうと思っています。
田中: そうしますと、やはり今までとちょっと違うなと思ったのは、今まではマニフェストを評価をするというところで、政治家から出された題材を評価していましたが、これからは、あるべき政策の姿についても議論をし、提案をしていくという、ある意味一歩進んだ活動をするということですね。
工藤: 僕たちが政策に対する対案を持って行かないと、政治家をそういう形で仕分けができないのですよ。だから、全てじゃないですけど、日本の課題にとって非常に大事な問題に関しては、僕たちは政策の提案をして行かざるを得ない。そして、その議論を政党に呼びかけないといけないと思っています。同時に、その中にいる政治家がどういうことを考えているか。やはり、全部がダメというわけじゃなくていい政治家もいると思いますよ。そういう人たちの姿を表に出していかないといけないだろうし、政治家が何を考えて、国会の活動で何をやっているかということを含めて、みんながそれを判断できるような材料を提供する必要があると思っています。
田中: 言論NPOでは、今一番の問題になっている、中国との関係において、6回以上の議論形成、フォーラムを行ってきましたが、去年のフォーラム直後に尖閣諸島問題が起きて、非常に難しい状況になりましたが、2011年の「北京-東京フォーラム」はどのようなことを予定されていますか。
工藤: 中国とのフォーラムは、国民間の相互理解をどう深めるかということが目的です。つまり、日本と中国が国同士で何をやっていくかということは政治の舞台でやるけど、今回の尖閣諸島を始めとする色々な問題の背景には、国民の相互理解があまりに幼稚で、基礎的な理解もないという本質的な問題があります。その中でも、メディアの様々な報道が十分に機能していない、という問題があるわけです。この問題に関しては改善するしかないので、僕たちは尖閣諸島問題も含めて、嫌な問題でも中国と本気の議論をして、そのプロセスや結果をきちんとみんなに見てもらう。そういうことをやっていく必要があるわけです。ただ一方で、僕たちは、日本がアジアや世界の中で、どのような生き方をしていけばいいかということに非常に関心があります。そういう大きな夢というか、ビジョンを語る議論にこの対話での議論をつなげていきたいと思っています。僕たちは、中国だけではなくて、色々な国とも議論したいと思っています。つまり、国際社会においても、日本の将来についての議論を他国の人たちとも議論をしていくということも考えないといけないと思っています。今、僕が言っていることは、さっきの国内問題の政治、それから海外問題もそうなのですが、今年は、日本が歴史上、日本の未来に向けて本当のスタートが切れるかの、大事な年だと思います。この大事な時に、僕たちはそこの現場から逃げたくないのですね。この場の中で、議論の舞台をつくって、多くの人が参加できるような仕組みをつくるので、ぜひ言論NPOの議論に参加して、来してほしいと思っています。
田中: 最後になりますが、今まさにオープンな議論の場と仰いましたし、それから有権者の近くに政治がきているという話なのですが、そのためには、私たち自身がしっかりとしなければいけないと思います。言論NPOでは、「市民を強くする言論」という活動を柱の1つに据えて活動をしていると思いますが、これについては、最後に言及していただけますか。
工藤: 強い民主主義をつくりたいと思っています。強い民主主義とは、テレビの中に政治があるという傍観者ではなく、当事者として自分たちの判断が日本の政治をつくるということをきちんと自覚するような、そして、そのためにきちんと選挙に行ったり、議論していくことが強い民主主義をつくる源だと思います。それをつくり出すベースは、僕たちそのものが自立していかなければダメなのだと思います。市民が今の社会に対して、自分たちも当事者の1人なのだということで、政治を選ぶだけではなく、自分自身が社会のために何かをしていくとか、社会と繋がって、自分のできる範囲でいいので、何かの課題に対して答えを出していくという循環が必要なわけです。つまり、強い市民社会と強い民主主義というのは表裏一体なのです。なので、私たちは、この自由な社会の中で、自信を持った生き方をしたいのですよ。それは、自分たちが逃げることではなくて、この社会の中に自分たちが参加することだから、その参加という手段を、僕たちは議論というかたちで皆さんに提供したいのですね。
田中: そうですね。今日、最後に非常にいいメッセージを下さったのですが、2011年は私たちが自信を持って生きる年にしたいですね。
工藤: そうですね。非常に大事なチャンスの年なので、必ずこの1年を大事にしていきたいし、皆さんと一緒に色々な議論をしたいと思っていますので、よろしくお願いします。
田中: よろしくお願いいたします。ありがとうございました。