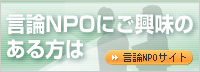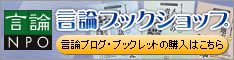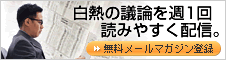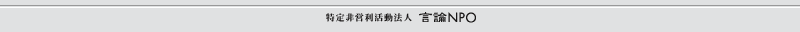2011年2月23日
「日本の民主主義は揺らいでいないか」
-ON THE WAY ジャーナル 2011.2.23 放送分
放送第21回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、スタジオに元東京大学総長で学習院大学教授の佐々木毅さんをお迎えして、「そもそも民主主義とは何か?」という原点から議論します。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「日本の民主主義は揺らいでいないか」
工藤: おはようございます。ON THE WAY ジャーナル水曜日。言論NPO代表の工藤泰志です。私がこの番組を担当してからもう20回が過ぎたのですが、ここからは、少し私たちが今まで当たり前と考えてきたさまざまな問題を、みんなで一緒に考えてみたいと思っています。特に日本の政治の現状を見ていると、この政治が日本の未来に向かってまったく機能しなくなっている。地方でもさまざまな新しい変化が始まっている。これは真剣に考えなければいけない、真剣で重要な問題というのはいろいろとあるのだなあ、と感じたんですね。そのために今日はスタジオにスペシャルゲストを呼んでいます。元東京大学総長で今は学習院大学教授の佐々木毅さんです。佐々木さんおはようございます。
ゲストは佐々木毅教授
佐々木: おはようございます。
工藤: あの、佐々木さんにスタジオに来ていただいたのは、今、私達が考えなければいけない政治の問題、つまり民主主義という問題について皆さんと一緒に考えてみたいと思ったからです。ここでは民主主義のルーツを考えながら、民主主義にはどのような問題があって、それを乗り越えるために過去どのような取り組みがあったのか、そして民主主義を機能させるということをどういう風に私たちは考えていけばいいのか。そして最後にはですね、今の日本の政治の状況を民主主義の視点からどう立て直していけばいいか、ということまで議論を進めていきたいと思っています。この話はかなり大きいので今週と来週の2週にわたって議論をしたいと思っています。
今日のテーマは、「日本の民主主義は揺らいでいるのではないか」ということです。これから私が佐々木さんに質問しながらですね、その内容について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。早速ですが佐々木さん、民主主義という制度は人間が持っている基本的人権とか平等とか、それに適合する非常に大きな、ひとつのきちっとした政治の形だ、ということになっていたんですが、そのためには、この制度の仕組みで社会の課題に対してちゃんと解決、答えを出していく、ということができていないといけないのですが、どうもうまく進んでいないような感じもしているのですね。
民主主義の仕組みが、今の日本の政治を考えてみると、どういう風な現状にあるのか、ということを最初にお聞きしたいのですが、どうでしょうか。
日本の民主主義はどんな状況か
佐々木: いや、もう本当にいきなり根本問題で(笑)。
工藤: (笑)。
佐々木: 今、工藤さんが言われたように、民主主義といっても中学・高校の教科書にあったように古代のギリシャから形が出来上がってきて、そしてこの3世紀くらいの間にだんだん近代の民主政治というものが定着してきた。ということがあって、その古代のギリシャと近代の民主政治の大きな違いは、今、工藤さんが言われたように、基本的人権とかね、人間の自由と平等というものを基盤にして民主主義を制度化する、仕組みを作っていく、という点にあったわけなのですが、民主主義も政治の仕組みでありますから、やはり結果を出さないといけないということがあるわけですね。考えてみれば、何千万人もの人間が政治に参加するというような政治体制ですから、揺らいでいないかと言われれば毎日揺らいでいる、という面が否応無しにあるわけですね(笑)。
工藤: はい(笑)。
佐々木: ですから、民主主義は、みんなが参加するのはいいのだけれども、果たして結果を出せるかなぁ、ということが実は古代以来、ギリシャの民主政治もそうだったんですけど、ずっと問われてきたテーマなんですよね。だから、参加者が広がれば広がるほどいろいろな意見が出てきて、たとえば「国民の意思に従った政治」と言うけれど「国民というのは誰のことか」と言われて、「工藤さんのことだ」と言われると僕は相当異論があるし、「私(佐々木)だ」と言うと工藤さんは相当異論があるでしょう(笑)。
工藤: (笑)。
日本の民主主義は、課題解決で結果を出せない
佐々木: だから、そういう意味で集合名詞なものだから「国民の意向に従った政治」と言われても、答えにはならないところがありましてね。その意味で特にアウトカム、結果ですよね、これが民主主義にとってひとつの大きな課題として、この間ずっと問題にされてきました。ですから「そこがうまく行っていないじゃないか」という議論は決して珍しいものではないと思います。
工藤: そうですね。だからこの結果を出さないと、20世紀は民主主義の時代と言われたんですが、それが信用を失って、ある時はファシズムになったり、いろいろな形になるという、だからこそ、やっぱり民主主義の大事さというか、これを機能させるようにしなければいけない、ということになると思うのです。そもそも長い歴史の中で、さっきはギリシャのポリスの話が出ましたが、民主主義に託された目的というか希望とか、そういうことってどういう風に発展して、どうだったのでしょうか。
佐々木: 託されたものというのは、もちろん元々ギリシャでは大勢の人間が政治に参加するという体制ですから、それ以上でもなければそれ以下でもない。その判断が間違っていれば、さっき問題になったような結果を出せない、というようなことになるわけで、とかく騒がしくてしょっちゅうこっちへ揺れたりあっちへ揺れたりしているような形で、安定のしない政治体制ということであまり評判が高くなかった。
工藤: 民主政治に対する評判がよくなかった、と。
佐々木: 古代ではあまりよくなかった。それでご案内のように、歴史はその後、王制だとか貴族制だとかいうものが長く続いて、また近代になって民主制になっていった、ということです。ですから、その時々の究極的にはそれを担う政治集団、今で言うと政党になるのですが、それからそこに住む人々の判断というものが非常に民主主義の内実というのかな、内容を方向付けるものですから、何かひとつの目的が、輝ける目的があって、ずっとそれを目指して動いてきた、という風には必ずしも言えないと思います。歴史が大きく変わりますと民主主義の中身も大きく変わるし、例えば、20世紀を見ても戦争みたいな大きな変化の時は、やっぱり民主主義の中身もそれに応じてどんどん変わっていくというか、姿も変わっていく。「大変柔軟である」と言えば柔軟ではあるのですが、逆にその分、常に揺らいでいる可能性があって、それが限度を超えて振れますとね、「機能していないじゃないか」という議論がいつも起こってくる。こういう仕組みだと思いますね。
代表制民主主義は機能しているか
工藤: 僕も佐々木毅さんの本を読んで勉強したのですが(笑)。昔って、みんな自由でいっぱい意見を言うと、いろいろな意見になっちゃうので、その意見が正しいかどうかわからない、という状況の中で、佐々木さんの本で見たアリストテレスが民主制の評価をかなり低く見ていた。ただ、その後ルソーなどに代表されるように、人間の権利として、基本的人権とか平等とかいう中で、自由な人間の自然的な権利とか何かを、いかに政治の仕組みに適合させるのか、という形に変わってきますよね。
佐々木: おっしゃる通り。
工藤: そして、アメリカで合衆国ができて、大統領制とか、イギリスみたいな形(議員内閣制)になりましたよね。その中でずっと見ていると、みんなの意見を集めれば集めるほどいいものになるというものではなくて、それが大衆の専制みたいなものになってしまう。それをどう「代表」という概念にしてやるか、かなりみんな知恵を出し合うというか、悩んでやっていましたよね。
佐々木: そうですね。ですから、みんなの意見を集めるということ、あるいはもっと言うと、裏から言えばみんなの意見に耳が傾けられるべきだ、と。いろんな人の意見は聞かれるべきだ、というのが基本的なこの3世紀あまりの歴史の中で定着した政治のスタイルなわけです。ただ、いろいろなものを聞かれるべきだ、言うべきだ、ということを、実際に結果を出さなければいけませんから、どう絞っていくのかということで、結局そこで導入されたのが、代表者というものを通して政治をする、という代表制民主政治というようなスタイルだったわけです。これは古代にはなかったスタイルなものですから、そこで今度は代表者及び代表する人々がどんな権限を持って、さらにはどんな考えを持ってこの国民の意見をまとめる作業をやるのか、というところへ焦点が移っていって、我々が知っている国会だ、大統領だ、なんとか...といったような仕組みや枠組み、これがひとつなければいけない。その上で、その実質的な担い手である政治家たちの動きというものがどうなるか、という問題がこの2世紀あまりずっと焦点になってきまして、時にはうまくいかないことがいくらでもありました。ですから、よく言われるように、そこで独裁的な方がかえって結果が出せるのだ、という議論が今でも、たとえば時々ビジネスの人なんかに聞くと中国と日本の違いなんか...。
工藤: 中国の方が戦略的に行動している。
佐々木:長期的、戦略的に行動しているのではないか、と。かえって民主主義国家の方が短期的でその場その場と...。なにしろ単年度予算で行動しているのだ、という意味では非常に結果が貧しいのではないか、心配だ、と、こういう議論が出てきています。そういった議論はおなじみの議論で、だからといって民主政治というものを捨てるのか、それともこれをどの水準まで持っていけるか、どういう風にしたら持っていけるのか、という課題が、民主制の課題として残されているわけです。独裁的なところは、逆に言えば結果が出なくなったら直ちにアウトになってしまいますよね。おそらくそうなるだろうと、こういうことだと思いますね。
代理と代表
工藤: 僕も政治学の初歩的なことを理解して非常に感じたのは、僕がやっている言論NPOの活動の中でそういうことを痛感するのですが、一番理想的なのは有権者が全員合理的な判断ができて、いろいろなことに関して志があって、それを意見として言うという仕組みがあれば、それくらい民意の質が高ければ、多分非常に理想的な「人民のための人民の政治」というのはありえると思うのですが、実を言うと、歴史の流れを見るとそうではなくて、圧倒的な多数の人々は、一部頑張っている人達はいたとしても、いろいろな情報とか政治のデマゴーグ、宣伝的なことに影響されて、ある時は「戦争へ行け」みたいになってしまうのです。
だから本当はみんな基本的人権などの権利があって、その人達がちゃんとしていればいいのだけども、なっていないとすればその人達を代表する人達に託して...という形になって、それをチェックする、という形になっていますよね。
だから、ここのチェックのところがちゃんと機能しないと、どちらにしてもこの仕組みは同じことになってしまうのではないか、つまり、ただ政治家がいて、有権者がただ選挙の時だけ...。これでは有権者と政治が離れてしまいますよね。
佐々木: だから、ここが非常に難しい問題でね。たとえば、民主主義を導入しようとしている19世紀の終わりくらいの考え方だと、民衆は非常に合理的に判断する、そういう人達の集まりである、と。だから代表者達はただそれを本当に代理すればよいと。
工藤: 余計なことしないで...。
佐々木: という議論が支配的だったんですね。だから「民主化しよう」という話になったのだけど、どうも10年20年経ってみると無関心な人間は結構多いし、それから大体新聞なんか読まないし、それから情報収集能力はそんなに高くない、とかいろいろなことが言われて、結局、逆の問題、側面が出てきました。つまり、代表する側がいろいろな国民の意向というものからピックアップしてきて、自分達でシナリオを組み立てていくという意味で、単に代理ではなくて、もっと積極的な役割を果たすということが実際じゃないだろうか、と。
例えば、日本でいえば郵政民営化なんかもそうだった。ああいう風にひとりの政治家がアピールすることで世論の方が変わる。だから世論が御本尊みたいにあって光り輝いていて、ただそれを代理すればいいのだという考え方ではなくて、その関係はきわめて複雑で、ある意味で言葉は悪いけれども、働きかけたり、かけられたり、という感じで、この代理では済まなくなってきた。代表というものの機能が、ある種、機能的独立性というものを持つ要素としてこの政治に関わる人々、政治家といえば政治家、こういう人達の役割を重視すべきだ、という民主主義論に少しずつ変わってきたわけですね。だから、問題はそういう民主主義を担う国民と、国民に向かい合う政治家集団というもの、この向かい合い方がうまくいくのかいかないのか、というところにだんだん焦点が絞られてきて、こうした視点から日本の民主主義が揺らいでいるのではないか、という不安定感が増してきている。
有り体に言えば、政治家、政党というものの機能的独立性というものが、これで大丈夫かな、とか、あるいは政治家集団の中でいろいろとトラブルが多すぎて、国民に向かって有効な動きをする余裕がなかなか見られないとか、そういった問題を今、先程工藤さんが出されたんじゃないかと。
今の政治家は自分らの代表との意識があるか」
工藤: そうですね。つまり、民主主義というものが機能するためには、みんなが、有権者が非常に強くならなければいけないのですが、一方で代表を送ったのであれば、「この人は代表だ」という意識がなければいけないし、ちゃんと監視しなくては、政治家が自分たちの代表だという意識で国民に向かい合っていく仕組みがないと、多分、関係が切れてしまいますよね。
佐々木: だから、例えば、古典的に言うと地元の利益を代表するか国民の利益を代表するか、と何十年も議論してきたことなのですね。これも必ずしもひとつの答えが出ない面があります。そういう問題に見られるように「代表する」ということはきわめて大変なことです...。
工藤: 大変なことですよね。
佐々木:で、それをどう代表するか、ということについて、プロの側はどれだけ練った議論をして、準備をしておくかということが、やっぱり大きな、重要な要素なのですね。
民主主義の仕組みは改善する努力も大切
工藤: そうですね。話が尽きなくてこれを来週も続けないといけないのですが、やはり民主主義が揺らいでいるというのは、そこの絆というか関係が弱まって、多分、多くの有権者は今の日本の政治が自分の代表だ、と思っている人がいないような気がする。いるのかもしれないけど(笑)、いないとしたら、それは何なのだろうと。民主主義という形がせっかく歴史をベースにしてそこまで作り上げられたのに、それをどんどん今に合うような形で改善したり、努力するというプロセスが何か足りないのではないか、という気がちょっとしました。佐々木さんもそう思ったでしょうか。
佐々木: ええ、それはまた仕組みの問題とも絡むし、動こうにも動けないという場合もあるかもしれません。だけど、それを変えていくのも政治の仕事だろうと思うのですね。
工藤: そうですね。ただ僕、佐々木さんの本を見てわかったのは、つまりそういう風な仕組みがちゃんとないと、たとえば大恐慌とかいろいろな危機があった時に、それを吸収できないために、「わっ」と不満だけが出てしまうという、そういう歴史がこの100年にあったわけですね。
佐々木: たくさんあります。
工藤: あったので、つまり日本が今、課題が多い中で、民主主義の仕組みがきちんとないと、非常に脆弱な体制になってしまって、この民主主義というせっかく作ったものを覆してしまいかねない、という岐路にあるのではないか。それはまだ言いすぎでしょうか。
佐々木: どこが限界なのか、ということはなかなか判断が難しいのですけど、メルクマールとして言うと「ちゃんと予算が通せないと困る」とかね(笑)。それから「毎年、首相が変わるようでは困る」とかね、いくつかメルクマールがあるということは確かですよね。
工藤: そうですね。つまり、今日の話では、民主主義というのはいろいろな問題点があるけれど、それをきちんと克服しながらうまく使っていく、今は、どんどんいいものにしていくという段階なのだな、ということを、非常にわかっていただけたのではないかと思います。さて、では、日本の民主主義はどこが問題で、どう立て直せばいいのかということが次の大きな問題になってくると思います。それは申し訳ないけど次週、佐々木先生とまた話をしていきたいと思っています。今日の話、「民主主義」ということは、僕達の未来に関わっている問題でもありますので、是非、意見を寄せていただければ、と思っています。今日はどうもありがとうございました。
佐々木: どうもありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
投稿者 genron-npo : 14:32 | コメント (0) | トラックバック
2011年2月16日
「強い市民社会に向け、変化を起こそう」
-ON THE WAY ジャーナル 2011.2.16 放送分
放送第20回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、これからのNPOのあり方と評価基準について考える緊急座談会を実施。渋澤健さん、島田京子さん、田中弥生さんとの鼎談の様子をお伝えします。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「強い市民社会に向け、変化を起こそう」
工藤: おはようございます。言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝、様々なジャンルで活躍するパーソナリティが、自分たちの視点で世の中を語る「ON THE WAYジャーナル」。毎週水曜日は「言論のNPO」と題して、私、工藤泰志が担当します。
市民社会の中には、非営利セクターというのがありますが、皆さんの中ではなんか、胡散臭いと思っている人たちがいらっしゃるかもしれないですね。ただ、確実に、市民社会、そして非営利の中で変化が始まろうとしているのです。それを、今日、皆さんに伝えたいなと思っています。言論NPOは、この前、市民会議というものをつくって、望ましい非営利組織は何か、ということで、「エクセレントNPO」というものを提案しました。つまり、「エクセレントNPO」、望ましいNPOを目指して、みんなで努力をしようよ、ということで「エクセレントNPO」の評価基準というものを提案して、みんなで議論しようと呼びかけたわけです。で、非営利セクターの評価基準というのは、何なのかということがあるのですが、つまり、一般の企業ならモノとかサービスを提供するのですが、その中で利益を出すことを目的にしますよね。だから、利益を出すということで、この会社は利益を上げているか、売り上げは増えているかとか、効率的な経営をやっているかということで、評価ができるのですが、非営利セクターは、別に利益のためにやっているわけではありません。じゃあ、どういうところが凄いのかとか、どういうところが仕事をがんばっているかとか、別の尺度でそれを評価するしかないのですね。実を言うと、そうした評価基準というのはこれまで無かったのです。だから、それをきちんと表に提起しないといけないということで、私たちは「エクセレントNPO」の評価基準を提案したわけです。
今回は、この評価基準をつくることに関わってくれた人と、それから市民社会で様々な活躍をしている人たちの3人を中心に、2月2日に座談会をやったのですが、この話をベースにして、どうやったら強い市民社会に向かって、市民社会に変化を起こせるのか、望ましいNPOとは何なのか、について議論をしていきたいと思います。
座談会に出席したのは3人
渋澤健さん、島田京子さん、田中弥生さん
早速、その議論の内容を皆さんに伝えたいのですが、登場したのは3人。1人は、渋澤健という人で、これはファンドを運営している会社の社長なのですが、何を隠そう、昔、この国に資本主義をつくった渋澤栄一さんのお孫さんです。彼は、そのファンドをやりながら、その一部を非営利のセクターに還元できる仕組みをつくれないか、ということをやっている、私の友人でもあります。もう1人は、島田京子さんという方です。カルロス・ゴーンさんが、日産の会社再建のためにやってきたのですが、その下で社会貢献、つまりCSRを担当する部署を立ち上げてやっていた女性なのです。そして、最後は、以前、このON THE WAYジャーナルにも出ていただいたのですが、ドラッカーのお弟子さんで、まさに日本の政策評価をやっている、田中弥生さんです。この3人と僕が議論を行いました。日本の市民社会に今、何が問われているのか、非営利組織をどう評価するのか。まず、それを聞いていただきたいと思います。
不幸を社会の基軸に置く社会でいいのか
幸福の拡大を目指す社会こそ大切では
渋澤: 今の政治は、お金を使って、ツケをどんどん後世に回してしまうという仕組みになりがちなのですね。私たちのよりよい明日をつくるのであれば、一人ひとりの市民が、現状維持ではなくて、まさにサステイナブル、持続性のために、我々はどういう判断をしなければいけないのか、ということが問われ始めたと思うのです。直近、気になったのは、この前ダボスで菅首相が、「不幸を最小化します」と語った。不幸を減らすことは当然のことだから、それはそうなのですが、それを聞いて僕が凄く気になったのは、そもそも不幸ということを社会の基軸に置いていることです。ちょっとそんな社会では子ども達を育てられない、それでいいのかなと思います。幸福を増やすということは、そこで幸福な人たちは不幸な人たちに、自ら手を差し伸べるような動きが出てくると思うのですね。要するに、幸福を拡大することによって政府の役割がどんどん小さくなっていくのですが、不幸を最小化するということだけにとどまってしまうと、どんどん政府が大きくなってしまう。やはり市民社会とは何かというと、政府が全てやるというような、1つの価値観ではなくて、市民の多様性がある価値観で社会を形成しましょう、ということが市民社会のあるべき姿の根源だと思います。
島田: 不幸を最小化するというのは、幸福ということがどんな姿なのか、全然見えないですよね。で、その幸福が何かということの1つの基準ですが、これからの時代、多様性だと思うのですね。とにかく経済成長と言って上り詰めてきたときには、政府の一元的な価値観でやってくれればかなり多くの人を救えたけれど、これからは、ある程度のところまでくると違ってくる。で、その多様性を誰が担保するかというと、やはり政府では無理ですよね。
目指すべきは多様で自由な社会なのでは
田中: 多様性の高い社会って、その中で生きている人たちの能力が凄く求められると思うのですね。というのも、自分の目で選んで、自分の責任で選択をしなければいけない。私は、それが本当の自由な社会だと思うのですけど、そうすると、個人の自立性とか、何でも自分のために選んでいたのでは大変なことになりますから、そこには、他者を思いやったり、公共性というものの両方を持ち合わせていなければいけない。そうなると、個人の力が問われてくるので、それはまさに知識社会とも大いに連動してくるところだと思いますね。
NPOに問われる役割とは
工藤: 強い市民というのは、まさに今おっしゃったような、政府に依存しない、自分たちの意思で判断するとか、何か自分たちでも社会に貢献していくとか。そういう人たちを社会につなぐのが非営利セクターの役割だと思っている。だからこそ、強い市民社会をつくりながら、それを支える非営利組織が本当にその役割を果たさなければいけない局面にきたのだなと思うのですが、実を言うと、非営利組織はその役割を果たせるのか、という問題もあります。むしろ、ほとんどが逆で、政府に依存する形が非営利組織ではないのかという見方もあるのですが。
渋澤: 私は、今、非常に危ないタイミングになっていると思っていて、カリスマ性がある人が、私に任せてください、全てやりますと言った場合に、多分、日本国民はお任せいたします、と。だから、独裁主義になるのですよ、流れとしては。大きな人類の歴史というのは、何回もこういうことを繰り返しているのだと思いますけど、そっちの方にいくリスクをたくさん今の日本社会は抱えている。だからこそ、一人ひとりの市民が意識を高める、それはやっぱりNPOの役目であり、...。
工藤: アメリカでよく言われている、非営利セクターの人が、学生の就職順位の中で一番になったという...。
田中: Teach for Americaですか。
工藤: ディズニーランドを抜いたとか言っていました。つまり、海外では価値観が変わり始めており、多くの優秀な若者が課題解決できるような、また公共的な仕事に自発的に参加するという動きがあるわけです。日本にも、そういう動きは始まっているのでしょうか。何か感じますか。
日本でも市民社会の変化は始っている
渋澤: 私は感じています。10年、20年前のNPOの方々は凄く素晴らしいお仕事をしていたのですけど、結構NPOの世界しか知らない方々の固まりだったのですね。今は、本当にこの5年ぐらいで変わったと思います。NPOに勤めている若手ですが、前はインベストメントバンクとか、コンサルタントかで働いていたという異分子の方々が入ってきたのが1つ。もう1つは寄付という考え方が、前だと寄付というものは大切だよね、でも日本は寄付文化がないという状況だったじゃないですか。最近は、そういう意識も徐々にですけど変わってきたと思っていて。
島田: ボランティアもそうですよね。
渋澤: メインストリームじゃないのだけど、きざしとしては、僕は絶対に変わったと思いますよ。
工藤: 市民の中にも大きな変化が始まり始めていると。で、その受け皿として、非営利組織が今問われなければいけなくなってきている。実を言うと、僕はメディアにいたからわかるのですが、NPOというと、本当に嫌だという人が本当にいるのですよ。NPOというと、悪い団体みたいなね。でも、本当はそうではないはずです。つまり変化が目に見えないとならない。つまり、非営利の世界にある、社会の課題に向かい合い、質の向上を得目指す動きが、多くの市民に見える必要がある。それが、私たちが提案した「エクセレントNPO」を目指す動きなのです。じゃあ、強い市民社会に問われている「望ましい非営利組織」とは何なのだろうか。ということを、ちょっと立ち止まって考えることが必要だと思うのですが。
望ましい非営利組織とは何なのか
― パッションを持っていること
渋澤: 社会起業家とかNPOに私が魅力を感じるのは、凄いパッションを持っていることですね。元気をもらうことができる。そのパッションをどのように評価するか。そこが非営利の側に絶対に必要だと思うのですが、大きなチャレンジはそこにあるのではないかと思います。
― 具体的なミッションが示されていること
島田: NPOというのは行政でもなく、企業でもない。行動原理が全然違う。一律とか利益性だとかそういうことではなくて、まだ世の中で形になっていないものを掘り起こしながら、新しい仕事をやっていく団体だと思うので、まさに思いの部分、それはミッションじゃないかと思うのです。そのアウトカムは何かということをNPOもきちんと定めていかないと、人に伝わらない。どんな社会にしたいのかとか、どんなサービスを提供したいのかとか。それは、やっぱりそういう目標をつくるということだと思うのですね。
― 市民に開かれていること
田中: 私、非営利セクターの研究を20年ぐらいやっているのですけど、ずっとデータを追いかけていて、今の日本で一番顕著なのは、寄付に対して、4万団体の過半数が、0円で計上していて、これは集まっていないのもありますが、集めていない。そこには市民参加の発想が全くないのですね。どうもこの10年かけて日本の非営利組織像の中で全く抜け落ちてしまったのが市民参加の部分だと思います。
工藤: 実は市民に開かれているということは大事だけれど、規模が大きければいいというわけではないですよね。小さくても、社会に対して何かできるかもしれない。そうなってくると、質の評価がないとダメになってきますよね。
― 課題解決で求められるプロのNPO
島田: やはり今、プロのNPOが求められているのではないか。まだ、人に見えていなかったり、形になっていないことを形にしていく、事業にしていくとか、そういうことができる組織、人々の集まりじゃないかと思います。
工藤: つまり、競争力を持たないといけないですね、非営利セクターが。
島田: みんながそんなに大きな課題では無いだろうと思っていたところに先駆的に取り組んでいく。それは課題の発見力と実行力なのですが、別に規模ではなく、種を播いていく仕事というのは小さくても十分できる仕事ですよね。
― 規模ではなく変革を起こす力
渋澤: 変革のプロトタイプというか、全体がすぐ変わらないじゃないですか。で、規模が小さいところで成果が出るような変革を起こすことができるのであれば、組織が大きくならなくてもいいのですが、そこのナレッジをほかと共有すると全体的にスケールアップする。組織は別に小さくていいのですが、ネットワーク。小さいからこそできることはたくさんあると思います。
― 自由な発想で課題に挑む力
田中: 米国のジョセフ・ナイの資料を見ていると、50年間アメリカの政府の信頼度は下がり続けているのですね。それを大学の同僚に話すと笑うのですが、実は大学の信頼度も30年下がり続けているのですよ。大企業もです。それは、先程、島田さんもおっしゃったように、社会が大きく変わる時に、いわゆるestablishmentsと言われている者が付いていけなくなっているのですね。そこに、ある程度、既存のしがらみに絡まれないで、制約されないで自由に動ける主体が先導役として課題にチャレンジしていく、あるいは見つけていく、提示していく、という役割がある。総体的に非営利の役割が上がってきていると思います。
島田: やはり異質なものが共同して取り組まないと、とても先に進めない状況。establishされた大企業でうまくいかないということは、それをしてこなかったということによるのかなと思います。
― 変革を起こすのは「若者」「よそ者」「馬鹿者」
渋澤: 「市民社会」とか「市民性」は、我々は聞いた瞬間に分かる。言論NPOの議論を見ている人はわかると思うのですが、そうでない人に、わかるのかと言われると、多分通じないと思います。そういう意味では、どうやって新しい層の日本人に「市民社会」や「NPO」のことを伝え、我々の孫の世代のためにいかに大切なのかということを気付かせるか、ということが必要なのだと思います。
地域再生のためによく3つの種類の人間が必要と言われる。「若者」「よそ者」「馬鹿者」。それは地域再生だけじゃなくて、いろいろなところで変革が起こるのは、やはりその3者が必要なのだなという気がしています。「馬鹿者」はリスクが取れる人だと思っていますが、そういう人たちがたぶんNPOセクターに入りつつあったんだと思います。だけど、よそ者が入ってくることによって、内から外と外から内の視点、同じ存在なのですが、中から見るのと、外からみるのと全然違うように見えてしまうということが、中にいる人は分からなければいけないのですね。
工藤: つまり、自分たちが当事者で、主人公で、未来がつくられているということに関して、理念だけじゃなくて、達成感とか、そうだねという気付きとかをもっとつくるためにも、非営利セクターは自立して、自発的に社会の課題解決に取り組んでいる姿を「見える化」しなければならないなということですね。
島田: 「見える化」したところに、市民なり他のNPOなりが参加して、そこで議論が始まらないと共有できませんし、共感もできない。そこに批判があったり賛同があったりする中で次のステップが見えてくるんじゃないかと思います。
渋澤: 望ましいNPOという意味では、日々いろいろな人から、「理想ばかり語って、寄付も入らないし、持続性と言っているけど、お前の組織は持続性が無いじゃないか」と言われても、「いや、出来るのだ」と。根拠ない自信かもしれないけど、NPOって、そこがないとできないと思うのですよね。いろいろな批判があって、そんなことできるわけないじゃないか、というのが、周りにいて、いやできるのだということを言い切れるのは望ましいNPOじゃないのですかね。
― 辛抱強く、忍耐強く続ける力
田中: もう1つは、忍耐強く続けるということが重要だと思います。1995年にドラッカーの「非営利組織の自己評価書」を翻訳した際にも、「善意を評価するとは何事か」という批判がありました。そのドラッカーもアメリカに移住して、10年ぐらい経ったところで、非営利組織の方々に「management」が必要だと言った途端にボコボコにされたのですね。でも今は変わったとおっしゃっていて、やはり辛抱強く忍耐強く言い続けることが私は重要だと思います。
新しい変化に向けた競争を起こそう
工藤: まさに市民社会の中で変化を起こそうという、そういう人たちに集まってもらって、急遽、座談会をやったのですが、この模様を聞いて、皆さんはどう思われたでしょうか。僕が象徴的だと思ったのは、時代が大きく変わる時には、今までのエスタブリッシュメント、今まで中心的にやってきた人たちがその動きについて来られなくなってしまう。でも、新しい変化を起こすためには、それを乗り越えて動かさないとダメだ、という感じの発言があったのですが、僕は今、その通りだと思っているのですね。今の国会の議論を見ていても、ほとんど機能していない。ただ、本当に日本を変えなければいけないという時には今の人たちではない、新しい人たちが、多分、それに対してプレッシャーをかけていく、場合によっては新しい動きを始めていかないとダメだという感じだと思うのですね。ただ、最後に厳しい意見もあって、そうした挑戦は持続してやり続けなければいけないということです。僕も、今、まさに新しく市民社会に変化を起こそうと思っています。そういうことを突破する人たちが沢山出てきて、今度はその人たちに俺たちもできるのではないか、俺たちもやってみたい、というような人が出てくるような循環を始めなければいけないし、こういう変化を起こすためには、初めに突破する人は、最後までやり続けなければいけないという感じが凄くしたし、座談会に参加してくれた人たちも、みなさん同じ考えだったと思います。
今日は、市民社会に大きな変化を起こすために、非営利セクター自体が変わらなければいけない。まさに、プロになり、課題解決に自発的に挑んでいく。そういう風な競争が始まらなければいけないということを提起して、評価基準を提案したという状況を、座談会の中でも、皆さんに説明させていただきました。ということで、きょうは「市民社会に変化を起こしたい」ということをテーマに、熱く語らせていただきました。また、私たちの議論に対する皆さんの意見をお待ちしております。どうもありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
投稿者 genron-npo : 12:15 | コメント (0) | トラックバック
2011年2月 9日
「リスナーの質問に答える」
-ON THE WAY ジャーナル 2011.2.9 放送分
放送第19回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、これまでに番組にいただいているリスナーからのご意見やご質問に、工藤が答えました。まだ春遠く感じる季節ですが、日本が「春」を迎えるために、何をすれば良いのか考えます。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「リスナーの質問に答える」
工藤: おはようございます。言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝、様々なジャンルで活躍するパーソナリティが、自分たちの視点で世の中を語る「ON THE WAYジャーナル」。毎週水曜日は「言論のNPO」と題して、私、工藤泰志が担当いたします。
今、僕が非常に嬉しいことは、春が近づいて来たな、ということなのです。というのも、僕の住んでいるマンションは高台にあるのですが、日の出が見えるのですね。太陽が出てくるところが見えるのですが、冬になると目の前のマンションに隠れて太陽が出てくるところが見えなかったのですよ。でも、今日は太陽が見えたのですね。ということは、太陽の位置がだんだん春から夏の方向に向かい始めているという状況で、季節は間違いなく春に向かって来ているな、ということを実感して、非常に嬉しくなってきたのですね。この国も、ワクワクするようなそんな気持ちになれたらいいな、という風に思っている今日この頃です。
今日は、この間、ON THE WAYジャーナルの私のところに、メールとか便りが着いているのですね。そのメールや便りにお答えする中で、私が感じていることについて、少し話していきたいと思っております。
山崎: おはようございます。ON THE WAYジャーナル「言論のNPO」スタッフの山崎でございます。よろしくお願いします。
工藤: よろしくお願いします。
山崎: 今日は、工藤さんが今お話になられたように、皆さんからのメールをご紹介していこうかなと思っておりますので、お答えいただければと思います。まず、お二方のメールを紹介させていただきます。
一人目です。ラジオネーム"DR880さん"でしょうか、30代の男性の方からいただきました。いつも楽しく聞かせて頂いております。
工藤: ありがとうございます。
山崎: 『放送でよく聞く「財政破綻する日本」についてですが、その後、どうなるのでしょうか。今できる事は、何なのでしょうか。』
もう一方ご紹介させていただきます。ラジオネーム"やす"さん。
工藤: この方、僕の名前と同じですよ。パクッてるんじゃないんですか。
山崎: それはないんじゃないですかね。
工藤: ないと思います(笑)
山崎: 20代の男性の方から。男性ということで、工藤さんと同じということですね。
『僕は今23歳のサラリーマンですが、将来の事を考えると不安です。「時代の変化」とは言いますが、時代の変化に政府も対応できていないのではないでしょうか。僕たちの世代がこれからを支えていくにあたって、僕たち個人は何をしていけるのでしょうか。』
という、2つのご質問でございます。
自分たちが未来を考えるべき時期
工藤: このお二方の思っていることは、非常にその通りというか、正しい感想だと思うのですね。実をいうと、僕も昔は、政治家や社会の人たちがやることというのは、ちゃんと考えてやっているのではないかと思っていたのですね。だから、それを理解していけば、日本は何とかなるのではないかと思っていたことがあるのですが、僕もメディアの世界にいて、今は非営利の世界に入って世の中を見ていると、意外にみんな考えていないですね。考えていないというよりも、視野が日本の未来とか、国民レベルに広がってないのですよ。私、この前、ある人と会うために、首相官邸に行ってきたのですが、その時に言いたいこと言ってきたのですね。つまり、政治家の国会答弁、今、予算委員会とかやっていましたので、ずっと見ていると、お互い批判し合っているだけで、全然国民と向かい合っていないのですね。これは、なぜなのだろうかと思っていたときに、みんなが言っていたのは、政治家の視野が永田町ぐらいしかないということでした。官邸から見ると半径1キロ以内しか無いわけですよ。そこの中で、権力闘争をやって、自分たちの次の選挙にどちらが有利かとか、そういう感じしかないのですよ。つまり、政治が語っていることは、あくまでも自分たちのことで、国民に対して何かを言う、という感じがないのですね。そうであれば、僕たちが政治家とか何かに、全てを任せるのではなくて、今の状況や日本の将来について、自分たちで考えないといけないという段階にきたのではないかと思うのですよ。そういう意味では、非常にいいチャンスだと思うのですよ。そもそも、民主主義というのは、僕たちが一票を投じて政治家を選んでいるのであって、その時に、政治家に全部任せるから徹底的にやってくれ、というのではない。一回僕たちはそこに戻らなければいけない。つまり、政治家を選ぶ権利を、僕たちにもう一回戻さないといけない、という段階だと思うのですね。
この財政についても社会保障についても、この今の日本の状況が、未来に向けて持続可能ではないということですね。このままいったら、未来が全く見えない状況なのですよ。で、実をいうと、政治家と話をすると、みんな知っているのですよ。
山崎: 状況が分かっているということですか。
政治家は課題解決の覚悟ができているのか
工藤: 分かっている。中には分かっていない人もいるのですが、自分たちが、何が何でも命がけで解決していく。国民にも、こういう状況だから理解してくれ、と説得していく。そういう人が少ないのですね。だから、選挙の時にはそれよりも、状況は知っているのだけど、今はこういうことを言うと、次の選挙で自分が危ないのではないかと思ってしまう政治家が多いわけです。
山崎: 多いですね、本当に。
工藤: でも、今のままいくと、間違いなくはっきりしていることがあるわけですよ。今のままが続いたら、日本の国は財政破綻しますよね。で、実を言うと、僕がメディアにいたときも、財政破綻のリスクは、色々な人たちが警告していたのですが、色々な理屈がついて、まだ破綻しないじゃないということになる。そんなこと言うから君はオオカミ少年だと言われたりしました。別に僕はオオカミ少年ではないのですが...。
バランスシートを見ると、負債はあるけど資産があるのではないか、だからそれで見合っているのではないかとか、そういう議論になってしまうのですね。実を言うと、このバランスシートで考えることは間違いで、バランスシートが仮に見合ったとしても...本当は見合っていないのですよ。年金ということの保障がないから、隠れ債務があったり、色々なことがありますから。でも、一番大事なのは資金繰りなのですよ。つまり、政府は、毎年国債を出している訳ですよ、来年度は44.3兆円。この前財務省が出した試算で見ると、このままいけば、24年度は49.5兆円、25年度は51.8兆円、26年度は54.2兆円。
山崎: どんどん膨らんでいく。
今の日本は持続可能ではない
工藤: どんどん膨らんでいくわけですよ。で、その時の借金よりも税収の方が遙かに少ないわけですね。つまり、家計でいえば、税収よりも借金がどんどん増えているということは、政府も認めているわけですよ。そうすると、問題なのは、国債を発行したときに、誰が買ってくれるのか、ということですよね。この前、S&Pというアメリカの格付け会社が、日本国債をネガティブにして、マイナスにダウンさせたのですね。そうしたら、マーケットがちょっと気にしたよね。で、世界的にもそうですし、日本の中でも金利が少しずつ上がっているわけですよ。
金利が上がるということはどういうことかというと、国債の価格が下がるということなのですよ。そうすると、国債を買っている金融機関とか何かが、自分の持っている国債という資産がどんどん目減りして、下がっていくわけですね。そうすると、これはもう買えないよとなる。それから、全ての国債のファンディングという調達を海外投資家も一部やっているわけですよ。そういう人たちが、格付け機関の判断にリスクを感じて買わなくなると、金利がまた上がってきて国債が暴落ということになる。実をいうと、財政破綻のリスクというのは、国債に対する信頼性によって決定するわけですよ。そうすると、市場に対する信頼性を確保するためには、実を言うと、政府がちゃんと財政再建に向けて取り組んでいること、何が何でもやるのだ、ということを示す必要があります。それだけではなくて、日本の潜在成長率を上げて、つまり税収が将来増えていくような形に取り組んでいくのだということを、強烈な覚悟でマーケットに伝えないといけないのですね。それを今の日本の政治ができないというところが、非常に厳しいわけですね。
そうなってくると、国債も厳しい。それから社会保障も、特に若い世代ですが、自分たちの老後に対してどうすればいいかということが見えないわけだから、すると自分たちが将来どうなるかわからないじゃないですか。そうなってくると、未来というのは、人に任せていられないはずなのですね。
山崎: そうですね。
自分らが主役だという意識が必要
工藤: だから、自分たちが考えないといけない。僕は、今のお二方の質問や、意見に関しては、だからこそ自分たちが問われているのではないか。自分たちが当事者として、社会をもっと見ていくとか、変なことには騙されないとか、自分たちでも考えていくということが必要だと思います。その中で、自分たちの投票行動に結びつけていく、というサイクルが日本の社会の中で始まればいいのですよ。今、何が問題かというと、若い世代のみなさんが、投票していないことです。僕は政治家と話をすると、若い世代は全然恐くないというわけですよ。恐くないというのは何かというと、投票しないからだと。それでは話にならないわけで、やはり今の時代のこの状況というのは、まだまだ変えられるのですよ、僕たちは。だから、自分たちが主役だということに気付く必要がある。これは、当たり前の議論のような感じがするのですが、それに気付く、目を覚ます契機になっていくという状況が必要な段階なのだと思います。
あとは、騙されないというところで見ると、メディア報道だけでは無理だと思いますね。さっき言った、官邸から見て1キロぐらいしか政治家の視野がないということは、メディアも結構それに近くて、政治部の人たちと話をしていると、やっぱりそういう発想になってしまうわけですよ。権力闘争というか、政局の話ばっかり。なので、国民のレベルから見てどうすればいいか、ということを考えなければいけない、そういうメディアが今後必要なのですね。だから、やっぱりメディアだけではなくて、自分で考えるために、色々なものを見たり聞いたりするようなことを、意識的にやっていくしかないと僕は思っています。
山崎: なるほど。やっぱり、国民として、もう一回個人としての意識改革が必要だということも含めて、今後の政治、日本をよくするために、政治家選びというところも、一つひとつ興味を持って望んでいただきたい、ということも一つです。
工藤: そうですね。僕が小さいときに、よく田舎で「長いものには巻かれなきゃダメなんだよ」っていつも言われていたのです。でも、巻かれていたらダメになっちゃうから、やっぱり自分で目を覚ますしかない、というのが僕の気持ちです。だから、このON THE WAYジャーナルでは、徹底的に本質というか、背景をきちんと説明していくように努力をしますので、ぜひそれを聞いて、また意見を寄せていただければと思っています。
有権者側に、日本の変化の覚悟はあるのか
山崎: あとお二方、簡単にですがご紹介させていただきます。
お一人目。ラジオネーム"Kさん"。「国政選挙の結果には、浮動票と呼ばれる人たちが大きくかかわっています。それを動かすのが有識者であると思いますが、生活の中で深刻に悩み、研究し、特定の専門的基礎をもっているわけではない薄っぺらな有識者と呼ばれる人たちの発言、特にジャーナリスティックな発言がメディアに乗せられて一時的に世論を左右する現状に、私は危機感を持っています。隠れている賢人を発掘してリーダーや参謀に育て、努力することも、このようなNPOの一つの役割になるのではないでしょうか。」
もう一方。ラジオネーム"Wさん"。この方は、イギリスのロンドンからメールをいただいております。海外から日本を見ていらっしゃるということで、「私は、今海外から日本を見ていますが、仮に龍馬のような人間が出てきても、本当に日本を変えられるのか、やっぱり、社会の隅々で既得権を持っている人間がそれを若い人や女性に譲る覚悟がないとだめだと思うのです。今しかないけど、今政界にそういった人材(小泉さんのような人)はそんなにいるとは思えません。民間にもあまりいそうにないのが、もっと悲劇なのでしょうか。」とうご質問です。
工藤: 僕も全く同じように感じていまして、最近よく思うことはオピニオンリーダーという人たちが日本の中にいるのだろうか。つまり、何か日本が変わったり、困難になったときに、健全にこういうことを考えなければいけないのではないかとか、そういう声がなかなか聞こえなくなってきましたよね。やはり、単なる批判だけという感じになってしまっていて、官僚が悪い、政治家が悪いとかですね。今のお二方の発言は、その状況、風潮を結構言っていると思うのですね。健全な社会には、健全な議論が必要なのですが、ただ議論している人たちが、もう少し目覚めなければいけないわけですよね。例えば、日本の社会には、知的な人たちが本来、沢山いるわけですよ。政治家もそうだし、大学の先生もそうだし、色々なひとたちがいっぱいいるじゃないですか。その人たちが、経済界も含めて、どういう主張をしているのだろうと思うのですが、あまり聞こえてこないと思うのですね。つまり、日本の社会の論壇なり、メディアの役割が非常に形骸化してしまっている。ただ、一方で、その人たちが全てかというと、社会の中にはもっとこれからのリーダーになりそうな人たちが、結構いるのですよ。
山崎: そうですか。
新しいリーダーとは何なのか
工藤: そのリーダーって何なのだろうかと思うのですね。この前も言ったのですが、課題解決をしている人たちなのですよ。大きな話ではなくてもよくて、地域でもいいし、色々なことについて自分で何かしないといけないということに関してある意味で志を持ったり、給料が安くても働いて、何かを変えていく、まさにチェンジメーカー。何かを変えられるという人たちが結構いるのですね。ただ、その人たちは表には出ていない。なので、その人たちをもっと出さないといけないと思っているわけですね。つまり、民主主義というのは非常に大事なのですが、民主主義とか自由な社会というのは、ただお任せしていたらダメになってしまうのですよ。つまり、僕たちが守らなければいけない自由な社会というのは、色々な選択肢を選べる社会だと思います。こういう生き方ができるのではないかとか、こういうことをしてみたいとか。それを自由に自分たちが決めるという社会が、僕は大事だと思うのですね。
つまり、全てが政府なり国だけがやってしまうという社会は、非常に不自由な感じがしているのですが、その自由な環境を守ろうと強い意志を持っている人たちが、まさに挑戦していくとか、新しいビジネスをやったり、社会の中で色々なことをやったり、そういう人たちのドラマの連続の中で、日本が変わっていくわけですね。
だから、やはり一般の人たちもそうだけど、そういう人たちはなおさら責任感を持って、今の日本は未来にこれから立ち向かわなければいけないわけだから、今度はもっと発言を強めなければいけないと思うのですね。やはり民主的な仕組みを自分たちで使いこなしていく。そういう強い意志を持つ人たちがいないといけないし、その意志を持った人たちが突破していかなければダメなのですね。突破していくと、それを見て誰かが、あの人たちかっこいいなとか、がんばっているなとか、俺たちもできないだろうか、といってどんどん循環が始まるじゃないですか。そのサイクルとか...「良循環」と言っているのですが、それが日本の社会で起きてくると、多分、目に見えて、日本が変化したということを感じることになると思います。さっき、ロンドンからメールをくれた人も、龍馬だけじゃダメでみんな変わらないといけないのではと。つまり、有権者が変わらないといけないという話をしているのであって、そういう流れを、起こさなければいけないタイミングにきているという感じがしているのですね。そして、その主役は僕でもないし、色々な専門家や、政治家だけでもなくて、皆さんなんですよ。皆さんが、まず主役なのだという時代に入ったということだから、そういうことを考えて動いて、そのいいことが成功体験として色々な形で伝わっていく、「見える化」していくという社会が、これから始まろうとしているので、ぜひ皆さんには挑戦してほしいと、私は思っています。
僕らがまず突破する
山崎: ある意味、国民からしたら、本当に一つのチャンスでもあるということですよね。これからの日本を、自分たちが担っていく、後世に残していくための一つのチャンスであるということですよね。
工藤: だから、その人たちには、どんどん活躍してほしいし、守る姿勢ではなくて、自分たちが攻めていって、この可能性を現実にすることによって、日本が新しい転機を迎えるので、だからそういう形になってほしいし、僕のこのON THE WAYジャーナルも、そのお役というか、何かお手伝いをしたいと思っています。実は、メールやお便りがまだまだ届いているのですが、日本のメディアだけ見ていたら、こんなこと分からなかったという声が結構あるのですよ。それが、やっぱり僕たちの責任だし、僕たちもそういう形での議論をしますので、もっともっと声を寄せてほしいと思っております。今日、ご紹介できなかった人はごめんなさい。また、色々な形で紹介したいと思っております。
ということで、時間になりました。今日の内容は、言論NPOのホームページでも見ることができます。また、どんどん意見を寄せていただいたら、それをまた、必ず紹介して、僕と皆さんで対話できるようなチャンスをつくっていきたいと思っています。日本の未来は、みんなで考えよう、ということで、これからもやっていこうと思っております。今日は、どうもありがとうございました。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
投稿者 genron-npo : 09:25 | コメント (0) | トラックバック
2011年2月 2日
「これからの中国とどう付き合うか」
-ON THE WAY ジャーナル 2011.2.2 放送分
放送第18回目の「工藤泰志 言論のNPO」はゲストに、昨年夏まで中国大使をお務めになられていた宮本雄二さんをスタジオにお迎えして、前週の工藤氏の中国訪問を受け、これからの日本と中国の関係について議論しました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「これからの中国とどう付き合うか」
工藤: おはようございます。ON THE WAYジャーナル水曜日。言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝、様々なジャンルで活躍するパーソナリティが、自分たちの視点で世の中を語る「ON THE WAYジャーナル」。毎週水曜日は、私、言論NPO代表の工藤泰志が担当いたします。
先週は僕が正月に北京に行ったときの話を皆さんに伝えて、今の日中関係がどうなのかということを考えてみました。
今日はその延長なのですが、中国という国と僕たちはどう付き合っていけばいいのかということを今回は考えたいと思っています。ただ、これを考えることは非常に難しいことなので、今日はスペシャルゲストをスタジオにお呼びしております。昨年の夏まで中国大使を務められた宮本雄二さんです。
ゲストは宮本雄二前中国大使
宮本: みなさん、おはようございます。宮本でございます。今、工藤さんから私が長いことやってきた、しかし大変難しい問題についての提起がございました。私の感じは、日本と中国は相手をよく理解せずに、そして、自分のイメージを相手についてつくり上げて、そのつくり上げたイメージに、お互いに腹を立てている、殴り合いたいと思っている。こういう風に見えてなりません。なぜ、こういう風に思うのかについても、工藤さんとのお話の中で、ご説明していきたいと思っています。
工藤: 何か、影に対してシャドーボクシングをしているような感じかもしれません。さて、宮本さんは、実をいうと『これから、中国とどう付き合うか』という本を出されているんですね。まさに、このテーマこそが今非常に大事だと思うのですね。なので、今日はこのテーマを中心に、宮本さんと話をしていきたいと思っています。
宮本さん、この本の中で一番言いたかったことは何だったのでしょうか。
著書で言いたかったこと
新しい日中関係を根付かせたい
宮本: 中国との関係が非常に難しい。中国という国はわかりにくい。何を考えているのかわからない。しかし、恐い。そういう長い間難しい関係を続けてきた日本と中国の関係が、実は多くの方がお気づきになっていないのですが、新しい出発点に立てる、そういう約束事をしていたのですね。それが、2008年の胡錦濤さん訪日の時の福田総理との間の共同声明なのですが、ここで新しい日中関係ができあがっているのに、それを多くの方が段々忘れていらっしゃる。これに対する危機感ですね。それまでもどうしようもなかった日中関係を、やっとこさあそこまでたどり着く枠組みを両国首脳が責任をもって出したのに、その先に進めない。そういう現状を見て、ぜひこのことを多くの国民の方にお伝えをしたい。その半分以上は中国の人たちに向けてなのですが、中国の人にも考えていただいて、そして新しい日中関係を根付かせていきたい、これが最大の理由です。
工藤: まさに逆に言えば、チャンスというか、これからドラマが始まるのだから、みんなで考えようということですよね。
宮本: そうですね。そもそも中国は引っ越しできない隣国ですし。
工藤: そうですね。僕たちもひょっこりひょうたん島みたいに、どこかに移動できないですからね。
宮本: 行ければ、ブラジル辺りまで行きたいという気にならないことでもないのですが、それはできませんし、なおかつこれだけ大きくなって、更に大きくなろうとしている国ですから。この国との関係は安定した、できればいい協力関係を築くべきだと思います。
工藤: そうですね。宮本さんが、「予測可能な協力関係」と言っていますが、確かに予測不可能なことがあるのは良くないですよね。
宮本: これは、外交そのものをお前たちはどれぐらい予測して、ちゃんとやってきたかと言われると、キッシンジャー博士は、なかなか立派なことを仰っているのですが、あの方は学者さんですから。後で、あぁだった、こうだったという立派な理論をおつくりになっているのですが、現場の我々は、結構行き当たりばったりでございまして、申し訳ございません、国民の皆さま方に。そういうのが外交の現場なのですが、その中でも特に中国はわからない。要するに、どういう風に出てきて、どういう風に進展するかわからないということでありますから、これをできるだけ、外交的に言います計算のできる関係にしたいということですね。
ダメージの背景の7割は「誤解と理解不足」
工藤: なるほど。ところで、僕が正月に北京に行ってきて、やはり尖閣諸島事件以降、日中関係は非常にダメージを負ってしまっているという感じがしていました。今回の訪中で、中国の若者も含めて色々と話をしたのですが、やはり日本を嫌いになってしまったという声がありました。一方で、ちょっとどういうことか分からなかったのですが、魚をいつも獲っていたのだけど、急にルールが変わってしまった感じがあって、逮捕にまで至ってしまったとか、大臣の発言が非常に不用意で刺激的で非常にびっくりしたとか。それから、急に日米韓で色々な動きが出てきて、非常に中国と事を構えるみたいな、表面だけ見るとそうみえることをどう考えればいいかとか、結構本音ベースで話を聞いてきたのですが、これをどう受け止めて判断すればよろしいのでしょうか。
宮本: 冒頭に申し上げました通り、日本と中国、あるいは中国とそれ以外の世界は、大いなる誤解と理解不足があります。しばらく前に、中国で自分の見るところ、日本と中国との間に生じている問題の7割は誤解と理解不足だと思うという話をしました。ところが東北大学で6年間勉強して帰ってきたばっかりの中国の日本研究者は「宮本さん、それは違います。7割ではなく8割です」と言うわけです。日本で生活していた中国の人もそういう感じを持っているのですね。やはり日中双方が、お互いに十分理解できていません。
今回の尖閣諸島の問題にしても、やはり中国側が日本の状況を見誤っているのです。中国側は何を考えたかというと、日本政府が、ああいう風に漁船がぶつからなければいけないような状況を仕組んで、そして日本の裁判にかけて、そうすることによって日本が尖閣諸島を有効支配しているのだ、という基礎を更に固める。そのための陰謀だというのが、私が調べた限りでは中国側の認識なのですね。日本なんてそんなこと考えてもいません。中国側はそういう認識でやっているものですから、強硬な姿勢に出なければいけなくなった。ルールを変えたというふうに受け止められるかもしれませんが、ルールを変えたことはありません。しかし、日本の領海はしっかり守らなければいけないという気にはなっていました。理由は中国がつくったのですね。2008年の12月に中国の海洋局の公の船が、9時間尖閣のあの領海の中にとどまりましたが、中国側の、このような行為は初めてでした。ですから、日本政府は中国が力で日本の尖閣に対する有効支配に挑戦しようとしていると受け止めて、ならば領海はしっかりと守らなければいけないなと思って、今回のケースに繋がっていくのです。ですから、ルールを変えたと中国側は言うのですが、ルールを変えたように感じさせる原因は、実は中国側がつくった、ということも中国の人は分かっていないと思いますね。要するに、双方とも相手をよく理解していない。色々なことを想像して、相手はこういう風に我々にきつく出ているのではないかと思って、だんだん強い姿勢をとり、日中関係が厳しくなっていった。この誤解を解いて理解を深めるという仕事は早急に大規模にやらなければいけないと、今回の事件を通じてしみじみと感じました。
誤解を解いて理解を深める作業を
早急に大規模に行うべき
工藤: そうですよね。まず1つは政府間同士でのコミュニケーションとか相互理解も大事です。一方で、国民レベルはもっと荒れちゃっている状況がありますよね。僕たちも世論調査をやっていて感じることは、中国人は日本のことをまだ軍国主義だと思っている人が半分ぐらいいるなど、もともと基礎的な理解が不足しているじゃないですか。そういうことを含めて、非常に弱い相互理解の状況の中に、またこういう形が加わっていくので、非常に不安ですよね。
宮本: 『これから、中国とどう付き合うか』という本の中にも書いておきましたけど、日中それぞれ国民の声が政府の方針に強い影響を与えるようになりました。日本は、本当の意味での民主主義になったなと思っています。すなわち、政府の一挙手一投足を国民の皆さんがちゃんと監視できる、監視する、というそういう民主主義になったと思います。ということは、国民の皆さんのお考えが、日本の政府の政策に影響を与える、とりわけ外交も例外ではないという状況になるわけですね。中国の中でも別の形で国民世論、社会の雰囲気というのが、中国共産党の政策に影響を及ぼすようなそういう仕組みになってきています。そうすると、両国とも結構大きな力で国民世論が政府の政策を決める、影響を及ぼすのですね。ですから、本当に日本と中国の関係を改善しようと思ったら、究極的には国民同士の和解といいますか、国民同士の相互理解といいますか、この段階までなりませんと、先程おっしゃった、私が言っていたという「予測可能な協力関係」というのができてこない。したがって、実は日中関係で一番大事なのは、国民レベルの相互理解と信頼関係をどうつくっていくか、ということが最大の課題だと思います。
日中に問われているのは、高度な相互理解では?
工藤: そうですね。ここで、僕も難しい課題が出てきたなと思うことは、今までは圧倒的に交流不足なので、お互いに沢山友達をつくったり、日本に何回も来てもらったり、逆に中国に行ったりすることによって...ただ、これも圧倒的に足りないのですが、多分、そういう交流が出てくることによって、自然に相手を知っていくチャンスが出てくるのでいいと思うのですが、ただ知っていくことによって、今度は意外に「違い」ということが見えてきますよね。国の違いなど色々なことに関して。その「違い」を認めるという形まで入っていかないと、相互理解が深まらない、かなり高度な相互理解が問われるような気がするのですが、どうなのでしょうか。
宮本: それはもうおっしゃるとおりで、私が最初に中国とお付き合いした大昔は、着ている洋服も違いましたし、女の方は全く化粧もしてらっしゃいませんでしたから、日本人か中国人かはすぐに見分けがつきました。でも、今は中国の若い子は、日本のファッションやお化粧が大好きですから、もう分かりませんね。
工藤: 確かにそうですね。
宮本: 外見で見分けがつかなくなってしまっています。そうすると、お互いに相手が自分のことを理解できるものだと錯覚してしまうのですね。例えば、アメリカの人に会ってこの人が理解できないということはある意味で納得できるのですが、全く同じ格好をした人間が自分のことを理解できないのはなぜだろうと。そういうことで、日中の相互理解の逆の難しさというものがあるのですが、やはり違うのですね。それを理解して、やらなければいけないということと、もう1つ、日本の人が特にできていなくて、中国の人もまだ不十分なのですが、異なる文化を持った相手に、自分の事を上手に伝えるということが日中双方ともできていないのです。そのために、例えば、中国の日本理解といっても、まだルース・ベネディクトが日米戦争をやっていたときに書いた『菊と刀』という日本に関する本とか、明治時代に新渡戸稲造が欧米の日本理解を進めようとして書いた『武士道』、この本がまだ中国の日本理解の基本的教科書になっているわけですよ。
異なる文化を持った相手に自分を上手に伝える
ですから、中国の中でも、日本をきちんと紹介する本がないのですね。日本でももっと中国のことをきちんとする紹介する本...日本の方が中国よりははるかに多いと思いますけど、それでもまだ不十分。中国ではもっと足りない。ですから、日本のことに関心を持った人が行って話をするだけではなくて、もう少しそういう形で理解できるような環境を早急に整えないとお互いの理解が進むのには時間がかかってしまうな、という感じがしています。
工藤: 本当にそう思いますね。僕も6年前までは中国のことを、全く知りませんでした。でも、中国の人たちと色々付き合って、共同のプロジェクトを一緒にやることによって、相手を理解できるようになりましたね。それは嫌なこともあるけれど、きちんとやると、ちゃんと真剣にやるし、共通の目標に対して合意をすれば、成果を出そうとなるし、本当に付き合うことが重要ですよね、そういう感じで。
お互いの「違い」を認めて付き合うと共通点は広がる
宮本: 日本は1700万人ですけど、中国も毎年4000万人ぐらいの人が海外に行っています。それでも、中国の外の知識というのは、まだまだ限られているのですね。ですから、中国の人たちは基本的には中国の社会で成り立つ中国的な発想方法、ものの言い方できているわけです。ですから、日本人がそれにぶつかると、ちょっと違和感を感じたり、感情を傷つけられたり、色々なことをするわけです。これは文化の差なのですね。ですから、外見は似ているのですが、それは脇に置いて相手は違う文化を持っている人だと思い定めて、お付き合いいただいて...
工藤: その違いを理解するということですね。
宮本: 理解をした上で付き合ってみると、私の経験でいうと欧米人よりは共通点が広がってくるのですね、ある段階を超えると。
工藤: 僕もある段階を超えると、志を共有...何て言うんでしょう。中国にもそういう言葉が好きな人がいるのですね。
もう1つありまして、僕が世論調査をやっていて感じるのは、中国の人は日本のことを過去の視点で見ている人が多い。一方で、日本人は今の中国を見ているために、中国が大国的に巨大になっていくことに、いいも知れない不安感を感じているのですね。この大国的な中国に、僕たちはどう向き合っていかなければいけないのでしょうか。
中国の大国化にどう向かい合うか
宮本: 中国は今曲がり角にきていると、私は強く感じています。日本を追い越し、図体が大きくなって世界の中で生活をしている。今度は世界に対してどう対応するか。どういう理念で、どういう価値観で、どういう世界像で、世界をどう引っ張っていくか。これを中国の人たちが自分で決めかねているのです。今彼らを突き動かしているのは、昔の中国が弱かったころ...中国は色々な国からいじめられて、強くならないといけない、強くならないといけないと、ずっと自分に言い聞かせてここまできた。でも、まだその強くならないといけない、という意識が強すぎて、軍事面で見れば、周囲の国が中国は脅威ではないかと思い始めるような状況になってしまっているわけですね。その時に、中国の人が我々に語りかけるべきは、中国はどういうアジアをつくろうと思っているのか、どういう世界をつくろうと思っているのか、そこで我々はどういう役割を果たします。人民解放軍はどういう役割を果たします。皆さま方の脅威と感じることに対してはこうします。あるいは、脅威が拭いきれないのであれば、この分野はこれ以上やりませんとか、世界を意識した発信をしていく必要があると思います。ですから、中国はまだその途中にある。中国がすでにはっきりとした方向を決めて、そちらの方向に邁進しているのではない、ということだけは事実として理解しているほうがいいのではないかと思います。
中国自身、明確な自画像を描き切れていない
工藤: つまり、明確な自画像が描き切れていないということですね。宮本: そういうことなのですね。
工藤: ただ、その中国と日本は一緒になって世界に貢献する、つまり中国にそういうふうになってほしいわけですよね。
宮本: ですから、彼らがどういう自画像を描いたらいいか、日本人もそうですけど、中国の人は「あたなはこうしなさい」と教訓めいて言われると、内心反発するものなのですね。ですから、そういう言い方を中国の人にすると反発を招くだけです。しかし、上手な言い方というものがありますから、こうするのが中国のためではないですか、世界のためになるのではないですか、という感じで、我々の意見を中国にどんどん入れていくことによって、気がついてみたら中国の人の考え方が変わっていたということはあります。これは、私が外務省にいて、中国の人と付き合ってきて、ある日突然、中国側が自分の意見としてなかなかいいことを言い始めるのですよ。ところが、それはね、3年前に私たちが言っていたことだったのですよ。そういうことがあるのです。だから、いい話も目立たないように、工藤さんもこっそり大いに中国側に伝えてもらえれば、気がついたら工藤さんの言っていることが中国の政策になっているかもしれません。
でも、問題は日本自身が将来の自画像を描いていないこと
工藤: 3年後に。やっぱり、そういう形で、あの国と本気で、未来志向で付き合っていくことが大事だと分かりました。もう時間になってしまいましたのですが、宮本さんの話を聞いていて、中国が明確な自画像を描いていないということは、僕も分かります。一方で、この日本も明確な自画像を描いていないという問題があって、僕たちは日本も素敵な国にしていって、中国も将来素敵な国になっていけば、本当に一緒にやっていけるということですよね。
宮本: 間違いなくそうだと思います。それは、日本の国民一人ひとりの方が、どういう日本の社会をつくるのか、それを真剣に考えて自分の周辺のコミュニティから始めてもらいたいと思いますが、住みやすい、これこそ人間が住む街だ、というものをぜひつくっていく。そして、このソフトパワーで、日本は当分の間、中国は体が大きくなりますが、こちらは頭を大きくして、体の大きな中国と頭の大きな日本のバランスで日中関係をやっていければと思います。
工藤: そういう形で、これから中国と付き合いたいと思います。本当に、今日は宮本さんありがとうございました。今日の話は、言論NPOのWebサイトでも映像でご覧いただけますので、ぜひ見ていただければと思います。
ということで時間になりました。今日はゲストに、昨年の夏まで中国大使を務めていた宮本さんに来ていただきました。本当に貴重な意見をありがとうございました。なお、冒頭にも言いましたが、宮本さんは『これから、中国とどう付き合うか』という本が、日本経済新聞出版社から出ています。よければ、書店等で買っていただければと思います。私たちも、これを読んでまた勉強したいと思っています。ということで、これからの中国とどう付き合うか、皆さんも色々と考えることがあったと思います。ぜひ、みなさんも意見を寄せていただければと思います。またよろしくお願いします。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
【 前編 】
【 後編 】