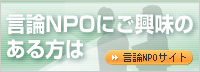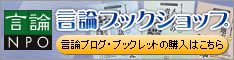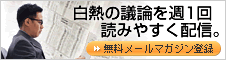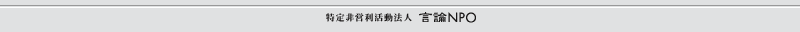2011年3月31日
明日の本格的な事前協議に向けて
 |
明日の本格的な事前協議に向けて
|
いま北京です。僕たちは今年の「北京-東京フォーラム」の事前協議のために北京に来ているのですが、気温が20度くらいあって暑いです。
さて、今回は、国連の事務次長をつとめた明石さんを団長に、前中国大使の宮本さん、元防衛事務次官の秋山さん、評論家の松本さんと私の5人で来ています。明日は東大教授の高原さんも合流します。
私たちは今回、今年の夏に行われる「第7回 北京-東京フォーラム」に向けて、いま、何を議論しなければならないのか、事前に協議をするためにやってきました。この事前協議は、今まで「北京-東京フォーラム」を6回やってきて初めてのことです。今回、なぜ初めて行うかというと、昨年9月の尖閣諸島事件以降、日中両国民の感情がかなり悪化したからです。この民間対話は、両国民の相互理解を進めるためにやってきましたが、色々な形での認識のギャップや、政府間のコミュニケーションの問題等の中で、それが直接国民感情の認識に跳ね返るという状況にあるのです。
そうなると、日中どちらが正しいか間違っているかということよりも、お互いがなぜそういう事を考えているのか、日中関係に対してお互いどんな認識を持っているのか、ということを、まずは本気で話し合ってみる機会が必要ではないのか、その中から今回のフォーラムの一つのアジェンダを見つけ出そう、というのが今回の事前協議の目的でした。
そういう流れを考えていたところ、日本では3月11日に東日本大地震が発生したのです。中国に来ても感じていますが、中国の人たちも、この地震のことを非常に気にしています。メディアでも日本のいまの震災の被害状況などがかなり報道されていて、日本のことを何とかしたい、という世論が非常に強いことを感じています。こういう状況の中で、私たちはもっともっとお互いの相互理解を深められる、という可能性を感じているわけです。
協議は、明朝9時から夜までずっと行われます。その後、記者会見を行い、協議の結果を公表することになっています。そこでは、尖閣諸島や今回の大震災の問題を含めて、今の日中関係のあり方や国民の認識に対して、日中の有識者がどのように捉えているのか、そして今後どう考えていけばいいのかということを本音で話し合います。その上で、安全保障や経済、メディア報道の問題などについて、夏のフォーラムで突っ込んで議論をするためのアジェンダ設定をどうすればいいのかということまで、じっくりと話し合ってみたいと思っています。詳細は明日、日本側参加者の間で座談会をやって、その中で日本と中国の協議結果をお伝えします。
言論NPOは震災の救済、復興の議論をかなりやっているのですが、一方で、こうした国境を超えた世界との対話にも力を入れています。日中の相互理解のための議論を、ここから本格的に始めます。ではまた、明日報告させてもらいます。
投稿者 genron-npo : 21:33 | コメント (0) | トラックバック
2011年3月30日
「『防災』の原点をこの時点で考えてみよう」 2011.3.30 放送
今回(第26回)の「工藤泰志 言論のNPO」は、3月11日に発生した地震を受け、都市基盤安全工学国際研究センター長の目黒公郎教授にインタビュー。防災の主役とは誰なのか?市民は何をすべきかを考えました。なお、この放送は3月17日に収録いたしました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
『防災』の原点をこの時点で考えてみよう
工藤: おはようございます。ON THE WAYジャーナル水曜日。言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝、様々なジャンルで活躍するパーソナリティが、自分たちの視点で世の中を語るON THE WAYジャーナル。毎週水曜日は「言論のNPO」と題して、私、工藤泰志が担当します。
さて、あの想像を絶する震災から、多くの市民が被災者の救援や支援に乗り出しています。この間の動きを見て、僕が非常に感じたことは、「市民の力」でした。多くの人が相手をいたわったり、ボランティアや支援の輪が急速に広がっている。この東京でも、一時交通網が遮断されて、色々なデマが飛ぶなど、様々なことがありました。しかし、市民は非常に冷静な対応をしていました。ただ、これからのことを考えた場合に、被災者の人達を救援するということは、多くの一人ひとりの市民の力をつないでいかないとダメだ、と私たちは思っています。ただ一方で、これからこういう危機に対して、防災ということに対して色々な問題がまだまだ出てくると思います。それに対して、僕たちはどう考えていけばいいか、ということを一度冷静になって、原点に戻って考える必要があるのではないか、と私はそう思っています。私たちは、自分や地域、家族、そしてこの国を、どういう風に守っていけばいいのか。多分、これは防災というものの原点だと思います。これについて、今回はみんなで考えてみたいと思います。
本当は、スタジオにお越しいただきたかったのですが、今は、こういう事態ですから、私が、東大の駒場キャンパスの生産技術研究所の安全工学国際研究センターセンター長の目黒公郎先生を訪ねてきました。目黒先生は、世界各国の防災問題の権威でして、ご自身でも色々な活動をされている方です。私は、目黒さんと、今、僕たちに問われている「防災」についての考え方、防災という言葉は、非常に堅苦しい言葉になってしまうのですが、私たちにとっては、自分たちを守るということに他ならない。これについて、目黒先生に話を聞いてきましたので、それを軸にみなさんと考えてみたいと思います。
では、早速ですが、目黒先生の話を聞いてみたいと思います。
工藤: 今回、想像を超えるような震災でしたよね。ショッキングな映像を見ていると、津波で町が無くなってしまうみたいな、しかも何回も地震があるとか、今後日本がどうなっていくのかということを思うところがあったわけですよ。
目黒: 今回の地震は、祖先も含めて、わが国が過去に体験した地震の中で最大規模の地震ですので、今回被災した方々に、あのレベルのものを事前に想定して、それに十分なだけの事前対策を全部とっておきなさい、と今の時点でいうのは、僕は気の毒だと思います。
工藤: ただ、その中でも、全員がダメだというわけではなくて、その中でも、自分は自分の家族を守ったり、地域を守ったりしていかなければだめなわけですよね。
目黒: そう思います。
工藤: ということになると、「防災」も自分で考える癖をつけていかなければいけない。
目黒: まさにそうです。
防災では「自助」、「共助」、「公助」の順が大切
目黒: 僕らが考える「防災」というのは、まず、地震そのものを起こさないようにしようだとか、津波そのものを起こさないようにしようだとかは、無理な話ですよね。やるべきことは何かというと、そういうものが仮に起こった時に、それらが我々の社会に与える、人的・物的、様々な障害の総量を最小化したいということです。その時に、誰が主役になるのか、という考え方があって、その中では、自分で自分を助ける努力をする「自助」、次に、ご近所などでお互いに助け合う「共助」、その次に「公助」。これが、行政ですよね。重要性としては、我々は、自助、共助、公助の順番で大切だという風に考えているわけです。その理由は、「量」と「時間」の2つの視点から大切だと思っています。経済的な被害額でいうと、首都直下地震だと110兆円とか、東海・東南海・南海合わせて80兆円とか、あるいは上町断層で74兆円とか、そういうスケールになっています。なので、国に期待したいのは山々だと思うのですが、でもそれを期待していて達成できなかったら、結果的に誰が不幸になるのかと言われると、自分ですよね。なので、まずは自分で最低限の努力はして、被害を減らすということをしておかないと、防災は達成できませんよということです。2つ目は、「時間」の視点なのですが、起こっているその瞬間に、自分を守れるのは誰かと考えたときに、いつも自分の横に行政がいて、助けてあげましょうということはあり得ないですよ。だから、その瞬間は、自分で自分を助けなければいけないし、その次に助けてくれる可能性があるのはご近所さんですよね。そういう視点で言えば、やはり自助、共助、公助なのですよ。
防災対策というのは非常に細かく整理されているものなのですよ。我々はそれを6つか7つに整理しています。
抑止力、事前の備え、直前の予知・予見と警報、直後の被害の評価、災害対応、復旧、復興、この7つの対策を自分の対象とする地域で、どれが最も遅れているのかとか、あるいは自分が対象とする地域には、どういった災害が起こりうるのか、。その規模とか頻度とか、そういうものを考えながら与えられた時間とお金の中で、最も効果の高いものから順番に選び出して、具体的に対策をするということで防災力というものは高まっていくわけです。その時にも、どこの部分は自助に最も適しているとか、共助がいいのだとか、公助がいいのだということがあるわけです。例えば、直前の予知・予見で警報を出すということは、なかなか自助では難しい。そのシステムは公助がつくらないといけない。しかし、その仕組みをつくって、出してくれる公助が出してくれる情報をいかにうまく使うか、というところは自助の部分で、事前にちゃんと使い方を学んでおかないとうまく使えないということですよね。それは津波警報だけではなくて、緊急地震速報などは、なおさらそうですよ。与えられている時間がもっともっと短いから、事前にこの空間で5秒もらったら、どう使えるのか、ということを議論し、しかもトレーニングをする。そして、繰り返して行動を取れるようにする。そうやって努力をすればするほど、逃げようと思った時に、家具が転倒してきたりする状況だったら逃げられないなとわかる。家が潰れたら逃げられないなとわかる。ということで、どんどん事前の対策が進んでいくということになるのですよ。
もっとも大事なのは「災害イマジネーション」
僕は、防災対策で何が一番重要かと聞かれると、災害イマジネーションですよ、といつも答えます。人間は自分が想像したり、イメージできないことに対して、事前に備えるだとか、準備するなんてことは絶対にできないのですよ。絶対にできないのだけど、僕らは防災教育と称して今までやってきたことは、Aやれ、Bやれ、Cはやるな、と言っているわけです。でも、これはよくよく考えると、思考停止させているわけです。これじゃいけないということなのですよ。震度6強の揺れを感じた。さあ、私の回りで時間の経過と共に、どういうことが起こるのだろうか。あるいは、どんなことをやらなければいけないのだろうか、そういうことに関してのイマジネーションが、余りにも低いのですよ。それは、わが国でいえば、トップレベルの政治家や行政とか、我々研究者なんかもそうかもしれない。それから、マスコミの人たちも一般の市民の人たちも、それぞれのレベルで、イマジネーションが低い。そうすると何が起こるかわからない。、だから何をやっていいかわからなく、い。だから、何もやらないというスパイラルに入ってしまっているのですよ。兵庫県南部地震で対応にあたった方々の手記を読んだり、彼らと色々と話をさせていただくと、彼らは何を言っていたかというと、先が見えない、何していいかわからない、不安だ、この繰り返しでした。そうすると、大規模災害における災害対応って、長期化するわけです。つまり、災害イマジネーションを高めるということは、日常的に真剣に、例えば、この瞬間に震度6強の揺れを感じたときに、私の回りで何が起こるのだろうか。服装はこんな服装だ、履いている靴はこんな靴だというところから、いつも考えるクセをつけるということですよ。ただし、その時に、自分だけでは取りようがない情報がありますよね。例えば、行政が持っている情報などが挙げられます。そういう情報は、行政は積極的に開示していかなければいけない。以前は、行政は、この情報を自分たちは持っているのだけど、この情報を出したらば、それに対しての十分な対応が、今は取れないので、市民の方々を不安におとしいれてしまうかもしれない。だから、無責任なので、この情報は出さない方がいいのではないか、といって出してなかったことが多いのだけれど、僕はもう時代は変わったと思うのですよ。どういうことかというと、その情報を出して下されば、行政は行政として解決策を提示しにくいかもしれないけど、市民側がその情報を自分で活用して、自分の力で、自分のお金で、自分の考えで、対策をとれるという人たちが沢山出てきているのですよ。
工藤: 目黒さんの話は非常に重要で、僕たち自身が災害に備えなければいけない、と言っているわけですね。しかし、その場合、情報というのが決定的に重要なのですね。ただ、原発の事件を見ても、やはり市民なり個人が備えるための、そういう立場に立った情報というのは提供されているのか、ということが、非常に大きな疑問でした。一方で、まだまだ、市民側の中にも、政府が何かをやってくる、という安易な気持ちもあるのではないかと。そうではなくて、自分たちが「自助」という形で備える、ということが非常に重要だと、ということを目黒先生は言っていました。続きを聞いてもらいたいと思います。
市民目線に立った情報を行政は提供できたか
目黒: 僕は、自分にもそれを問いかけるのですが、もし、行政サイドからそういう説明をしている人がいらっしゃった時に、あなたが行政の人だということはわかるけど、税金を払うという市民の顔を持っていますねと。だったら、自分が税金を払っているという一市民として、今、自分がやっている行動、あるいは自分が出している情報、それに満足しますか。その情報をもらって、自分は何かアクションを取れるだろうか、という観点で、自分たちのやっていることを、もう一回見直してみたらどうかと。そうすると、随分、やれることややるべきことが変わるのではないかと思います。マスコミの人だって同じですよ。マスコミの人たちが、被災者の人たちに対して、この時点でこの情報を出せば、被災者の人たちはその情報をこんな風に使って、今の苦しい状況をこんな風にして改善できるのだというイマジネーションがあれば、そういう情報を出していかれるのだと思うのですよ。ところが、あまりそれがないと、誰向けの何のための情報としてこれを出しているのかがよく分からない。例えば、今回の地震のメカニズムは、と専門家が説明するような場を設定してくれるマスコミがありますが、それはそういうことに興味がある人は、ある比率いらっしゃるかもしれませんが、でも、それが分かって、本当に被災地で苦しんでいる方が、どう使ったらいいのだろうかという視点は、僕はあんまりないように思うのですよ。
工藤: 政府に全てを任せるということが、今ある被害というか、それから見ても全部はこなせないのだと。だとすれば、まさにその中で、自助を促すような目線とか...
目黒: そう、メッセージとか、情報の出し方とか、タイミングとか
工藤: 全てが、そうなっていなければいけないのに、何となくそうなっていなくて、何となく中途半端というか、ある意味では、それは政府のことだとか、何かそうなっている感じがあるじゃないですか。そこは、頭を切り換えないといけないですよね。
目黒: 僕は、本当にそうだと思いますよ。そうしていかないと、市民側はいつになっても、安全・安心は、お上が我々にタダでくれるものだという意識に、どうしてもなりがちだし、お上側はお上側として、何か出来事が起こった時には、それは想定外でしたと逃げ腰にならなければいけないような、双方にとって不幸な状況じゃないですか。やはり、適切なタイミングにものを出せば、両者が相互補完的にそれを活用できるという風になったほうが建設的だし、それで、市民の方の成熟度も高まるし、結果的に将来受ける被害も減るという、そちらの正のスパイラルの方に回っていくのではないかと思うのですよ。
己を知って敵を知る、とは
工藤: それは、己を知るということですか。
目黒: そう、己を知って敵を知る。そうじゃないと、いい対策なんかが取りようがないですよね。そのための、自分たちの今の対策の程度、自分が住んでいる地域の理解度、それから自分が将来受けるかもしれない災害がどういうものなのか、ということを理解するための情報を自分も努力するけど、行政もきちんと出してほしいと。そういう風になっていないと。健全な方法にいかないと思います。
「自助」があって、「共助」が可能となる
工藤: 目黒先生が言っている「自助」というのは、何でも自分だけが助かればいい、ということを言っているのではなく、自分を守ることによって、それが地域なり社会に対する守る力になると。つまり、「自助」は、「共助」や「公助」の前提なのだという考え方なのですね。なので、僕は、目黒先生にあえて東京で起こった現象、つまり、帰宅難民で僕たちも困ったのですが、あの対応については正しかったのか、ということを聞いてみました。
工藤: あの時は、何が正しかったのですかね。例えば、みんな歩いて帰ろうと思ったら、今日は帰らないで、職場に待機して下さいとありましたよね。
目黒: 今回、東京自体はそれ程大きな被害があったわけではないのですが、これがもうちょっと被害が発生したことを想定した場合も、帰宅困難者という困難に直面している人間として考えるか、怪我もしていない普通の動ける人たちだという風に考えれば、その被災地の中に、活動できる600万人もの人間が、資源として人的資源として、そこにいるのだという風に考えるかでは、大きな差じゃないですか。つまり、ケアされる側の人間か、ケアに回ってもらう側の人間かということですよ。そうなったときには、問題は安否確認だけですよ。家族との安否確認ができて、家族も大丈夫だということになれば、今回は被害があまりないですけど、それこそ20キロの道のりの途中、火事があったり、いっぱい被害ある中で、ずっと徒歩で歩いている過程の方が、よっぽど問題がある可能性があるわけです。だとしたら、ちゃんと分かっている場所にいてもらって、そこでその地域の被災している状況をケアする側の人間に回ってもらって、地域をある程度まとめた後で、交通がちゃんと復旧した段階で安心して帰るとか、そういうシステムとして持っていくことを考えた方が、全体としてずっとプラスではないですか、ということです。
工藤: 町が全部壊れてしまう状況の中で、まず復旧と復興の定義もあれなのですが、僕の仲間のNPOの人たちも、みんな行きたいという人沢山いるのですね。でも、行くと言っても、ある意味で邪魔になって、ちゃんとしたラインとか行政のコアである町役場とか、そういうことがちゃんと整わないと、それすらどうなっているかわからないとかいう状況があります。
「復旧」と「復興」は異なる
目黒: 復旧と復興の定義を簡単に言うと、復旧というのは元の状態まで戻すことなのですよ。でも、考えてみると元の状態まで戻しても、その状態でやられたのだから、不十分じゃないの、もう少し改良したほうがいいのではないかという時に、改良型の復旧を復興というのです。
復興というのは、次のイベントに対しては、被害抑止力を高めていることに相当するのですよと。で、その時に被害抑止力をどこまで高めればいいのか、というところが議論の非常に重要なところで、その議論はそこの地域に住んでいる人たちの議論でしか成立しないと、僕は思うわけですよ。
工藤: その人たちがまず安定というか、生活できるような生活支援というのですか、そこの辺りは、皆さんの助けが必要なのではないですかね。
目黒: それなりの支援がないと、あの地域だけで、ということは当然不可能だと思いますね。
「自助」は、強い成熟した市民社会につながる
工藤: 僕は、今回の震災で、救助から復興まで、まだまだ長い時間を要することを覚悟しなければいけない、と思っています。多分、この間、政治や経済で色々な問題が出てくると思います。しかし、この間に私たちは、市民一人ひとりが力を合わせて、こういうことを乗り切ろうという時期に直面していると思います。多分、この僕たちの取り組みを、どうしても成功させなければいけない。この取り組みを成功させることが、日本の未来につながる第一歩になるのではないかと思っています。みなさんは、今日の目黒先生の話を聞いて、どう思ったでしょうか。また、意見があったらどんどんお寄せ下さい。今日はありがとうございました。
投稿者 genron-npo : 10:21 | コメント (0) | トラックバック
2011年3月23日
「被災地のため市民は何ができるか」 2011.3.23 放送
今回(第25回)の「工藤泰志 言論のNPO」は、3月11日に発生した東北関東大震災を受けて、現地にいち早く先遣隊を出したボランティア組織「難民を助ける会」の事務局長・堀江良彰さんをスタジオにお迎えして、現状報告と今後市民が出来ることはなにか考えました。なお、この放送は3月17日に収録いたしました。
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「被災地のため市民は何ができるか」
工藤: おはようございます。ON THE WAY ジャーナル水曜日、言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝、様々なジャンルで活躍するパーソナリティが、自分たちの視点で世の中を語るON THE WAYジャーナル。毎週水曜日は、私、言論NPO代表の工藤泰志が担当します。
さて、3月11日に東北地域で巨大地震がありました。まず、今回の地震でお亡くなりになられた皆様のご冥福をお祈りすると同時に、一人でも多くの皆様や、ご家族の方がどうかご無事であること、被災地の復興が1日でも早くなされることをお祈りしたいと思っております。ただ、こうした困難の時には、僕らは黙っていていいのか、という思いがあります。そこで、今回のON THE WAYジャーナルでは、みんなでこの状況をどう乗り切ろうか、ということを考えてみたいと思います。そういう思いから、「被災地のために市民は何ができるのか」をテーマに、今日は皆さんと議論したいと思っています。
今日は、スタジオにゲストをお招きしております。日本のNGO団体で、真っ先に被災地へボランティアの先発隊を出した、難民を助ける会の事務局長の堀江良彰さんです。堀江さん、今日はよろしくお願いします。
堀江:よろしくお願いします。
工藤: その前に、私たちの番組に、幾つかお便りをいただいています。全部を紹介できないのですが、一部紹介させていただきます。
まず、Hさん。「本当に今回の大災害に直接あわれた方に、1日も早い平穏が訪れることを、ただ祈るばかりです。しかし、こんな日本の現状では、立ち直りはできない。否、地震ではないが、ますます沈み行くばかりです。みんながファイトを出すように、そして、もっと明るくなるように、ぜひ言論NPOを通して、呼びかけてください。」
もう一つMさんから。「みんなで力を合わせて、この難しい局面を乗り切りましょう。日本の底力を見せる絶好のチャンスです。音頭取り、方向付けをよろしくお願いします。」
皆さんも、ご意見、ご感想をお寄せください。番組ホームページの水曜日、工藤泰志のページに行っていただいて、メールやツイッターでお願いします。ON THE WAYジャーナル「言論のNPO」、今日はスタジオに、難民を助ける会の事務局長の堀江良彰さんをお招きし、議論を進めます。そして、今日のテーマは「被災地のために市民は何ができるのか」です。
さて、難民を助ける会では、被災地に真っ先に先発隊を出したという話なのですが、現地はどのような状況だったのでしょうか。
堀江:私ども難民を助ける会では、被災から2日後の3月13日に、3名のスタッフを被災地に派遣しました。着いた第一報が、大混乱していて大変な状況だということでした。もちろん、被災地へ向かう道中にも地震や津波の被害の跡が見られたのですが、災害対策本部にまず行きましたけど、とにかく大混乱しているという状況でした。で、全く支援が届いていないという状況が、まず第一報でした。
どうやって被災地に入れたか
工藤: 被災地へはどうやって行ったのですか。車ですか。
堀江:車です。
工藤: 道路は大丈夫だったのですか。
堀江:道路ですが、高速道路は通行止めでした。警察の方から緊急通行車両ということで、許可を取ろうとしたのですが、NPO法人にはすぐには許可が出なくて、先発隊は14時間以上かけて、被災地に入ったような状況です。
工藤: 通行証を取れなくて入ったのですか。
堀江:取れないまま国道を、東京から400キロ弱を北上しまして、途中で支援物資を買いながら現地入りをしました。
工藤: 今、色々なNPO団体が、どんどん行きたいと声を上げていますが、通行証が取れないというか、だんだんできていくと思うのですが、地元の受け入れ先ができていないので、気持ちははやっているのですが、なかなか行けないという状況がありました。よくそこを突破しましたね。
緊急通行証から始まった
堀江:そうですね。とりあえず、まず現地に行きたいということがありましたので、時間がかかっても下道で行こうということで、最初は行きました。で、3月16日に第2陣が出ました。その第2陣は通行証がもらえました。というのは、第1陣が県庁の災害対策本部に行きまして、そこから支援要請の紙をもらいました。それがあると、警察の方で緊急通行証を発行してくれますので、第2陣については、東北自動車道を使って、5時間から6時間ぐらいで到着することができました。
工藤: 今は、一般の市民の人たち、つまり寄付とかボランティアをしたいという声は、かなりきいているのでしょう。
堀江:堀江:はい、もの凄く来ています。メール、電話等で、問い合わせが数百件にのぼるぐらいきていまして、お金のご寄付は大変ありがたいので、それはそのままぜひいただきたいと思っています。ボランティアの問い合わせも沢山きております。自分も被災地へ行きたいのだけど、どうしたらいいかとか、後は、物資を送りたいという方も沢山いらっしゃいます。大変、申し出はありがたいのですが、今の問題が、現地の方で食料や燃料が足りていないという状況があります。ですから、例えボランティアに行ったとしても、そのボランティア自身が食べる食料ですとか、滞在する場所を確保できない状況ですので、人は必要な状況なのですが、なかなかそういった人達を受け入れる態勢が、今の段階では整っていないということ。それから、ガソリンを始めとする燃料が全くありませんので、例え、支援物資を積んだトラックが行っても、帰りの保証が全くないのですね。そうすると、支援物資を下ろしたところで立ち往生してしまうと、そのドライバーを含めて、避難民という形になって、本来、元々の避難民が食べる食料などを使わなければいけなくなる。そういうことが、現状です。
工藤: 確かに、メールなどの情報では、行ったのですがガス欠で、そこに残らなければいけないという人達も結構いるみたいです。今回の地震は、昔の阪神淡路大震災とは違って、アクセスですよね。それから、津波の影響とかがかなりあって、壊滅している状況で、地元の受け入れ態勢というのが、なかなかできていないという状況ですかね。
救援の全体調整は必要
堀江:堀江:そうですね。全体の調整機能が、まだ働いていないような状況です。ここを一刻も早く解決しないといけません。気持ちがある人は沢山いますし、現地へ行きたい人、物資を送りたい人は沢山いても、そういう人達の声を集めて、有効に被災者へ届けられれば、かなりの人を支援できるはずなのですが、そのための基礎的な燃料、食料が足りていないところ。そこが、一番ネックになってしまっているところです。
工藤: 今回、東京でもガソリンを買うために行列になっているような状況なのですが、震災の規模はかなり大きいですよね。範囲が広い状況で、しかも、被害のレベルが想像を超えるようなレベルということで、僕たちも何とかしなければ、と思っているのですが、これをどういう風に実現に向かって組み立てていけばいいか、というのがイマイチ見えない人も多いと思います。今は、多くの方のお金とか、それから食料とか物資を集めている段階で、同時に先発隊が行って、そこの中で何ができるかということの組み立てをする段階という感じですかね。
堀江:そうですね。もちろん、その組み立てもしていますし、どうやったら支援が届くかということを、県の災害本部とかとも調整をしています。同時に、私たちもできる範囲で買えるものは買って、配布を始めています。既に、お米を含めて色々な食料を買って送ったりしています。第2陣の便は、毛布と衛生用品、簡易寝袋を積み込んで送っています。それから、現地も寒いですから、灯油とか軽油なども現地に送っています。
ですので、各方面と調整をする、そして、どこに被災者がいるかを探す作業、物資の配布ということを並行してやっています。ただ、支援に関しては、どこでも足りないというのが明白なものですから、今はどの地域も、食料が欲しい、暖をとるものが欲しい。最低限、生き延びていくためのものが欲しい、という状況になっています。
工藤: なるほど。普通、まず行政なり、地元の受け入れの動きがありますよね。それはちゃんと機能しているのですか。
堀江:まだ機能していません。ようやく、震災から1週間余りが経ちますが、そろそろ立ち上がり始めたところです。これがしっかり立ち上がって、うまく機能していけば、かなりの人を受け入れられますし、モノも受け入れられるのですが、ただ、そのためにはどうしても移動するための燃料と、その人達の生活も含めた食料の確保が第一になりますので、それがないと、せっかく行ったにもかかわらず立ち往生という状態になってしまう。そこが一番懸念されています。
工藤: 2つあるのですが、医療というか救助という点では、今でも救助されたという報道がありますよね。まだ、やっぱりその段階のあるのですよね。
堀江:
工藤: そこに、まず自衛隊とか色々な人達が関わっていて、一方で、地域的な広がりということで見れば、まだ「面」ではなくて、「点」で動いている感じですよね。ということは、取り残されている地域は、まだある可能性がありますよね。 堀江:まだまだあると思います。私どもは仙台に行きました。で、実際にもっと北の岩手県の方でも、大きな被害が出ていると思われますが、そこに入っている団体は少ないですし、福島県は原発の問題もありますので、入っていける団体はほとんどいないような状況になっていますので、この被害の甚大さ、広さに対して、まだまだ足りていない状況が続いています。 工藤: これは、どれぐらいになるのですかね。つまり、かなりお金が集まっているという話は聞いているのですが、それは集まっているというよりも、全然足りないというレベルなのですか。 堀江:全然足りないと思います。復興していくためには、それこそ何年もかかることです。で、とても、私たち一団体ではできることではありませんし。 工藤: まず、今は、救済と生活支援ですよね。そこが足りるかどうかというところで、まだ目処が見えないというところですか。 堀江:まだ見えていません。 工藤: こういう場合の進め方というのは、誰が全体像を把握したり、アピールしたりするような流れになっていくようなことが理想なのですか。 堀江:そうですね、私ども難民を助ける会では、ハイチとかパキスタンとか、スマトラ沖の津波の時にもこういう緊急支援をしていて、こういう現場にはよく遭遇します。国々によって態勢は違いまして、国が機能していないところでは、国連とかが入っていて、大規模に調整をしていきます。日本の場合は少し違って、政府がしっかりありますので、やはり国が中心になって、支援や調整をまずしていく。そこに、NGO団体を含めた多くのNPO団体、ボランティア団体が、調整の元に活動をしていくという形態がいいのかな、と思っています。 工藤: 日本の場合は、まず行政にきちんとした拠点を作ってもらって、一方で、そこと連動する形で、市民の動きが動いていく。その動きがいつできるかということですね。 堀江:そうですね。 工藤: 今回は、私たちも何かの形で行きたいという気持ちは非常に強いし、そう思っている人は沢山いると思います。ただ、驚いたことは、市民の力というものが、日本は非常に強いという感じがしています。その辺りは、どうでしょうか。 堀江:それは思います。やはり、こういう状況でも大きな略奪もありませんし、支援したいという人も沢山申し出てくれています。そういう意味でも、本当に市民の力は強いですし、行政が調整機能を果たすのですが、最終的には市民同士の繋がり、助け合いで、全体を復興させていかないと、とても行政任せですむ問題ではありません。行政が調整するもとに、市民同士の連帯が進んで行って、みんなで助け合っていくという姿勢が、絶対に必要だと思っています。 工藤: なるほど。後は、市民側の動きがかなり入ってくるような受け皿ができて、そこを地元の必要なこととマッチングさせるような仕組みが、とにかく整ってくれれば動く可能性があるという段階にきているわけですね。 堀江:全く、その通りだと思います。NPO、NGOというのは、それぞれに強みがありますので、全部に公平にやるというよりは、色々な多様性のある団体が、沢山入っていって、結果的に全てに行き渡るという状態がいいと思っています。そういう意味では、難民を助ける会は、障害をお持ちの方、あるいは、高齢の方々に対して、中心的に支援をしていこうと思っております。というのも、海外のカンボジアやミャンマー、ラオスで、障害者の方達の支援をしております。そういった意味では、こういった災害の時に取り残されてしまうのが、障害をお持ちの方ですから、そういった方達の支援に、重点を置いて活動していきたいと思っています。 工藤: 今向かっている人達というのは、海外でそうした実績のある救済系というか、そういうNGOが多いですよね。現状、どういう人達が、誰でも行けるのですかね。 堀江:今は、まだ誰でも、という状態ではないかもしれません。というのは、ある程度自分たちの活動を自分たちで完結できるところがないと、現地での動きが取れなくなってしまう可能性がありますので、そういう意味では、国際系のNGOは、各国の災害地、紛争地で活動経験がありますので、まず、出られたのはそういう経験が活かせるということで、被災地に入っております。ただ、もう少し状況が落ち着いてきたら、多くの団体が、思い思いの活動をしたいという団体が入っていける状態になると思いますので、そうすると、もっと支援の輪が広がっていくのではないか、と思っています。 工藤: さっきの早瀬さんは、交通インフラがきちんと整って、動けるようになったら、積極的に行くべきだとおっしゃっていたのですが、どうでしょうか。 堀江:そうだと思います。ただ、その際にも、 工藤: 自分で燃料を持っていくとか、自分の食料とかを持っていく。 堀江:後は、ちゃんとした調整のもとですね。必ず、色々な調整、あるいは窓口になるところがあると思います。日本であれば災害対策本部、あるいはその下に、社会福祉協議会がつくるようなボランティアセンターのようなものが必ず立ち上がりますので、必ずそこを通じてやるということが必要だと思います。 工藤: わかりました。とりあえず、そこに行って、とにかく何かできることはないだろうか、という輪がどんどん広がることが本当にいいと思いますね。最後に、お金なのですが、寄付とか義援金が色々と集まっているのですが、このお金というのは、どういう風になりますか。難民を助ける会へというのならわかるのですが、沢山の寄付がありますよね。これはどういう風に使われていくものなのでしょいうか。 堀江:難民を助ける会にいただいたものは、難民を助ける会が行う物資の配布とか、長期的には、これから建物の再建もありますし、様々な支援活動に使っていきます。また、国の方でも... 工藤: 色々な団体、メディアも含めてやりますよね。 堀江:これは、かなりのお金を通じて、インフラの整備から色々なことをやっていかないと、と思っています。 工藤: 早瀬さんが、義援金は災害にあった人にわたるもので、支援金というのは、活動に行っている人達が集めている、ということをおっしゃっていたのですが、そういう理解でいいのでしょうか。 堀江:そうですね。いいと思います。 必ず乗り越えられる 堀江:ありがとうございました。
投稿者 genron-npo : 22:09
| コメント (0)
| トラックバック
今回(第24回)の「工藤泰志 言論のNPO」は、前回に引き続き、ゲストに岩手県知事や総務大臣を務めてきた野村総研顧問の増田寛也さんをお迎えして、地方自治を立て直す方法などについて、議論しました。 「ON THE WAY ジャーナル
工藤: おはようございます。ON THE WAY ジャーナル水曜日。言論NPO代表の工藤泰志です。さて今日も、先週に引き続き、スタジオに岩手県知事や総務大臣を務め、今は野村総合研究所顧問の増田寛也さんをゲストにお招きしております。増田さん今日もよろしくお願いします。 増田: よろしくお願いします。 工藤: 先週、地方自治はまさに民主主義そのもので、民主主義の学校と言われていたのですが、まだそこまでいってない。しかも増田さんからショックな話があって、政治家は本気で地方分権をやる覚悟が決まってないのではないか、という話も出ました。ただ、その中で、民主主義の統治の仕組みにおいて地方の中にもさまざまな問題が出てきている。これはやはり僕たちが解決していく段階にきている、ということが増田さんの強い主張でもあったし、私たちもそう思ったわけです。こういう訳で今日は本題に入らなくてはいけなくなってきました。つまり、今の地方の民主主義の現状を踏まえて、日本の地方自治をどう立て直していけばいいのか。また地方から始まる変化が、地方だけではなくて、この国の未来を切り開いていくきっかけとなるのか、という問題もあります。そう考えれば、今度の統一地方選挙も含めた地方の選挙って日本の未来にとっても大事な選挙だと思いますね。そういうことで今日は議論を進めていきたいと思います。早速ですけど、この前のお話を聞いて、地方と国政の違いがよくわかりましたが、やはり地方の方が民主主義の機能としてはかなり住民に近い。例えば、地方では自分たちが選んで自分たちの代表として送り出し、それを監視し、場合によっては代表を変えることもできる、そういう民主主義の統治の仕組みがある。この仕組みを使いこなさないと話にならないという局面です。そういう視点から見て日本の地方の民主主義の程度というのはどういう状況になっているのでしょうか。 増田: 今までは、選挙では知事、市長に誰がなるのだろうかとそちらの関心ばかりが高かったのですが、今回の統一地方選挙で、初めて今の議会はこれでいいのかということがみんなの意識に出てきた。このままの機能不全でいいのかどうか。これは大選挙区制度の中では、議会の一人ひとりを誰にするかを考えると、結局は地縁とか血縁がどうしても主流になってしまう。けれども、議会を構成している会派の中で、最近よく地域政党とか首長さんが主導する首長新党の話が出てきましたね。議会の投票率は統一地方選挙でいま50%ちょっと、52%くらいにまで下がっているのですが、今回は議会の在り方が今のままでいいのかどうかという意識が、皆さんの中にもかなり出てきたのではないかという実感があります。 工藤: なるほど。僕たちもある程度うすうす分かっているのですが、議会が機能していないということですよね。でも、確かに議会は議員の数が多い。なんであんなに多くないといけないのでしょうか。 増田: 議員の数ですか? 増田: もちろんこれは多ければ多いほど地域の声が細かく反映されるということかもしれませんが、ただ私が見るに、地域の全体の人、老若男女、職業も含めた属性の縮図に議会はなっていないですね。日本の議会というのは、議員になることについて非常にリスキーですよね。例えばヨーロッパではよく市役所の職員が一時期休職して議員になって、任期が終わったら復職するということもあります。日本の場合にはそういうことはなくて、生活をかけて立候補してうまくいけば当選、ダメだったら失職、と生活を全部失うことになり、やはりお金持ちであったり、自営の人にどうしてもなってしまう。特に地方の場合には自営と言っても建設業が多いから、建設業に関係する人が議員に多くなる。これは良い悪いは別にしても、結局その人たちの関心というものは公共事業がどれだけ増えるか減るかの話で、議会の議論はぐっとそちらに偏ってしまう。 工藤: あれはチェックだけですか? 増田: ええ、チェックです。もちろん、否決はできます。減額修正もできるけどもお金を増額する修正はできない。要するに、それは知事・市長の権限となっています。ですから、結局、陳情を受けてそれを実行するためにお金がかかるのであれば、知事に頼み込むかあるいは知事を脅かすか、それで実行するしかない。その結果、だんだん知事の力が強くなって、結局それを追認するだけの議会になってしまう。 工藤: 地方は二元代表制といって住民は知事や市長と議員の2つを選ぶわけですね。どっちが代表なのでしょうか。 増田: 今までの日本の歴史的な位置づけは、明らかに住民の意識として知事を自分たちの代表者だと思っています。議会の議員、その代表者たる議長が誰かということに対して、すぽっと意識が抜けています。これは制度的な問題です。 工藤: なるほど。でも有権者は自分たちが忙しいから、一応議会の人たちにはその監視役として執行を監視してほしい、意見を言ってほしいとか、そういう期待を持っているのですよね。本来はそういう役割は持っているのでしょ。 増田: 本来は持っています。結局、あまりにも執行部の方の権限が強くなり、それから議会が外から見えないから、夕張のようにどんな過大な予算提案をしてきても議会がチェックできず、それを住民が見過ごしている。だから、さっき工藤さんがおっしゃったように、本当なら住民は任期途中でも引きずりおろすことができるのですよね。市長もそれから議会も。でもそれを行使することはなかなかできなかった。 工藤: そうなってくると、議会が全く機能してこないことはますます問題なわけですよね。増田さんは前回もおっしゃっていましたが、議会を中心にすべきで、住民の代表は議会だと。その場合、知事や首長と、議会の適正な関係はどういう風な形にしていけばいいのでしょうか。 増田: まず1つは、執行部へ徹底的に質問など何でもして、出してくる予算案をはじめ、議案を徹底的にチェックする。これは最低限のことです。それから、現在の議会というのはほとんど99%が執行部とのやり取りだけなので、執行部とは関係なく、議員間討議を行うことが必要です。今の制度では、確かにお金に絡むことは議会で提案はできないけれども、地域の声をまとめてまちづくりに関わる条例をつくるということはできます。ですから、そういった議員間討議で、地域の声や地域の意思を自分たちで集約していくことが本来の役目ではないでしょうか。 工藤: なるほど。そうすると何か陳情する代表ではなくて、住民の意思を聞いて自分たちの政策などを作っていくことが求められますね。ただ、議員も数が多すぎる点や、ボランティアでやったらいいのではと言われていますが、いかがですか。 増田: これには両面あって、ボランティアだと、中をいろいろチェックするのはどうしても難しい。人口の多いところはボランティア議会でやるか、本当に専門の意識の高い議員だけでやるか、2つの道があると思うのですが、どちらにしても執行部がやっていることが適切かどうか、監視する能力があればいいので、ボランティアでも良いと思います。そういうニーズは多いですよね。横浜のような大きな自治体の監視もボランティアでいいのだけれども、その時には監視役の専門的な監査機関、専門職の人間を雇うなど、何か一工夫がいるとは思います。でも、ボランティア議会というのは世界的に見てもかなり多いですよね。 工藤: いま地方の議会というのは何個あるのでしょうか。1800くらいですかね? 工藤: すると、それでどのくらいがちゃんと機能しているのですかね。さっき言った執行部提案はほとんどスルーだし... 増田: 90%くらいは自分たちで条例も提案したことがない、というのがありますね。それから、最近「三ない議会」と言われるけど、要は執行部が提案してきたものを修正もしたことがない。これも非常に多い。8割か9割。それから、ましてや自分たちで条例を提案したことがない、あともう1つは、自分たちの投票行動を明らかにしていない。 工藤: 議会の中で?明らかにしていないというのは、秘密ということですか? 増田: HPを見ても誰がどの議案に投票したのか全然分からない。で、会派で拘束してしまうので、頭数だけの議論になってしまっています。それを外に出さない。でも、私は4年間の議員活動の本当の通信簿というのは、一つひとつの議案についてこの人は賛成したのか反対したのか、それだと思うのですね。 工藤: かなり深刻ですね。 増田: ここであえて言うと、視聴者から反論があるかもしれないけれども、選んだのは結局、有権者だということです。棄権した人もいるかもしれないけど、選んだ責任というのは一方で住民にある。一度選ぶときだけ権限を行使し、4年間任せて放ったらかしで傍聴にも行かないとすれば、それが本当に良かったかどうかが逆に問われる。 増田: 「選ぶときだけ権利を行使して、あとは奴隷となる」という有名な言葉がありますよ。 工藤: この議会に関しては、地方の中でいろんな変化がありますよね。先週も言及されていたのですが、名古屋の議会との対決、執行部との対決とか。この現象はどう見ればいいのですか。 増田: これは地方議会が確かに機能不全だということですよね。しかし、その地方議会には、無所属議員もいますけれども、少なくとも都道府県レベルでは、多くが今の中央政党の支部単位で会派を構成しているわけです。ですから中央政党の地域支部の役割が、今まで通りでいいのかということが問われていて、それが地域政党という話が最近よく出てきていることとつながります。実は、中央政党で地域主権とか分権を進めるというお題目を唱えていても、実際の支部の在り方を見ると、みんな中央集権的で、マニフェストが選挙の時に出たらみんなそれを配っているだけ。ですから、そういう中央政党が、地域での役割を果たしていないことが本当にいいのかどうか、そのことが突きつけられている。 工藤: これは、この前、佐々木さんと話したのですが、日本の政党そのものが問われているということの裏返しで、それに対する抗議や警告が地域で出ている。つまり、日本の政党というのは中央集権の政党ですから、先週も話題に出ましたが、国政にいたいのですよね。地方の陳情を吸収して、それで何か実現するだけであれば、地域のことを誰が考えるのか。地域における政党そのものの存在がいま問われているということですよね。 増田: そうですね。政党の在り方が。何をするのか、と。 増田: 地方の制度というのは結局、その住民が大変だけど一歩でも二歩でも自分たちで前に出ていって、それであまりに自分達の代表がひどければリコール権を使って任期途中でも引きずりおろす。あるいはそういうことだけでなくて、まちづくりにしても最初の案は市役所からプロが作ったものが出るけど、途中で主役であるべき住民がまちづくりの主役へと変わっていかなくてはならない。ですから大変ではあるけども、地方自治はやっぱり住民が一歩でも二歩でも前へ出て、自分たちでやっていくという覚悟と気概を持っていかなければ、全国的に見てもいいまちづくりにはどうしてもつながっていかないと思う。これは非常に大変なことのように聞こえますが、私は年に1回でもいいから議会に傍聴に行くといいと思います。色々な問題のあった名古屋市議会も、あの問題以降みんな傍聴席に来るものだから最近は非常にぴりっとしているという話です。だから、その「見られる」ということ自体だけでも、議会の機能を向上させることになると思います。 工藤: こういうことも聞いたことがあります。あるエコノミストの話なのですが、地方に出かけてその地域再生のためのことを講演に行くらしいのですね。するとその地域の経済人から、経産省などの国がモデルをつくってこれを地域で実現すればいいと言ったことをやってきたけど、実現しても全然雇用も、地域経済もよくならない、と言われたそうです。つまり国はもうモデルを立てる力もないのではないかという声もあって、そういう政策的なことでも地域はもう自立しないといけなくなっていると感じます。 増田: ヒントにはなるかもしれませんが、決定打にはやっぱりならないと思いますね。 増田: ええ。結局それが全国どこへ行っても、駅前が同じような形をしていた、という今までの反省につながっているのではないでしょうか。ですから、今はどちらかというと、そういうことよりも多様化というか、個性を重んじるという方向性ですね。これは自分たちの今までの身近な経験則からもやはり、多様化だ、自分たちの住みやすさだと、今言われているのは、結局、自分たちの感性で作っていかなくてはならないということの裏返しだと思いますよ。 工藤: つまり、もう国に任せるだけでは自分たちの地域の未来は描けないと。自分たちが主役にならないといけない状況に追いつめられてきている、そういう現象でもあるわけですよね。 増田: まあ、幸いなことだと私は思っています。自分たちでやらないといけないのは、幸いなことだと思っています。原点はそこに戻りますね。 工藤: その時にいま、統治の仕組みとして出てきているのが議会の在り方、政党の在り方であり、住民自治を機能させるためには非常に不全だ、ということですよね。機能していないことに対する問いかけが今出てきていると。 増田: 私は選択肢を増やすべきだと思います。人口が1000人を切るようなところもあるわけです。それにも関わらず、教育委員会を独立させたり、議会の議員を選んだり。そういうところだったら、場合によっては総代会のように直接の統治でもいいじゃないかとか、あまり人口の多くないところは、シティマネージャーで市長をわざわざ選ばなくても議員さんだけ選んでおけばいいのではないか、と私は思うのです。これは外国でもありますよね。ですから、住民の選択にゆだねて、いろんな自治の形をいくつかの中から選べるようにして、それで自分たちにあったものを段々とつくっていくということが大事ではないかと思いますね。 工藤: いま、名古屋とか大阪とか大都市の中に議会と首長さんとの対立があったり、そのシステムの変更に伴う動きが出てきていたりしますが、この前の名古屋とか見てもすごい投票数を集めているわけですよね。この動きというのは、日本を変革する、1つの大きなエネルギーの源流になり得るのですかね。 増田: 私はその1つが現れたことだと思います。ただ、大都市特有の問題であるかもしれません。大都市の方が地方議会の姿はもっと見えずに離れているから、大都市はもっと小さな民主主義を回す仕組みというものを、真剣に考えないといけないのかもしれません。それから、これは鋭い問いかけであり、住民が確かに気付いたというか、触発されて自分たちで解を出したということでもあります。それにしてもやや住民を煽った扇動的なことにつながるかもしれない、という危惧もありますね。 工藤: そういう危惧があるのですね。確かに民主主義のプロセスというのは、やはり耳心地、聞き心地のいいものにみんなが動いてしまうという部分があるわけです。だから、減税をやるのだったら無駄を徹底的に削減するとか、いろんな形でやっていくと思うのだけども、そういうことが問われずに、減税だけが話題になることもある。今の動きが、住民自治の動きにつながればいいわけですね。 増田: そうですね、それだけのパワーを持っているという可能性は明らかになった。また、多くの自治体で首長はピリッとしなければいけないと思います。その一方で最終的には住民が決める話ですが、本当に現世代に対しての減税、つまり住民税の減税はいいのでしょうか。結局これは高額所得者にとって有利です。借金や市債の発行もしていて、更には交付税ももらっているところが減税でいいのか、そういういろんな問題を含んでいます。 工藤: ただ、例えば一票の格差の問題もありますが、このような大都市が地域型に動いてきて、国会議員を出すという状況になってきたら、先週の話にもありましたが、日本の国会議員はその日本の地方分権にあまり真剣じゃない、といった日本の統治の大きなシステムチェンジになり得るかもしれませんね。良い方向か悪化させる方向かは分からないですが、何かの動きが始まった感じはしないですか。 増田: それは一方で、国政のふがいなさでもあるでしょうね。 増田: 私は、あの河村さんの動きに、国会議員が引きずられるように見えることこそ、情けないなあと思っていますが、それだけのパワーが住民の方にあるということは、もっとよりよく変えられるチャンスでもあると思いますね。 工藤: はい。今日も話がかなり進んでいって、日本の民主主義が問われている中で、大きな変化が1つ地方にも始まってきていると。ただこの地方の問題は、まさに地方が自立しなければならないという課題として、その局面に追い込まれてきている状況ですね。このような流れの中で、地方自治ということを住民がしっかり責任を持って行える仕組みへの展開が図れるかどうか、まさに非常に大きな段階に来ていますよね。 増田: そうですね。初めてじゃないですかね。統一地方選挙の時に、住民は自分たちの代表である議会のことを通じてそういうことが問いかけられる。今までは首長の人気投票みたいな感じでしたよね。 工藤: そうですね、まさに歴史的一歩、大きな動きが始まったということでした。ということで、今日も時間になりました。ゲストに岩手県知事や総務大臣を務め、現在は野村総研の顧問の増田寛也さんをお招きし、「日本の地方自治をどう立て直すのか」ということで話をしました。また皆さんからもいろんな意見を頂きたいと思っております。僕たちのこのON THE WAY ジャーナルは日本の民主主義を考える議論を徹底的に進めていきますので、またよろしくお願いします。今日は増田さん、ありがとうございました。 増田: ありがとうございました。
投稿者 genron-npo : 18:43
| コメント (0)
| トラックバック
今回(第23回)の「工藤泰志 言論のNPO」は、スタジオに岩手県知事や総務大臣を務めてきた野村総研顧問の増田寛也さんをお迎えして、「地域主権、地方自治と民主主義」について議論します。 「ON THE WAY ジャーナル
工藤: おはようございます。ON THE WAY ジャーナル水曜日。言論NPO代表の工藤泰志です。今日は民主主義とも非常に関係があるといいますか、まさに民主主義の原点というものなのですが、地方自治の問題ですね。ちょうど4月から統一地方選挙もありますので、地方の自治とか地方の自立ということを、有権者の視点から根本にさかのぼって考えてみようと思っております。今日もスタジオには重要なゲストを呼んでおります。岩手県知事や総務大臣を務め、現在、野村総合研究所顧問の増田寛也さんです。増田さん、おはようございます。よろしくお願いします。 工藤: 地方選挙というと、国政と違ってかなりローカルな感じをイメージされる方もいらっしゃると思いますが、今回の統一選はかなり重要だなと僕は感じています。地方自治は「民主主義の学校」と言われているのですが、まさにその日本の民主主義が問われている中で地方の選挙が行われるということは、これからの日本にとって非常に重要な局面に来ていて、はっきり言ってそのきっかけになるのではないかと思っているのですね。考えてみれば日本の政治が非常にまずいということであれば、それは地方の自立のチャンスにならなくてはいけないのですが、やはり地方議会の問題など様々な問題が出てきているし、また大きな動きもある。こういう動きが日本の変化のきっかけに本当になるのかということを、僕たちは根本から注意深く見ていく必要が出てきているのではないかと思うのですね。そういうことで、私たちは地方自治や地方分権という問題、それから最終的に民主主義の視点から、この地方の自立ということを問い直し、またその流れを興すために何が必要かということを、これから今週と次週にわたって、増田さんにお付き合いして頂きながら、みなさんと一緒に考えていきたいと思っております。 今日のテーマは「本当に地域主権の覚悟はあるのか」です。これは要するに、今まで地方分権とか地方自立とかいろんな掛け声だけはかなりあったのですが、なかなか進まないですよね。それで考えてみたら、本当にそれをやろうとする意思があるのか、というところまで僕は疑問に思っているのですね。そういうことを、まさに実践して、知事、総務大臣も務められた増田さんのお考えも踏まえて、議論を進めていきたいと思っています。まずは本論に入る前に、先週は僕たちの民主主義というものが、今、かなり機能不全になっているのではないかという問題を問うて、その原因を民主主義の政治論として考えていきました。これについて増田さんはどうお考えでしょうか。 増田: 民主主義の基本というものは話し合いですよね。徹底的に話し合う。最近の流行り 工藤: ええ、はい。 増田: 熟議はただ単に何度も何度も話し合えばいいということではなくて、中身をもっとお互いに深め合う。逆に言うと政治家が妥協をしてもいいから、話し合いで一定の結論を得ようということですが、この「話し合い」が完全に崩れている。形だけの話し合いであったり、あるいは相手に喧嘩をふっかけてあとは蹴散らすだけ、といったものであったり。だから今話していてやはり、かなり重症ではないですか、機能不全。 増田: 物事が決まらない。あるいは、決まったかのごとく相手を蹴散らす、と。 工藤: そう。何だか政治家同士のゲームをやっていて、有権者は関係ないという状況ですよね。 増田: そうですね。 工藤: 本来こういう国政の問題で問われている話は、皆さんの地方の現場ではどうなのかと。やはり日本の国政でも民主主義の機能がかなり大きな問題を抱えているのですが、実をいうと地方も同じような問題があるのではないか、と僕も思っているのですね。ただ、本当は地方こそが住民と一番近いところで、住民が代表を出すことと非常に近い関係である、という状況でした。そういうことを目指して、ずっと昔から地方分権が唱えられて進められてきたのにも関わらず、どうも最近、地方分権という言葉自体が色あせたというか、あまり盛り上がらないのですが、何がどこでこういう状況になってしまったのでしょうか。 増田: 住民の本当の代表は誰かというと、今まで知事や市長の方が目立っていたということが実際ありますが、本当は議会ではないかと思うのですね。欧米に行けば議会の議員を選んでいるのだけれども、市長は議会の議長が兼ねている、とかね。あるいはシティマネージャーだとか。住民の代表というのは議会であって、そこで決まったことを市長にただ単にやらせるだけでいいのではないか。私は、議会こそ住民の代表だと思います。ただ、この肝心の議会が、日本の場合は著しく機能不全というか、市長とか知事の追認議会だったり、中で既に長老同士で決めてしまっている場合は、あまり外には見せたくないから外から見えないようにしたりしている。 工藤: そうですよね。傍聴を禁止したり、誰かがそれをツイッターで書いたら突然全面禁止になってしまったり、とかありますよね。 増田: できるだけ外に見せないですよね。そして、陰で力を行使するのが本当の議員の実力だみたいな、誤った考え方というか、国会の真似事、しかも国会の悪い部分を真似てしまっている。例えば小さな町の議会の会派でも、国会でいうと党議拘束というのですが、投票する時に一人ひとりの意思を縛ってしまう、とかね。そういう国会のおままごとのような悪いところばかりをやって、ますます住民の代表ということから離れているということです。 工藤: 今までそういうことには薄々気づいていましたが、そろそろ限界になってきたという状況ですね。ただ、地方の分権の動きを見ると、本当は地方分権というのは手段であって、最終的には、住民が自分たちの地域の未来や今を自己決定し、ある意味で競争をして、自分たちの魅力的な地域を創ることが地方分権の目的だった訳ですよね。しかし、その手段争いの間、やはりメディア報道を見て感じるのは、結局は知事と霞が関の闘いのような状況になっていきましたよね。増田さん自身も改革派の知事の筆頭であった訳ですが、その進め方がやはり少し違っていたということですかね。 増田: 地方住民の代表としては、私は議会の方に本当はウェイトがあって然るべきだと考えています。一方で、確かに知事や市長も住民の代表なのですが、今までの分権というのは、その2つの代表者のうちの知事や市長の権限を強めるということだけに焦点を当て、それに終始していた嫌いがあった。それも必要なことなのですが、端的に言えば国会の役割や機能を地方議会に移す、ということがすっぽり抜けていた。国会議員は、与野党問わず、私が会った限りではみんな、地方議会にそんな機能は果たせない、あるいは地方議会に任せたらドロドロになると言ってそれを好まない、やらせない。最終的には、国の法律で地方分権というのを決定しないといけないのですが、私は中央省庁の官僚よりも、むしろ国会議会が実は心底地方自治体に役割を移していくことを嫌っているが故に、全体として国会自身も動かないので、何事も物が進まないのだと思います。ただ国会議員はあまり表に出るのが嫌だから、中央省庁の役人などを通して分権にいろいろ抵抗するという、そういう側面もあるのです。 工藤: 今の話、非常に重要な話ですね。つまり国会議員は地方分権、本当は嫌なわけですね。 増田: はい。日本は三権分立ですよね。アメリカは州ごとに全て司法権まで分権しているのですが、日本では、司法権は中央でいいと私は思います。ただ残りの行政権と立法権を分権しなくてはいけない。行政権については、今まで議論の俎上に上がって、まあ曲がりなりにも少しずつは進んでいる。一方で立法権の分権、言い換えれば条例制定権を拡大する部分に全く手を付けなかった。またそれを嫌っている人たちがいる。こういったことが全体として分権の歩みを遅くしたり、あるいは、地域の受け皿となる地方議会が、逆に漫然と役割を果たしていなかったり、ということで住民からは信頼を受けていない。住民としても、本当に地方に移ってきても大丈夫だろうかという不安があって、全体として後押しをする状況ではないようですね。 工藤: 確かにそうですよね。昔、政党別討論会を僕たち言論NPOでやった時に、増田さんにも出て頂いたのですが、政党の人に、あなたたちは国会議員を辞めて地方議員に変わったらどうだ、と提案したことがありました。つまり、国会議員700人もいらないですし、本当に地方の主権をやるというのだったら、それくらいの覚悟でというような意見がありましたけど、何だかきょとんとしていましたよ。 増田: 意表をつかれたような様子でした。 増田: 僕は永田町改革が本筋でないかと思いますね。 工藤: 今の話を聞いて、少し分かりにくい所があるのかもしれませんが、今までは霞が関が持っている権限や財源を地方に移そうとしていました。それを増田さんなど、いろいろな知事が頑張って実行してある程度進んだのですが、なかなかそれ以上進まないのですよね。でも、何となく知事が結構格好いいというか、それなりの人がいたので知事が改革をやっていたのだけど、実はこの勝負は基本的になかなか進んでいませんでした。民主党政権になって、地方主権を一丁目一番地といってやっていました。でもやっぱり進まなかったわけですよ。ただお金の問題はそうなのだけど、それを分配されたとしても最終的にはその地域がそのお金を使って、どういう風な地域を創るか、という時に初めて分権は意味を持つのであって、単にその手段で争っているだけのゲームのようになっていた。増田さんは、財源や権限を霞が関から委譲することが大事だと思っている一方で、だったら立法の分権、つまり地域でどういう風な地域づくりをするか、ということも自分たちで決定するところまでいかないと、権限が移されても本当の意味での住民自治の根幹ができないのではないかと。その点に関して日本の政治家のほとんどが、やはり興味がないというか、真剣ではなかった、覚悟がなかったということですよね。 増田: そのこと自体に問題意識がないというか、気が付いていない。権限をどうすればいいのかという権限の根拠は法律に基づいているのだけれども、法律でなくてそれぞれの地方議会で、地域ごとに条例を作ったらいいのではないかということが、まず意識されていなかった。それからもう1つは、地域で条例を作るときには地域の実態を深く考えて、どういう地域づくりの上で、例えば、保育所の設置基準をどうするか、都市計画の中でどういうまちづくり条例をつくれば、まちが良くなるのかといった、その中身を真剣に考えなくてはならないですよね。それらのイシューをまとめて、条例を制定し、市長とか知事に根拠を与える。その中身を考えるということを今までやっていなかったので、結局、行政で考えたことの追認だけをやっていたから、議会として中身を考えられない。更にもう1つ付け加えて言うと、住民の意識が多様化したので、ただ住民の人たちに意見を聞いていてもまとめられない。政治的にまとめる、前回出演した佐々木毅さんの言葉でいうと政治的統合を言いますけど、それを議会の中でお互いに議員同士で話し合ってやる、ということが今までなかった。議員間討議というものですね。悪いことだけをたくさん並べてしまいましたけれども、もちろん良いこともやっているのですが、端的に言えば大事なことが議会として決められないということです。 工藤: そうすると、本当の地方自治や地方主権として、目指さないといけないのはどういう形なのでしょうか。 増田: 議会を中心にして、住民の本当の代表者は議員であり、議会だと。「代表なくして課税なし」の「代表」と言うのは、歴史的にみればアメリカでは明らかに議会を意味していました。その議会運営をもっと健全な姿でやる、ということです。一人ひとりの人たちは、皆さん仕事など生活で忙しいですから、代表者を選んでそのプロに、しっかりとしたまちづくりをしてもらうことを考えています。しかし、選んでお任せのようにやりっ放しではなくて、やはり傍聴席に行って監視をするなどが必要です。民主主義や、とりわけ地方自治というのは、一番身近な地方政府をいかに住民がコントロールできるかということだと思うので、お任せではなくて、いざとなったら自分たちで立ち上がらなくてはなりません。あまりにもひどければリコールで代表者を変えてもいいけど、その前に、まず監視をして代表者が良い仕事をするかどうか、それを見張るということが必要ですね。 工藤: やはり地方分権の目的は住民自治なのですね。住民がちゃんと自分たちで意思決定できないといけない。ただ、その部分の住民の声や姿というものが、今までの中央分権の中の議論にあまり出てこなかった。やはり制度論というか、権限移譲の話でした。 増田: ええ。結局そうですね。これまでは、中央省庁が持っている権限を、知事や市長にいかに移すかという、その部分だけにとどまっていました。議会の議論が出てくると、当然住民の代表者ですから住民との関わりが出てくるし、いわゆる住民自治が議論されるはずなのですが、今まではその団体自治のところだけを議論していた。 工藤: そうですね。地方6団体と政府の協議とか、そうなってしまうでしょ。 増田: 要するに国からの自由というものは、国から知事が自由であるかどうかということであって、議会のことは議論していなかったから住民の姿が出てこなかった。 工藤: でもこれは、上から下に与えるという改革の姿は難しいということですかね。例えばさっきの「代表なくして課税なし」と言いますが、地方税の税率を変えられるけれども、なかなか自主的に変えられない、というかなり中央集権的な統制的な流れがありますよね。 増田: これは我が国の場合には歴史的な問題があるでしょうね。連邦国家でなくて、江戸時代の幕藩体制にしても、結局、江戸幕府が肝心なところは押さえている。明治以降もずっとそうですよね。ただ、連邦国家か単一主権国家か、どちらの体制が歴史的に合うかどうかは別にして、現在は住民自治ということで住民の意識水準が上がってきています。ですから住民自治により、身近な政府をどうコントロールするかという観点からは、いろんな改革がなし得ると私は思います。端的に言うと、やはり、税の負担と給付、要するに受益と負担のような議論など、非常に見えやすい議論があるから、そういうものを真剣に考えるというのは極めて重要です。 工藤: ですよね。ただ、今の政治家にやる気がないと、やり方に困りますよね。どうやって進めばいいのか、ということが本質的に問われている感じがしますね。 増田: ですから河村さん(たかし、名古屋市長)のようなやり方も1つはあるとは思います。しかし、最後は住民が立ち上がる、ということです。住民が立ち上がらないと変わらない。立ち上がるというのは議会の傍聴席に行くだけでも緊張感が出て、がらりと変わってきますから。 工藤: 今日の話はですね、次回もう少し進めないといけないのですが、今の地方自治という点から見ると、今までの分権の論議、目標が見えなくなって曖昧になってきている。しかも国政だけでなくて、地方の民主主義の仕組みに関しても、様々な機能不全というものを起こしてしまっている。これが目に見えてきているという状況の中で、もう1回住民という視点で、議会との関係や地方の枠組みを考えないと前に進まない段階にきている、という話だったと思うのですけれどもそういう理解でよろしいですか。 増田: そうですね。手段が独り歩きしていった、と。 工藤: わかりました。まだ話が尽きないのですが、これでひとまず終わりにします。次回は、地方をどういう風に具体的に民主主義の立場から立て直すべきなのか、ということについて話を進めたいと思います。今日は増田さんをゲストにお呼びしまして、日本の民主主義、つまり本当の意味での地域主権というのは、本当に覚悟があって臨んでいるのか、ということについてお考えをお聞きし、議論を進めました。今日はどうもありがとうございました。 増田: ありがとうございました。
投稿者 genron-npo : 22:20
| コメント (0)
| トラックバック
放送第22回目の「工藤泰志 言論のNPO」は、前回に引き続き、ゲストに元東京大学総長で学習院大学教授の佐々木毅さんをお迎えして、日本の民主主義社会はこの先どこに向かうのか、議論しました。 「ON THE WAY ジャーナル
工藤: おはようございます。ON THE WAY ジャーナル「言論のNPO」。今日も、先週に引き続き、スタジオに元東大総長で、現在、学習院大学の教授の佐々木毅さんに、ゲストで来ていただいています。 佐々木: よろしくお願いします。 工藤: 早速ですが、先週も少しそのような話になったのですが、やはり民主主義は色々な問題を抱えています。しかし、民主主義が機能するということは、社会が直面している色々な課題に対して成果を出すということです。それができないとすれば、民主主義のどこに問題があって、それをどういう風に改善していけばいいのか、を考えなくてはならない。世界も日本もそうですが、そういう風な問題に対応できない時に、どのような見直しの動きがあったのでしょうか。 佐々木: そうですね、やはり結果を出せないということは、結果を出さないで内閣だけがクルクル、クルクルと変わり、同じメンバーが入れ替わり立ち替わり出てきて、2、3ヶ月で終わる。それはつまり、政治家のための政治ですね。 工藤: そうですね。政治家のゲームですね。 佐々木: 政治家のための政治家ゲームとしての民主主義になってしまうと、長期的な視点に基づく施策で結果を出す、ということは脇の方に追いやられてしまう。これは一つの欠点、問題ですね。 工藤: そうですね。今、まさに日本がそういう状況ですね。 佐々木: 日本もちょっとそういう雰囲気がありますね。同じことはかつて、フランスの第四共和制とか、第三共和制とかいう時期にはよく言われました。一時のイタリアもそのような時期がありました。それを変えようということで、ご案内のように、今、フランスはアメリカのように大統領も選ぶし、それから議会も選ぶという仕組みに制度を変えました。見違えるように安定したと言えるかどうかは分かりませんが、少なくとも、かつて問題にされたような事態はある程度是正されたと思います。こういう中では大きな政治の制度、日本で言えば議会制というようなものが多くの人の念頭によることになり、衆議院と参議院の「ねじれ」などの議論になっていますが、これはいわゆる憲法問題ですが、この憲法問題も含めて、仕組みを整理して、一定期間は安心して結果が出せるような仕組みにすることが考えられる。選挙は選挙で競争はちゃんとやるという。この「競争」と「結果」を出すということが、うまくコンビネーションができればいいのですけど、いつも競争しているけど、結果は出ないというのでは話にならないし、非常に具合が悪いわけですよ。だから、僕はやはり、制度の問題が非常に大事だなと思います。それは制度の問題ですから、最後は選挙がどのように行われるか、選挙制度の問題もありますし、それからどれぐらいの票を取れば議員になれるのか、というような問題もありますし、投票率の問題もあります。それから、最近の日本だと、若者が投票にいかないという問題など、実態問題から制度問題まで沢山あります。 工藤: 私も民主主義の仕組みを直すという課題があると思いますが、議会のほうでは、確かに佐々木さんがおっしゃったような、参議院と衆議院の二院制で、相互にチェックするような仕組みだったのだけど、今はその機能が働いていなくて、動かない状況になってしまいました。こうした状況はどう考えていけばいいのでしょうか。 佐々木: この議論をやりますと、必ずチェック機能は重要だという世論が出てきます。しかし、他方では結果が出ないので困った、という議論が出てきます。一体、国民はどう考えているのか、ということについて、私から見るところ、総じて全て曖昧なままに、これまで過ごしてきた感じがあります。その曖昧さでいつまで持つのかということは、国民の意識の面でも、少し詰めて考える必要があるのではないかと思います。だから、国会というものは、実際上はないわけです。あるのは、衆議院と参議院しかないわけで、国会というのは国権の最高機関だと言われていますが、国会の意思というものが決まらない中で、国会を中心にして議会制民主政治だと言われても、どういうことになるのかという問題は、みんなの目にいよいよはっきり映っているのではないかと思っています。そういう意味で、この問題は大きな問題ですが、もっと議論されていいのではないかと思っています。 工藤: 先週も話にありましたが、例えば、今の国会を見ていると、政治と国民の距離がかなり開いてしまっている。本当は、国民は色々なことを考えて、悩んで、年金や社会保障など、結果を出して欲しいと思っているのに、政治が全く機能しない。でも、解散は首相の権限ですから、解散がなければ僕たちに選ぶチャンスもありません。世界がどんどん変わっている状況にもかかわらず、今の政治の状況のままにそのままずっといなければいけない。これは、仕組みとしてやむを得ないのでしょうか。 佐々木: 政権を担当している以上、現実は常に変わっているわけですよ。例えば、マニフェストというものを何年か前に出しました。だけど、その時に頭に描いていた世界と、今とではかなり違う世界になってしまう、ということはあるわけです。従って、当然見直しをしたり、新しい政策を提案するということは、一定のスピードで動かない限り、とても結果が出せるような雰囲気にはならないわけです。何か、昔の手形を落とすことをやっていれば、政治になるという話は、私はむしろ極端なのではないかと思っています。 工藤: 変更するのであれば、きちんと説明すればいいのに、もう見直しているにもかかわらず、秋までに見直すとか言っていますよね。 佐々木: だから、説明をして、もちろん国民の中にはそれはけしからん、という人もいる。しかし、そうだろうなと思う国民もいる。問題は、そこをきちんと説明をして、そして可能な限り納得してもらう、ということ以外に、政権を担っている人たちの責任の果たしようはないのだろうと思います。 工藤: そうですよね。すると、ここまで目に見える形で国会が膠着してるな、ということが分かると、地方自治体では、よくリコール制などのように、住民側が直接的に参加できるような仕組みがあります。一方の国政は、代議制ということで、私たちの代表だということの信頼があればいいのですが、その信頼が全部とまでは言わないまでも、全く無くなっている状況になると、仕組み上のミスマッチや用意が足りないような気もするのですが、それは政治的な問題にはなっていかないのでしょうか。 佐々木: おそらく、これも2つの考え方があります。解散という話もよく言われるのだけれど、「解散」という話になった途端に、頭の中が真っ白になる人たちばかりだから。そうなると、「結果」なんてどっかにいってしまうわけです。解散のときこそ、最も頭が冷静でなければいけないのだけど、日本では新聞も含めて、解散と言った途端に選挙だけになってしまう。だから、選挙民主主義なのですよね。頭が真っ白になるように、選挙に取り組む。だけど、国民にとって選挙は、次の政権をつくるための手段ですよね。だから、頭が真っ白になるのではなくて、色々なものが詰まっている中で選挙をやってもらわないといけないのだけど、国民も含めて、選挙になると頭が真っ白になるという伝統がなかなか無くならない。この辺も含めて、非常に未整理なのですよ。だから、おっしゃるように、選挙の時にこそ頭脳を充実させた上で、例えば何年間か任せて政治をやってもらう、ということが、私は成果が上がる道筋だと思います。もし、選挙になると、政治家、国民も含めて、頭の中が真っ白になるという話であるとすれば、やればやるほどひどくなっていくという可能性もあって、にわかにいい「結果」が出てくるとはいえません。問題は、選挙自体もさることながら、どのように選挙をやるのか、そのためにどんな準備を政党がするのか。こういった話とセットでなければ、どうぞみなさん意思表示をしていくださいと言われても、同じ話の繰り返しになりはしないだろうか、という心配がなかなか消えません。 工藤: 解散をするということは、確かに首相の専権事項ですが、国民側から、そろそろこの状況は厳しいので、国民に信を問うてもらえないかとか、そういうアプローチは、政治の仕組みとしてあり得ないのでしょうか。 佐々木: だから、例えば、憲法を改正するということとの関係で話題になった、国民投票法みたいなものを、少し適用範囲を広げるようなことを、場合によっては考えないといけない、という議論はもっとやってもいいかもしれませんね。ただ、これも、ポピュリズムだとか、何とかいう批判も出てくるので、それをどう使うかについて政治のほうで、冷静な判断があればいいと思います。要するに、政治の世界で、どうにも決着がつけにくい、あるいは、事柄が人間の本来の在り方に関わる問題などで決着がつかないので、国民の意思を聞きたいという事柄など、どのような事柄に限定するかを考える必要はありますが、やってもいいのではないかと思います。何かわけのわからないうちに、何でもダメになったということを続けられると、これはやはり具合は悪いと思います。自分たちは責任を持っています、と言っているけど、いつも決着をつけない。 工藤: 政治家が責任から逃げるのでは、どうしようもないですね。 佐々木: そこなのですよね。例えば、リコールの問題が地方議会では起こっていますけど、リコールが国政にもなじむのか。あるいは、6年間も議席を確保できる参議院をどうするのか。あるいは、衆議院は解散があるから、今の制度でいいというのだけど、参議院を別の制度にするという話もあるのかもしれませんが、よくわかりません。ただ、あまり議論はされていません。 工藤: そうですね。ただ、時代と共に民主主義を発展させるためは、政治の仕組みなど、色々と考えないといけないなという感じがしています。今、佐々木さんがおっしゃった中で、選挙の問題なのですが、選挙というものは、国民が代表を選ぶということで、本当に大事な機会だと思うのですが、政治側も有権者側も、選挙の大事さを何となく理解していないのではないかと思っています。例えば、政治側は、国民にいい候補者を立てて、しかもきちんと政策を説明して、成果を出したいから任せてくれ、という形になっているか。有権者側も、投票に行かない人も多いし、休みになると遊びにいってしまうというようなこともあるわけです。それでは、まずいわけですよね。佐々木さんの本を読んでいて思ったことですが、衆議院選挙の場合、投票者数の6分の1をとらないと当選できないわけですよね。そうすると、単純に言えば、投票率が60%だとすると、その6分の1ですから、投票者の10%で当選してしまうとう構図になってしまうわけですよね。佐々木さんの本にも書いてありましたが、例えば、その基準をもっと厳しくして、総有権者数の3分の1とかにすると、本当に激しいというか、本当に真剣にならないと当選しなくなりますし、多くの人たちがその人に託すということで、投票所に足を運ばないと当選できなくなりますよね。凄く緊張感が出ると思うのですが、こういう制度に変えるという一案ですよね。 佐々木: 僕は、前からそういう制度も考えてみてはどうかと言っています。そうなると、多くの人に投票してもらえるように、候補者も相当いい人を揃えるようになりますよね。つまり、候補者供給側としての政党の態勢の問題ということが、今以上に厳しく問われるようになると思います。そうすると、その結果として、工藤さんが言われたような制度にすると、一番票を得たトップの人が、一定の得票数を獲得できなかった選挙区は、議員を持たないことになるのか。それとも、また再選挙をするのか。 工藤: 代表不在ということにすれば、それが議員削減になるわけですよね。 佐々木: 私は、その辺を少し考えた方がいいと思います。そうしないと、どうも上っ面だけ修正すればいいのだ、という感じが残ってしまいます。そうすると、参加する側の意識も変わりません。要するに、選挙は、投票に行く人だけがマーケットのメンバーで、国民全員が選挙のマーケットだということとは違う、という既成事実ができあがっています。そうすると、対象が6割ちょっとでしかない。 工藤: それが当たり前になるから、初めから、選挙活動はそこに目標を設定して、やっていますよね。直接的利害者とか。 佐々木: だから、そのことを含めて、日本の場合は、政党というものが色々な意味で非常にお粗末だと思います。 工藤: 日本の場合、政党があって議員なのか、単なる議員の寄せ集めが政党なのか、ということが佐々木さんの本に書いてありました。そこまで言ったら言い過ぎかもしれませんが、後者に近いですよね。綱領もないところもありますから。 佐々木: ですから、唯一、マニフェストでとにかく何年間はこれでいこう、ということでも作ってもらわないと、候補者として出てこられても、この人何をやるのだろうね、という話になりますよね。だから、私も窮余の一策で、マニフェストをせめて作りなさいよと。 工藤: つくるプロセスが大事ですよね。 佐々木: ところが、組織力が非常に未熟なものだから、今度は作るプロセスが整っていない。 工藤: 5人ぐらいで作っちゃうとか、そういうのでは話にならないわけですよね。 佐々木: そういう意味で、マニフェストの作り方が充実する、そして内容が充実することと、候補者、特にトップリーダーの充実ということが、政党の最低限の条件なのだけど、これがなかなかできないのだよね。ですから、結局、国民もトップリーダーに対して、慢性的な不安感を抱くような感じが出てきているよね。これは、トップリーダーは、やはりつくらなければならない、という面も何割かはあると思うし、自ずから育つ面も何割とかね。これはどうしたらいいのかということについて、結局、各政党はルールがないし、それからキャリアパスもない。ですから、他の組織に比べて、非常に平等主義的で、何となく人が集まっている組織、という印象をぬぐえないですね。 工藤: 政党そのものもきちんと問われないといけませんね。佐々木さんが冒頭に言っていましたけど、「競争と結果」というのは、確かにいいですね。競争を迫られるから政党は鍛えられる。 佐々木: 競争するから、内部を鍛えて、マニフェストであれ人材であれ、鍛えられる。このメカニズムを潰してしまうと、ますますわけがわからなくなってきます。ここは、僕は譲れない点ですね。ただ、競争させるのだけど、さっぱり努力しないということになると、これはちょっと我々が外部から言っても、いかんともし難いところがあって、それは本人の問題でしょと、最近みんななりかけているところが残念だけどありますね。 工藤: やっぱり、競争のレベルをどんどん上げていくということも大事だし、一方で、それを見る有権者側の目も必要になりますね。 佐々木: その通りですね。 工藤: 一方で、成果をあげなければいけないという政治の仕組みをどうすればいいのか、ということも民主主義にとって重要だということですね。最後ですが、日本の民主主義が問われている中で、有権者には何が問われているのでしょうか。 佐々木: 簡単に言いますと、有権者の目線は、今の話にもあるけれど、気分的には未来の日本社会は持続可能性があるものとして、どんな政策が、そして何が優先的に先行して、考えなければいけないか、ということを政治がどの程度受け止めているか。私は、これを見て頂きたいと思います。今ここの話は、いずれにしろ出てくるのですけど、「今」ばかりをやっていると、最後まで「今」と「ここ」しかないということになってしまいますよ。気がつくと、結局何もやっていなかったということになりかねないので、やはり政治は、「未来」というものから目を背けてはいけない、未来と今の現実から目を背けないということを、国民はきちんと見ているのだぞ、ということが伝わっていくような世論を望みたいと思いますね。 工藤: 2週にわたって、佐々木さんと日本の民主主義について考えてきました。佐々木さんの発言のキーワードは、競争と成果を出す、あと、時代に合わせた民主主義。民主主義というのは、基本的人権や平等にとって非常に適合する仕組みだと。ただ、これを活かすもダメにするのも、僕たちだということなので、歴史的にできたこの仕組みを、どんどん活かして発展させていかなければいけないと思ったのですが、その時に、民主主義とか日本の未来もきちんと考えるというのは有権者自身だから、有権者の役割が非常に重要だということを、今、佐々木さんは言ってくれたのですね。僕もそう思います。もう一つ思ったのは、やはりインフラが重要ですよね。例えば、大学の先生やメディアなども含めて、権力とは距離を置いた形で、きちんと政治を監視したりする仕組みもなければいけない。そういうことがあって、総合的な国民の力を高めていくということが必要だと思っています。そのためには、僕たちが問われているという感じがします。僕も、何とかこの国の民主主義を前に進めたいと思っていますので、佐々木さん、これからもよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
「点」から「面」に広げる
市民の力
先日、言論NPOに、早瀬さんという、阪神淡路大震災の時に、市民や民間、経済界の人達を集めて、ボランティアをコーディネートして、地元の救済のために、仕組みをつくってやった人の話を聞いたのですが、やはり行政の役割と、住民やボランティアの役割は決定的に違うのだとおっしゃっていました。行政というのは、かなり公平にやらざるを得ないのだけど、こういう被災者の人たちは一人ひとりドラマがあって、色々な思いがあって、自分の生活を立て直したいと思っていると。そこに、きちんと寄り添うのがボランティアなのだとおっしゃっていました。やはり、このボランティアなり、市民の役割と行政の役割はやはり違うのでしょうか。
もう1つは、日本にいる外国人の方ですね。まだ、情報もないような状況ですし、皆さんどうしていいかわからず、途方に暮れている状態だと思います。そういった人達にも目を向けて、やはり災害から取り残された人達がでないようにしていく、そこもNPOの大きな役割だと思っています。
まず具体的な行動から
工藤:わかりました。僕たちの想像以上の災害が起こっているのですが、こういう時というのは、市民の一人ひとりが力を合わせるしかないと思っています。今の状況は非常に厳しいのですが、非常に重要だというか、これからの日本にとって、何かが変えられる、必ず乗り越えられるという確信をもてるような動きが始まっているということに、非常に安心をしております。とにかく、この輪を広げないといけないし、まさにこのON THE WAYジャーナルのチャネルというのは、市民一人ひとりが自立して、社会の問題に挑んでいこうという話ですから、まさにそれが今問われているのだと思っております。ですから、引き続きこの議論をしていきたいと思っています。今日は、堀江さんどうもありがとうございました。2011年3月16日
「日本の地方自治をどう立て直すのか」 2011.3.16 放送
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。

工藤泰志 言論のNPO」
―日本の地方自治をどう立て直すのか
(2011年3月16日放送分 19分16秒)
「日本の地方自治をどう立て直すのか」
地方の民主主義の程度は?
今までは既成政党の支部に結局は頼らざるを得なかったのですが、それを変えたいという動きへの転換点ではないかと私は思います。
工藤: 議員の数です。
地方議会になぜ建設業の議員が多いのか
制度的には諸外国に比べて、私は日本の議会制度の中での議会の権能は弱いと思います。アメリカは連邦議会で予算も自分たちで決めます。オバマさんが出す予算教書、あれは参考図書であって議会が全部提案して自分たちで決めます。日本の場合にはお金に関わる予算関係のものを議会は提案できないのです。
知事の提案を追認するだけの議会
議会の役割は議案のチェックと民意の集約
増田: そうですね。1800弱。
三ない議会とは?
工藤: ルソーが言っていますよね。
名古屋などの現象をどう判断すべきか
政党自体の存在も問われている
工藤: これはどういう風に最終的に収斂していくのですかね。
工藤: 国の政策が、ですね。
国に任せるだけでは地域の未来は描けない
住民パワーは住民自治につながるべき
工藤: そうでしょうね。
地方の自立への歴史的なタイミング2011年3月 9日
「地方の自立を問い直す」
-ON THE WAY ジャーナル 2011.3.9 放送分
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。

工藤泰志 言論のNPO」
―地方の自立を問い直す
(2011年3月9日放送分 17分39秒)
「地方の自立を問い直す」
増田: おはようございます。よろしく。
言葉と言うと少し語弊があるかもしれませんが、「熟議」とよく言われますよね。
日本の民主主義はかなり重症
工藤: 重症ですよね。しかも国会の意思が決定できないとなれば、代表を送り出している有権者から見れば、何がどうなっているのだろうという状態ですよね。かなり、深刻ですね。
地方分権はなぜ盛り上がらないのか
まず地方議会に機能不全も
国会議員は地方分権が本当は嫌い
工藤: そのような感じでしたよね。
増田: いやそれは、中央省庁の話ではないのか、という表情だったですね。
工藤: 霞が関の改革しか、関心がないのかもしれない。
永田町改革こそが本筋
工藤: なるほどね。
増田: 霞が関の改革も大事ですけど、逆に、永田町改革の意識が全くないということを、現時点で一番問題にしなくてはならないことだと思いますね。
問われる立法の分権
地方議会の立て直しこそ急務
住民が立ち上がらないと変わらない2011年3月 2日
「日本の民主主義をどう立て直すのか」
-ON THE WAY ジャーナル 2011.3.2 放送分
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。

工藤泰志 言論のNPO」
―日本の民主主義をどう立て直すのか
(2011年3月2日放送分 19分6秒)
「日本の民主主義をどう立て直すのか」
先週から、「民主主義」という問題について、僕たちは考えているのですが、民主主義というのも、基本的には「基本的人権」や「平等」とういうものにきちんと適応するような制度としては、これしかないわけです。ただ、そこには色々な問題があって、その問題を時代に応じて機能するように、色々と改善していかないといけないし、そのプロセスが始まっている、しかもそれが大事だということが前回問われた問題だと思うのですね。今回いよいよ本題に入るのですが、日本の今の政治を民主主義という視点から考えれば、何が問われていて、どういう風に変えていけばいいのか。ということで、今日のテーマは「日本の民主主義をどう立て直すのか」ということです。佐々木さん、今日もよろしくお願いいたします。
民主主義は政治家のゲームでない
大事なのは「競争」と「結果」
国会の意思が決まらないのに、議会制民主主義
国政にリコール制度はないのか
日本は選挙民主主義?
僕らの代表を選ぶのが、選挙
競争を高める選挙制度とは
佐々木: そういうことになるのか、制度の作り方は色々ありますが...。
工藤: 議員の定数が、民主主義の仕組みと連動するというのは凄いですね。
政党とは単なる議員の寄せ集めなのか
競争を迫られるから政党は鍛えられる
今の現実と未来から目を背けるな
強い民主主義をつくる