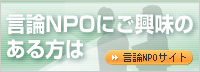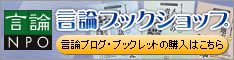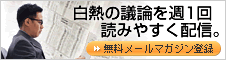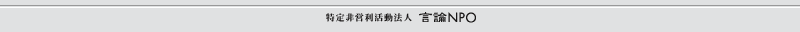2011年5月28日
誰がこの国の政治を変えるのか?
その答えは政治家にではなく代表を選ぶ市民の側にある
阪神大震災と比べ なぜかくも政府の対応が遅れるのか
震災から2ヵ月がたったにもかかわらず、被災地では依然、20万人近い人が実質的な避難生活を余儀なくされている。
政府の取り組みの遅れは、阪神淡路の震災時と比較すると分かりやすい。被害の規模や広がりは異なるが、被災地の「命の救済」という点で、政府に求められる時間は同じなはずだからだ。
政府は被災地の出口として、瓦礫処理や仮設住宅でも8月目処の達成を明らかにしたが、それがそのまま実現するとは現段階では判断できない。
例えば、瓦礫の処理では阪神淡路では2ヵ月時点で約80%が処理されたが、今回はその規模は2倍程度とされており、阪神淡路のときのような埋め立て地もない。このため5月2日時点で岩手が16%、宮城が2%、福島は4%に過ぎない、という。
また仮設住宅も、阪神淡路では2ヵ月後に3分の2は完成していたが、今回は目標の11%程度しか現段階で完成していない。
復興に向けた取り組みも、阪神淡路の際には復興の関連法案が2ヵ月の時点で16本成立しており、プランに基づいて実行する仕組みが具体的に起動している。今回は復旧を主体とした補正予算は成立し、復興構想会議での議論が始まった。
が、それを受けて実行する仕組みが未だ出来ておらず、いまだ復興に向けた動きは議論の段階で事実上停止している。5月13日、国会にようやく提案された復興法案では、実行機関の「復興院」は1年以内に検討、とされている。
先日、石原信雄元官房副長官ら3氏による緊急の公開座談会を行ったが、こうした震災対応の遅れに対して、3氏は口を揃えて「原発の処理に追われたのは分かるが、政治家のパフォーマンスが目立ち方針も決定できず、官僚を使いこなせていない。政府全体の動きになっていない」と、手厳しかった。
被災地では避難の長期化から関連死の増加が続いている。原発処理の先行き不安から人生再建の目処が付かない人も多い。対応の遅れは直接国民の命に関わる問題なのである。
米国の9.11ではブッシュ大統領はテロ攻撃という危機に際して、その解決に強い意志を示すことで、与野党の合意と国民の高い支持を得て、国土安全省まで創設している。政治のトップは最悪の事態を想定し、その解決に責任を果たし、その決意を国民と共有する必要がある。これは人的災害や自然災害でも、危機下では同じはずである。
民主主義が揺らいでいる
その不安感はどこから来ているか
では、日本ではこの2ヵ月あまり、そうした政治の責任あるリーダーシップがあったのか。
政治は一致してこの危機に向かうどころか、民主党は事実上分裂しており、野党の協力も取り付けられない。政権に対する支持は各種世論調査でもそう上がらず、むしろ政権の維持自体が危うくなっている。
なぜ、日本の政治は機能しないのか。今こそ私たちも政治を、自分の問題として考える時期なのではないか。
「日本の民主主義は揺らいでいるのではないか」。今年の初めから、私はこんな議論を言論NPOのウエッブサイトなどで行っている。
なぜ、今民主主義を問うべきなのか。本来、民主主義では、政治は有権者の代表として機能しなくてはならない。だが、政治が今なお行っているのは、選挙に有利かどうかの権力基盤を維持するだけの争いであり、この国の未来を競うものではない。この状況をどうやって変え、日本の政治に新しい変化を起こせるか。
その答えは、もはや政治家にではなく、自分らの代表を選ぶ私たち市民側にある、のではないか、というのが、私の問題意識である。そのためにも、民主主義という問題の基本に立ち戻って考えよう、と思ったのである。口火を切っていただいたのは、元東大総長の佐々木毅学習院大学教授である。
工藤 民主主義というのは人間が本来持っている基本的人権とか平等とかそれに適合する政治の仕組みとして位置付いた。ただそれを機能させるためには様々な知恵が必要で、みんなの意見をそのままの形ではなく「代表」という形で機能させることにした。つまり代表制が機能して結果も出さないとならない。
佐々木 みんなの意見に耳を傾けるべきだと。ただ実際にはそれを絞り込んでいくわけで、代表者を通して政治を行うという代表制民主主義のスタイルが導入されることになる。大統領制や議会制というのはその一つの枠組みとして生み出された。
問題はそういう民主主義を担う国民と、国民に向かい合う政治家集団との間で、この向かい合いがうまくいくのか行かないのか、という点に焦点が絞られてきて、それが民主主義が揺らいでいる、という不安感になっている、日本の場合は政治家や政党自体の機能にも疑問が出され、工藤さんのような問題意識に繋がっている。
工藤 民主主義が機能するということは、社会が直面する様々な課題に成果を出すこと。それができないとすると民主主義のどこに問題があるか、考えなくてはならない。
佐々木 やはり結果を出せないで内閣だけがぐるぐる代わる。これは政治家のための政治。政治家のための政治ゲームとしての民主主義になってしまうと、長期的な視点に基づく施策で結果を出すことは脇の方に追いやられてしまう。
工藤 まさに今の日本がそういう状況。有権者には何が問われるのでしょうか。
佐々木 やはり政治は「未来」から目を背けてはいけない。未来と今の現実から目を背けないということを国民はしっかり見ているのだぞ、ということが強く伝わるような世論を望みたい。
意識は政権交代への期待から
国家危機の段階へと変化
私がこの国の政治の先行きに危機感を覚えたのは、昨年12月末に菅政権の100日時点で行った有識者アンケート結果からである。アンケートには500人が回答したが、今の日本の政治の現状に関して、43.7%もの有識者が、「政治の統治が崩れ、政治が財政破綻や社会保障で課題解決をできないまま混迷を深める国家危機の段階」と回答したのである。
「国家危機」という表現はそう簡単に言える話ではない。だが、こうした認識はこの1年で様変わりしたものだ。このアンケートは毎年行っているが、前年で最も多かったのは、「これまでの政治を一度壊し、新しい国や政府、社会のあり方を模索する時」の40.7%だった。
多くの有識者は政権交代に変化を期待したが、それが失望に代わっていく。その大きな理由は、民主党のマニフェストの実行が崩れ、その統治能力に疑問を感じたからだ。佐々木氏が言う「民主主義に向かい合う国民」と、「国民に向かい合う政治集団、つまり政党」との距離が大きく広がったのは、この頃からだと私は思う。
言論NPOが、政党のマニフェスト(政権公約)や政府の政策の実行の評価を定期的に開始したのは、8年前からである。有権者が自ら政治や政策を判断する。そのための一つの判断材料を提供したい、という思いで30人に近い専門家がこの作業に参加している。
マニフェストとは、選挙の際に政党が国民に提起する約束だが、日本の政治に導入された意味は、国民との約束を軸とした政治を実現するためである。その意味では約束を通じて、国民と政党が繋がることが目的となる。
しかし、評価の際に悩むのは、約束を軸とした政治がなかなか形成されないことだ。そうした政治に最も積極的だったのは、野党時代の民主党だったが、政権を獲った民主党のマニフェストは、今では意味を見いだすのが難しいほど形骸化している。
民主党のマニフェストの評価については、別の機会に譲るが、民主党政権下で政治と国民との距離が広がった理由は、政権交代を果たした際の一昨年の総選挙のマニフェストが、全面的な修正に追い込まれているにもかかわらず、その修正を国民に説明できず、修正をごまかし続けていることが大きい。
私たちの評価では、マニフェスト修正自体を否定していない。ただし、その修正が国民に説明され、新しい約束を設定しない限り、国民との関係は大きく崩れてしまう。
マニフェストで大事なのは、政治はこの国が直面する課題から逃げるわけにはいかない、ということである。超高齢化と人口減少という新しいパラダイムに合わせて、社会保障などの様々な仕組みを組み直すこと、新しい成長を生み出せる経済体質を作り出すこと、そして財政破綻を避けること。この3つがこれまでの政権に問われた課題だが、そのいずれにもまだ日本の政治は答えを出していない。
これらの解決には、国民の負担やサービスのカットが問われる。そのため、民主党のマニフェストでも、この点が明確には触れられない。それどころか、財源が曖昧なままのバラ撒きリストに過ぎず、課題解決を国民に問うよりも、選挙に有利かどうかだけの配慮が優先された。また、こうした政策立案は少数の政治家の間で行われ、党のガバナンスが機能したわけでもない。
さらに言えば政治主導で課題解決を行う力もなく、政治家が官僚の仕事を奪う形で混乱を招いた。
政治主導の柱と位置づけた
国家戦略局を断念
今回の震災復興では、学者などを主体とした復興構想会議の議論が始まったが、同じような会議が官邸に乱立し、個人的なつながりでの参与を多数登用した。同じことが政権では何度も繰り返された。政治家主導では政策決定が機能しないのである。象徴的だったのは、5月11日に政治主導法案を取り下げて、政治主導の柱と位置づけた国家戦略局を断念したことである。ある関係者の見方はかなり厳しい。
「昨年の参議院選の直後にすでに国家戦略室は、戦略の立案の調整はもういいからアドバイスをしてほしいと、みんなが首相に言われている。率直言えば、責任をもって課題を解決する政治家なんていない。それよりも未だに政権維持だけのパフォーマンスに明け暮れている」
菅政権はその後、財政再建などの差し迫った課題に強引に戻されるように舵を切る。財政再建に向けた取り組みやTPP交渉参加の検討や、社会保障と税の一体改革での消費税の増税の問題である。
が、これらも5月17日には、TPPの交渉参加が見送られ、民主党がかねてから主張していた最低保障年金でも増税を想定しなければ、それが適用される所得制限がかなり厳しいことが明らかになり、それを国民に説明できないため、モデルの年金受給者を個人から世帯に変えるなどの操作を行っている。
国民にはそれがマニフェスト修正かどうかは明らかにされない。マニフェスト修正はこれから秋にかけて検討する、という分かりにくい説明が行われたのみである。
いま行われていることが
国民に向かい合う政治なのか
問題は、こうした政治が国民に向かい合う政治なのか、ということである。
こうした政治は、今回の震災の対応でも見え隠れしている。被災地では復興の議論を優先する中央の動きと、意識の差が大きくなっている。多くの人はこれからの人生再建に不安を募らせているからだ。
原発被災で放射能の汚染の予測を国民に明らかにせず、被災地の住民の被爆の状況の検査もしない。海水への放射性物質の放出に際しては、周辺国への影響も調べて公表するなどもしない。私たちに問われているのはこうした政治を、どう変えていくかである。
はっきりしているのは、政治に安易に期待したり、お任せするような状況では、もう直面する課題にこの国の政治は答えを出せない、ということである。むしろ市民こそが、課題に挑み、政治にその解決を迫って行くべきである。それなしにはこの国の政治は変わるまい。
今回の震災は、多くの課題をこの国の政治に突きつけている。被災地の救済と復興、原発政策の見直しや、省エネルギー下での成長戦略の全面見直し。菅政権がここで国民との距離を縮め、合意に基づく政治を復権させるつもりならば、自らが考える復興対策で国民に信を問うべきである。
投稿者 genron-npo : 22:28 | コメント (0) | トラックバック
2011年5月26日
震災から2カ月、見えてきた日本の課題
今回の「工藤泰志 言論のNPO」は、東日本大震災から2ヶ月、日本の課題として見えてきたものとは何か。言論NPOに寄せられたご意見を元に考えました。
(2011年5月25日JFN系列ON THE WAY ジャーナル「言論のNPO」で放送されたものです)
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
震災から2カ月、見えてきた日本の課題
工藤:おはようございます。言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝、様々なジャンルで活躍するパーソナリティが、自分たちの視点で世の中を語る「ON THE WAY ジャーナル」。毎週水曜日は、私、言論NPO代表の工藤泰志が担当します。
さて、先週から、「震災から2カ月、見えてきた日本の課題」と題して、色々議論を始めています。本日は、言論NPOやこの番組に寄せられた声を軸に、これまで震災に対応してきた政府の問題について、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。
東日本大震災から2カ月が経ち、この番組でも様々な議論を行ってきました。
そこで、今一度立ち止まって、議論を総括してみたいと思っています。
ここで考えなければいけない問題が2つあるのですが、1つは政府の取り組みがどうだったのかということです。もう1つは、私たち民間側の取り組みについてです。やはり、政府の取り組みというのは、この非常事態においては決定的な役割を果たすわけですが、この政府の取り組みはかなり遅れていると思っています。これは単なる被災地の状況、復旧とか、被災者のための救済とかだけではなく、中長期的な復興ということを考えた場合、議論自体は4月11日に復興構想会議ができたのですが、それを実行するという仕組みが全くないわけです。そうなってくると、議論は始まっても物事は進まないという状況になっている。
はっきり言うと、復興に対する動きは、実際には止まっていると言わざるを得ない状況です。なぜこのような状況になってしまったのか、ということを僕たちは考えなければいけない事態になっていると思います。
そこで、まず、今の日本の政治がどうなっているのかということを、みなさんに提起したい、1つのテーマなのですね。私たち言論NPOの議論でも、そういう発言が結構寄せられています。今、言論NPOなり、この番組に寄せられている発言が48本もあります。その1本1本がかなり長くて、しかも、専門家からの発言も寄せられています。匿名を希望されている方もいらっしゃるのですが、非常に重要なので、それを紹介しながら、番組を進めて行きたいと思います。
まず、1人目ですが、50代であるシンクタンクの研究員の方からです。今回の政府の対応はどうなのかという質問に対する発言です。
「政府のトップが子どもの使いのようにデータの発表を繰り返しているだけで、今後のロードマップや見通しを示していない。これが国民にとっても海外にとっても、不確実性と不信をかえって高める結果になっている。また、各分野のプロに任せる所は任せて、責任は自ら取るという姿勢が欠如し、ここでも下手な政治主導を演出しようとしたことが、有効な対策を後手に回している。総理が悲壮な顔をして怒鳴りちらしている姿は、一国のリーダーとして疑問である。冷静で落ち着いた姿勢を示す一方で、きちんと国民に語りかける姿勢が不可欠だった」ということをおっしゃっています。
これは皆さんも感じていると思います。その他にも政府の指導性を問う声が結構あります。
「圧倒的な指導力の欠如。変革期には感覚的にも未来が見えること、それをしっかり主張することが大事だが、それが行なわれていない」とか厳しい声ばかりです。
これは佐藤さんと言う方からのご意見ですが、「日産のゴーン社長が被災地を訪れた際のインタビューが示唆的です。それは、4月中に工場の機能を回復し、6月中には通常の生産体制に戻すという内容でした。国民、とくに被災者にとってもっとも重要なことは、この『期間』であり『目安』です」と。これを具体的に政府はきちんと意思決定をして国民に伝えることが重要だったとほとんどの方が言っています。これは何を言っているのか私は考えてみました。
まず日本の政治そのものが何をしなければいけないのかと言うことです。それは官僚も含めて政府の機能をすべて使って、政府として課題解決に答えを出すことが必要です。その課題解決は今の発言にあったように、避難されている方が11万5,000人くらいいらっしゃって、その方々をいつまでに仮設住宅に移して、それだけではなく恒久的な住宅が必要であればそれをどうするかについても、政府が断固たる決意でやります、というのを言わないといけないのです。政府の機能はそういうものだと思います。
だけどその点で見ますと、やはり色々おかしいなあと思うことがありました。例えば、仮設住宅ですが、僕たちもこの番組で早くやらないといけないと何度も言っていましたが、ようやくこの前「お盆までに完成させたい」と菅首相は言っていました。でもこれについて、単に見通しを言ったに過ぎない、という発言もあります。また、よく誰かに「指示をした」と発言しますが、これに非常に違和感があります。「指示した」という言葉の裏側にあるのは「指示したけど官僚が動かなかった」とかという意味なのか。あるいは、首相はよく「見込み」とか言う言葉を使います。必ず逃げを作っています。
しかし、その政策の正面には常に被災者がいるのです。被災者の命の問題があり、そうであれば、そこに対していつまでにこれを解決するとかを明確に示してそれを絶対やりぬくと。それが1つでも成功すれば国民の目は変わると思います。この政府は非常に実行力がある、と。しかし今のところそうなっていない状況があります。
もう1つの機能は、国民に向かい合う。つまり国民の合意の形成をすべきなのです。つまり国民に「私はこういう考え方で、この被災地とか日本の復興を考えるので、皆さんも協力してほしい」と言う形をベースに、みんなで日本の困難に向かい合うといったリーダーシップが必要です。以前佐々木毅さんにこの番組に来ていただいた際に、日本の民主主義について議論をしたことがあるのですが、民主主義と言うのは、一言で言えば「自分たちが代表を出す」と言う行為です。僕たちは政治にお任せするのではなく、自分たちの代わりにきちんとやってくれる人をきちんと選び出す。それが選挙であって、政治家は「我々はこういうことをするので、だから私を支持してほしい」と言うことを伝えることによって有権者とキャッチボールをするのです。その1つの現象がマニフェスト(政権公約)だったのだと思います。約束ですね。しかしこのマニフェストが今どうなっているかといえば、これは改めてこの番組で1回やろうと思っていますが、今だに、復興法案を通すために与野党間でマニフェストを止めるか止めないかとか議論をしていて、非常に違和感があります。
もうすでに民主党のマニフェストは破綻していて、誰もこれが予定通り動くとは思っていない。破綻していると分かっているのに、それを国民に説明できない。菅さん自身がこの前の参院選で衆院選時のマニフェスト自体を否定していたわけですから、このマニフェスト問題で議論しているのは、多分、民主党の中で割れていて、マニフェストを実行すべきだと言う意見とそうでない意見とがあって、もうマニフェストが機能していないのにもかかわらず、党内で政争の具に使われているとしか思えません。
そうであれば今国民に約束することは何なのかと。やはりそれは今回の復旧・復興だと思います。被災者の命を助けて、いつまでに何をどういう形でやるかについて菅さんは命がけでやるべきであり、それを国民にきちんと説明して支持を得ないとならない。
そうした実行と説明があって、政治が機能するということだと思います。でも支持率が下がっています。
ここで皆さんに思い出してほしいのが9.11の時のアメリカとの違いです。ブッシュが前の選挙でどっちが勝ったのか分からなくて、投票として問題があるのではないかとなってもめていたのですが、でも9.11という、これは自然災害ではなく人為的な攻撃の問題なので比べるのもあれですが、でも国が攻撃されたときに、それに対してメッセージを出し、国民に一致団結して、この国を守るための戦いを訴えるのです。それでアフガン戦争に突き進むのですが、しかしその時、与野党、政府の中でみんなを合意させて法案を通し、国土安全保障省まで作って一気に動き出すのです。それで支持率がどんどん回復するのです。つまり危機の時だからこそ、たとえ政党としていろいろあったとしても、みんなを合意させてそれを乗り切ることができたのです。
しかし日本の場合は支持率が低迷して、この前、あるメディアの世論調査を見ていましたが、復興に関して首相に期待が出来ない部分があると出ていました。それであれば、まず政府はこの状況を改善しなければいけない。
自分がこの国を救って、この国をいつまでに立て直したいと言うのであれば、「私はこういう意思でやりたい」と言うのを国民に示して、場合によっては解散して自分の行うことに真意を問う、あるいは解散をいずれ行うことを明示して不退転の決意で難局に取り組むべき局面だと僕は思います。今はこの2つの機能、統治と国民の支持っていうのが非常に欠けているために、強い政治的な求心力を回復できないまま、政治が政局化して復興の動きが動かないのです。この危機下での政治の問題はゆゆしき事態だと思います。
よく「遅れているって言ってもこんな事態なので大変なので仕方ない」という声もありますが、そのようなわけにはいかないと思います。人の命がかかっていますから。
例えば阪神淡路大震災については、規模は今回の震災よりは大きくないのですが、しかし震災から2カ月の間に復興関連の法案も財源もすべて動いていて、もう実際には復興の動きがお金も付いてすでに始まっています。
地域には復興基金ができて、そこの下で被災者支援の動きも始まって、その数ヶ月後には、もうさっきの仮設住宅の建設が終わって被災者みんなの引っ越しが完了していたのです。
今はどういう状況かと言えば、復興関係の法案は何ひとつも通っていない。この前通ったのは復旧関係、仮設住宅やがれき処理などの最低限の復旧関係に4兆円の補正予算が通りましたよね。でもこれは復旧関係の予算です。でも復興の問題と連動しないといけない。しかも東北の場合は、阪神淡路大震災の被災地であった神戸市は140万人がいる大きい都市ですが、東北は人口も少なくかなり弱い自治体が多いのです。しかもそこに多くの被災者を抱えている。その人たちの人生の再建を考え、単なる元に戻すだけではなく、その人たちが誇りを持てるようなことをやらないといけない段階ですが、それも動いていない。
では何が問題なのか?この前この番組で石原信雄さんが言いましたが、「政治主導」というのは官僚を全部使い切って、その上で意思決定をしていくと言うことなのですが、やはりよく見てみると「政治家主導」、政治家として表には出るけど、責任を持って1つのものを動かさない。それは「政治主導」ではなく「政治家主導」になっていて官僚をうまく使い切っていないからなのです。
先週出ていただいた古川さんや、その前にご出演いただいた上先生もおっしゃっていましたが、皆さんも官邸に色んな話を持って行っても全然動かないと言うのです。でも実際問題、色んな人たちが困っているので何かをしなければいけないということで、自分の個人的な繋がりを使って政治家に頼みに行ったりして民間は色んな形で動いているのです。しかし政府の統治の問題は、それで済む問題なのでしょうか。原発の問題でこの前もありましたが、住民の健康問題や汚染の問題であれば適切な情報を一刻も早く提供しなければいけなかったし、当時色んな情報が政府にあったはずなのですが、なかなか公開しなかった。そのために後から謝罪しましたが、放射能汚染が日々刻々と風向きで動いていて、そのデータを持っているにも関わらず公開しませんでした。
住民の被ばくのモニタリングもすべきだし、海に汚染水を流しましたが、これはやはり国を超えて被害になるわけだから各国政府に伝えるべきだったのに、伝えなかったし。また、各国から支援がたくさん来た時に受け入れきれないから止めたりしていました。
だから容量がいっぱい、いっぱいになっちゃって、なかなか動けない状況なのです。でも官僚を使うよりも何となく自分の知り合いの学者さんを集めてやっている状況なのです。これを政治のあり方としてどう考えるべきなのか、ということです。
また復興の問題に関しては発言でもたくさん来ていまして、「やはり被災地が復興の中心になるべきだ」と言う声が多いのです。では政府は何をすべきなのか。それは被災地の復興のプランとか、まあそれはまとめ上げて政府が考えてもいいのですが、あくまでも政府がすべきなのはそれを実行することなのです。
阪神淡路大震災の時は、復興委員会が出来たのですが、その時には同時に各省庁の連絡会議が出来て、その官僚統合の仕組みが全部できていて、被災地の兵庫県でも復興の委員会が出来ていて、そこでは復興のプランが始まっているのです。すべてが動いて政府は実行のために制度や法案を変え、お金をそこに付けることに最優先で取り組んだのです。だから動いた。
四川大地震、中国なので国が違うのですが、あれは3年でやるという復興プランを前倒しして2年で進めて、もうこの政治的なリーダーシップはすさまじいのです。まあそれは政治的な体制の違いがあるのであれですが、他の例では政府は実行にこそ責任を持つという状況なのです。
こういう発言がありました。前々回の上先生の時に、被災地の病気の方を首都圏に連れてきた、医師が自発的に取り組んだのですが、その時に受け入れに動いたのが千葉県鴨川の亀田病院でした。その亀田病院の方からの発言です。「被災地の救済と復興を目指して、様々な活動が繰り広げられている。亀田総合病院もそのような形で動いてきたけど、その中で民間の公益活動、つまり民による公が重要だと言う認識が強くなった。その人たちが目の前に広がる現実をよく認識して、少しでも早く実行し、事態を好転させるためにどうすればいいかと迫力が違っていた」と。「政府の行政機能は遅れていたが、民間の個人のネットワークはかなり動いていた」と言っています。やはり政府が動かない中で、民間がやるべきだと言う声が出てきています。こういう事態を2カ月経って、僕たちはどういう風に考えるかが今回の提案です。僕の答えは、やはり公共や公は政府が担うものと民間が担うものがあるのだと思います。政府がやることを民間が補完するだけではなく、民間、市民が自発的に課題解決に取り組む社会が僕は理想だと思います。
それくらいの強い市民社会をつくるべきだと僕は思います。そういう強い市民社会ができることによって政府が機能していない点に関して強烈な牽制力になるのだと思います。そういうプレッシャーがかかることよって日本の政治が強いものになっていくと思います。ということで、今2カ月経ってみて、浮き彫りになっている政府の統治の問題、そして民間側の問題を僕なりにまとめてみました。一回改めて皆さんも考えてみてはいかがでしょうか。
僕は今回の震災復興を契機にしてパラダイムを変えないといけないのだと思います。つまり市民目線で全てを考えることです。原発でも市民に情報は提供すると不安を招いてしまうとかいうのでは駄目で、徹底的に市民に判断材料を提供して市民が考えていく動きをエンカレッジしていくような仕組みや社会が必要だと思います。さて皆さんはどう考えますでしょうか。
次回からもこの市民目線で、様々な問題を皆さんと考えていきたいと思います。今日はありがとうございます。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
投稿者 genron-npo : 06:52 | コメント (0) | トラックバック
2011年5月 2日
震災支援、善意とニーズがなぜ繋がらないのか
政府の限界を乗り越える市民の「課題解決」能力
私が「市民の力」を初めて感じたのは、1995年の阪神淡路の大震災の時である。
ビルが倒壊し黒煙が上がり続けるテレビ映像に釘付けになっていた私に、一通のメールが届いたのだ。
「今日の夜、みんなで集まりませんか」
そのころ、参加していたウェブ上の会議室の仲間からだった。まだ現場では震災の救済が始まったばかりの、震災当日(1月17日)のことである。
この仮想の会議室は匿名参加のため、誰が参加しているのか他の人には分からない。の喫茶店に行くと、弁護士や学者、ジャーナリスト、大手建設会社の役員もいる。その顔ぶれには驚いたが、もっと驚いたのは、この時初めて顔を合わせたはずなのに、簡単な議論で、倒壊したマンションの権利調整のためのマンション区分法(建物の区分所有等に関する法律)の改正案をみんなでまとめることになったことである。
そして、3月には「被災マンション法(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)」が施行される。この夜の取り組みが法案制定にどう繋がったのか、詳しくフォーローしていないが、ただ、多くの人が自発的に課題に一緒に取り組み、解決を目指した。
新しい変化、を感じたのは 私だけではなかったはずだ。
それから6年後の2001年。私はそれまで勤めていた出版社を辞め、言論NPOというNPO(非営利組織)を立ち上げた。非営利の世界で言論を行うという試みを決意したのも、もとはといえばその夜の強烈な体験がある。
課題解決に市民が組織を越えて向かい合う。そのための、議論の舞台を作ろうと考えたのである。
私がここで言う「市民の力」とは、市民が、自発的に社会の課題に向かい合う力である。こうした力は、震災などの大災害の緊急対応の際に大きな役割を発揮する。
だが、本来こうした力は、危機の際だけではなく、知識社会に共通した現象だと、あのピーター・ドラッカーは早くから指摘している。
『未来の決断』で彼が指摘した「漂流する知識ワーカー」には、組織から離れて自分の専門的な技能や知識で課題に向かい合おうとする労働者の存在がある。
多くの労働者は組織に忠誠心を持つよりも、自分の能力を生かそうとし、その場を探し求める。そうした知識ワーカーを社会に繋げることが、非営利組織の役割だ、というのである。
職場を越えて社会の課題に向かい合う。こうした当事者意識を持った市民の参加が、非営利の世界に地殻変動をもたらす力になり始めていたのである。
東日本大震災は被害の規模や広がり、そして原発の問題で過去に例にないほど深刻で複雑なものである。
過疎と高齢化が進んでいた東北地域の救済と復興は、私たちのこれからの人生に重なり合うほどに長期化するだろう。しかも原発の被害は、全国の活断層上の原発の安全性とこの国のエネルギーのあり方の全面的な見直しを迫っている。
でもそれ以上に深刻だ、と私が思うのは、この国の政府という統治が機能しない、ということ。こうした統治のもろさは今、分かったわけではない。長い間、この国の未来に向けた課題解決を避け、自分の権力基盤だけを争っていた政治自体が、この有事の際に機能を発揮できず混乱を深めている。
私が今回の東日本大震災で注視しているのは、「市民の力」が、どうしたら「本当の力」になり得えるか、ということである。
被災地の救済という課題から見ればそれ自体まだ十分なものではない。しかし、課題に向かい合う多くの市民の支援は広がり、救済に向けて具体的な行動が様々な形で動いている。
私が、こうした「市民の力」に期待するのは、課題に立ち向かう市民のエネルギーこそが、課題解決に答えを出せない、この国の政治自体を変える契機になると思うからだ。その力は、私があの阪神淡路大震災の夜に感じた以上に、高まっている。
では、こうした「市民の力」が今回の震災の緊急対応にどう生かされたのか。
私が痛感したのは、これまで通りの行政主体の論理と、市民の自発的な取り組みという新しい変化が被災地の現場でぶつかっていた、ということだ。
災害時の緊急対応を主導すべきなのは、政府や行政である。自衛隊の緊急救助の投入は人命救済に不可欠の役割を果たした。
今回の震災では幾つかの地域で役場ごと津波で流され、行政の機能は麻痺した。
震災時の初動の対応が遅れたのは、被災者救済の受け皿になるべき拠点を構築できなかったことも大きい。
そうであるならば被災者の命の救済のため、まず政府は行政の機能を復活させるために人員を投入し、さらに市民の自発的な取り組みを何よりも生かさなくてはならなかった。
次第に明らかになり始めたが、震災直後からの1週間、被災地では、医療関係者たちの必死の取り組みがあった。
現時点での死亡判明は1万4000人。岩手、宮城、福島3県の検死の結果、9割が津波での水死だが、この1週間、現地の医療機関や医師や、全国から入ったボランティアの医療チームにとっては1秒を争う「時間との戦い」だった。
救助された被災者の蘇生等の緊急治療、孤立した病院からの搬送や避難所での対応が、「命の救助」の最大の課題となった。
全国からは、DMAT(災害派遣チーム)やそれぞれの医療組織から1万人を越すボランティアが現地入りしたという。だが、私が聞いているところではまさに「綱渡り」である。
多くの医師は、「政府や行政も力にならない。あとは自分達でやるしかなかった」と口を揃える。蘇生や避難時の骨折、打撲だけでなく、高齢者の多い東北では糖尿病などの慢性疾患の対応も急務となった。不足した大量の薬は融通し合ったり、人工透析は1週間以上途絶えることはできないため、地元で対応できない患者は他に移すしかない。
医師の個人的なツテで全国に呼びかけ、それに呼応してバスの手配や首都圏の病院とのマッチングや病院に輸送する人も現れた。つながりを生かした多くのドラマが始まる。そこに見られたのは紛れもない自発的な「市民の力」だった。
ただ、こうした取り組みは順調に進んだわけではない。様々な分野で立ちふさがったのは 政府や行政の壁であり、それが救助の障害になっていた。行政の規制もその1つである。
被災地では津波で薬が消失し、在庫が払底したことが東大医科学研究所の上昌広特任教授らが行っている医療メールマガジン上で報告された。大学病院等の基幹病院が薬を購入し、分配しようとしたが、これは「授与の目的で貯蔵する」ことになり薬事法で違反になる。規制が緩和されたのは震災後から1週間後だったという。
このほかにも不足したガソリンを公平に分配するため、給油制限は行われたが、それを受けるためには緊急車両に認定される必要がある。その認定に時間がかかり、病人の緊急搬送や現地入りする支援側の移動にも障害がでていた。平時の規制が有事の際にも残り、それを変える政治側のリーダ-シップもなかった。
行政の壁にぶつかった医師は、「官邸に話をあげても全く動かない。知り合いの政治家に頼んだり、個人で対応するしかなかった」という。
震災対応で最も大事な課題は、被災者の命を救い、その後の人生再建の道筋を付けることである。そのためには被災地は一刻の時間の猶予も許されない状況にある。
この膨大な作業は、政府や行政だけで対応できるものではない。にもかかわらず、なぜ行政の壁が問題になるのか。
被災地の支援対応の機能は官邸にある。その司令塔がなかなか機能せず、全体像や工程が描けていない。それが緊急時の初動を遅らせ、自発的な市民の緊急支援を生かせなかった。
ただ私にはその背後に、行政側と被災地に根強いお上意識があるように思えてならない。行政はその受け皿の能力不足から、市民等の広範な支援の動きを管理しようとし、被災地側の一部にも行政の支援しか安心できないという意識がある。
被災地は見も知らぬ市民からの支援を受け入れることには不慣れである。戸惑うことは分かるが、行政側の対応は内向き過ぎる。
仮設住宅建設の遅れの中で避難の長期化が続いている。寝たきりになったり、肺炎や感染症を繰り返す高齢者も出始めた。自宅に帰った被災者も余震が続き、衛生状態が悪い環境下で、人生の再建は容易ではない。
その人たちの一人ひとりの人生再建に寄り添うケアや避難所での介護、そしてがれきの処理や家の泥だし、水に濡れた畳の運び出しなど、長期的で圧倒的な支援が必要とされているのである。そのためにも支援の輪は被災地に繋がなくてはならない。
先日、昼食を共にしたあるアジアの大使は「余り言いたくない話」だが、と断りながらもこう話してくれた。「震災翌日には我が国の空港に100人の専門の救助チームが離陸準備の態勢だったが、日本政府からは連絡がなかなか入らない。最終的に10人程度まで絞ってくれと言われた。支援物資も日本に運ぶまでかなりの時間を要した。なぜこんなにまで閉鎖的なのか」
私も意外に思ったのは、支援物資が足りないと言われながら、支援物質は倉庫に山積みされたまま、それが被災者に届かないという話をNGOに聞いた時だ。配分方法がなかなか決まらなかった被災地への義援金(見舞金)も同じである。被災者の罹災証明などその確定にも時間がかかるという。
ここで問われたのは、公平と時間の問題である。行政の支援は公平や平等が前提となるが、ボランティアはあくまでも自発的で一人ひとりの被災者に寄り添うことが基本となる。公平な支援は大切だが、それにこだわり続ける限り、その枠組み作りに時間がかかり、緊急時には機能しにくい。また、被災者の一人ひとりに寄り添うサービスは行政で提供できない。
今回の震災で、問われたのは「課題解決の力」である。政府が司令塔の役割を果たせなかったことは、震災から2カ月近く経った今もなお、被災地や被災者の再建の目処や出口が全く見えない状態に現れている。
震災1カ月後の4月11日、東北地域の復興プランを立案する復興構想会議が発足して議論が始まった。が、その実行体制や復興関連法案の提出すら、目処が立たない事態となっている。こうした危機対応の力のなさが、政権自体への批判の声に繋がり、政権自体がこのまま持つのかどうかの段階になっている。
日本の政治は、2つの点で危機的な段階にあると私は思っている。直面する課題に回答を出せないこと、そして政治家主導の限界から政府自体が統治の機能を失い始めていることだ。こうした政治の危機は今に始まったことではない。これまで未来を競えず、選挙での当落だけを考えた政治自体の限界が、取り返しの付かない状況にきたということだ。
ここで考えなくてはならないことは、こうした政治を選んだのは、私たち自身だということ。安易に政治を選ぶことの怖さを実感した人もいるだろう。逆に言えば私たちの一票でこの国を壊すも立て直すこともできる。
もう1つ直視すべきことは、震災で見られた市民の連帯のエネルギーである。被災地の救済に対して多くの人が痛みを共感し、被災者を救うために多くの人が力を合わせ、課題解決に向かい合った。問題はこの「市民の力」をこの国の未来に向かう変化につなげられるのか、である。
震災の被害は原発の放射性物質の汚染流出も含めて現在進行形である。私たちが直面している課題は被災者の救助や東北の未来に向けた振興だけでなく、日本自体の「復興」である。そこでは、政治の立て直しや、そうした政治を作り出す民主主義のあり方まで多くの解決が求められている。
未来に向かうため作業は多くの分野で始まるだろう。私は、「議論の力」でその役割を果たしたい、と思っている。