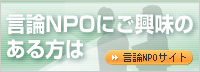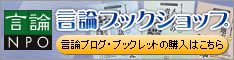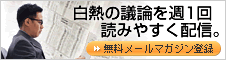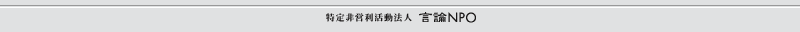2011年4月22日
なぜウェブサイトを全面リニューアルしたのか ― 言論NPOの10年目の覚悟
言論NPOは、2011年11月に設立10周年を迎えます。この間、言論NPOは、「健全な社会には健全な言論が不可欠」との立場から、『議論の力』でこの国の民主主義をより強いものにするため、この国が直面する課題解決や政府の政策実行やマニフェスト評価、そしてアジアとの民間対話に取り組んできました。
私たちはこの10年目を迎えるにあたり、「新しい覚悟」で日本の未来に向けた議論づくりに取り組むつもりです。私が「新しい覚悟」と申し上げたのは、未曾有の大震災を受けて、この国は被災地の救済から復興にかけ、待ったなしの困難な取り組みに直面しているからです。このプロセスは、被災地の問題にとどまらず、これまで様々な課題解決を先送りしてきた、日本自体の未来をかけた「復興」だと考えております。
この困難の中で私たちは二つのことを発見しました。一つは多くの市民の連帯感や支援の大きさです。一人ひとりの市民によるこうした行動は、この国の困難や未来に対する市民の覚悟の現れだと私は思います。一方で、この危機の局面にあっても、政治がそれに十分に対応できないという、統治の脆弱性も思い知らされました。
この二つの発見は、いまこそがこの国の未来をかけた正念場だということを、意味しています。政治を安易に選んでしまうことの怖さ、そしてこの苦難に多くの国民がそれぞれの立場で真剣に立ち向かっていること。私はそこにこの国が未来に向かって大きく変わる可能性を強く感じます。そのためにも、私たち自身はここでそれぞれの覚悟を固めなくてはならないと思うのです。
言論NPOにとっての10年目は、まさにこの国が未来に向かう起点であり、私たちは『議論の力』でその役割を果たそうと考えているのです。
私たちが、ウェブサイトを全面的にリニューアルしたのは、日本の「復興」にむけて今こそが最後の局面という、強い思いがあるからです。政府の取り組みを厳しく監視するだけではなく、この国が直面する課題の解決策をみんなで考え、その答えを出さないといけない。議論の中から、この国を変える大きな変化を起こしたい。そのためにも、いま、議論を始めなくては、と考えたのです。
私たちが目指しているのは、当事者としての自覚をもった「強い市民社会」の形成であり、当事者意識を持った「強い民主主義」の実現です。そのためにも、言論NPOはこの日本の「復興」に真剣に向かい合い、この状況を乗り越える議論を提起し、また、日本が抱える様々な課題解決ためにみんなで一緒に考える、議論のプラットフォームとしての役割を、より一層全力で果たしていく覚悟です。
私たちのこうした覚悟や取り組みにご理解をいただき、ぜひ私たちの取り組みにご支援、ご参加いただきますよう、お願いいたします。
投稿者 genron-npo : 08:26 | コメント (0) | トラックバック
政府の「復興構想会議」に異議あり 2011.4.27 放送
今回の「工藤泰志 言論のNPO」は、阪神大震災当時に内閣官房副長官として政府の取り組みに関わった石原信雄さんにインタビュー。震災復興への取り組み方などについて、阪神大震災との比較などを踏まえてお送りします。なお、インタビューは4月13日に行われました。
(2011年4月27日JFN系列ON THE WAY ジャーナル「言論のNPO」で放送されたものです)
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
政府の「復興構想会議」に異議あり
工藤: おはようございます。言論NPO代表の工藤泰志です。毎朝様々なジャンルで活躍するパーソナリティが自分たちの視点で世の中を語るON THE WAYジャーナル。毎週水曜日は「言論のNPO」と題して、私工藤泰志が担当します。
さて、先週は東日本大震災後の復興について3人の座談会をお送りしました。ここで非常に大きな論点になったのは、この復興計画というのを誰が作り、誰が担うのか。そのとき地域の意志は関係ないのか、ということでした。というのは、政府が、今進めている復興構想会議には、東北の知事も入っていますが、学者さん達がアイデアを出すという、あくまでも国レベルで考えるという状況になっています。このあたりが、非常におかしいなと思ったわけです。 今回インタビューしてきた方は、阪神淡路大震災のときに内閣官房副長官で、今は地方自治研究機構の会長をしていらっしゃる石原信雄さんです。このインタビューの前に、簡単に一言言わせてもらいます。阪神淡路大震災と、今回の東日本大震災の取り組みの点で比較して考えることが大事なのですが、決定的に違うことがありました。それは、阪神淡路大震災の時の復興は、まず被災地、つまり地元の兵庫県が主体となって復興計画を作成して、それを国が最大限支援するという態勢をとりました。その為に、政府の中に有識者会議があり、閣僚会議つまり政府の対策会議があり、その下にその全省庁をつなぐ省庁連絡会議がありました。これらは、全て一体として設計され、一気に国と地方が連携して、速やかにプランを作りそれを動かすという体制ができました。さて、今回は、まだその実行体制の全体像が、なかなか固まらない。国と地方の連携も決まらない、という状況が今あるわけです。これらの問題について、石原さんはどう考えているか、まずここからずばり聞いてみたいと思います。
メンバーは学者ばかりで実務家がいない
石原: 今回は復興構想会議の立ち上げも遅く、メンバーが学者ばかりで実務家が1人もいません。これは驚くべきことですね。実務が分かる人がいないで、夢のような話をしても実際の計画に反映するのは大変です。
工藤:政府は、いつまでに復興プランを。
石原:6月までだと言っていますね。
工藤:それは、会議の案でしょ。青写真。
石原:それは、大きなグランドデザインのことを意味しているのでしょう。それを受けて実行計画を作らないといけません。それを実行に移すためには、裏付けとして法律が必要です。どういう法案がいるのかは、皆目わかりませんが、これから議論するのでしょう。阪神大震災の時(1月17日)には2月28日には、財政特例法をはじめ16本の特例法がすべて上がっています。
工藤:それはどこが作ったのですか。
政府の対応は明らかに遅い
石原:政府です。復興委員会の意見などを踏まえながら、政府がどんどん特例法を作っていきました。それは大きな復興ビジョンに関しては復興ビジョンとして議論してもらって、それの裏付けとなる予算はまた別です。当面必要な法律はどんどんやっています。今回もいくつか上げていますが、あの時と比べてまだまだ少ないですね。
工藤:昔、何本って言いました。
石原: 6本です。
工藤:今も、何か案ができていますよね。
石原:税制上の特例など、幾つか今上がったものもあります。だけど、あの時のように当面必要とする法律が整備されていないので、明らかに今回は対応が遅いですね。
工藤:これは、どういう所に原因があるのでしょうか。
石原:1つは、今回の災害は非常に範囲が広いのが原因です。青森から千葉まで関係県が6県もあります。そして災害の内容も千差万別。それから、何よりも福島県の場合は、原子力災害をどうするかが大問題です。これは異質の問題です。政府はこれに相当なエネルギーをとられていますので、全体の復興計画がどうしても遅れがちです。遅れている最大の理由は、原子力発電所の事故の対応に追われている点だと思います。
工藤:復興構想会議が学者だらけになっているのは、実際に機能させるという仕組みよりも、アイデアだけ欲しいという考え方ですよね。
石原:そうなのです。今度の復興構想会議は「構想」を示してほしいだけなのです。大まかな方向性やビジョンを出してください、それを出していただければ政府の責任で具体的な計画を作ります、という建前になっています。復興構想会議が色々な分野で、どこまで具体的に掘り下げた議論をするか、まだよくわかりません。もし、掘り下げた議論をするのであれば、専門分科会を作らないといけない。
工藤:昔、石原さんが官房副長官をしていたときは、先ほどの復興委員会と復興対策本部、そして省庁の連絡会議がありましたね。
石原:各省庁の実務担当者を全部つけました。復興会議で大きな方向を決めて、それで対策本部に閣僚は入っていて、その下にそれをサポートする事務次官以下の事務組織が直結していました。なので、直ぐに執行できました。
阪神淡路の際は実行体制も同時にできていた
工藤:昔は復興委員会をベースにした復興の執行体制がすべて決定した上で復興委員会が始まっているわけですね。
石原:執行体制も同時平行で出来ていました。あとは復興委員会の方で意見が出たのを、直ぐに復興対策本部が受け取って実施計画に反映させました。僕は復興構想会議を作ったときに、同時に対策本部を作るべきだったと思います。どうせ各省の大臣は入るのですから。その下の事務方の連携体制ですね。復興対策本部は、それ以下の本部ができたらそれをサポートする各省の事務体制を同時に作らないといけない。実務家がはいらないと計画はできないです。
工藤:この政府の復興に対する取組みでは、関東大震災時の復興委員をつくるとか、色々なアイデアが出ましたが、そこに貫かれているのは政府主導という考え方なのですね。ただ、これだけでいいのだろうか、地域の意思がどこに反映されるのか、というのが僕の疑問です。これを次に聞いてみたいと思います。
復興院は戦前の内務省時代の発想
石原:後藤新平がやったような復興院を作れとの意見がありますが、あれは戦前の内務省全盛期の中央主権体制の下で、直轄で地方の事業を内務省がやったわけです。今は地方分権の時代なので無理です。今は都道府県知事がやるのです。関東大震災の時は、復興院が実施部隊でした。それは戦前だから出来ました。当時は、都道府県知事だって内務大臣が任命していた時代ですから。今は選挙で知事を選んでやっていますので、東京都知事をあごで動かすわけにはいかないのですよ。都道府県知事は、都道府県民が選んだ、独立性のある組織ですよね。これが実施機関ですから。そこに対して政府は方針を示して、福島県なら福島県の復興計画を作る。それは政府の方針と整合させないといけないから。県の計画をつくるための前提となる復興計画をつくるということであって、実施部隊を東京に作るのはナンセンスなんですよ。いま復興構想というのは、後藤新平がやったことをやらせようというのは、都道府県知事はどうなるの、ということなのですよ。
今の組織と戦前の組織の根本的な違いをご存じないのですよ。戦前は中央集権体制なのですから。何でも中央政府が直轄で仕事できたんです。今はできませんよ。直轄事業はごく限られているので。漁港の復興とか町の復興は県知事なんですよ。
地方の立案を政府がバックアップする
工藤:今の話が非常に重要なんですが、昔の文献を見てみますと、やはり兵庫県がかなり、国内の英知を集めた復興委員会をつくるんですよ。そこの中でまず復興のビジョンをつくり計画を作り、県民の意見を聞いたり、すごい努力して案を作って、それを復興委員会は認めると。認めて、それを政府の支援の枠組みを決めてやりますと。そこに法律とか財源の問題とかやってフォローした。だから、地方分権ベースに地方の立案づくりを政府がバックアップすることで実行性を高めたと。
石原:そのとおり。今日私が申し上げたのは、政府がやることは、所詮実施機関は都道府県なんだから、都道府県に人が足りなければ出して、都道府県の体制を強化しなさいと。お金がなければ実施事業である都道府県の財源をきちっと面倒みなさいと。それが復興の一番の早道だと。復興院をつくって、国が直接やるようなイメージは混乱のもとだと。
工藤:誰か歴史の認識を間違ったんですかね。
石原:いま後藤新平がやってもできないんですよ。今の憲法体制では。地方分権ですから
工藤:すると例えば、なぜ地方にビジョンとか計画づくりを頑張れと、政府はそれを実行すると、それを復興という特別な法体系もきちっと考え、未来に向けていろんな意見をいうかもしれないけど、地域が主体なんだと、地方分権なんだと、なぜ今の政権は言わないんですかね。
石原:宮城県はすでに計画を作り始めていますよ。でも彼らは、自分のところでこういう計画をつくりますと、発表すると思うんですよ。そうしたら、復興構想会議では、その構想に対してこういう点があったらいいんじゃないかとかなんかいって、県の計画の最終決定の参考になるようなことを復興構想会議がいうということが、現実的なんですよ。そう運用されることを願ってますけど。
工藤:僕は青森なんですが、東北の皆さんが自分たちの未来に対して責任を持ったり誇りを持てない計画は、東北を発展できないじゃないですか
東北復興庁は出先機関なら意味はない
石原:僕が心配しているのは、一部の人達が、東北復興庁を作れといっている。これは、私は、復興庁が、宮城県や青森県の権限をとって代行するんですかということですよ。これは、北海道開発庁というものがあるでしょう。今度、東北復興庁をつくるというのであれば、第二の北海道開発庁を創るんですねということです。
工藤:道州制の一歩にするというのもありますがそれでもだめですかね。
石原:道州制は私は賛成ですけど、そこまでの覚悟があるのであればです。道州制の予行演習をやると。将来はそこをベースにして東北地方を創るというのは、一つのやり方ですよ。どうも東北復興庁というのは国の官庁の一つとして北海道開発庁みたいなのをつくるというイメージなんですよ。そうするとその実態は県の権限になっているものの一部を国の官庁にもう一回取り上げる、取り戻すと。国交省は喜びますよ。
工藤:つまり、出先機関ではダメということでしょ。
石原:国の出先機関としてつくるなら私はつくらないほうがいい。将来の東北地方の、道州制の先取りだというのなら、私は賛成。
工藤:でもその覚悟が感じられないということですね
石原:民主党は道州制の議論全くやっていません。反対とも言わないけどやるとも言っていない。
工藤:ただ僕は思うんですが、彼らたちが夢を語ったとしても、実際の県民が納得しない限り、自分たちが作ろうとしない限り無理ですよね。
石原:県民が納得しないような夢のような話ではダメですよ。東北の人たちはそうでなくても厳しい現実に直面しているんだから。
工藤:昔の阪神淡路の時は、昔はビジョンづくりは兵庫県なんですよ。それで、政府の委員会は、復興対策の国の支援をどういうふうな枠組みでやって行くかとか、そう言うのを提案しているんですよ。
民主党政権には地域主権の覚悟がない
石原:ベースは県の具体的な案がベスト。それを追認したわけですよ。かつ、必要な立法措置をし、必要な予算措置も講じた。あれが一番いいのですよ。
工藤:それが地方分権、主権という考え方ですよね。
石原:今の基本的な流れに合う。だって民主党は地域主権ということをマニフェストでも言っていた。
工藤:なぜそれが、今回は見えないのでしょうか。
石原:民主党の地域主権改革はどこ行ったのということになっちゃいますよね。私申し上げたのは、大事なことは、実施部隊は県ですよ、中央の省庁ではないですよ。県の実施計画をいかにバックアップするかということが、復興構想会議の役割ですよと。
工藤:地域には未来に対する提案力はないとみているんですかね、東北は。
石原:一部の文化人は、地方にはそれだけの人材はいない、地方の将来のビジョンを描けるような人材はいない。だから我々がビジョンを描いてやるのだと、そういう思いがある。口には出さないけれど。
工藤:それをなにくそと地域には考えて欲しいですね。
石原:私は大いにビジョンを、将来に住民希望を持てるビジョンを示すということは必要なことです。ただし、それを具体化するのは県ですから、県の意見をよく聞く。それから、県の計画の中身というのは漁港どうするか、道路どうするか、河川どうするか、港湾どうするかという話なのですから、そちらの方の専門家、責任者、具体的には担当の具体的には役人の意見を聞かないと、本当にいい計画はできませんよと言っているんです。
今のような政治家主導では実行は無理
工藤:すると、石原さんがおっしゃる将来に向かいあうようなプランを実行するためには、今の政府が進めている枠組みでは、難しいと思っていますか。やはり足りないと思いますか。
石原:私は、今のように政治主導で官僚組織を分離していたのでは、できませんよ。まず、官僚を取り込まないといけませんよ。復興計画づくりの際に、実務家、官僚組織をフルに組み込まなければいけないのですよ。
工藤:後、もう一つは地域の力を信頼しないといけないということですよね。
石原:その通り。だから、私は各省の役人を事実上宮城県なり岩手県にどんどん派遣して、向こうで計画をつくればいいのですから。要するに、宮城県に行ってつくれば民主党の政治主導の影響を受けないのですよ。自由に、彼らの意見が通るのですよ、地方に行けば。中央は、全部政務三役経由ですから、彼らの意見がすぐには上がっていかないのですよ。
石原:私は、学者を集めるのはいいけど、大きなビジョンの議論をするのはいいけれど、そこで実施計画をつくるのは無理です。本来、そういう対象になっていないのですから。実施計画をつくるのは県なのですよ。だから、実施計画をつくるところに、国の色々な技術者などをどんどん応援に行かせればいいではないかと。
地域が未来に責任を持つ流れこそ大事
工藤:かなり厳しい議論になったのですが、やっぱり考えないといけないのは、今回の事態というのは、現状に戻すとう復旧だけではなくて、新しく東北が未来に向けて自立するようなきっかけ、スタートにしなければいけないということです。そのためには、やっぱり、色々なアイデアは必要だけれども、地域の人たちが責任を持つという流れができていかないとだめだと思います。この「復興」の動きに関しては、言論NPOもそうですし、このON THE WAYジャーナルでも、何回もこれから議論していこうと思っています。そして、皆さんの意見も聞きながら、今回の緊急避難から始まって、今度は復興に向けて大きな議論をつくっていきたいと思っていますので、ぜひ皆さんも協力していただければと思っています。
(文章・動画は収録内容を一部編集したものです。)
投稿者 genron-npo : 08:14 | コメント (0) | トラックバック
2011年4月 8日
「約一カ月で見えてきた、被災地支援の課題」2011.4.6 放送
今回の「工藤泰志 言論のNPO」は、スタジオにボランティア組織の代表3人(ワールドビジョンジャパン・片山信彦氏、難民を助ける会・堀江良彰氏、シャンティ国際ボランティア会・関尚士氏)をお迎えして、3月11日に発生した東北関東大震災を受けて、現状報告と今後市民が出来ることはなにか考えました。なお、この放送は3月30日に収録いたしました。(JFN系列「ON THE WAY ジャーナル『言論のNPO』」で4月6日に放送されたものです)
ラジオ放送の詳細は、こちらをご覧ください。
 |
「ON THE WAY ジャーナル
|
「約一カ月で見えてきた、被災地支援の課題」
工藤:おはようございます。ON THE WAYジャーナル水曜日、言論NPO代表の工藤泰志です。さて、この番組が放送される4月6日は、震災の発生から20日を超えています。現地では、被災者の救済、支援が懸命に行われていると思います。ただ、割り切れない思いになるのは、色々な支援が動いているのですが、この支援がどの段階にきていて、いつになったら出口が見えてくるのか、ということがなかなかわからない。僕が分からないということは、現地の人は全然わからない、非常に不安なのではないかと思います。そこで、ON THE WAYジャーナルでは、一度このタイミングで、今の状況がどうなっているか、ということを冷静に総括した上で、本当に今必要なのはなんなのか、その出口に向かって、どのように動けばいいのかということを、みんなで考えてみたいと思っています。今日は、日本を代表するNGOの方々にスタジオに来ていただいています。彼らは、既に被災地に支援に入っていらっしゃったりして、現地の色々な状況を見てこられています。その人達の話を伺いながら、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。
ON THE WAYジャーナル「言論のNPO」。さて、今日はスタジオに、被災地に行って支援活動を行っている、国内を代表するNGOの代表方3人に来ていただきました。
まずは、ワールドビジョン・ジャパンの片山信彦さんです。よろしくお願いします。
国内の3つのNGOの代表が見た被災地の課題
片山:よろしくお願いします。
工藤:そして、この前も来ていただいたのですが、難民を助ける会の堀江良彰さんです。よろしくお願いします。
堀江:よろしくお願いします。
工藤:そして、シャンティ国際ボランティア会の関尚士さんです。よろしくお願いします。
関:よろしくお願いします。
工藤:みなさん、今日はよろしくお願いします。ということで、今日はNGOのみなさんをお迎えして、「被災地のために、今、何が必要なのか」ということを、みなさんと考えていきたいと思います。早速ですが、みなさん被災地に行き、色々な被災の状況を把握していると思うのですが、この20日余りで、被災地の状況がどのように変わってきたのか、また、今どこに問題があるのか、ということについてお話を伺いたいのですが、片山さん、いかがでしょうか。
片山:そうですね、やはり最初の段階は、人命の救助と安否確認です。まだ、安否確認は続いていますが、人の命に関わることが最優先です。その次のフェーズには、助かった方々を、いかにケアするかという意味で、食料や水など救援物資を送ることが必要です。その物資も、初期の頃と最近とでは、かなりニーズが違ってきていて、初期の頃は、水や食べ物が必要で、パンでもおにぎりでもあれば、みなさん喜んでいたのですが、今となってはそれ以外のもの、例えば温かいものが食べたい、などの声が沢山出てきています。それから、着るものについても、みなさん着の身着のままできていますから、下着とか着替えが欲しいとか、ニーズはどんどん変わってきています。それから、既に始まっていますが、次のフェーズが仮設住宅とか、少し安定した場所に一次的に住んでいただけるようなフェーズ、つまり、復興に向かうようなフェーズですね。それが終わると、本当の意味でのまちづくりにいける、こういう風になっていくと思います。
工藤:僕たちも番組をやっていたら、いろいろメールがありまして、食事が少なくて、パンを分け合って食べているとか、そういう話をつい最近聞いたばっかりなのですが、食料などの物資は、かなり届いているということなのでしょうか。
片山:僕の感覚だと、絶対量としてはかなり届いているのではないかと思います。ただ、避難所によって、届いているところと届いていないところ、それから、避難所に入らないで、自宅にいる方には食料はない。特に、東北地方は、お年寄りが多いので、例えば、避難所にパンやご飯がありますので、取りにきてくださいと言っても、取りに出てこられなかったりするわけです。そういう意味では、絶対量はあるけど、あるところと無いところの差が出てきています。
工藤:地域的な偏在があるわけですね。堀江さんはどうですか。
堀江:私も先日、相馬市と仙台市、そして陸前高田に行ってきました。やはり、大きな避難所には物資は届いています。ただ、個々の家々にあるかというと、家の中で避難していて物資が届いていない人はいるように思います。それは、燃料不足が続いているということ、当初に比べると、多少は改善してきていますが、まだ、被災地にいるそれぞれの方々が移動するためのガソリンを簡単に入手できるような状況ではありません。そのため、避難所にものがあっても、取りに行けないという状況になっています。そういった意味で、物資は一応は届き始めてはいますが、全体に行き渡っているかといえば、まだばらつきがある状況だと思います。それから、避難生活が長引いていますので、色々なストレスやプライバシーの面、そういった面でのネガティブなところが出てき始めています。これからは、そういったところにも対処していかないといけない、という状況だと思います。
工藤:なるほど。関さんはどうですか。現地には入られたのですか。
物資は届き始めたが、それを繋げる仕組みは遅れている
関:私自身は、4月4日から拠点の立ち上げのために入っていく予定です。私たちのチームは、3月15日から第1陣、第2陣と人を送って、気仙沼を中心にサポートを始めています。物資の状況に関しては、お二方がおっしゃっていただいた状況かなと思います。ただ仙台などを中心として、物資倉庫にはかなりのモノが備蓄されてきていますが、それを供給する仕組み作り、つまり配送する仕組み、避難所のニーズを集約していく仕組み、それに伴う人繰り、それからガソリンが供給できないということが、もうすぐ3週間という時間が経過するにもかかわらず整っていないことが、これまでの国内災害に見られない様相です。普通であれば、10日経てば常態に回復していくものが、現在も続いている状況だと思います。
工藤:関さんが言ったことに関わるのですが、全体像の中で、避難所が何カ所あって、ほとんどの避難民はそこに収用されているのか。新聞を見ていても、行方不明者の数字が毎日変わっていくじゃないですか。ということは、戸籍や住民台帳が無くて、その確認からまだまだ広がっていく、という状況がありますよね。それから、避難所への収容は一応終わったとみていいのでしょうか。それから、大きな避難所には物資は届いているのだけど、今、関さんがおっしゃったように、備蓄倉庫にはあるけど、非常に小さな町などに、それが届けられる仕組みがない。そういった全体像は、誰が把握しているのでしょうか。
片山:一応、今、安否確認ができていない人が1万人近くいらっしゃいます。それは、行政の方で確認作業を行っていますが、例えば、ご遺体などが瓦礫の中に埋もれていて確認ができない、それから、行政の人達も自分の家族などが被害を受けていて、なかなか機能していないわけです。ただ、本来的に行政が行う仕事だと思いますし、市町村や県で集約しようとしていると思います。
工藤:今日、スタジオに来られているお三方は、はっきり言ってプロなのですね。プロというか、今まで国際的にも色々な活動をやられている。だから、その人たちが先行して、現地に入るということは非常に分かるし、そうでないと活動ができないと思います。ただ、それだけではいけない。その人たち以外に、多くの市民の参加が必要とも思うのですが、こういう方たちはどのようにコーディネートされて動いているのでしょうか。そのあたりは軌道に乗っているのでしょうか。
ボランティアの受け入れもまだ始まった段階
片山:おっしゃる通りで、初期の頃からボランティアに入りたいという声を、随分多く聞きました。私の知っているNGOには3500人以上のボランティアが登録しているそうです。で、いつでも現地のニーズに合った形で出したいという風に言っているのですが、ある程度NGOやNPOがまとめて、ボランティアの人達の調整をして現地に送っているということは始まっています。ただ、全体的には、行政の側、つまり社会福祉協議会が窓口になって調整をするということになっています。ですから、そこへ登録をするなり、問い合わせをして、「どこそこへ行って下さい」という形で、ようやくボランティアの受け入れ体制が整い始めたかな、という感じですね。
堀江:現地では、社会福祉協議会等があって、そこで現地に住んでいる方々のボランティアの受付をされています。うちにも、荷物が着いて荷下ろしをする際に、そういったところのボランティアをかなりの人数お願いして、下ろしてもらったりはしています。ただ、東京や大阪など、被災地以外からボランティアを送ろうとすると、まだ、その人たちの滞在場所が確保できないという状況があります。我々のスタッフ10名強が岩手県と宮城県に行っていますが、彼らの宿泊場所の確保もかなり大変な状況がありますので、この段階で、ボランティアの方々が100名、200名単位で来られてしまうと、彼らをどうやって滞在させて、食事を出していくか、ということは、まだ解決できていない問題になっています。
工藤:堀江さんの所は10人強の人を送っているということですが、最終的にはどの程度の規模を出したいのですか。
堀江:スタッフとしては15人ぐらいになるかと思います。今、岩手県の全域の障害者施設、高齢者施設を1軒1軒回ろうとしています。宮城県につきましては、既にかなりの施設を回っています。その2カ所で15人ぐらいの人数で展開をしたいと思っています。ただ、それは、スタッフの数であって、それぞれの施設なりに訪問してもらうなど、色々なことを行なってもらうボランティアの方々はこれからもっと必要になってくると思います。そういう意味では、ボランティアの方は数十名は必要になってくるのではないか、と思っています。
工藤:関さんどうでしょうか。今、10人でもケアする態勢づくりをするのは大変だとうことですが、本当の現地の受け皿をつくらないと動けないですよね。
善意を受け入れる態勢は支援の広がりに追いついていない
関:私たちも今から16年前の阪神淡路大震災の初期的な取り組みからお手伝いをしましたが、その時からの教訓としてもそうですが、まず、多くの善意を受け止めるための態勢を整えていかないといけない。それが整わないうちにボランティアを受け入れてしまうと、二次的な混乱を呼び起こしてしまう。そのために、私たちも気仙沼市の社会福祉協議会が立ち上げている災害ボランティアセンター、本来であれば、これは一市町村、あるいは県が被災した場合には、近隣県や全国ネットワークで応援が入り、人的なサポートが入ってくるわけなのですが、これだけ広域になると、その人材も追いつかない。その中で、時間を要していますけれど、ようやく3月28日から一般の市民ボランティアを受け入れています。ただ、まだ県外からは受け付けていません。県外の人達が活動できる状況は4月の下旬を目指してやっています。また、態勢の問題以外にも、先程もおっしゃっていたようにガソリンもない、それから宿泊場所も確保できない、被災された方々の生活がそういう状況におかれている中で、もう少し地域の方々ががんばって、あるいは県内の人達に支えていただく状況の中で乗り越え、県外の人達のサポートまで息長く続けていけることが求められているのかな、と思っています。
工藤:阪神淡路大震災の時もそうですが、ボランティアは135万人ぐらいですよね。それを上回るような規模の人達の支えが、しかも中長期的に継続しなくてはいけない。そのための受け皿となる態勢は、まだ始まったばかりということですかね。
片山:一応、政府にも首相の補佐官として辻元議員が入っていますよね。やろうという思いは政府の側にもあるし、今、関さんがおっしゃったように、社会福祉協議会が窓口となって調整しようということで、一応の青写真みたいなストーリーはあるのだけど、現実は全然追いついていません。おっしゃったように、ボランティアで入りたいという人は、沢山いらっしゃるのですが、まだそういう人を受け入れたり、コーディネートをしたりする態勢は整ってはいません。
工藤:私たちのところに届いたメールには、お金とかものを早く送ってくれという声も多いです。これらはどういう仕組みで動いているのですか。みなさんのところに来たものは、被災地に届けるわけでしょ。
関:基本的には、災害対策本部の各救援物資倉庫があるわけですが、実態は非常に厳しいわけです。なぜかというと、整理がついていかない。
救援物資は日々運ばれても、倉庫の仕分けが間に合わない
工藤:とにかく、物資がぶち込まれているだけの状況ですか。
関:そうです。今は、多少収束しつつありますが、昼夜問わず、救援物資がトラックで運び込まれてきます。そうすると、自治体の方、自衛隊の方が、益々疲弊していくわけです。整理がつかない間に、モノがどんどん仕分けされない状況が続いていくと、極端な話をすると、二次災害的なものになってしまう。善意がそういう形になってしまっている状況です。ですから、そういう事実もみなさんに少し知っていただくということが重要なのだろうと感じています。
工藤:なるほど。確かに、今回の善意の盛り上がり方は半端じゃなくて、みなさん何とかしたいと思っていますよね。しかし、それが被災地にちゃんとつながらないという状況があるわけですよね。
片山:昨日、政府の被災者対策本部で話を聞いたのですが、今、関さんが指摘されたように、物流が滞っているということがあります。物流の専門家は、ロジスティクスと言いますけど、その専門家を各所に政府で派遣した、と。それで、調整がつき始めているようです。
工藤:遅いですよね、凄く。
片山:ちょっと遅いですね。そして、もう1つの問題は、県のレベルにはものがきているけど、市とか避難場所に運ぶ手立てがなかなか確保できない、ガソリンが無いということも関係しています。それで、3月29日から一般の宅配業者に委託をして運ぶようなこともして、もう少しきめ細かな対応をしようとしています。
工藤:企業が結構動き始めたということですよね。電車も日本海側から通れるようになったとか。しかし、今、話を聞いてみても、折角みんなが何とかしたいと思っているのに、現地とちゃんとつながらない。この問題を解決しないといけない、という1つの課題が見えてきたという形ですよね。
堀江:ミスマッチが起こっているので、必要なものは必要なところに送らないと、逆に混乱を招いてしまいます。
義援金(お見舞金)の配分もまだこれから
工藤:今後、この問題をどのように考えていけばいいかという話になります。あと、お金の問題というのはどうなっているのでしょうか。つまり、1つは、義援金は赤十字ベースで分配されますが、これはまだ配られる段階ではないわけですね。
片山:まだできないですね。
工藤:阪神淡路大震災の時は、すぐにやりましたよね。
片山:やはり、阪神淡路大震災の時と比べて、地域が広いことと、まだ完全な安否確認もできていません。そして、さっき工藤さんがおっしゃった、自分の身分を証明するものすらないということもあって、幾ら配ったらいいかということもわからない。まだ、協議会というか、委員会もまだ立ち上がっていません。
工藤:つまり、民間の力、善意の動きをコーディネートするなど、救援のためのロジスティクスを含めた形で課題が見えていますね。これはやらなければいけない。それと、行政の機能を早く回復させなければいけない、という大きな問題があるということですね。
片山:おっしゃるとおりです。
行政機能の立て直しも急務
関:そうですね。ただ、各市町村の状況を伺うと、先程、片山さんがおっしゃられましたけど、役場の多くの方たちがなくなり、上役の人達がほとんどいない状況で、不眠不休の状態でやっています。避難所にも、1000人規模の町の中で職員が20人しかいないという場所もあって、もう限界を超えているわけです。応援の方たちも入っていますが、これはもう少し時間を置いて、支えて見守っていくことが必要かなと思います。
次週もこの議論は継続します
工藤:20日余り経って、今、現地の状況を把握しながら、課題が明確に浮かび上がってきている感じがしました。この話は、次週も続けてお送りします。僕たちなりにどうしていけばいいか、ということを考えていきたいと思っています。今日は、どうもありがとうございました。