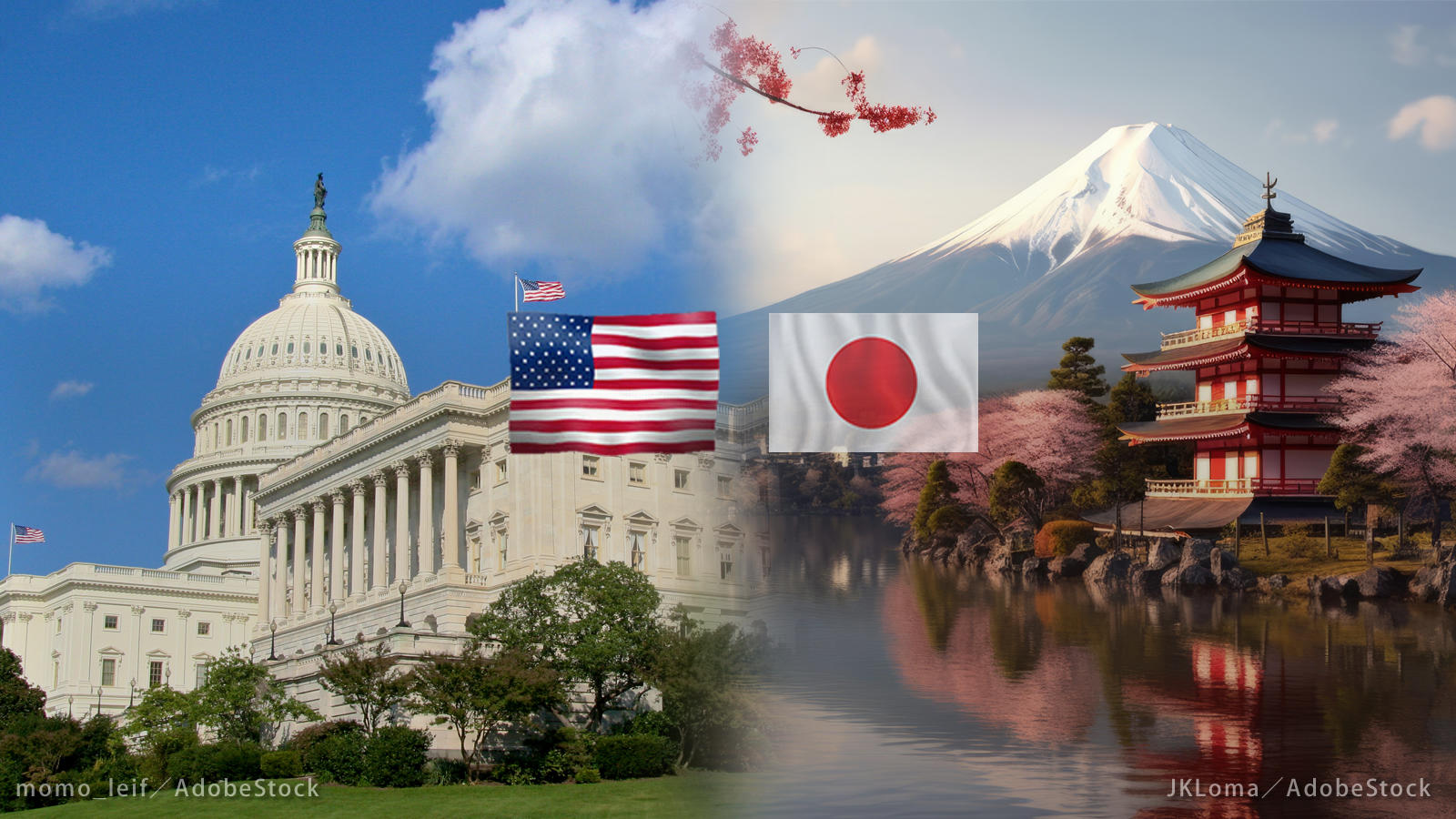中国とは、日中関係が非常に厳しい2005年から対話を毎年続け、今では世界が注目する本音の対話の舞台に発展しています。さらに、この地域の平和を考えるために、日本、アメリカ、中国、韓国の4カ国と対話を行うほか、流動化する世界の中で、この地域の協力と発展を考えるために、東南アジアの各国との対話を始めています。
今、取り組んでいる議論
「第21回東京-北京フォーラム」間もなく開催します
言論NPOが2005年から行ってきた「東京-北京フォーラム」の21回目のフォーラムを11月22日~24日に北京で開催することが決まりました。
すでに日中の両主催者は、これまで20年間続けてきた対話を30回まで延長することで合意しており、今回の対話は「次の10年」に向けたスタートとなります。両主催者は、今回の対話では日中二国間の問題だけではなく、世界の課題をグローバルな観点から議論することでも合意しており、今回はそのためグローバルガバナンスをメインテーマに掲げて、8つの分科会で議論を行うことになります。
世界の中で大国による「力の支配」が強まり、世界経済の不確実性が高まる中で、日本と中国の本格対話に向けて準備が動くことになります。今後の決定事項や詳細は、言論NPOのホームページで順次お知らせしていきます。
「第21回東京-北京フォーラム」に向けて
工藤泰志(「東京―北京フォーラム」日本側執行責任者、言論NPO代表)

今回、世論調査の設問や、フォーラムの内容について、過去にないほど合意に時間がかかったのは、世界が不安定化する中で、この問題をどのように対話で扱うべきか、日中両主催者の間で、かなりの意見の相違がみられたからだ。ただ、グローバルガバナンスや多国間主義が壊れて、世界が分裂に向かって動いているいるということに関しては、それを解決する必要があるという認識では両主催者は一致し、そのためにこの対話が重要な役割を果たすということで合意したため、最終的には様々な違いがありながらも、分科会テーマなどで歩み寄ることになった。
さらに、世界で唯一、日本国民と中国国民の意識を明らかにする日中共同世論調査も、8月29日までに設問案で合意し、9月6日から両国内で調査を開始することになった。昨年の調査で、日本国民だけではなく中国国民でも相手国に対する国民感情が悪化した結果が大きな話題となった。そのため、中国側でも今回は調査の対象となる都市を10都市から20都市に倍増するなど、中国国民の意識をより多く把握するための試みが行われるなど、様々な改善を進めていく点でも合意している。設問に関しても、日中両国だけでなく、世界で起こっていることについても我々は目を向けて踏み込んだ内容を入れており、この結果は今年も世界的な話題になると私たちは考えている。我々としては、今後の世界を見据えて、アジアにおける2つの巨大な国の国民がどのように考えているか、ということを明らかにする必要があると考える。
開催まで残り僅か、20年間一度も中断することなく、本音で議論できる中国との対話の舞台は世界には存在していない。対話ということがいかに重要か、ということを今回のフォーラムを通じて明らかにしたいと考えている。
東京-北京フォーラム特設サイトはこちらカテゴリー
アジア平和会議

東京-北京フォーラム

日米対話

日韓未来対話

世論調査・有識者調査

【議論】アジアの安全保障

【議論】日中問題

【議論】日韓問題

【議論】日米問題